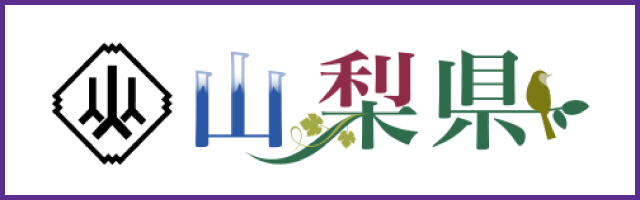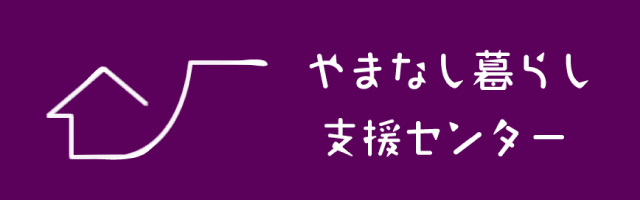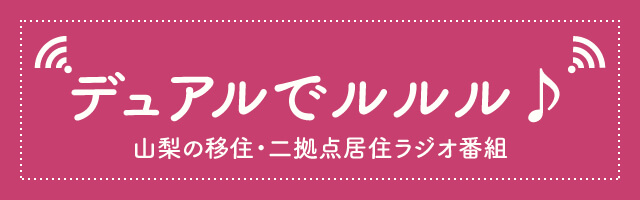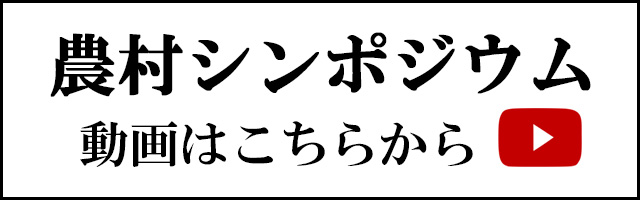- 1
畑・農場から生中継、先輩就農者の農業ライフ紹介

最初の中継は、笛吹市の甘い香りが漂うモモ畑から、就農7年目の青木祥子さんです。大阪出身の祥子さんは、以前は接客業に携わり、雇用就農で醸造用ブドウ栽培に従事することをきっかけに山梨県へ。その後、生食用ブドウとモモの栽培で独立就農していた夫の竜一さんと出会い、農園の手伝いを重ねるうちに結婚。夫婦二人で合同会社HOPE園を経営し、モモ20品種、ブドウ13品種を栽培し、JA出荷に加え、ネット直販や加工品の販売も手がけています。
今は、生後10か月の息子との3人暮らし。休日には、家族で富士河口湖方面や隣町の知人を訪ねるなどコミュニケーションを大切にしています。中継では、モモの収穫を実演してくれました。
続いては、中央市のトウモロコシ畑から、独立就農5年目を迎えた平野嘉朗さん(よしろーさんちの農園代表)です。地域の特産品であるスイートコーン「ゴールドラッシュ」をメインに、裏作にはキュウリのほか、新たにモモやキウイフルーツを加え、通年の出荷体制を整えています。埼玉県出身の平野さんは、大学卒業後に海外支援活動、会社員、小学校教師を経て、農業への思いを胸に中央市へ移住。県の制度を活用して2年間研修を受けて独立しました。
現在は、妻が2歳と3歳の子どもの育児中で、多くの農作業を一人でこなしながらも、子どもと公園やプールに出かけたり、農閑期には実家や知人の元を訪ねるなど、家族との時間を確保しています。