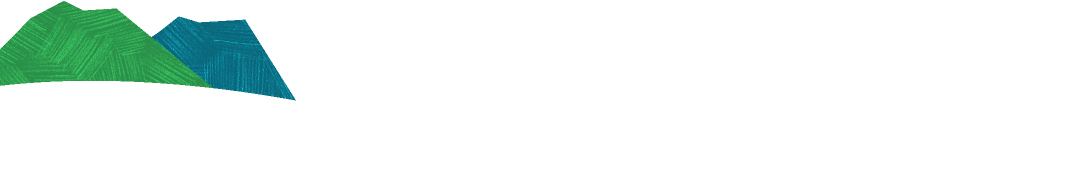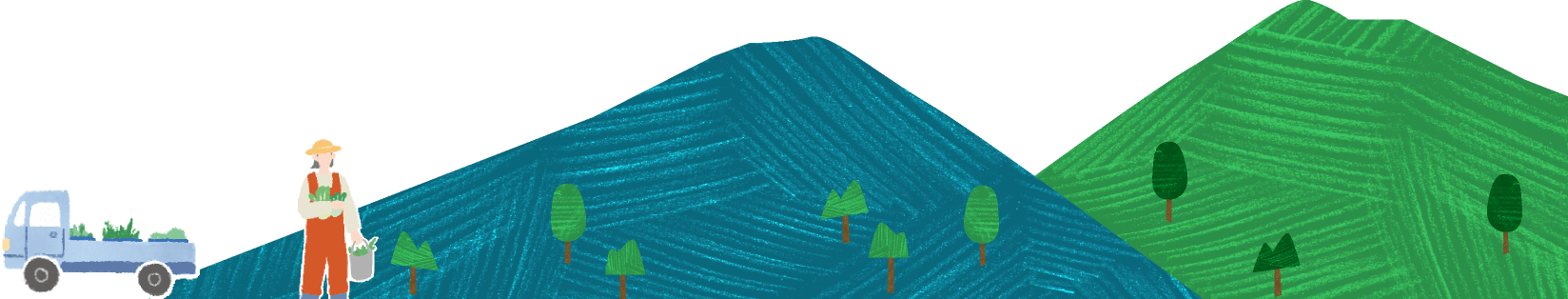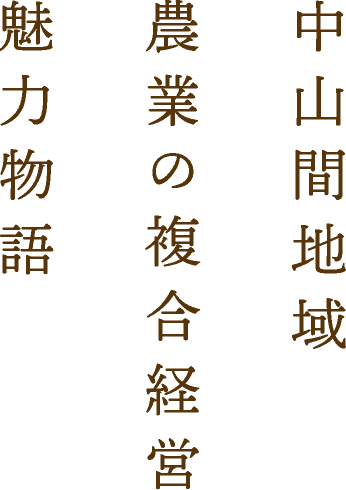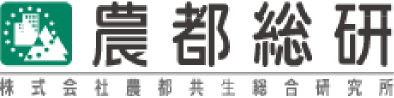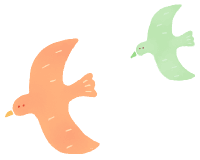中山間地域 農業の複合経営魅力物語 黒瀬 公雅さん
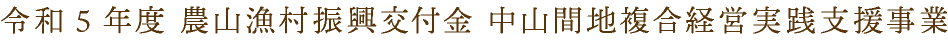


03
福井県(北陸)
きみごろFARM
黒瀬 公雅さん



|
栽培作物 野菜多品目 |
耕作面積 8〜9a、ビニールハウス4棟 |
|
経営規模 本人 |
移住形態 Uターン |
|
前職 金融機関 |
農地の取得 実家所有の土地 |
|
就農までの期間 ふくい園芸カレッジ1年半 |
移住した年 2019年 |
農業
×農業
- 多品目
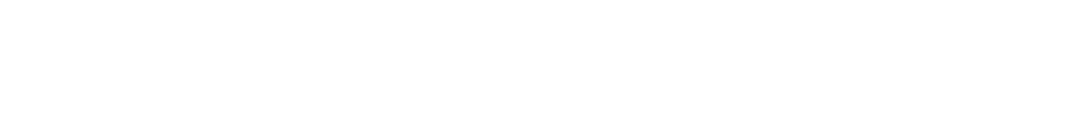


もともと兼業農家で水稲をしていた実家を継業し、新たに野菜づくりを始めた黒瀬さん。福井県の提供する研修制度をうまく活用。作付する品目や補助金についての相談ができる環境にあると言います。地元のネットワークを活かした農業団体にも参加しています。
実家の米作りを継業+αで野菜づくりも展開。地域の農家との連携も

ふくい園芸カレッジと兼業農家のお父様から農業を学ぶ公雅さん
農業をはじめたきっかけは?
「お米を買わない」ってことが、実はすごくありがたいこと
実家が兼業農家で、お米を作っていました。学生時代は大阪で生活していたんですが、そのときに「お米を買わない」ってことが、実はすごくありがたいことだったんだなって気がついたんです。お米はいつも送ってもらってましたから。実家にいたときは農作業の手伝いを億劫に感じていたこともあったんですが、外に出たことで、農業や農作物が近くにある環境が当たり前ではないことに気づきました。そこから、農業に興味を持ちました。

通勤時間数秒?ご実家の隣が仕事場
農業技術の学び方
2020年に仕事を辞めて、福井県が主宰する「ふくい園芸カレッジ」の新規就農コースを受講して毎日1時間以上かけて通いました。カレッジでは、栽培のノウハウを基礎から教わるだけではなく、マーケティングや販売時のPOPの書きかた、ビニールハウスの建てかた、解体のしかたまで、1から10まで学べましたね。実際にビニールハウスを1棟貸りて、自分で野菜を栽培して売るまでの模擬経営などもをやらせてもらえました。ここでみっちり1年半基礎を学んでから、就農したっていうカタチです。
新たに野菜作りを展開するうえでの品目決め
重たいものはなし、少ない面積でもたくさん採れるもの、獣害ないもの
品目を決めるときは、一人でもできるものを選びました。重たいものはなしにして、キュウリやトマトといった、少ない面積でもたくさん採れるものを作付けしていきました。路地ではナスとブロッコリー、ハウスでキュウリとミディトマト、スイートコーン、冬はほうれん草を作っています。あと、獣害がない作物、というのも選ぶ基準になりましたね。ただ、我が家の場合、犬のアルバの存在が大きいと思います。いつも畑や田んぼを歩き回っているせいか、これまで獣害の被害に遭ったことがありません。
補助金の使い道と苦労したこと
福井県の農林課の「儲かる福井型農業総合支援事業」という補助金を使って、ハウスを建てました。ただ、当時コロナ禍で鉄の値段が上がってしまって例年の見積もりで出していた分の差額を借り入れすることになってしまった。もうひとつ、福井県の補助金を使ったのは機械ですね。防除機と噴霧機、耕運機です。この辺りの情報も、カレッジの先生が勝山市役所の農林課に繋いでくれて、機械の善し悪しや助成金申請についても相談することができました。
いざ自分でやってみると失敗続き
カレッジに通っていたときは、先生がたが毎日見てくださるのでうまくいっていた野菜づくりも、いざ自分でやってみると失敗続きでした。あわら市と勝山市では気候が違うこともあって、野菜が枯れてしまう、虫にやられるなど、初年度はさんざんでした。こんな状況をカレッジの先生に報告して相談にのっていただき、時期をずらして作付けをするようになりました。役所の方にもカレッジの先生にも、お世話になりっぱなしです。

少ない面積で収量が多く、重くない品目からスタート
販路と今後の展望・課題
ミディトマトとナスはJAに出荷しています。それ以外は、仲卸の人が買いに来る青果市場と直売所、勝山や大野、永平寺の道の駅に出しています。2022年に地元で農業団体「ディノファーマーズ」を立ち上げました。勝山は恐竜が有名だから。20代から40代の農家が集まって情報交換をしたり、マルシェイベントに一緒に出店したりしています。この団体で、新しい特産物を作りたいねっていう話が出ています。個人的な課題としては、販売金額を伸ばしたい。耕作放棄地が増えているのでその有効活用についても考えたいです。ゆくゆくは規格外の野菜を使って、加工品にも挑戦したいですね。

愛犬アルバのおかげで獣害被害はゼロ
新規就農者へのメッセージ
自分が本当にやりたいこと、できることを具体的にして、ある程度計画や目標を持って動くといいと思います。住む地域が選べる人は情報収集をすれば、その土地に合った農業ができますよね。そして、地域に入っていくならなおのこと、人との関わりを大切にしてほしいです。私もイベントに出たり、飲食店で野菜を扱ってもらえたりと販路が広がったのは人のご縁からでした。個性を出すのも大事ですが、周囲の人と関わりながらうまくやっていくことも、就農にあたっての大事な要素のひとつだと思います。
取材・文=乾祐綺 写真=乾祐綺 編集=養父信夫