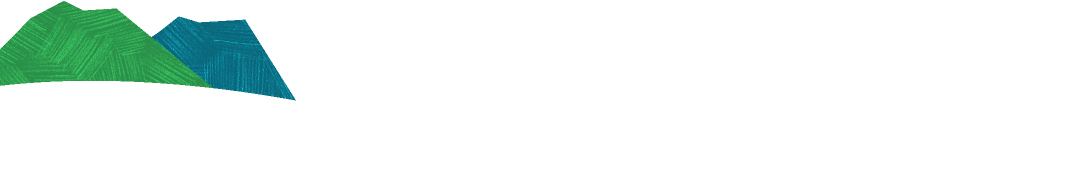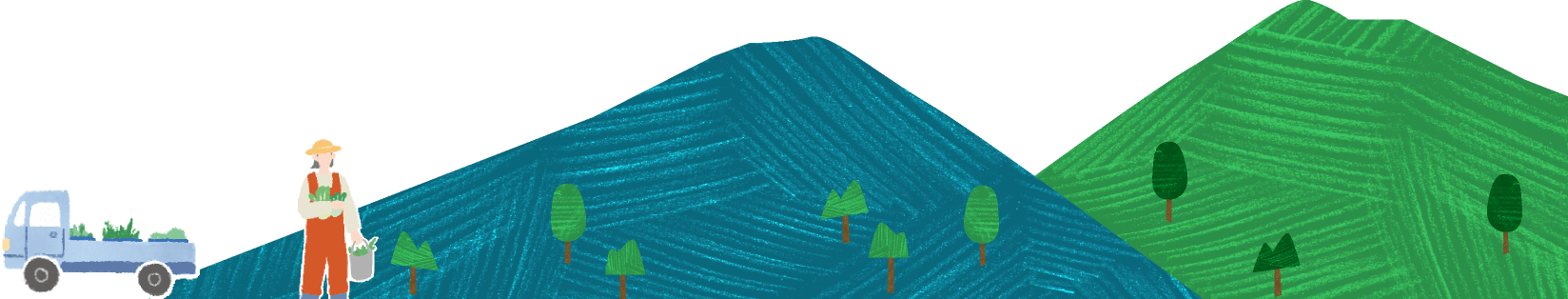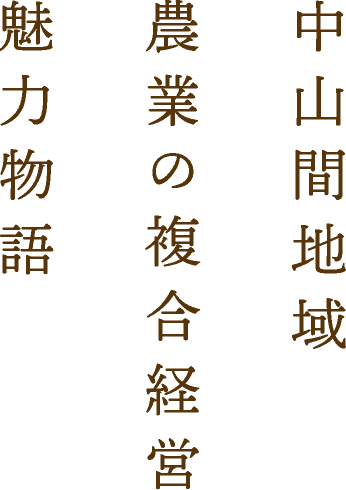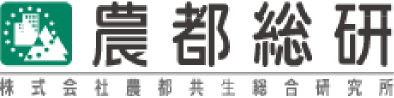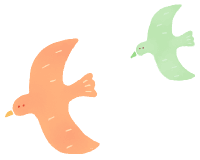中山間地域 農業の複合経営魅力物語 金子 勝彦さん・阿部 由佳さん
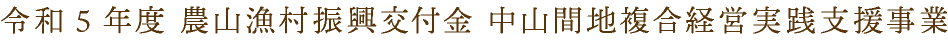


04
埼玉県(関東)
Love Life Farm
金子勝彦さん・阿部由佳さん



|
栽培作物 水稲、野菜多品目 |
耕作面積 2ha |
|
経営規模 本人 |
移住形態 Iターン |
|
前職 飲食店・香港 |
農地の取得 借地 |
|
就農までの期間 自給自足大学1年 |
移住した年 2015年 |
農業
×農家民宿
×加工品
- 多品目
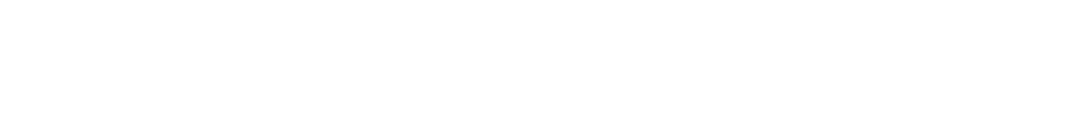


海外も含めた飲食店勤務の経験を持つ金子さん。カフェ経営を夢見て、埼玉県ときがわ町にやってきました。この町で背中を押してくれる存在と出会い、農家民食をスタート。そこから農業の道が開けました。どう生きるか?という哲学を軸にし、多くの人を受け入れています。
人との縁と運を大切にし、農家民宿で”開かれた循環農業”を目指す

農業×農家民宿×加工品。金子さん、阿部さんは新たな農業スタイルを実践中
農業をはじめためたきっかけは?
「自給自足大学」に入学
埼玉県川越市の出身です。京都の大学を卒業して、営業や会計事務所勤務など、サラリーマンも経験しました。そこから、飲食業界に入りまして、沖縄県西表島、東京の飲食店で働きながら、調理師免許を取りました。海外などにも行って故郷の埼玉に戻ってきたのが35歳。いろんな土地での生活を経て、好きだったハーブを使ったカフェ起業の構想が生まれ、老人ホームのキッチンに立ちながら畑仕事を始めました。そこで出会った地元の名士である新井さんとのご縁が、今に活きています。畑を貸してもらって、農作業を始めることができました。のちに農家民宿を始めることができたのも、新井さんのおかげです。自給的な暮らしをめざして農業やDIYを学ぼうと、2014年、栃木県那須で発明家の藤村靖之さんが運営する非電化工房「自給自足大学」に入学しました。ここで、藤村さんの哲学とともに農業技術を学んだり、刺激的な仲間と出会ったり。得たものは多かったですね。

栽培技術は、非電化工房の「自給自足大学」で学んだ
農家民宿の道が開けた
畑を始めたのも、きっかけは新井さんでした。「畑から始めれば?人脈ができていいよ」って誘ってくださって。新井さんは、僕が自給自足大学に通っている間に亡くなってしまった。大変お世話になったので、お線香を上げにご自宅へ伺うと、息子さんがいて、「この家が空いちゃうから使わない?」と言ってくれたんです。新井さんのお家は、それはそれはすごい豪邸なんですよ。大々的な改装はできないからどうしようって考えたときに、農家民宿を知るんですよね。当時、宿をやるにも規制が厳しかったのでなかなか手が出ない人が少なくなかったのですが、農林水産省が認可する「農林漁業体験民宿」というのがあって、規制緩和があったんです。これはいい!とこの制度を使って農家民宿を開業することにしました。
農地の取得と栽培技術の学び方
家中葉っぱだらけになったことも
栽培技術は、非電化工房の「自給自足大学」のカリキュラムでしっかり教えてもらいました。稲作の方法や、コンバイン、トラクター、ユンボの操作にも触れることができました。有機農法を学びましたね。一方で、販売の方はからきしで。パッキングも全然わからなくって。白菜ができたはいいけど、外葉も全部畑から持って帰っちゃって、家中葉っぱだらけになったこともありました。このままじゃいかんと思って、「ときのこや」という有機農家が10軒くらいでやっている任意団体で、毎週日曜に直売しているところがあるんですけど、そこに深谷市の農家でバリバリ働いていた人がいて、彼に教えてくれと頼み込みました。

農産物生産(一次)×農産加工品(二次)×農家民宿(三次)=6次産業化を実践
販路の広げかた
販路としては、この「ときのこや」から始まって(現在は休会回中)、出荷業務の修行中に出会った有機野菜・無添加食材などの宅配サービスを展開する「らでぃしゅぼーや」さん。これがメインですね。あとは地元のスーパーの直売にも出しています。 もうひとつ、面白い活動があって。「NPO法人ECOM(エコ・コニュニケーション)」という東松山を拠点に活動している森さんというかたがやられている都市農村交流にも関わらせていただいています。大学の非常勤講師もやっていたかたで、江戸時代に、船で江戸の肥溜めの肥と、こっちの農産物を交換するというサイクルがあったそうです。そういった都市と地方の関係性は現代にも必要だということで、東京のオーガニックショップやカフェと繋がりをつくり、注文を取って、こちらの農家数軒から野菜を持っていくという仕組みをつくられたかたです。
それぞれのニーズに合わせた体験を提供したい
開業当時は、新井さんが住まわれていたお家で農家民宿をやっていましたが、2019年に現在の場所に移転をしました。当初から変わらないコンセプトは「農的暮らしや、無理のない範囲の自給自足に触れる宿」ということ。農業体験やDIY体験を提供しています。農業や自給自足に触れたいと思うときって、「よりよく生きたい」と思うときだと考えていて。お客さん一人ひとりに、なぜ農業や田舎暮らしや自給自足に興味があるのかをよく聞くようにしています。子どもに自然に触れさせたいという人もいれば、仕事や人生そのものを見つめ直したいという人もいる。田舎への移住を真剣に考えている人も。それぞれのニーズに合わせた体験を提供したいと考えています。
「農的暮らしや、無理のない範囲の自給自足に触れる宿」
もちろん、最初からうまくいったわけではありません。当初は自給的暮らしがしたいという人が泊まって、畑も町も全部案内して、丸一日話して送り出してっていうやりかた。平日でもいつでも受け入れてましたし。3泊4日の場合は、日中お客さんが観光している間に僕らは農業やって、帰ってきたら夜また接客しますよね。僕もこうやってペラペラしゃべっちゃうので、夜中まで話します。それで3日終わったあとに、また1泊2日の別のお客さんが来るっていう感じで継ぎ目がなかった。休みがなくなっちゃうんで、これを続けていくと、自分の生活が成り立たなくなっちゃうなって思い、試行錯誤しながら、今は宿泊の受け入れは土曜日限定にしています。
「援農」の活動
堆肥撒きとか雑草取りとか結構ハードなところをご一緒に
農業のリアルを知りたい人もいるので、そういったかたに向けては民泊というよりも、昼間に「援農」の活動に参加してもらっています。朝10時から夕方4時くらいまで、その方の体力に合わせて、作業をしてもらいます。とは言っても、収穫体験じゃありません。堆肥撒きとか雑草取りとか結構ハードなところを一緒にします。参加するかたにお金を払ってもらうカタチになります。1000~1500円いただいて、ご飯を提供するという仕組みにしています。
新規就農を目指したい人へのメッセージ

参加者からお金をいただき、農作業をやってもらう援農活動も
まず、売り先から確保しましょう。そして、商業的研修をしていなかった身からすると、研修は遠回りではない。研修をばっちりやることをおすすめします。やって損はないです。あとは、いろんなところに足を運んで、どんどん聞いて知識を入れていったほうがいい。あとは販売形態を考えること、それに付随する倉庫、機材などの環境を整えること、段取り、アルバイトを入れる入れないなど、こういう〝農家としての導線〟っていうのがあるので、一つひとつを手を抜かずに考えてやることが大事だと思います。 あとは、いきなり就農しなくてもいいんじゃないか、ということ。農業をしている人の元でお試し体験をすることもできますよね。それぞれに適正っていうものがあるから。農家民宿でいろんなケースを見てきて思ったことですが、「本当に求めていることは、実は農業じゃなかった」という人が少なくないので。
取材・文=乾祐綺 写真=乾祐綺 編集=養父信夫