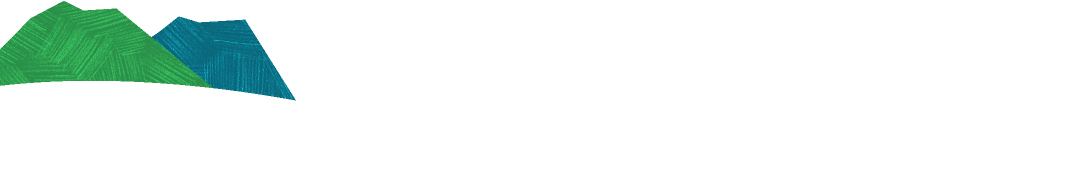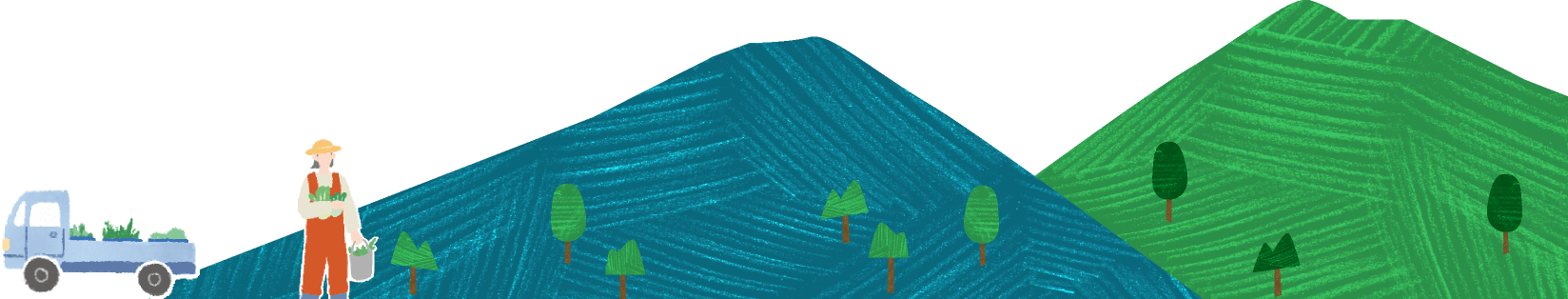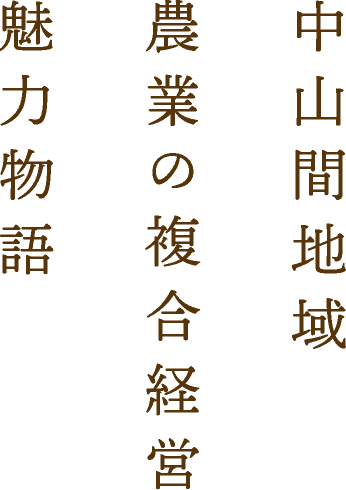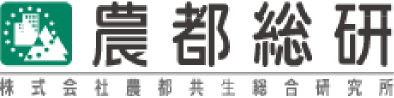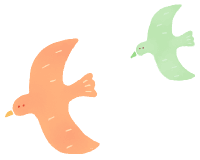中山間地域 農業の複合経営魅力物語 小池 なつみさん
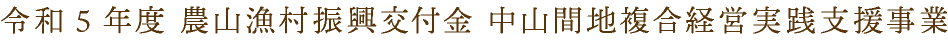


05
岐阜県
Koike lab.
小池 なつみさん



|
栽培作物 里芋、サツマイモ、落花生、じゃがいも、菊ごぼう、水稲など、40品目 |
耕作面積 畑1.5ha、ビニールハウス0.5ha |
|
経営規模 本人 |
移住形態 Iターン(非農家) |
|
前職 証券会社の会社員 |
農地の取得 ご主人の実家の農地 |
|
就農までの期間 結婚して継業まで3年 |
移住した年 2014年 |
農業
×加工品販売
- 多品目
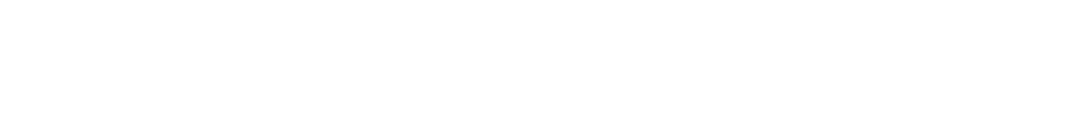


持続可能な農業を目指し、フードロスゼロの加工場や、オンライン販売やマルシェを展開し、そのスキルを周辺農家にも伝授しています。写真家や市議会議員など、さまざまな顔をもつ小池さんは農業経営について独自目線を持っています。
100年超の芋農家を継業し、写真家、市議会議員としても活動

中津川は栗きんとん発祥の地としても知られた栗処
移住・就農を考えたのはいつごろですか?
大阪出身です。大学を出て、お金の計算が得意だったので証券会社に就職しました。そのときに今の主人が同期で同じ部署だったんです。私の方から「結婚して!」ってアプローチしました。そうしたら「農家の長男だから、もうちょっと慎重に考えた方がいいよ」って言われました(笑)。 会社員時代は、日本企業の成長産業を分析しながら、株を売っていました。その分析する過程が好きで、今後の社会や経済を深堀りしていったら、先が見えなくなってしまったんです。そこには人口動態と世界の輸出という、ある意味「数」で結論が見えてしまう世界しかなく、「おもしろくないな」と感じてしまった。成長産業を、これからも生き残れる業界、そしてなによりも魅力ある仕事ってなんだろうって考えたとき、農業だって思ったんです。

小池 なつみさんは芋農家、写真家、市議会員としての顔も
これからも生き残れる業界、そしてなによりも魅力ある仕事、それが農業!
農家の長男に嫁ぐことで始めた農業
農業と縁もゆかりもなかったんですけど、たまたま出会った会社の同期が農家の長男だったので、「よし。君と結婚して農業やろう」って(笑)。2011年に結婚しました。 でも、うちは2haしかなく暮らしていけるような規模じゃなかったので、東日本大震災が決め手になってもともと興味があったカメラの仕事を始めました。中津川市・坂本地区にリニア中央新幹線が通ることになり、土地の買収が始まったとき、両親から「農業をやる気がないなら売ってしまうよ」と言われ、慌てて帰りました。それが2014年の1月。大急ぎで継業しました。
農業技術の学び方と販売ルートの開拓
農業のやり方は、すべて祖父母の通りにやっています。農業研修には参加していません。祖父母は農薬を極力使わないやり方。もとから環境に配慮した農業だったんです。
この地域はJAは水稲のほか、トマトやナスといった決められた品目しか扱ってくれない。民間市場はサツマイモが1キロ30円という値段。量を作ればなんとかなるかもしれませんが、1.5haなのでどうにもならない。なので、この地域のスーパーに営業に行ったり、都会のマルシェに売りに行ったり、販路開拓を自分で行いました。

100年以上続く芋農家を継業
コロナ禍の売上は9割が通販
通信販売とマルシェの企画運営
2018年に「Koike lab.」という屋号を使って、オンラインショップをスタートさせました。当時はネットで野菜を買うということが一般的ではなかったので、軌道に乗るまでは苦労しました。合わせてまちづくりの仕事もするようになり、マルシェやイベントを開催していたので、通販も最初はマルシェで購入した方がリピートしてくれるという買われ方でしたね。当時サービスを開始したばかりの『食べチョク』からも連絡をいただき、そこでも売るようになりました。 まちづくりの関連で、毎月同じ場所で開催する「たべとるマルシェ」を始めました。2020年コロナの中で、野菜が売れなくて困っているときに、この地域の農家が作る野菜をまとめて販売をする通販『恵那山麓野菜』もやりました。
加工場「もったいない工房」の運営
夫が子どものころ、祖父母が丹精込めて作った野菜を山のように捨てていたのを見ていたんですって。こういうやり方はしたくないっていう思いが強かったみたいです。当時、フードロスとかSDGsなんていう言葉がまだなかったころ。一生懸命考えて「もったいない」をキーワードにしようと、加工品に力を入れることにしました。「いのちを1gでも棄てない」という決意のもと、規格外・傷物野菜を専門に加工する「もったいない工房」を始めました。夫は中津川市の老舗菓子店に転職をし、野菜を使ったお菓子作りを学び始めました。現在は、スイートポテトや落花生、カボチャ、玉ねぎを使ったクッキーなどを販売しています。最初は、廃棄が300から400キロありましたが、今ではゼロです。 農作業も基本的には祖父母のやり方ですが、「捨てないための作業」が新たに加わっています。作業場を造って、収穫した野菜を全部持ってきて選別という作業です。それまでは全部畑ではじいていました。
補助金と農業経営の考え方
夫がやっていたら違っていたのかもしれませんが、よそから来た私が経営者なので市町村の補助金情報はほとんど入ってきませんでした。当時私も無知だったので、役所に聞きに行くということもしなかった。自分のお金で商売するしかないと思っていましたので。2022年、岐阜県農政局の「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」を、初めて申請しました。それまで6年間は無借金・無補助金でやってたわけです。情報があれば、使おうと思ったかもしれませんね。だけど、その考えが一切なかったおかげで、コストを抑えるといった経営的な目線は強くなったと思います。

規格外・傷物野菜を専門に加工する「もったいない工房」の加工品
農業で得た収入は、全部農業に投資していく
農業のほかに、写真家、まちづくり法人臨時職員、中津川市議会議員などの仕事をしています。これらの収入と農業の収入は別にしています。持続可能な農業における〝合理的な説得力のある価格〟について熟考しました。たとえば、子どもが一人だからこの価格、二人だったらもっと高くって、生活が価格に反映してしまったらおかしいことになるじゃないですか。持続可能な農業において、生活水準が価格付けに反映されてはならないという決断に至り、農業部門で稼いだものを生活費では絶対に使わないということを2018年から徹底しています。
「+農業」という考えかた
今後の展望
私たちの畑は農業振興地域で、ほかにも優良農地がたくさんある場所なんです。それがなんと400haもある。一方で担い手は今把握しているだけで、5人しかいない。我が家は1.5ヘクタールしかやっていないので、せめて水稲をやらないとまずいよねっていう未来が見えています。 水稲をやるならば、日本産小麦や大豆についても作っていける体制にしたいなと。岐阜県北部に「うすずみ」という小麦粉の一大産地があるんです。食文化の変化に合わせて、国産小麦や大豆の収量アップに微力でも貢献できたらいいなとも考えています。
新規就農を目指したい人へのメッセージ
前述したように、坂本地区はリニア新幹線駅の開業ですごく便利になります。 私はあくまでも、農業経営ではなくて「+農業」という考えかた。バイトや本業がありながら農業に携わるっていうのはありだと思います。「恵那山麓野菜」を組織にしようとしているのは、農業に少しでも興味のある人の受け皿にしたいから。ここで野菜を作ってみたり、販売してみたり、デザインしてみたり。やりたいことを発揮する場を作れればと思っています。