白桃とは?

白桃の魅力
白桃は、桃の中でも果肉が白く、みずみずしい果汁と上品な甘さが特徴の白肉種に分類される品種です。果皮は袋をかけて栽培されることが多く、うっすらとした乳白色〜淡いピンクのグラデーションを帯びた美しい見た目も魅力のひとつ。完熟すると手で簡単に皮が剥けるほど柔らかく、とろけるような食感を楽しめることから、生食用として特に人気が高い品種群です。
白桃と黄桃の違い
桃は大きく分けて白桃と黄桃に分類されます。白桃は果肉が白く、果汁が豊富でジューシー。食感は柔らかく、香りも華やかで、贈答用としても重宝されます。一方、黄桃は果肉が黄色く、比較的しっかりとした硬さがあり、かつては缶詰などの加工用途に多く使われてきました。黄桃も生食向けに改良が進んでいますが、柔らかくてジューシーな食味を楽しみたい方には、やはり白桃がおすすめです。
白桃の人気品種5選
白桃は、みずみずしさととろけるような甘さが魅力の果物で、多くの品種が存在します。特に人気が高く、食味や見た目も優れた代表的な品種を5つご紹介します。
白鳳(はくほう)

ジューシーで糖度が高く、酸味が少ない白鳳は、非常に人気のある白桃の代表格です。果肉は柔らかく、とろけるような口あたりが特徴で、7月中旬〜下旬にかけて旬を迎えます。多くの白桃品種のルーツともなる存在で、まさに桃の王道といえる品種です。
清水白桃(しみずはくとう)

岡山県を代表する高級白桃で、果皮は透き通るような白色、果肉はなめらかで香り高く、上品な甘さが楽しめます。旬は短く7月下旬ごろに限られますが、贈答用としても根強い人気があります。桃の女王と称されるのも納得の気品ある味わいです。
あかつき

白桃と白鳳を掛け合わせて誕生した福島県の主力品種。しっかりとした果肉と濃厚な甘み、ほのかな酸味のバランスが絶妙で、果汁も豊富です。旬は7月下旬〜8月上旬で、日持ちも良いため、家庭用から贈答用まで幅広く親しまれています。
川中島白桃(かわなかじまはくとう)

長野県発祥の川中島白桃は、硬めの果肉とずっしりとした大玉が特徴。しっかりとした歯ごたえと強い甘みで、スイーツや加工にも適しています。8月下旬〜9月上旬が旬で、大ぶりで見栄えが良く、贈り物としても人気です。
加納岩白桃(かのういわはくとう)

山梨県で栽培されている早生(わせ)品種で、他の桃より早い、6月下旬〜7月上旬に旬を迎えるのが特徴です。白鳳に似た上品な甘さと香りを持ち、果皮には柔らかなピンクのぼかしが入る美しい外観が魅力。やや小ぶりながら果汁もたっぷりで、初夏の贈答にもぴったりです。
白桃の旬の時期と食べ頃

白桃の旬は6月〜9月まで
白桃の旬は、一般的に6月から9月にかけて。出荷時期は品種や産地によって異なります。早生種は6月から市場に出始め、中生種は7月中旬〜8月にかけてピークを迎え、9月には晩生種が登場します。例えば、山梨県の加納岩白桃は6月下旬頃、長野県の川中島白桃は8月下旬頃が収穫期です。各品種の旬を押さえておくことで、最もおいしい状態の白桃を味わうことができます。
白桃の食べ頃を見極めるポイント
おいしい白桃を楽しむには、食べ頃を見極めることが大切です。皮の色が白っぽくなり、ほんのりとピンクが差すようになったら、完熟が近いサイン。また、果皮にしっとりとしたツヤがあり、ほのかに甘い香りが漂ってくるのも食べ頃の目安です。手で持ってほんの少し柔らかさを感じたら、いよいよ食べごろ。冷蔵庫で冷やすなら、食べる1〜2時間前がベストで、冷やしすぎると甘みや香りが損なわれるので注意しましょう。
おいしい白桃の選び方
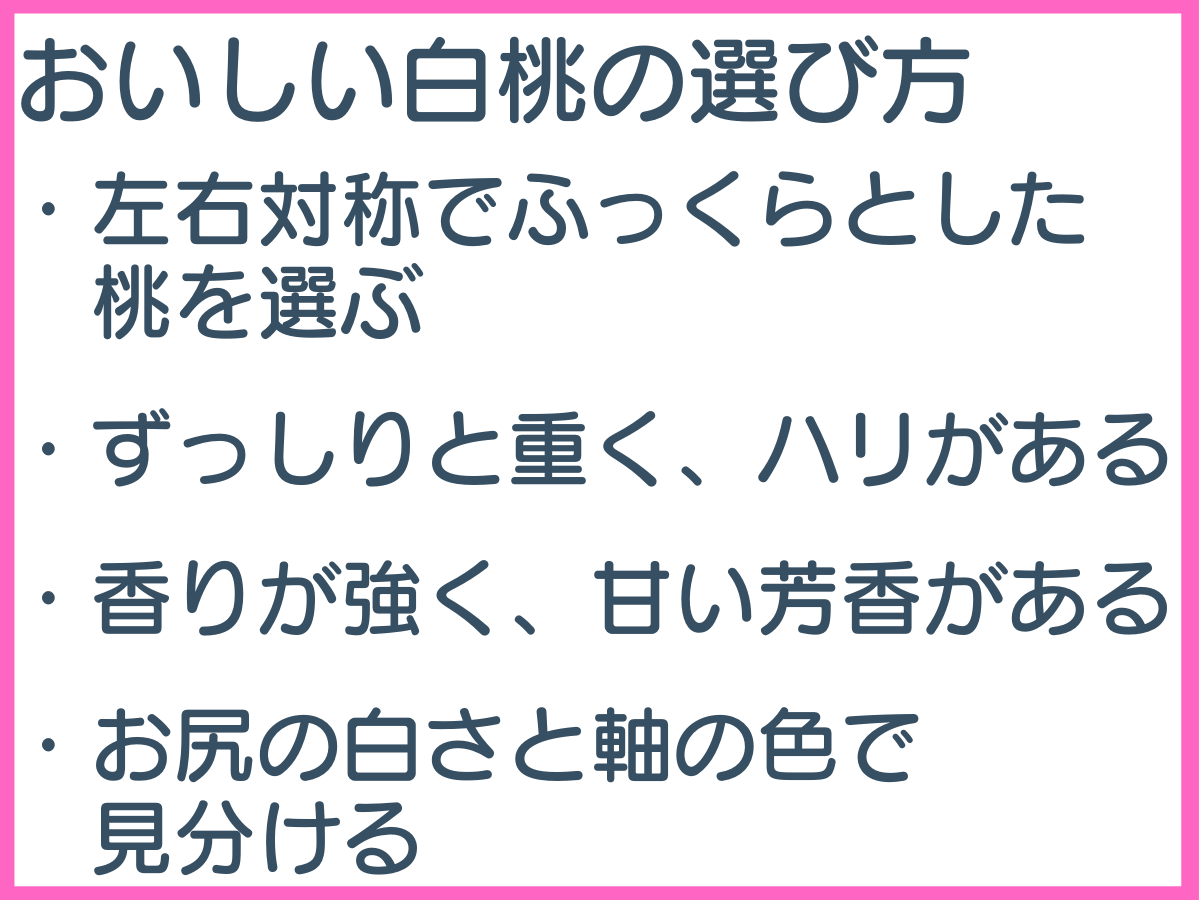
左右対称でふっくらとした桃を選ぶ
おいしい白桃は、見た目がふっくらしていて、縫合線(割れ目)を中心に左右対称な形をしています。形がいびつなものは熟成のムラが出やすく、味にもばらつきが出ることがあります。また、上から見て少し横長の豊円形の桃は、果肉が詰まり甘みも安定しやすい傾向です。形の整い具合は、初心者にもわかりやすい選び方の基本です。
ずっしりと重く、張りがある
手に持ったときにずっしりとした重みがあり、皮に適度な張りがある桃は果汁たっぷりで熟している証拠。軽い桃は中身がスカスカだったり、水分が抜けていたりすることがあります。表面にシワがなく、滑らかでしっとりしているかも確認しましょう。大玉だからおいしいとは限りませんが、一定の重みと張りは当たり桃のサインです。
香りが強く、甘い芳香がある
桃は熟してくると袋越しでも甘い香りを放つようになります。香りの強さは熟度や糖度の目安になるため、ぜひ確認しておきたいポイント。袋に入っている場合でも、近づければほのかに香るものがおすすめです。逆に香りが薄いものは未熟で、甘みが乗っていない可能性があります。
お尻の白さと軸の色で見分ける
お尻の部分(果頂部)が白く、軸の周辺に緑が残っていないものを選びましょう。これは完熟に近いサインです。白桃は収穫後も追熟しますが、緑色が濃く残るものは早採りの可能性があり、甘みが薄く硬いことも。お尻が白くなっていて、全体的に色づきが良い桃は、食べ頃に近く香りもよく仕上がっている可能性が高いです。
白桃の栽培方法
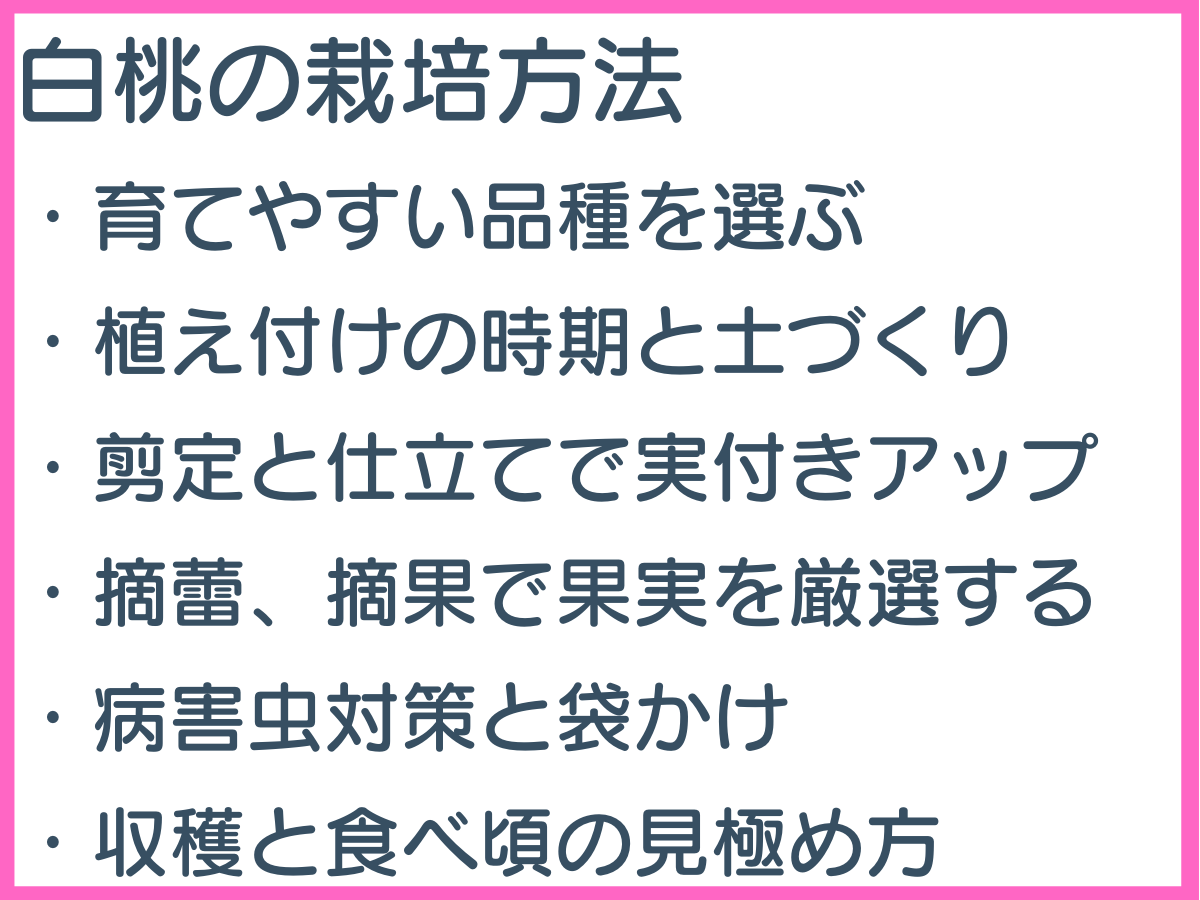
白桃は育てるのが難しそうに見えますが、基本を押さえれば家庭でも十分に栽培を楽しめる果樹です。ここでは品種の選び方から植え付け、剪定(せんてい)、病害虫対策まで、白桃をおいしく育てるための方法を段階的に解説します。
育てやすい品種を選ぶ
家庭で白桃を育てるなら、病害虫に強く自家結実性(※)がある品種を選ぶのが成功のカギです。あかつきや日川白鳳は比較的育てやすく、1本でも実をつけやすいので初心者におすすめ。まずは手間のかからない早生種から挑戦してみましょう。
※ 植物が自分自身の花粉で受粉して実をつける性質のこと
植え付けの時期と土づくり
植え付けは、寒冷地では春(3月頃)、暖地では秋〜初冬(11〜12月)が最適です。水はけがよく、肥沃(ひよく)で通気性のある土壌を選びましょう。鉢植えなら赤玉土7:腐葉土3が目安。地植えの場合は50センチほどの穴を掘り、堆肥(たいひ)や石灰、元肥をよく混ぜ込んで土壌改良してから浅めに植え付けます。根が広がるように配置し、支柱で固定します。
剪定と仕立てで実付きがアップ
白桃は剪定によって実付きや品質が大きく左右されます。冬(12月〜2月)は主に樹形を整え、通気性と日当たりを確保するための剪定を行います。基本はY字仕立てで低樹高を保つのが管理しやすくおすすめ。夏の間には、強く伸びた枝(徒長枝)を間引いて、来年の花芽がつきやすい枝を残します。若い枝を中心に残すのがコツです。
摘蕾(てきらい)・摘果(てきか)で果実を厳選する
桃は放っておくと多数の実をつけますが、そのままでは栄養が分散されて、どれも小さく味も落ちてしまいます。2月末〜4月にかけて蕾(つぼみ)を間引く摘蕾、5〜7月には実を減らす摘果を行い、枝の太さや葉の数に応じて実の数を調整します。目安は1果あたり葉20〜30枚程度。これにより糖度の高い、大玉の桃に育ちます。
病害虫対策と袋かけ
白桃は灰星病や縮葉病、アブラムシやシンクイムシの被害を受けやすいため、薬剤による予防が重要です。春先には殺菌剤を散布し、摘果後は晴れた日に袋かけを行って病害虫から果実を守ります。袋かけをすることで、病気の侵入を防ぎつつ、色づきをコントロールできるので、美しい見た目の実を収穫するためには欠かせません。
収穫と食べ頃の見極め方
白桃の収穫は品種により異なりますが、7〜8月が中心です。果皮が赤みを帯びて、全体に緑色が抜けてきたら収穫のサイン。指で軽く押したときに耳たぶ程度の弾力があれば食べ頃です。収穫後すぐに冷蔵せず、常温で追熟させてから1〜2時間程度冷やすと、甘みと香りを最大限に楽しめます。
まとめ
白桃は、みずみずしく上品な甘さととろける食感が魅力のフルーツです。白鳳や清水白桃、あかつきなど人気品種も多く、品種ごとの旬や特徴を知ればよりおいしく楽しめます。形や香り、重みなどで食べ頃を見極めるのもポイント。栽培はやや手間がかかるものの、基本を押さえれば家庭でも育てることが可能です。



























読者の声を投稿する
読者の声を投稿するにはログインしてください。