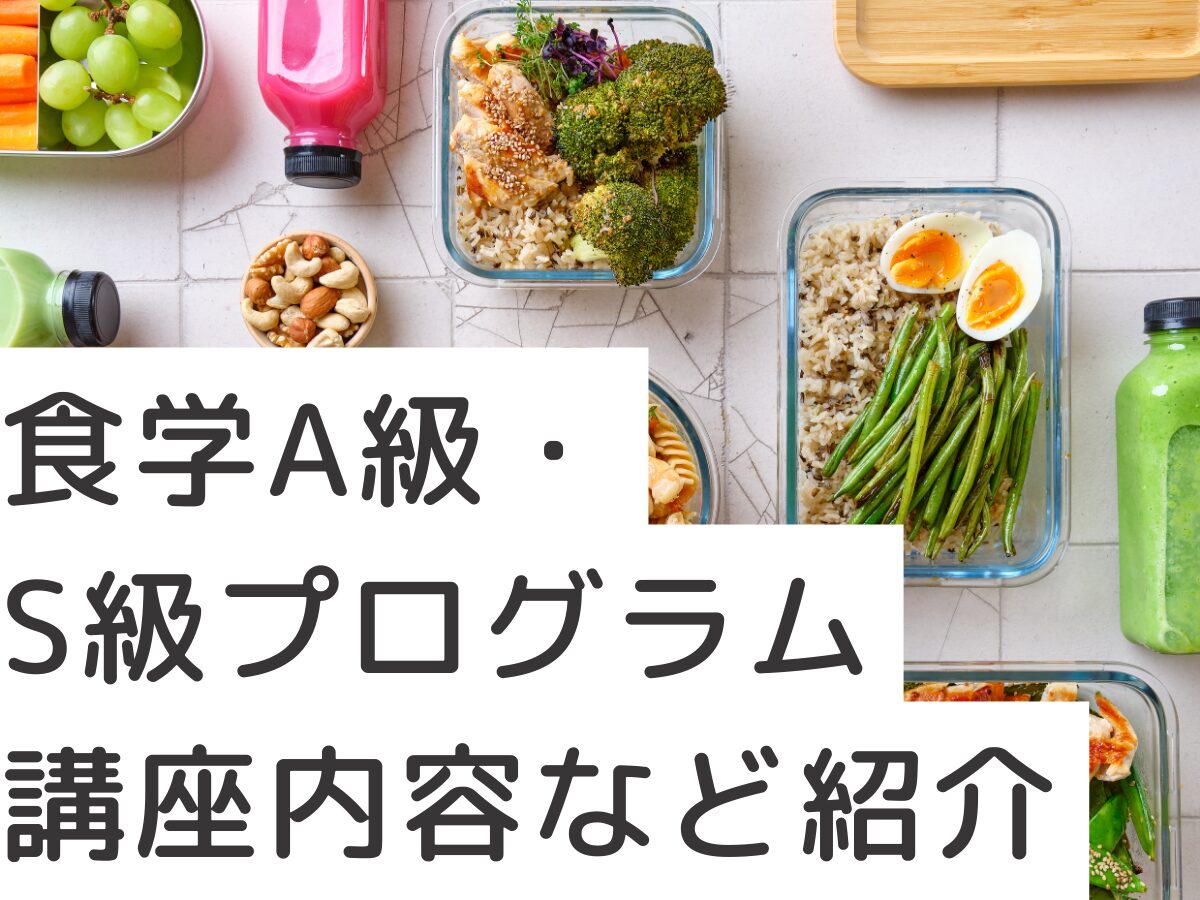食学A級・S級プログラム

| 食学A級・S級プログラム | |
|---|---|
| スクール名 | 国際食学協会 |
| 料金(税込) | 165,000円 |
| 学習期間 | 12ヶ月 |
| 学習方法 | テキスト・レポート提出 |
食学A級・食学S級は指導者レベルまで学べる
食学A級・食学S級は、今まで食育を学んだことがない初心者から、食育に関する知識を有する指導者レベルの方まで対応可能な講座内容となっています。最初に食に関する基礎知識を幅広く学んだ後、基礎知識を応用する段階へと移っていきます。
基礎知識を学ぶ段階では、食の基礎となる栄養素や、日常よく用いる食材の知識を学ぶ他、日本料理の作法や食生活の現状など、食に関わる幅広い知識を身につけることができます。
基本知識を学んだ後は実践学習
基礎知識を学んだ後は、レシピに沿って実践する実習に入ります。学んだ知識をすぐに実習で活かすことができるため、無駄なく学習を進めていくことができます。
食養学からおばあちゃんの知恵袋まで、様々な知識を無駄なく学べる内容となっているため、食に興味のある方から将来ビジネスに活かしたいと考えている人まで、幅広く対応可能です。季節のレシピなど、日常生活に応用できるレシピも多数学ぶことができるため、献立のレパートリーを増やしたい方にもおすすめです。
BrushUP学び/資格講座掲載数No.1(※)
※2025年3月期_指定領域における市場調査
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
講座のポイント
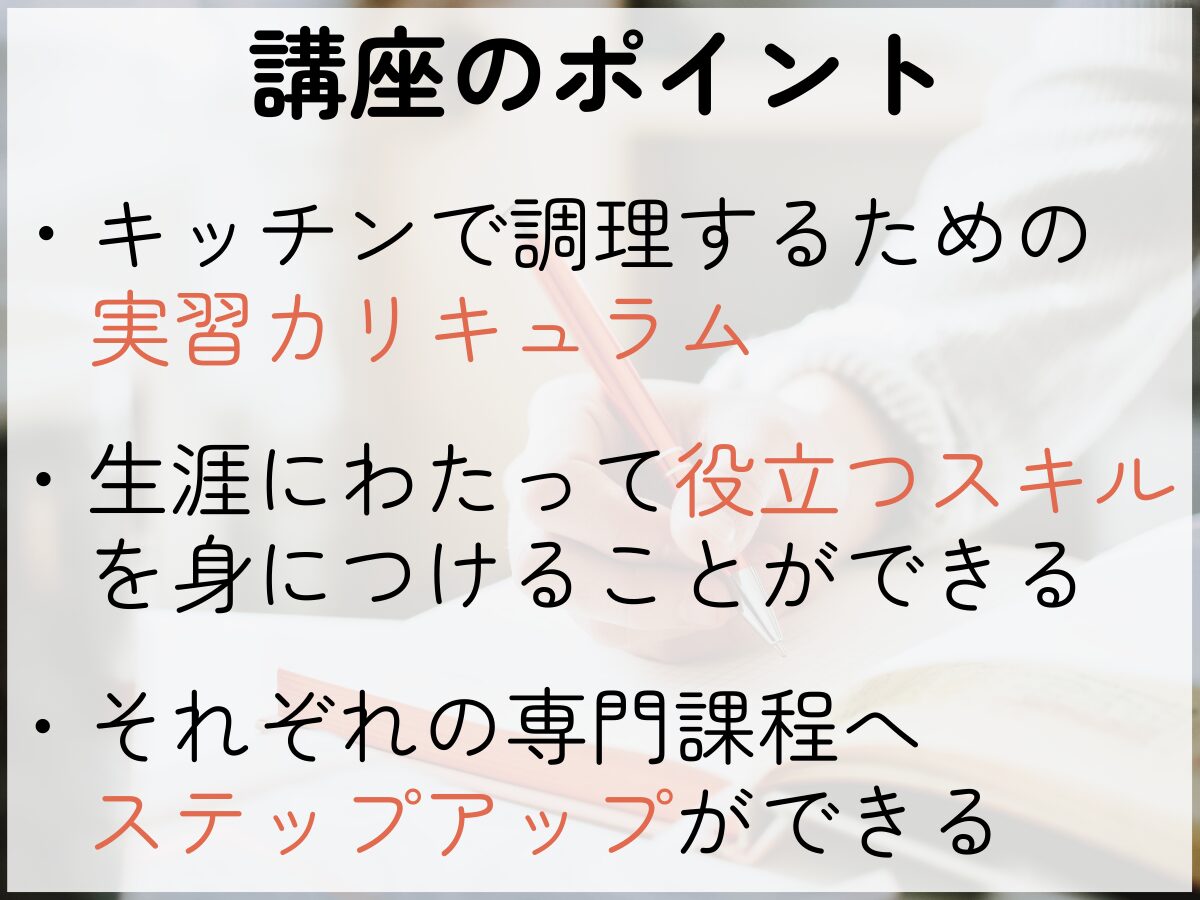
キッチンで調理するための実習カリキュラム
バランスよくレベルアップできるように設計されているのが、食学A級・食学S級講座のポイントとなります。自らの意思で調べて模索する力をつけるカリキュラム設計となっているため、1カリキュラム進めるごとに着実にステップアップしていくことができます。
講座では食に関する知識を学ぶだけでなく、実際にキッチンで調理するための実習カリキュラムが用意されています。実習カリキュラムでは、事前に身につけた食の知識を実際のキッチンで活かすことができます。このカリキュラムによって、生涯にわたって役立つスキルを身につけることができます。
それぞれの専門課程へステップアップができる
最初に食学A級プログラムで入門課程を学んだ後は、自分の目的に応じて専門課程へステップアップすることができます。食学S級・マクロビオティックS級・美容食学S級・食学指導者養成の4つの専門課程が用意されているので、将来設計に合わせて好きな専門課程へ移りましょう。
最初にきちんと基礎を学んでおけば、ビジネスに役立つ専門課程へステップアップすることができるため、講座で学んだ基礎知識は生涯にわたって役立ちます。
学習の進め方

理論を学び、実践に移る
学習の進め方として、最初に理論カリキュラムのテキストで学習した後、実習カリキュラムへと移ります。
理論カリキュラムでは、食と栄養の基礎知識や様々な食材の知識など、食に関する基礎知識を身につけます。基礎知識が身についたら、食事バランスや献立の考え方、健康のための食習慣など、日々の生活に役立つ知識を学習していきます。
理論カリキュラムを学習した後は、学んだ知識を実践する実習カリキュラムへと移ります。実習カリキュラムでは、レシピを元に自宅のキッチンで実例を数多くこなしていくことになります。春・夏・秋・冬それぞれの季節のレシピを実際に調理して、技術を習得しましょう。
マイテキストを活用
理論カリキュラムと実習カリキュラムのテキスト内には、自分の調べたことや考えたことが書き込めるスペースが用意されているので、学習を進めながら随時メモしていくことによって、マイテキストを完成させることができます。
テキストは特性ファイリングとなっているため、学習が不十分なカリキュラムがあれば持ち出して、しっかり復習しましょう。
レポート提出で修了証を取得
理論カリキュラムと実習カリキュラムにはそれぞれ、カリキュラム課題レポートが1セット用意されているため、学習を終えた後にこのレポートを提出して自分の実力をチェックしてみましょう。
レポートでは5段階で評定が行われるので、学習した内容がどこまで身についているのか確認することができます。レポートには講師によるコメントも記されているので、復習する際の参考になります。
修了証を得たら、検定試験へ
食学A級・食学S級それぞれのカリキュラムが修了すると、修了証書が発行されるとともに、検定試験の受験資格が与えられます。試験に見事合格すれば資格証明書が授与され、IFCA会員に登録することができます。
食学A級・食学S級どちらも在宅受験が可能なので、普段仕事や家事に忙しい人も受験可能です。在宅受験に合格した後は、準食学士の取得に挑戦してみましょう。
準食学士を取得してIFCA所定の応用課程を修了すると、食学士認定試験の受験資格を与えられます。この試験に合格すれば、食学士として認定してもらうことができます。
まずは資料請求から
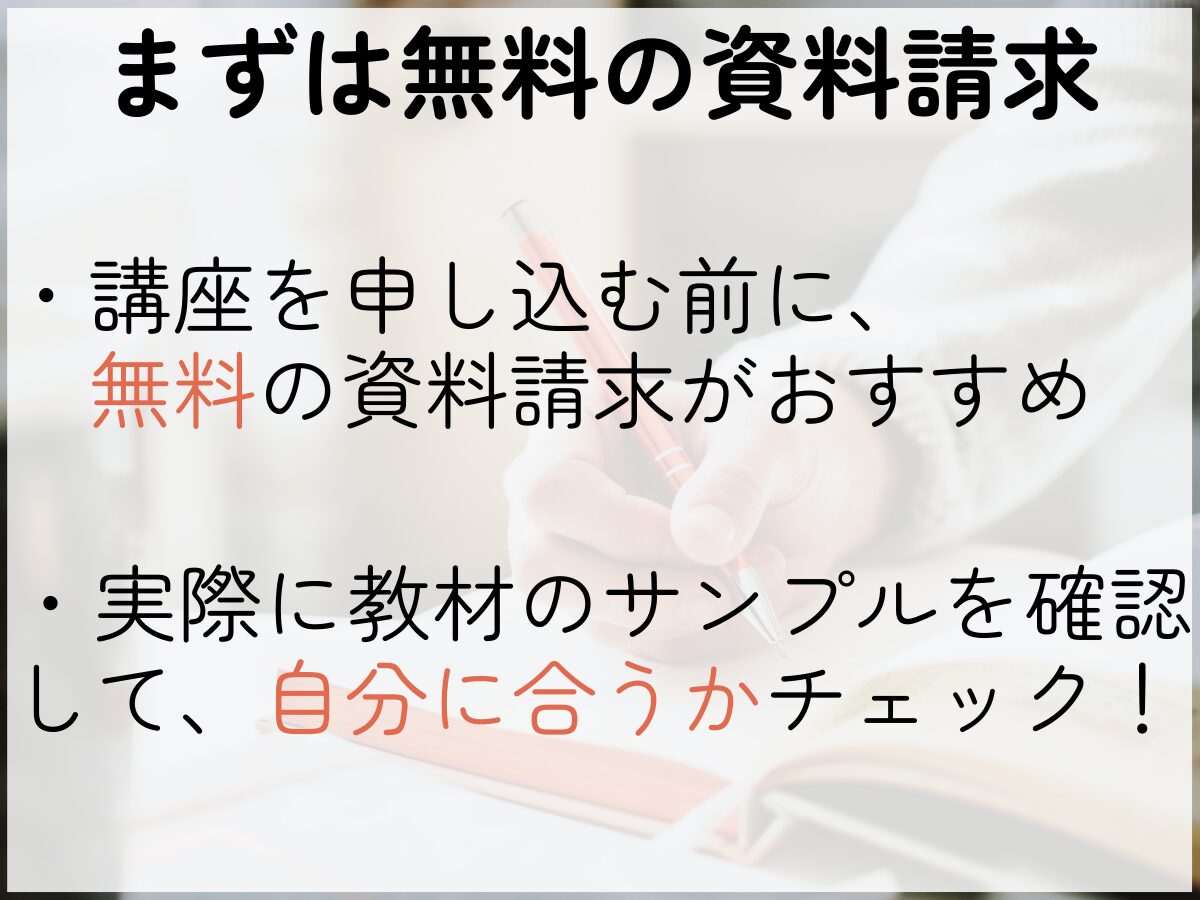
資格講座の資料を取り寄せてみませんか?資格・通信講座のサイトから資料を取り寄せることが可能です。
合うか合わないかを確認する方法として、実際に講座の教材のサンプルを確認して、自分に合うかチェックすることをおすすめしています。講座を申し込む前に、まずは資料請求をして確認してみてはいかがでしょうか?
BrushUP学び/資格講座掲載数No.1(※)
※2025年3月期_指定領域における市場調査
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構