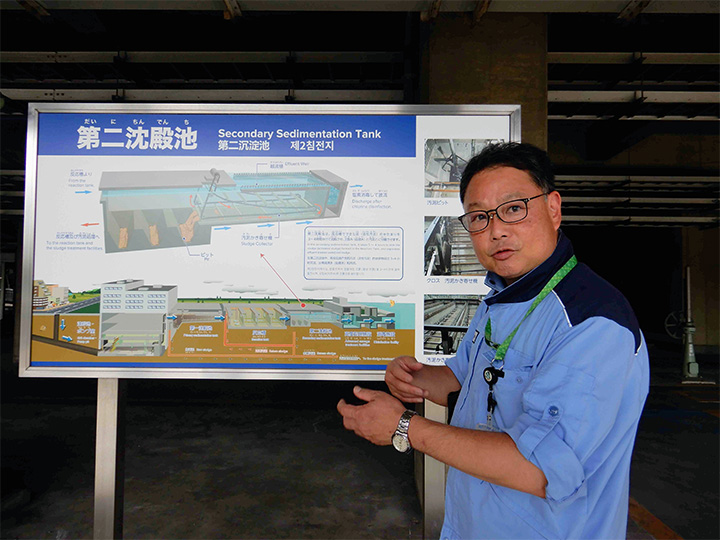羽田の目と鼻の先にある日本最大の下水処理場
グォーンと低い音を立てて、白い飛行機が目線よりわずかに高いところを滑降していく。
「羽田空港がすぐそこですから。向かい風を受けて降りるのが良いみたいで。今日は南風に向かって降りてくるんでしょうね」
だだっ広い敷地にまばらに立つ建物と建物の間を、青色に青磁色、肌色、銀色といったさまざまな色と形状のパイプが走っている。筆者から見てほぼ真横を低空飛行する飛行機は、しばしばその影に入って見えなくなる。肌色に見えるパイプはもともとオレンジに近かったようで、青磁色のパイプも退色して白みがかっている。地上の塗装のひび割れとともに、時間の経過を感じさせた。
東京の玄関口・羽田空港と幅100メートルの川を挟んで隣り合うここは、日本最大の下水処理場・森ヶ崎水再生センター。東京都23区の実に4分の1の面積から下水を集めて処理する。立地する大田区はもちろん、品川、目黒、世田谷区の大部分と、渋谷、杉並区の一部を対象とする。
24時間、365日休むことなく稼働し続け、職員が3交代で詰める。周辺のポンプ所といった関連施設も含めると、職員数は100人近い。
広さは東京ドーム9個分に当たる41万5309平方メートル。一日に約100万立方メートルの水を処理する。用地は幅100メートルの運河を隔てて東西2カ所に分かれている。1966(昭和41)年に西側が、1975(昭和50)年に東側が運転を始めた。
「ここを訪れて、かなり大きいと感心する人が多いんです。私はよそが分からないので実感がわかないんですが。狭い方の西施設を案内してもそう言われるので、ああ、そうなんだなって」。こう教えてくれたのは、東京都下水道局森ヶ崎水再生センター次長の濱村竜一(はまむら・りょういち、冒頭写真)さん。水色の上着に紺色のズボン、右胸に「東京都下水道局」と書かれたワッペンが縫い付けてある作業服姿だ。

森ヶ崎水再生センター
「羽田に近いからと言って、空港に行くついでに見学に訪れる人もいるんですよ」と濱村さん。敷地内には空港を臨む展望台もある。小学生が社会科見学で訪れることもあるという。
航空機が見えた角度からすると、離着陸する飛行機の窓から運が良ければセンターが見えるはずだ。だが、空港をよく利用する割にセンターを見た記憶は、全くない。
見学を始める前、濱村さんが場内を一望できる西施設の4階にあるベランダに案内してくれた。「ここから、あの中学校までが敷地です」。そう言って指さす白い建物は、400メートル先にある。そこまでに広大な打ちっぱなしのコンクリートが広がり、水の張られた池が並ぶ。その隣には樹木と芝生の植わった緑地が広がっていて、テニスコートやサッカーコートまで整備してある。大田区が管理しているこの公園のサッカーコートで、蛍光色のTシャツを着た集団が日差しを浴びて走っていた。

森ヶ崎水再生センター。左奥の緑地は公園として開放されている
臭気対策に機械化、自動化も
見学を始めて、まず意外だったのは、臭くないということだ。
トイレから出る汚水はもちろん、風呂やシャワーのお湯、台所で出る水など、人間は1日に200リットル以上の下水を出す。
センターに入ってきた下水がまず通るのが、沈砂池(ちんさち)。一番最初の工程で、ほぼそのままの下水を扱うので、建物内は臭うのではないか。警戒して沈砂池を覆う建物に入ると、ムワッと鼻腔(びくう)に入ってくるにおいがやはりある。ところが、カツオ節のような、だしが濃縮されたようなにおいだったので、拍子抜けした。臭い刺激臭ではない。アンモニア臭や腐った食べ物のようなにおいのいわゆる「下水臭」はせず、逆に驚いた。
「においがしますね。でも臭い感じではないです」と濱村さんに話しかけると、「慣れてるので、もう我々は分からなくなっているんですよ」との返事が返ってきた。
下水の臭気をファンで吸引する脱臭設備が付いているから、そのお陰でもあるのだろう。
建物の床にはコンクリートが打たれ、その上に配管や鉄骨などの構造物が見える。沈砂池の水面は、床よりもさらに12メートルほど下にある。下水が地下深くを流れてくるからだ。

沈砂池は床のさらに12メートル下に広がる
下水はまず、スクリーンという格子状の柵を通って、木片や浮遊している大きなゴミを取り除かれる。その後、ゆっくり流れる過程で、土砂を水底に沈殿させていく。
沈砂池を通った下水は、ポンプでくみ上げられる。
ポンプについては、濱村さんからバトンタッチした田中茂(たなか・しげる)さんが説明してくれた。100人もの職員を擁するだけに、仕事は細分化されている。ざっくりいうと6割が運転管理を、4割が保守工事を担当する。運転開始から半世紀以上が経ち、設備の更新や修理が欠かせない。
運転管理を担当する田中さんがずらっと並ぶ10台のポンプを前に「ポンプ1台で、学校のプールを2分間で空にしてしまう」と解説する。とんでもなく強力だ。このようにセンターの処理工程は機械化、自動化が進んでいる。

下水をくみ上げるポンプ
次に下水は第一沈殿池に入る。2、3時間かけて通過し、汚れを底に沈殿させる。沈砂池では大きかったり重かったりする異物を取り除いたが、この沈殿池は沈砂池で取れなかった小さな汚れを時間をかけて沈ませて取り除くのだという。

田中茂さん
浄化を担う微生物
次に通るのが反応槽で、6~8時間と最も長い時間をかける。これまで格子状の柵や重力で異物を取り除いてきたが、反応槽は微生物の力を借りる。下水処理といえば、塩素消毒という安易なイメージを抱いていた。実は塩素は一番最後に加えるだけで、重要な部分は薬品ではなく自然の浄化作用に頼っている。
ここを説明してくれるのは、森田健史(もりた・けんし)さん。水質管理を担当し、水処理が良好に進行しているか、また、処理した水の水質が法令の基準を満たしているか確認する。
「第一沈殿池まで固形物の除去をしてきましたけれども、反応槽は下水中の有機物や窒素、リンを微生物によって除去することになります。微生物は、基本的に人間と一緒で、生きていくためには空気が必要ということで、下からブクブクと空気を送り込む装置で酸素を供給するしくみになっているんです」
金魚の水槽の水に空気を混ぜ込むエアレーションのように、空気を送り込んで、微生物に下水に含まれる有機物を分解してもらう。さらに、汚れが微生物に付着して塊になることで、沈めて除去しやすくもなる。センサーを設置し、空気の量や微生物の濃度を測って、微生物が活動しやすいように制御している。
反応槽はすべてオレンジ色の樹脂でできた蓋(ふた)で覆われていた。ほぼ最終に近い工程の1カ所だけが見学のために蓋のない状態で開放されていて、においはまったく感じられない。微生物の力に感心させられる。

反応槽にセンサー(手前)が差し込まれているところ
反応槽の前の廊下には、クマムシやメンガタミズケムシといった微生物の絵が等間隔に描かれていた。
クマムシは、体長0.1~1ミリ程度で、8本のずんぐりした足を持ち、見た目が動物のクマに似ている。愛嬌(あいきょう)のある見た目で人気がある。センターの紹介ビデオにも登場し、もぞもぞとはい回っていた。他県の下水処理場でもよく紹介されている。人気に比例して重要な役割を果たしているのかと思いきや、そういう訳でもないらしい。
「実際に有機物などを処理してくれるのは、こういう微生物よりもっと小さくて顕微鏡でも見えないような細菌類なんです。食物連鎖で細菌類をこういう微生物が食べるので、微生物を見れば処理がうまくいってるかどうか分かります。ですから、定期的に顕微鏡で観察をしていますね」(森田さん)
見えないところで働く細菌類という無数の黒衣がいるのだ。
取材で訪れたのは2024年の夏。「夏の今この時期だと生物の種類が多くて大型化してるんですけど、冬は小型になって種類も少なくなり、処理の進みが悪くなってしまうんです。自然の営みなので、夏の方が処理は早いんですよ」(森田さん)
反応槽の微生物は、下水の中にもともといるもの。だからセンターは、箱こそ人工的に作られているものの、根幹は自然の営みに支えられている。

反応槽の蓋が開いているところ
なお、この反応槽の屋上には先ほどベランダから眺めた森ケ崎公園が整備されている。
公園を階下から見上げつつ、濱村さんが教えてくれた。
「広い敷地を下水処理場としてのみ使うのは、ちょっともったいないですから。それからやっぱり下水を扱いますから、対策をしていても、迷惑施設的なものであることに変わりはありません。公園の整備には、地域貢献の意味合いもあるんです」

森田健史さん
反応槽でできた泥、つまり汚泥の塊と処理された下水は第二沈殿池に流れ込み、3、4時間かけて汚泥の塊を沈殿させ、上澄みの水が処理水となる。汚泥は集められ、大部分は反応槽に戻して再利用され、一部は汚泥処理施設に送られる。
沈殿池の水がきれいなのに感心していたら、濱村さんに「何かにおいとかは感じられましたか?」と聞かれた。「ここは全然感じません」と答える。
「よかったです。処理がうまくいっているということだと思います。都市化が進んでいて、すぐ近くにもマンションや宅地があるので」(濱村さん)

第二沈殿池
第二沈殿池から出た処理水のほとんどは、塩素消毒して迷路のような水路を通り、時間をかけて混ぜられ海に流される。

センター職員の長井千花(ながい・ちはな)さんが処理水の透明度を確認しているところ。長い容器の底に書いてある目盛りがはっきり見えた
下水汚泥は集積して処理
汚泥は、生活や事業で生じた泥状の物質の総称だ。下水汚泥というと、ドロドロしているのかと思いきや、そうではない。
「最初は汚泥といっても、水分が99%。もうほとんどが水なんです」。こう説明してくれたのは、東京都下水道局のエネルギー・温暖化対策推進担当課長である池田亘宏(いけだ・のぶひろ)さんだ。
都では年間、東京ドーム約56杯分(約7000万立方メートル)もの下水汚泥が発生する。
都で汚泥を焼却する施設は、5カ所しかない。汚泥焼却設備を持たない水再生センターからここに汚泥を送って、まとめて処理している。
森ヶ崎水再生センターで発生した汚泥は、やはり大田区にあり直線距離で3キロの南部スラッジプラントに送られる。ほとんど水分だった汚泥はここで濃縮、脱水される。
「含水率をだいたい76%とか、高性能な脱水機になると、74%くらいまで下げることができます」(池田さん)
丸い筒を高速で回転させて脱水する、洗濯機と似たようなしくみの遠心脱水機で、水分を飛ばす。こうして半固形物の脱水汚泥ができあがる。
脱水汚泥は「脱水ケーキ」とも呼ばれる。そのため、プラント内には「ケーキ貯留槽」とか「ケーキ搬送ポンプ」「ケーキ圧送ポンプ」がある。脱水ケーキは濃い灰色、まさにチャコールグレーで、水分を含んでモソモソして、アンモニア臭を放つ。

池田亘宏さん
東京都は全量焼却
この脱水ケーキは、都で年間120万トンも発生する。ケーキ圧送ポンプを通って最後に行きつく先は、焼却炉だ。「東京都から発生する汚泥は、全量焼却という形になってます。23区内に5カ所の焼却施設がありまして、そこで焼却している状況です」(池田さん)
850度以上の高温で、瞬時に焼いてしまう。脱水ケーキは含水率75%前後なので、燃やすにはかなりのエネルギーが必要となる。
燃やした後に残る灰は、最初の下水汚泥と比べると、容積比で400分の1。焼却の最大の利点は、容量を減らせるこの「減容化」にある。東京のように人口の集中する都市部は、汚泥をそのままため込む余地がない。だから、政令指定都市や県庁所在地といった大都市において、汚泥の処分方法は、基本的に焼却一択となる。
「東京都は汚泥の発生量が多いので、やっぱり焼却で減容化しないといけないんです。そのまま埋め立て地に持っていってしまったら、それこそすごい量になりますから」(池田さん)
埋め立て地とは、羽田空港の沖合にある「中央防波堤外側埋立処分場」(江東区)を指す。そこには下水汚泥を含む廃棄物が埋め立てられている。残された貴重な埋め立て処分場を一日でも長く使用するため、ごみの減量や資源化などの取り組みを積極的に進めなければならない。
温室効果ガスの排出源という側面も
ところで、ここまで汚泥の処理を解説してくれた都下水道局の池田さんの肩書が少々変わっていることにお気づきだろうか。エネルギー・温暖化対策推進担当課長。実は下水処理は、多くの温室効果ガスを排出している。
「都の事務事業(目的別に区分された事業)による温室効果ガスの排出量のうち、下水道局が35%と最も多いんです」(池田さん)
都といえば、都営地下鉄や都営バスを運用する交通局を持つ。多数の車両を抱えるだけに、温室効果ガスの排出も相当なものではないか。こう思いきや、交通局の排出割合は14%(2020年度)で、下水道局の半分以下に過ぎない。
都は、2050年に二酸化炭素排出の実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現を目指している。その前段階として、2030年までに温室効果ガスの排出量を2000年に比べて50%削減する「カーボンハーフ」がある。これらの目標を達成するには、最も温室効果ガスを排出する下水処理をこそ、何とかしなければならない。

出典:東京都下水道局「アースプラン2023」
排出量の内訳を見ると、水処理が59.2%を、汚泥の処理が31.9%を占める(2021年度)。
「ポンプ所や水再生センターで大きなポンプを使ったり、水再生センターで空気を入れて攪拌(かくはん)したりするのに電気をかなり使います。汚いものをきれいにするのには、非常にエネルギーを使うんですね」(池田さん)
汚泥の処理でいうと、最も温室効果ガスの排出量が多いのが、濃縮から脱水、焼却に使う電力の使用(14.1%)。電力の使用に次いで温室効果ガスを排出するのが、処理の過程そのもの。一酸化二窒素(N2O)やメタンが汚泥の焼却の工程で生じ、12.6%に達していて、バカにならない。
二酸化炭素と比較したとき、メタンの温室効果は25倍、一酸化二窒素に至っては298倍とされる。下水汚泥を850度という高温で燃やすのは、その排出量を減らすためだ。
都民の出した下水は人知れず水再生センターに流れ着き、微生物による処理を経た後、燃やされる。都の下水道事業は近年、7500億円台の予算を確保している。下水道料金で賄えるのは、うち2割ほどで、国からの補助も含めた公共事業として成り立っている。
こうした背景もあり、大量の下水汚泥が発生する東京都は、その肥料化に乗り出した。次回は肥料の製造現場を訪ねる。