タルマーリーって?

不思議なパン屋さん!?
山間の田舎町、鳥取県智頭町にある「タルマーリー」をご存じでしょうか? 格さんと麻里子さん、「イタル」と「マリコ」だから店名は「タルマーリー」。素敵な夫婦が二人三脚で営むパンと地ビールのお店です。
……と言ってもただのパン屋ではありません! そこには多くの人を惹きつける“思想”があります。
東京で知り合い「田舎のパン屋」に
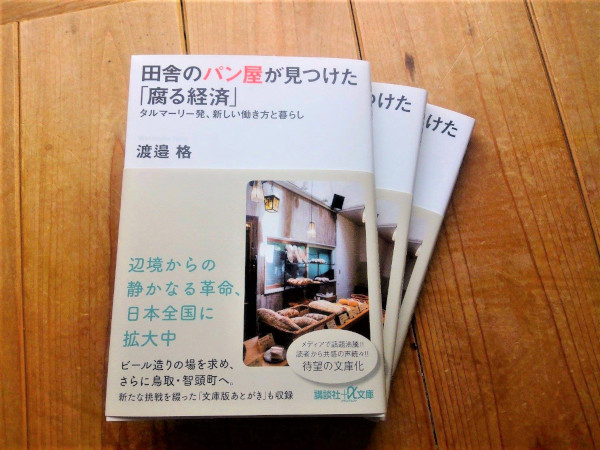
文庫化もされた格さんの著書「田舎のパン屋が見つけた『腐る経済』」。修行時代の話や発酵などについて詳しく書かれています
格さんと麻里子さんは大学時代、東京で知り合いました。2人とも「田舎」や「農」に憧れ、同じ有機農産物の卸販売会社に就職し、ほどなく付き合うことに。卸販売会社を退職し、「田舎のパン屋」になるための準備をはじめます。
2008年、千葉県いすみ市で「パン屋タルマーリー」は誕生しました。その後、東日本大震災を機に2011年岡山県真庭市勝山に移住。格さんは野生の麹菌を自家採取して酵母を起こし、パンを作ります。空気中の菌は目に見えないもの……、数々の失敗と試行錯誤を繰り返し、酒種パンを完成させたそうです。
さらに2015年、鳥取県智頭町に移転し、クラフトビールの醸造もはじめます。進化した現在の「タルマーリー」は天然の菌だけでパンを作り、野生酵母だけでクラフトビールを醸造する加工業者でもあります。
田舎だからできる「菌本位制」と「地域内循環」

廃園した保育園を改装した、鳥取の「タルマーリー」。すぐ背後に山が迫ります
なぜ鳥取に移転したのか
智頭町は人口7000人ほどの過疎地で、町の9割以上が山林です。山深いところには源流があり、豊富な地下水が流れます。「タルマーリー」はビール醸造に使う水を求めて、この地にやってきました。麦と酵母で作られるビールはパンと深いつながりがあります。ビールを醸した酵母でパンを作ることもできるのです。
また、野生の麹菌を採取するためには、菌がすみ着きやすい地域環境がなければなりません。そのためには農薬や肥料の使用を減らし、土壌や水をきれいにする必要があります。自然栽培が進むことでパンとビールは進化するし、菌は環境の状態を示す“ものさし”になる──。格さんはこの考え方を「菌本位制」と呼びます。
智頭町の「自然栽培農家を育てる取り組み」とは?

園庭を眺めながらビールが飲めるカフェ。内装はほとんど格さんがDIYしたと言うからびっくり!
パンとビールを楽しむためのカフェでは、ピザやサンドイッチが提供されます。具材は地域の農家さんが作った野菜や、近くの山で猟師が捕った野生イノシシの肉。
「タルマーリー」は無肥料・無農薬の自然栽培を条件に、作付けの時点で地域の契約農家からお米や野菜を全量買い取っています。「実はお米が余っちゃってね……毎朝家で食べてますよ」と格さんは笑いますが、これが「地域内循環」を生み出す「自然栽培農家を育てる取り組み」です。
「町長を交えて、今14名の農家さんと取り組みを進めています。もともと慣行農業をしている人や、脱サラして新規就農した人もいます。今は、ビールとパンに使うライ麦を生産する人が4名、米を生産する人が1名、あとはピザで使うトマトなど色々な野菜を作る人たちです」と格さん。
「70歳の竹下逸男(たけした・いつお)さんは定年後に農業をはじめた方です。奥さんがタルマーリーの建物が保育園だったときの園長さんで、そのご縁もあって、自然栽培でのトマト作りを依頼しています。依頼した責任もあるし、地域の農家さんとは切っても切れない関係がありますよ」

農家・竹下逸男さんの野菜はピザやサンドイッチに使われています
「タルマーリー」が智頭町に来て、地域の農業は変わり始めました。少しずつ、でも確実に「地域内循環」は起きています。それも格さんの「菌本位制」に基づいて。「タルマーリー」が多くの共感を集めるのは、パンとビールの背景に確固たる“思想”があるからこそだと言えます。
今、格さんが考える「これからの農業」

個人よりも地域ぐるみで
格さんは言います。「我々のように“周りの農家さんに自然栽培でやってもらう”っていうのは、たぶん昔ながらの伝統的なやり方だと思うんです。今、農業は大変な時代になってきていますよ。加工業者も含めて、こういうやり方で地域ぐるみで生き残っていくしかない」
そして「国の農業政策が変わっていく中で、農家が個人で食べていくのは簡単ではありません。個人でやるよりは、地域に入った方が可能性も広がる。面白いなって思える地域に行くことが、とても重要だと思います」と力説します。
厳しいからチャンスもある

イノシシ肉でジビエソーセージも手作りしている格さん
格さんに若手の農家さんへアドバイスはありますか?と質問すると、次のような答えをくれました。
「農業にはチャンスもあります。これから高齢で離農する人が増えて、どんどん畑もあいていくので、若い人たちはそれを使って地域ぐるみで面白いことをやっていける。加工業者とつながってもいいし、自分で加工してもいいし」と。
「本質的には、『仕事っていうものは、時間を忘れれば忘れるほど自分が自分の時間を持てるということ』と考えてもらいたい。農家さんが時給とか言い始めると面白くないんです。
そうじゃなくて、自分はずっと遊んでるんですっていうような状況を作り上げていくっていうのが、すっごい大切です。精神論になっちゃいますけど」
さらに格さんはこうも語ります。「自分が生きていくのに必要な食べ物を作って、災害などが起こったとしても食べる物があるっていう安心感の中で勝負して、時間を自分のものとして使っていくってことが生産者や加工業者にとって重要だと思います」

放課後や休日は長女の素子ちゃん、長男の光くんもお店に来ています。運がよければファミリーに会えるかも!?
(家族写真提供:トネガワハルカ)
ところで、集客の難しい場所に立地する「タルマーリー」、今後の販売戦略として都市部に出店する計画もあるのだとか。これからの「タルマーリー」からも、目が離せません……!
写真提供:タルマーリー

























