【橋本亜友樹さん プロフィール】
 |
1978年、兵庫県生まれ。神戸大学農学部、神戸大学大学院自然科学研究科にて植物育種学を専攻。卒業後はシステムエンジニア、ITコンサルタントを経て2012年に起業。経営の傍らグロービス経営大学院に通学、2015年にMBAを取得。同年、サツマイモ事業を独立させる形で「さつまいもカンパニー株式会社」を設立し、同社の代表取締役としてサツマイモの生産やコンサルティングを行う一方、スマート農業の普及にも携わっている。 |
“日本一のさつまいもオタク”が語る、サツマイモの魅力
産業の裾野が広く、全国で栽培されている
──その名も「さつまいもカンパニー」という会社を経営されていますね。
「サツマイモの生産から流通・販売」「サツマイモに関連したコンサルティング」「サツマイモを活用したイベントの企画」などを行っています。
具体的には、島根県の契約農家と埼玉県にある自社農場で新しい品種や在来種などを試行錯誤しながら栽培したり、群馬県・吉岡町の方々と干し芋を特産品として盛り上げようと活動したり、東京ではサツマイモ好きな人のネットワーク「さつまいもアンバサダー協会」を2019年8月に立ち上げる予定です。自称「日本一のさつまいもオタク」として、NHKの情報番組「あさイチ」のサツマイモ特集「もっと大好きに!さつまいも」(2018年11月放送)で解説をさせていただいたこともあります。

埼玉県にある「さつまいもカンパニー」の自社農場
──まさにサツマイモを中心にさまざまな活動をしているのですね。サツマイモの魅力は?
サツマイモって産業の裾野が広い感じがするんです。例えばジャガイモだと、ポテトチップスみたいな圧倒的に人気の商品があって、カルビーさんや湖池屋さんといった誰でも思い浮かぶ企業がありますが、サツマイモの場合はそれがない。また、土地を選ばないため、北海道から沖縄まで日本全国で栽培されています。
食べ方だけでもいろいろあって、家庭料理のほか、焼き芋、大学芋、芋羊かん、スイートポテト、芋けんぴになったり、原料として春雨やわらび餅、焼酎にもなったりする。
植物的に品種の幅が広いのも面白い。果肉が紫、オレンジ、白、黄色といろいろな種類があって、味わいや食感が全然違って、それぞれにあったさまざまな活用方法がある。サツマイモは準完全栄養食とも言われているんですよ。
──最近ではおしゃれなスイーツのイメージもついて、サツマイモ人気は高いようです。
はやっていますね。4、5年前からブームと言われていて、焼き芋はいま第4次ブームらしいのですが、今回は結構長く続いていて、このまま定着するのではないかとみる人もいます。ブームのきっかけを作ったのが安納芋で、次にべにはるかが来て、焼き芋を中心にした消費の伸びがあった。それに加えて干し芋を食べる人も増えています。

コンサルティングをしている群馬県・吉岡町の干し芋
農学部からIT業界を経て農業界に戻ったワケ
トマトの“木”とバイオに魅せられた少年時代
──農学部を卒業後、大学院にも進んで研究されていますが、農業に興味を持ったきっかけは?
最初は祖父と一緒にやっていた家庭菜園です。いろいろな作物を作っていて、肥料や土壌改良の必要性などの話を聞いていました。その後、85年の「つくば科学万博」で水耕栽培の巨大なトマトの“木”をテレビで見て衝撃を受けました。さらに、90年に大阪で開かれた「花博」でバイオテクノロジーの世界に触れ、いつかこういうことをやりたいと思ったのがきっかけです。
また、僕が中学生の頃から環境破壊や食糧危機が叫ばれるようになっていたのですが、農業や科学を学ぶことでこうした問題を解決できるのではないかと考えて農学部に進みました。
──専門は何でしたか。
植物育種学といって、品種改良の研究ですね。僕の担当はメロンでした。食糧問題の解決にはサツマイモが一番いいと思っていたんですが、やりたいものを何でも選べるというものでもなくて(笑)。大学院でも研究を続けました。
IT業界から農業界へ
──しかし、そのまま農業の道や研究職には進まずに、IT業界に就職されたのですね。
農業を学ぶきっかけは食糧問題だったので、青年海外協力隊に参加しようと思ったこともあったのですが、ボランティアでは根本的な解決にならないのではないかという思いがありました。かといって研究も事業化しないとなかなか続いていかないし、インパクトという意味でも小さくまとまってしまう気がして。
一方で、時代的には2000年ごろからIT革命などと言われるようになっていて、インターネット技術ってすごいな、これからのビジネスはITが変えていくんじゃないかと思いました。ビジネスとして、その新しいインフラみたいなものの知識を身に着けて活用したいと思って就職しました。
──農業に戻ってきたきっかけは?
最初に就職した会社では金融のシステム開発などを6年ほどやって、転職したITコンサルティングの会社ではシステムの保守や業務改善などを4年ほど担当しました。
その頃から経営を勉強するためにビジネススクールに通っていたのですが、そこが志(こころざし)を育てるような校風で、「起業したい」「農業に関わりたい」とずっと思っていた気持ちが高まって、2012年に6次産業化を推進する会社を作りました。
1年くらいはイモ全般の通販や、農産物のオンライン直売所のアイデアを試しましたね。その後、紆余(うよ)曲折あって、事業のメインをITコンサルに方向転換したりもしたんですが、サツマイモに特化した通販サイトはずっと残していて。その部分をスピンアウト(独立)させるような形で会社にしたのが「さつまいもカンパニー」です。

有楽町のマルシェでサツマイモ菓子などを販売しているところ(2017年)
異業種から転職して感じる強み
農業は総合知識産業 全部自分でやらなくてもいい
──IT、コンサルを経てきた経験がいまに生かされている点はありますか?
ITもそうですが、コンサルティングの経験やMBA取得で学んだことが大きいと感じています。
本来、農業って農地、人、技術、販売、企画などの総合知識産業で、変化する市場の中で、高度な技術力と営業・マーケティング力、それに経営判断が求められる複雑な仕事です。いまどこに課題があるのか分析することや、複雑に絡み合った課題を解きほどく際に、これまでの経験が生きているなと思っています。
──ITっぽい話では、スマート農業にも取り組まれています。
昨年スマート農業の会社を友人たちと作りまして、レタスなどの露地栽培で実証プロジェクトを行っています。
スマート農業というとトマトやイチゴなどの施設にセンサーを置いて室温を管理したりするイメージがあるかもしれませんが、うちがやっているのは露地栽培。特に、栽培技術というより経営の部分に関わっています。
栽培の記録や出荷の計画と実績、売り上げとコストをある程度リアルタイムで把握できる仕組みを作り、それを1年ではなく1カ月とか3カ月ごとに細かく見る。そうすると、レタスなんかは三毛作くらいするので、次の期の計画に反映できて経営が安定していくんじゃないかなと。使えるツールをうまく使って、考え方をモデル化して、農業経営ができる人を育てていきたいと思っています。

長野県でスマート農業の実証を行うレタス畑
──確かに、野菜づくりは得意でも経営は苦手という方もいるでしょうね。
起業時に6次産業化を推進する会社を作ったと言いましたが、6次産業っていうのはつまり1次産業の方が、2次産業、3次産業もやるというのが主流の考え。僕も最初はいいと思っていたんですが、実際にはなかなか難しい。生産もビジネスセンスも兼ね備えた方は確かにいますが、実は結構特異な存在なんですよね。
そうでない場合、自分はどこを伸ばしていくのか。生産はできるけれど経営・販売が苦手な人は、一緒に組む相手を見つければいいと思うんですよ。逆に異業種から入る人は生産にこだわらなくても、販売などそれをサポートする部分に入っていくのも面白いかなと思います。
例えば、サツマイモだけ見ていても研究から消費までいろんな段階があって、それをつぶさに見るだけで大変です。農業って一口に言っても、いろんな農法や品種による生産方法があって十把一絡(じっぱひとから)げに語るのは難しい。農業の中でも自分の好きな分野を見つけてそれに特化するのは大事かなと思います。
将来は海外でサツマイモづくり!
──今後の展望や農業界に対して思うことはありますか。
将来的には海外で農業とその6次産業化をやりたいなと思っています。日本の農業は小規模で付加価値の高い生産物を作る農業と、大規模で量と品質の安定化を目指す農業の二極化がより進んでいくだろうと思いますが、僕はどちらかというと後者の、安定的に農産物を供給し、国民の生活や命を支える農業の方に関心がある。こっちは国内生産だけでなく輸入なども挟みながらバランスをとってやっていった方がいいと思う。
例えばレタスのような鮮度が優先される野菜は国内産がいいですが、サツマイモのような日持ちしやすい野菜は海外で確保する方法もこれからどんどん進んでいくでしょう。東南アジアだけでなく、これからはインドやアフリカにも可能性がある。日本へ輸入するだけでなく、これから経済成長する地域では、現地産業の振興のために加工や流通を含む日本式農業を輸出するという考えもある。
いまナイジェリアからのインターン生と、現地の状況などについて話をしているのですが、今度現地にも一緒に行って具体的に何ができるか見てこようと思っています。もちろんサツマイモで。
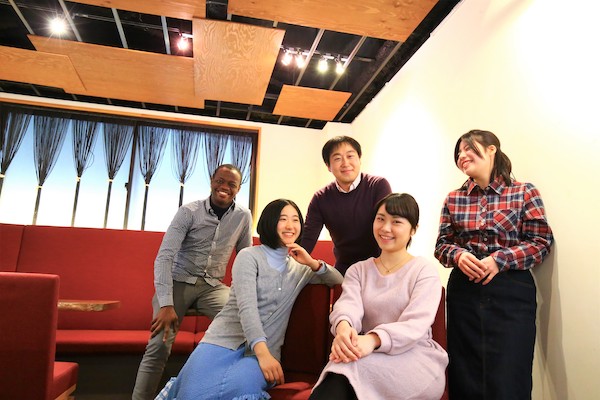
インターン生たちと

























