農作業との両立
――荻野さんは5代目だそうですね。農業を継ぐことに抵抗はなかったですか?
珍しいパターンだと思いますが、全くなかったです。周囲に聞くと、幼稚園の時から「農家になる」と言っていたみたいですから(笑)。
なりたいかどうかではなく、潜在的に「なるものだ」と思っていたのかもしれません。
中学校を卒業すると、迷わず地元の岩見沢農業高校に進学しました。その後は、実家で栽培している米、麦、大豆の栽培を学ぶために、北海道立農業大学校に進学しました。稲作関係のカリキュラムは、提携している拓殖大学北海道短期大学で集中的に学ぶことができるので、2年間で2つの学校を卒業したかたちになります。卒業後すぐに就農して、今年で5年目になります。

――進路からも一切迷いが感じられませんね。北海道アグリネットワークや4Hクラブの役員をされるきっかけは何だったのでしょう。
まず、市区町村の組織「栗山町4Hクラブ」に入りました。僕が就農したことを聞いて、近隣の先輩農家が誘って下さったんです。そこでは役職はないのですが、僕のことを面白いと感じて下さった先輩が、北海道の組織「北海道アグリネットワーク」の理事や、全国の組織「日本4Hクラブ」の役員に推薦してくださって、今に至ります。
――農作業との両立は大変ではないですか?
楽しんでやっています。栗山町4Hクラブでは地域の小学生に向けてうどん教室を開催しているのですが、先輩が教室を始めた時に僕が12歳で、最初の受講生でした。時が経って今は僕たちが運営している。何だか感慨深いです。
両立で難しい点は、集まりなどがあって家を空ける際に、家族に農作業の負担がかかってしまうことです。少なからずこうした活動に参加しない若者がいるのは、「農作業に専念して欲しい」という家族の期待があるからだと思います。
農家の息子は所属する組織が多くあります。JA青年部、地元の消防団、地域の活動……農業以外にやることが結構あるので、日本4Hクラブのような任意団体は、時間をやりくりしてでも参加したいと思える価値提供が必要だと思います。
――荻野さんはどんな点に価値を感じているのでしょう。
“繋がり”です。栗山町4Hクラブの活動が北海道に繋がり、全国の農家と繋がることができました。どれかひとつが欠けても実現しなかったことで、大きな価値を感じています。
僕はもともと、「農業だけをやっていたくない」という気持ちが強いので、特に魅力的に感じるのかもしれません。

アパレルから広げる農業の未来
――最近は農閑期を利用してアパレルショップの店員も始めたのだとか。どうしてショップ店員なんでしょう?
農家と縁遠い若者たちに農家を身近に感じてもらいたい、というのがひとつの目的です。農業以外の切り口から接点を持ちたいと思ったので、もともと関心のあったアパレルを選びました。実際に接客をして仲良くなって「普段は米や麦を作っているんだ」と話してみると、農業のこと、栗山町のこと、食べ物のこと……と話題が広がります。普段、自分の食べているものを気にしていない若者が、作物や産地に興味を持ってくれることは大きいですね。
もうひとつの目的が、服づくりの参考にしたいという思いです。
2019年11月から、地域おこし協力隊で栗山町に来ている友人と一緒に「ogiiinuts(オギーナッツ)」というファッションブランドを立ち上げました。テーマは、「農作業ができるくらい機能性が良く、そのまま街中へ出かけていきたくなるデザインを」。
今は知り合いから依頼を受けて、希望に合った無地の既製品を購入してロゴを付けて提供している段階ですが、ゆくゆくは工場と連携して生地から作りたいと思っています。
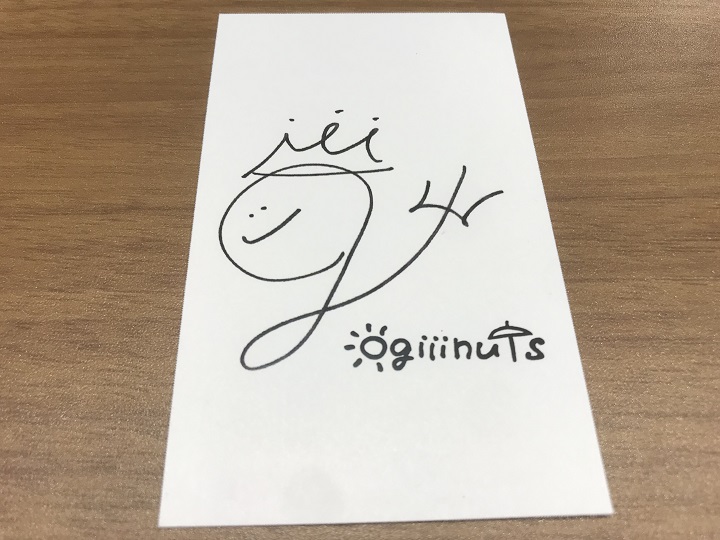
可愛らしいオギーナッツのロゴ
――そんな壮大なプランがあるんですね。ちょっと聞きにくいのですが、ご両親の反対はなかったんですか?
先に色々と進めちゃいました(笑)。購入したシャツが大量に自宅に届いたことで両親が知ることになったというか……。正直、今でも面と向かって話していません。黙認してくれていると解釈しています(笑)。
――農家の仕事をちゃんとやっているからこそ、ご両親も寛大なのかもしれませんね。でも、繁忙期になったら回らないんじゃないですか?
そうですね。繁忙期は本当に時間との勝負で、睡眠時間を削って農作業をする位なので、どうしようかなと。そう考えた時に、やはり農業経営を根本から見直したいと思っています。今は父が経営者ですが、生意気ながら非効率だと思う点もあるので。
――例えばどんなところですか?
『畑にいない=サボっている』という考えがあるからか、仕事の有無に関わらず畑に居続ける習慣があります。農家はこうあるべき、という考えを捨てて、農作業にもメリハリをつけたい。捻出した時間は服づくりや組織の活動にあてたいと思っています。
――どちらも農業や地域の活性になる活動ですね。荻野さんの農業に対する情熱を感じます。
僕を含めて農家の息子は、父という経営者の元で日々色々な葛藤を抱えています。だからこそ、自分の代になり次の代に託す時には、「農家っていいな」「こういう生き方って素敵だな」と思われる存在になりたい。そんな未来を目指して、少しずつ変えていきたいです。
――――荻野さんの挑戦、楽しみにしています!


























