材料・道具
材料

ここでは黒大豆を使用していますが、味噌はいろいろな種類の大豆で作れます
出来上がり 約2キロ
大豆(乾燥)…450グラム
米麹(こうじ)…675グラム
塩…245グラム
(塩分濃度 約12%)
※ 分量は数グラム程度なら誤差があっても大丈夫です。
分量外
アルコール度数35度以上の焼酎(殺菌用)…少量
塩…少量
道具
鍋(または圧力鍋)
ボウル
ビニール袋
ラップ
保存容器(※)
※ 保存容器は、一般家庭ではホーロー容器、プラスチック容器がよく使われます。ジッパー付き保存袋でも作れます。
味噌の作り方
1. 大豆を水で戻す
大豆(乾燥)をよく洗います。大きめのボウルを用意し、豆の約3倍量の水に浸して十分戻します。ふっくら戻るまで、冬場は18時間ほど浸水します。
2. 大豆を煮る

大豆の約1.5倍(体積)の水で、アクを取り出しながらじっくり煮ます(浸した時の水をそのままゆで汁にするのが基本です。誤って捨ててしまったら、湯冷ましで代用できます)。親指と小指でつぶれるくらいの軟らかさになるまで煮てください。
今回は薪(まき)とダッチオーブンで約5時間煮ました。大豆が硬いと失敗の原因になりますので、根気強く煮ます。煮汁約200ccを、後で使うので残しておきます。
3. 塩きり麹を作る

塩きり麹とは、塩と麹を混ぜたものです
麹をパラパラにほぐし、塩と麹を混ぜ合わせます。麹の表面にまんべんなく塩をまぶすような感じで、両手をもみ合わせるようによく擦り混ぜます。
4. 大豆をつぶす

粗熱がとれたら、大豆をビニール袋に入れます。

手のひらを使って上から強く押して豆をつぶします。粒をなくすようなつもりで、力を入れて押すのがコツ。ミンサーやマッシャー、すりこぎなどを使ってもOKです。
5. 大豆と塩きり麹を混ぜる

つぶした大豆が人肌程度に冷めたら、塩きり麹を少し加えてこねます。

よく混ざったら、さらに塩きり麹を少しずつ入れて混ぜることを数回繰り返し、全量を混ぜ合わせます。
6. 大豆の煮汁で水分調節
硬さは耳たぶ程度の軟らかさが理想です。水分が足りない場合は、とっておいた大豆の煮汁を少しづつ加え(200ccまで)、ムラなくこね上げてください。水分が多すぎるとカビの原因になります。
7. 味噌玉を作る

こねた味噌をおにぎり大の大きさで、空気を抜きながらボール状にまとめます。

8. 容器に詰める

保存容器の内側を焼酎で拭いて殺菌します。

殺菌した容器に、ボール状の味噌玉をひとつずつ詰めていきます。空気を抜くように手で押さえ込み、すき間を無くしながらすべて詰めます。
9. 表面にラップをする

味噌の表面を焼酎で殺菌します。味噌の上を覆うように少量の焼酎を注ぎ入れ、手でなでるようにして塗り広げます。

味噌が空気に触れないように、ぴっちりとラップを貼り付けます。ラップと味噌の間に空気が残らないように貼ってください。

最後に、縁に空気が入らないように、ラップの上から塩をのせていきます。
10. 約10~12カ月保管して完成

容器にふたをして、常温で約10~12カ月保管します。冬に味噌を仕込んだ場合は、暑さを越えた秋以降に食べることができます。
仕込みの時期・保管場所・カビ対策
どうして2月に味噌を仕込むの?
農家では、1月下旬から2月にかけて味噌を仕込む場合が多いです。冬に仕込むと夏のあいだに発酵熟成が進み、秋にはおいしい味噌が完成するからです。冬は気温が低く、雑菌が繁殖しにくいという理由もあります。
保管に適した場所は?
直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。麹菌は15度以下になると働かないので、冷蔵庫には入れないでください。
カビが生えてしまったら?
表面のカビは取り除いて食べましょう。
空気にふれるとカビは生えやすくなります。表面にぴっちりラップを貼り付けることが、カビを生えにくくするポイントです。味噌玉を作る時も、しっかり空気を抜きましょう。
カビが生えても失敗ではありません。おいしく食べられますので、安心してください。

大皿さんお手製の味噌おにぎり。農家さんの手作り味噌は、大豆のうまみと米麹の甘みが口いっぱいに広がる格別のおいしさです
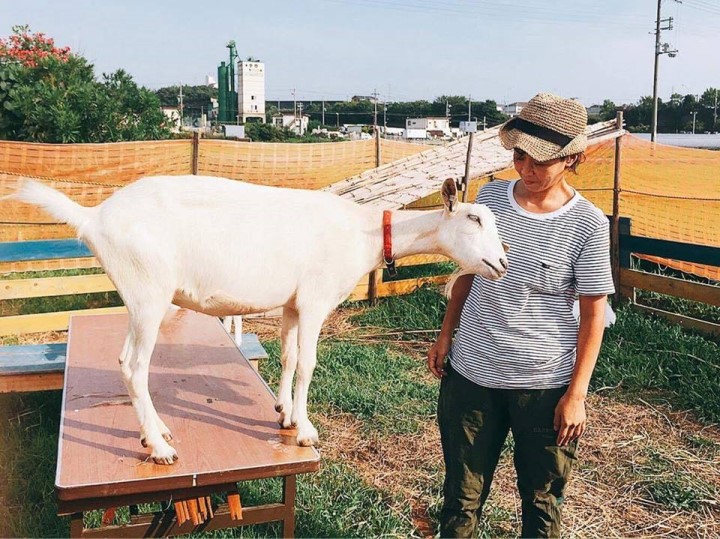 |
教えてくれた人 味噌の作り方を教えてくれたのは、神戸市にあるナチュラリズムファームの大皿純子さん。有機農法で約40種の野菜や米などを栽培しています。 |
取材協力:ナチュラリズムファーム



























