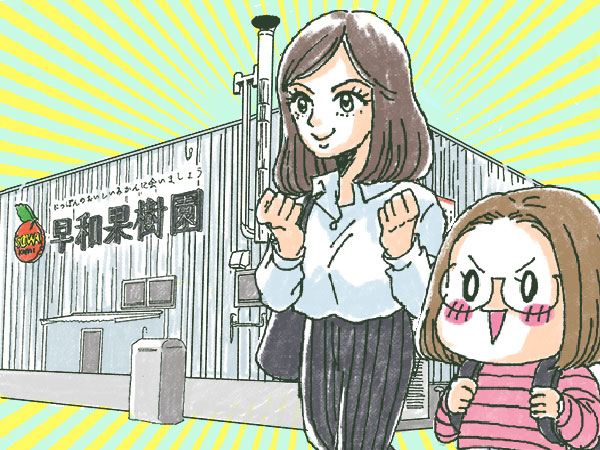紅まどんなとは?

2005年に品種登録された新しい柑橘で、一般的なミカンよりも少し大きい手のひらサイズ。濃いオレンジ色のツルンとした美しい見た目をしています。愛称となっている「紅まどんな」はJA全農えひめの登録商標で、正式な品種名を「愛媛果試28号」といいます。
愛媛県内のJAに集荷されたものの中から選果され、一定の厳しい基準を満たしたものだけが「紅まどんな」として出荷されます。ブランド管理は徹底していて、毎年収穫前にJAや市場の関係者が集まり、選果基準を確認する「選果目合わせ会」を開催して、その年の基準を決めているそう。
そんな紅まどんなの大きな魅力のひとつが「ゼリーのような」と表現される、新感覚のとろける食感です。果肉のひと粒ひと粒が一体化しているようになめらかで果汁たっぷり。
中の薄皮も極薄で食味に全く影響しないので、上品な食感を演出してくれます。甘みが強く酸味がやわらかいため、この食感と相まって、まるで高級スイーツを食べているようです。
また、愛らしい名前は愛媛県松山市を舞台とする夏目漱石の小説「坊っちゃん」のヒロインである「マドンナ」に由来すると言われています。
主な産地は?

愛媛県のオリジナル品種で、現時点(2020年5月)では愛媛県内でしか栽培が認められていません。外皮が非常に薄く繊細なため栽培が難しく、選果場ではデリケートな外皮を守るために桃と同じ選果機が使われているほど。
大変希少価値の高い果物です。
愛媛県には日本で唯一のみかん研究所があり、そこで長い年月をかけて開発されたものの一つがこの紅まどんな。そしてつい最近、「紅まどんな」と「甘平(かんぺい ※)」を掛け合わせた新しい柑橘が誕生し話題になっています。その名も「紅プリンセス」。
これから本格的に栽培がはじまり、私たちが口にできる日はまだまだ先になりそうですが、大人気の両親から生まれたサラブレッドなだけに注目が集まっています。
※ 甘平は2007年に品種登録された甘みの強い人気の高級柑橘。
旬の時期は?
旬は短く、12月上旬から中旬。最近では生産者や生産量が少しずつ増え、前後1カ月程度にも出回るようになってきましたが、それでもかなり短い期間しか楽しめない貴重な柑橘です。
もともと「12月にミカンを超えるようなギフトにもなる柑橘を作ろう!」ということから開発が始まったそうで、まさにギフト向けの品種。
豊かな香りと糖度の高さに加え、濃いオレンジ色のつるりとした外皮が見た目にも美しいことから贈答品にぴったりです。お歳暮などお世話になった大切な方への贈り物にしてみてはいかがでしょうか。
ミカンとは何が違う?

紅まどんなは「南香」と「天草」という品種を交配した、ミカンとオレンジの血を引くタンゴール(※)。それぞれのよい特徴を受け継ぎ、果汁が豊富で甘みが強く、薄皮が非常に薄くて食べやすい柑橘です。濃厚な風味と上品な香り、一度食べると忘れられない食感。
奇跡の掛け合わせによって誕生した柑橘といっても過言ではありません。ミカンとの大きな違いで唯一の弱点と言えるのは、手で皮がむきにくいことでしょうか。しかし、滴り落ちるほどジューシーな果汁がキラキラと光って美しいので、包丁で切って断面も楽しんでくださいね。
※ タンゴールとは一般的にミカンとオレンジの交配種のこと。
紅まどんなの栄養は?

ビタミンC
柑橘系フルーツといえばビタミンCというイメージがある人も多いのではないでしょうか。実際、柑橘系フルーツにはビタミンCが豊富に含まれているものが多く、紅まどんなもそのひとつであるといえます。
ビタミンCはコラーゲンのもとになったり、抗酸化作用があったりと肌や健康面で重要な栄養素です。
βクリプトキサンチン
βクリプトキサンチンは、みかんやオレンジの色の素になっているものです。強い抗酸化作用を持ち、がん予防や健康のために積極的に摂取するのがよいとされています。
必要に応じて、ビタミンAに変化して体調を整えるサポートをする栄養素です。
ペクチン
ペクチンは薄皮部分に多く含まれているため、紅まどんなを食べる際に薄皮ごと食べるのもよいでしょう。
食物繊維の一種で、コレステロールや糖尿病、動脈硬化などの防止に役立つ栄養素です。
カロテン
カロテンはみかんなど柑橘類に豊富に含まれている栄養素で、体内でビタミンAに変化します。抗酸化作用が強く、免疫力の保持や動脈硬化の防止に役立つ栄養素です。活性酸素を防ぐ役割があることから、アンチエイジングにもよいとされています。
クエン酸
クエン酸は疲れたときほど、積極的に摂取するのがおすすめの栄養素です。
疲れの素となる乳酸を体内で分解したり、全身の血流を促進したりする役割があります。血糖値が急に上がるのを抑える、胃腸の機能を促進するなど体調を整えるサポートをする役割もあります。
紅まどんなのおいしい食べ方・切り方は?

外皮が薄く、手でむくのが難しいため、包丁で切って食べるのがおすすめです。おいしく食べるコツは「スマイルカット」。
切り方をご紹介します。
1. 横半分に切る
横半分に切ることで、断面に放射状に薄皮が出て切り離しやすく、食べやすくなります。
2. 半分に切ったものをさらに4等分に
くし形に等分に切り分けます。大きめのものは5~6等分に切ってもよいでしょう。
この断面が笑った時の口の形のように見えることからスマイルカットと呼ばれています。
3. 外皮と果肉の間に切り込みを入れる
片側に切り込みを入れるとツルンと食べやすくなります。
果肉と皮の間に包丁を入れ、皮に沿って包丁を前後に動かしながら4分の3ほど切ります。包丁はまな板と平行に寝かせたままで、紅まどんなを動かすと切りやすいです。
紅まどんなの日持ちや保存方法は?
果肉を守る外皮が薄い柑橘は日持ちしないことが多いのですが、紅まどんなも例にもれずあまり長期保存には向いていません。ちょうど食べごろのものが出回っていることが多いので、手に入れたらなるべく早めに、1週間以内を目安に食べましょう。
ただし、収穫したてのものはしばらく置いておくことで酸味が減り、甘みを強く感じやすくなる傾向にあります。少し酸味があると感じた場合は2~3日置いてみるとよいでしょう。その際は、直射日光を避けて冷暗所で保存しましょう。
紅まどんなはどこで買える?

紅まどんな(愛媛果試第28号)は愛媛県のJA全農えひめ直販ショップ、楽天やAmazonなどの大手ショッピングサイト、愛媛県内であればスーパーでも購入できます。
特に、紅まどんなの多くは愛媛県内のスーパーで販売されているので、旬の時期に機会があれば足を運んでみるのもおすすめです。
また、期間限定になりますが、ふるさと納税でも取り扱っている場合があります。
よく似てる媛まどんなって?

紅まどんなにそっくりな見た目や味の「媛まどんな」というものも販売されています。
こちらは、品種としては紅まどんなと同じ愛媛果試第28号です。では、なぜ名前が異なるのかといえば「果樹園で商標を登録しているから」というのが理由となっています。
媛まどんな以外にも、同品種の商品として、愛媛まどんな、瀬戸のまどんなといったものが販売されており、紅まどんなの味を楽しむことが可能です。
ただ、紅まどんなと同じく手に入りにくく、一般的なみかんと比べて値段は高額で販売されています。
媛まどんなの果肉については、まるでゼリーのようにプルプルとしていると好評です。
オレンジを食べるときと同じく、8等分程度にカットして食べるのがおすすめされています。
南香と天草はどんなみかん?
紅まどんなの親である「南香みかん」は12月が旬で、さわやかな甘みとプチッとしっかりした肉質が特徴です。旬の時期は糖度が13度前後と甘くなり、たっぷりと果汁がふくまれてジューシーになります。
皮の厚さは温州みかんより厚めで、形も丸みがある130g前後のみかんです。
「天草みかん」は外皮も内皮も薄く、柔らかいのが特徴です。皮をむくとオレンジのような良い香りがします。
果肉は柔らかく甘味が強く、南香みかん同様にジューシーです。
美味しいみかんの選び方は?

皮のきめ
みかんの皮をチェックし、ポツポツが細かなものを選ぶのがポイントです。
みかんの皮のポツポツは「油胞」と呼ばれており、ポツポツが細かい(キメが細かい)ほど、栄養が溜まりやすい枝先になっていた実である可能性が高いといわれています。
色
自然界でなっている実は、色を濃くすることで動物の目に留まりやすくしています。動物が食べれば排泄物を通して種がさまざまな場所に芽吹き、子孫が増える可能性が高くなるからです。
おいしいみかんほど色が濃いと覚えておきましょう。
重さ
結論からいえば、重いみかんほどおいしいです。どのような果物でもそうですが、果汁が多い分、重量も重くなります。
みかんは水分が約80%を占めているフルーツなので、できるだけ重いものを選ぶのがおすすめです。
形
形についてはあまり気にする必要はありません。しいて言うならば、皮と実の間に隙間がある(皮が実から浮いている)状態のものは避けるほうが無難です。紅まどんなは皮が薄く、皮をむいて食べようとすると果汁がこぼれてしまいます。
皮が浮いているのは収穫から時間がたっている証拠であり、おいしさが落ちてしまっている状態です。
軸
みかんの軸は細いものがよりおいしいです。
みかんの軸は道管と呼ばれている水分を運ぶもの、師管と呼ばれている栄養を運ぶものがあります。軸が太いものは水分を多く含んでいますが、栄養は少ないです。逆に、軸が細いものは水分が少なく、栄養が豊富に詰まっています。
そのため、軸が細いほうがおいしく育っているみかんと判断することが可能です。
希少価値抜群の紅まどんな! 正しく扱っておいしさ最大限に
口の中でとろける新食感と極上の甘さを一度体験してしまうともう虜(とりこ)に。毎年12月が楽しみになります。
旬が短いため食べ逃しに注意。冬場の贈り物としても重宝しますので、お歳暮やクリスマスプレゼントの候補に加えてみては。
監修:日本野菜ソムリエ協会