農家の農地相続でよくあるトラブル事例2選

相続財産に農地がある場合、通常の土地と異なりさまざまなトラブルに発展する可能性があります。ここでは、農家の農地相続で発生しやすい、2つのトラブル事例を紹介します。
- 兄弟間の遺産分割トラブル
- 相続税が高くて支払えない
順番に見ていきましょう。
事例1:兄弟間の遺産分割トラブル
まずよくあるトラブルが、農家を継がない兄弟との遺産分割トラブルです。
例えば、相続予定だった農地に対して、農家を継がない兄弟が法定相続分の遺産分割を主張した場合、遺産分割協議がまとまらず手続きを進められません。
相続した農地を分割して手放すことは農業経営の悪化に直結するため、農家を継がない兄弟への分割はできれば避けたいことでしょう。
遺言書に農地の相続人が明記されていればスムーズに相続を進められますが、遺言書の相続内容が、他の兄弟の遺留分を侵害していた場合は注意が必要です。
兄弟が遺留分を侵害されたとして「遺留分侵害額の請求」を申し立てた場合、農地の分割または遺留分相当額の支払いをせざるを得ません。
遺留分相当の金銭を支払うことで農地の分割は避けられますが、このような相続トラブルは農業経営だけでなく、兄弟間の関係悪化にも影響を及ぼす可能性があります。
後味の悪い結果にならないように、相続発生前から兄弟姉妹とよく話し合っておくことが大切です。
参考文献:裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
事例2:相続税が高くて支払えない
農地の相続では、相続税が想定より高額になり、支払いが困難になるケースがあります。
特に高額になりやすいのは市街地にある農地です。市街地農地は「宅地比準方式」で相続税を評価するため、宅地と同等レベルの相続税額になる可能性があるのです。
市街地農地は、以下の宅地比準方式で評価されます。
【市街地農地の評価額=(その農地を宅地とした場合の1平方メートルあたりの金額 − 1平方メートルあたりの造成費)× 面積】
例えば、農地面積が500平方メートルで宅地とした場合の1平方メートルあたりの金額が10万円・造成費が1平方メートルあたり1万円の場合、上記の式に基づき【(10万円 − 1万円)× 500平方メートル=4500万円】となります。
農地の固定資産税は宅地と比べて安い傾向にあるため、相続税も安いと勘違いされがちですが、固定資産税と相続税の評価は全くの別物です。
農地の地域や面積によっては、かなり高額になる可能性もあるため十分注意しておきましょう。
なお、相続税の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。所有している農地の相続税を調べたい方は、あわせて参考にしてください。
参考文献:国税庁「農地の評価」
農家の相続で兄弟間の遺産分割トラブルを避ける対策方法三つ
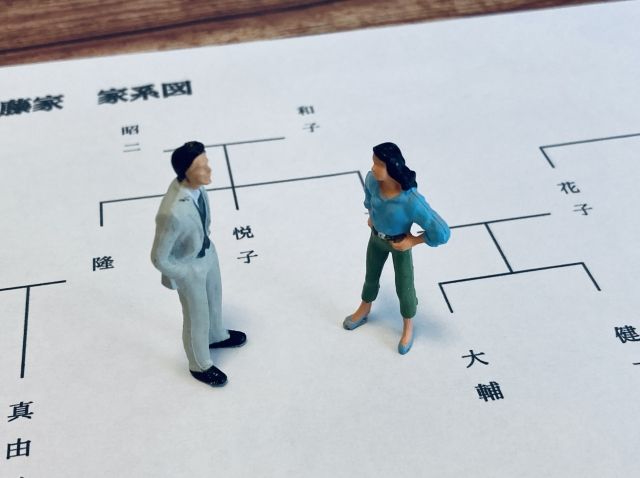
農地の相続でよくある二つのトラブル事例を見てきましたが、どちらも農家を引き継ぐにあたって大きな障害となる問題です。
それでは、兄弟間の遺産分割トラブルを避けるため、どのような対策を立てればよいのでしょうか?
- 被相続人の生前に贈与を受ける
- 相続発生前に家族の理解を得ておく
- 遺言書をのこしてもらう
順番に見ていきましょう。
被相続人の生前に贈与を受ける
兄弟間の遺産分割トラブルを避ける対策方法としてまず考えられるのは、農家である被相続人が亡くなる前に農地の贈与を受けることです。
生前贈与を受けておけば、相続発生時に改めて農地を分割することはほとんどないため、相続人間でのトラブル発生を避けられる可能性が高いでしょう。
また生前贈与を受ける場合、農家の後継者に農地を一括贈与する際に適用できる「贈与税の納税猶予制度」を利用すれば、贈与税の負担を大幅に軽減することが可能です。
この制度で猶予を受けた税額は、受贈者または贈与者のいずれかが亡くなった場合に納税が免除されるため、確実に農家を継ぐ場合は積極的に利用しましょう。
なお「贈与税の納税猶予制度」を適用するには、以下の要件を全て満たしている必要があります。
- 贈与者の推定相続人であること
- 農地取得日の年齢が18歳以上であること
- 農地取得日までに3年以上農業に従事していること
- 農地取得後、速やかに農業経営をおこなうこと
注意点として、贈与税の納税猶予を受けている期間は、税務署に対して3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。
期限内に継続届出書を提出しなかった場合、納税猶予は打ち切られ、納税猶予税額と利子税を納める必要があるため、事前に把握しておきましょう。
参考文献:
国税庁「農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例」
農林水産省「農地を生前一括贈与した場合の課税の特例」
相続発生前に家族の理解を得ておく
兄弟や家族間の関係が良好な場合は、農地の相続発生前によく話し合い、あらかじめ理解を得ておくことで、遺産分割トラブルを避けられる可能性があります。
農業はただでさえ後継者問題に悩まされている職業です。親族が代々守ってきた農地・家業を自分が引き継ぐと熱意をもって説得すれば、家族が応援してくれる可能性は高いでしょう。
できるのであれば被相続人も加えて話し合いの機会を設け、相続人全員の理解を得ておくことが大切です。
遺言書をのこしてもらう
相続発生前によく話し合い、相続人全員の理解を得ておくことはもちろん大切ですが、遺言書に農地相続の旨を明記してもらうことも重要です。
というのも、相続発生前の話し合いでは納得したものの、被相続人が亡くなった後になって、手の平を返して異議を唱えてくるケースもあり得るからです。
遺言書に農地の相続人が明記されていれば、ほとんどの場合で問題なく農地相続できるため、遺産分割トラブルを避けやすくなるでしょう。
このように、農家の相続における兄弟間の遺産分割トラブルは、被相続人の生前に対策しておくことが大切です。
すでに被相続人が亡くなっている場合には有効な解決策はなく、遺留分侵害額の請求を受けた場合には、農地の分割または遺留分相当額の支払いを余儀なくされるでしょう。
「農地を分割したうえに兄弟関係も悪化する」という最悪の結果にならないよう、相続の専門家のサポートを受けることをおすすめします。
「相続ナビ」なら自宅にいながら相続の専門家に相談や手続きを依頼することができます。
ほとんどの手続きをWeb上で完結することができるため、家事や仕事などが忙しく相続手続きにあまり時間を割けない方にもおすすめです。
登録や相談も無料ですので、まずは会員登録してみてはいかがでしょうか。
農家の相続で相続税が払えない問題の対策方法

相続した農地が市街地にある場合、相続税は宅地と同等程度、面積によっては宅地以上になることも考えられます。
農地の相続にあたって、相続税が想定より高く、支払いが難しくなってしまった場合は相続税が実質免除になる「相続税の納税猶予制度」を利用するのがおすすめです。
ここでは、相続税トラブルに有効的な納税猶予制度の概要や適用要件、手続きや期間を解説します。
相続税が実質免除になる「相続税の納税猶予制度」を利用する
「相続税の納税猶予制度」とは、被相続人から農地を引き継いだ相続人が、一定要件を満たした場合に相続税納税猶予を受けられる制度です。
相続税の納税猶予制度を適用するためには、被相続人・相続人・農地ごとに、下記の要件➀~➂のいずれかに該当している必要があります。
| 被相続人の要件 | ➀死亡の日まで農業を営んでいた者 ➁生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした者 ➂死亡の日まで特定貸付けまたは認定都市農地貸付け等をしていた者 |
| 相続人の要件 | ➀相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに農業経営を開始し、引き続き農業経営をおこなう者 ➁生前一括贈与(贈与税納税猶予)を受けた者 ➂相続税の申告期限までに特定貸付け、または認定都市農地貸付け等をおこなった者 |
| 農地の要件 | 被相続人が営農していた、または特定貸付け・認定都市農地貸付け等をおこなっていた農地で、以下のいずれかに該当する農地
➀相続により取得したもので遺産分割がされている農地 |
相続人が要件を満たしている限り相続税の納税猶予が続くため、生涯農業を続ける方であれば、実質的に「納税が免除される」と考えてよいでしょう。
参考文献:
国税庁「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」
農林水産省「農地を相続した場合の課税の特例」
相続税納税猶予の申請手続き・期間
「相続税の納税猶予制度」を適用するためには、以下の二つの手続きをおこなう必要があります。
- 相続税の申告手続き・担保の提供
- 納税猶予期間中の継続届出
まず、相続発生を知った日から10ヵ月以内に、税務署にて相続税の申告及び、納税猶予額と利子税に見合う担保の提供をおこないます。
申告の際には、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などの通常の相続税申告書類に加え、「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」などの添付書類の提出が必要です。
また、相続税の納税猶予が適用されている間は、3年ごとに継続届出書を税務署に提出し、引き続き制度を利用する旨を届け出なければなりません。
期限内に継続届出書を提出しなかった場合、納税猶予制度の適用が打ち切られ、納税猶予税額と利子税を納める必要があるため注意してください。
相続税猶予の手続きは、農地の状況や地域によって必要書類が異なり、書類の収集や作成に多くの時間を要するため、相続に関する知識のない方にとっては非常に過酷な作業となるでしょう。
そのため、税理士など相続の専門家に依頼し、手続きを代行してもらうことをおすすめします。
「相続ナビ」なら自宅にいながら無料で相談や相続の専門家に手続きを依頼することができます。
「何から始めたらいいのかわからない」「多くの書類を作成する時に間違えそう」「仕事が忙しくて手続きに時間がなかなか割けない」そのような方におすすめです。
相談は無料ですので、相続の手続きで困っている方は、まずは気軽に相談してみましょう。
参考文献:国税庁「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等」
農家をやめる場合は「相続放棄」や「農地転用」も選択肢に

相続トラブルなどによって農家の継続が難しくなった場合は、以下のような方法で活用または処分することを検討しましょう。
- 相続放棄
- 農地のまま売却・貸し出し
- 転用して活用・売却
農地は所有しているだけでも固定資産税や維持管理の手間などといったさまざまなデメリットが生じます。
特に売却の見込みや活用予定もなく、相続するメリットよりも負担が大きいケースでは、相続放棄も視野に入れるべきでしょう。
なお、農業をしない場合の農地相続や相続放棄の注意点に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はあわせて参考にしてください。
農家が農地相続する際はプロの無料相談を活用しよう
本記事では、農家の農地相続でよくあるトラブル事例やその対策方法などを解説しました。
農家の農地相続において遺産分割トラブルや相続税が高くなる問題は、農業経営だけでなく、兄弟・家族間の関係悪化にも影響を及ぼす可能性があります。
最悪の場合「農地を分割して経営が傾いたうえに家族関係も悪化する」という状況にもなりかねないため、必ず相続の専門家のサポートを受けて対策を立てておきましょう。




























