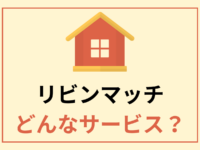いらない山林は手放そう! 相続した山林を放置するデメリット

「山林を相続したものの、売却や活用もうまくできず、使い道もないため放置している」という方は要注意です。
山林は所有しているだけで、以下のようなデメリットが生じるリスクがあります。
- 維持管理にかかる労力・コストの負担が大きい
- 土砂崩れや不法投棄などのリスクがある
- 子や孫世代まで続く負の遺産になる
長期的な放置は山林の価値をますます低下させ、処分方法の選択肢を狭めることになるため、山林放置のデメリットはしっかり把握しておきましょう。
維持管理にかかる労力・コストの負担が大きい
相続した山林を維持するためには、草刈りや清掃などの基本的な管理作業に加え、間伐や枝打ち、倒木の除去などといった専門技術を要するメンテナンスが不可欠になります。
たとえば間伐は、混みすぎた樹木をチェーンソーで伐採し、地表まで光が届くようにすることで、森林を健全な状態に維持するための作業です。間伐を怠った場合、樹木の根が十分に発達せず土砂崩れの要因となる可能性があります。
山林の管理には専門的な技術と知識が必要になり、不慣れな方が一人で行うのは大変な労力と危険が伴います。
そのため、専門業者に依頼することになりますが、山林の面積や状態によっては、依頼料がかなり高額になる可能性もある、という点に注意が必要です。
たとえば山林の伐採を依頼した場合、樹木の種類や高さにもよりますが、樹木1本あたりの費用相場は1〜2万円前後。面積の広い山林では、合計数百万〜数千万円にのぼることも考えられます。
土砂崩れや不法投棄などのリスクがある
相続した山林を放置していた場合、土砂崩れや山火事などの災害や、害獣や倒木などによる事故が発生するリスクがあります。
災害や事故が起きた際、適切な管理を怠っていた場合には管理責任を問われ、ケガ人が出た場合には、損害賠償を請求される場合もあるため、定期的な山林管理は不可欠です。
また、長く放置されて荒れた山林には、不法投棄が多発するリスクもあります。不法投棄は犯人を特定しにくく、泣き寝入りせざるを得ないケースも珍しくありません。
大量の廃棄物が不法投棄されていた場合、撤去費用はかなりの高額になることが予想され、山林の価値も低下してしまうため、所有者には非常に重いデメリットとなるでしょう。
子や孫世代まで続く負の遺産になる
山林は通常の土地と比べて不動産としての価値が低く、買い手や借り手、良い活用アイデアを見つけることは非常に困難です。
また長期的に放置していると、ただでさえ低い山林の価値がさらに低下し、買い手どころか処分も難しくなる可能性もあるでしょう。
このようなケースになると、相続した山林は、所有しているだけで大変な労力やリスクを伴う「負の遺産」となってしまいます。子や孫世代まで続く大きな負担となるため、早めに手放す方法を検討すべきでしょう。
いらない山林を手放す方法4選

山林を相続する負担やデメリットが大きい場合は、無駄な労力やコストをかけないためにも、なるべく早く手放すことを検討しましょう。
いらない山林を手放す方法には、以下四つの選択肢が挙げられます。
- 不動産会社や森林組合に売却する
- 自治体や個人・法人に寄付する
- 相続土地国庫帰属制度で国に引き渡す
- 相続時に相続放棄を行う
なお、相続放棄は相続する前にのみ選択可能です。
次からは具体的な相談先や注意点も紹介していますので、ぜひ処分する際の参考にしてください。
不動産会社や森林組合に売却する
いらない山林の処分方法として、もっとも理想的な手段は、唯一利益を得られる可能性がある“売却”です。
ただし、山林は通常の土地と比べて需要が低く、買い手を見つけるには長い時間と根気が必要になります。また、買い手が見つかったとしても、山林はもとの価値が低いため大きな利益は期待できません。たとえば、都市近郊から離れた田舎の山林は、売却相場が1平方メートルあたり100〜300円程度とされています。
とはいえ、活用せずに放置するデメリットを考えれば、利益が少なくても売却するメリットは大きいと言えるでしょう。主な売却先としては、以下のようなサービスが挙げられます。
- 不動産会社
- 買い取り業者
- 森林組合
どうせ売れないからと最初から諦めるのは機会損失です。相続した山林を処分する際は、まず上記のような売却先に相談してみましょう。
しかし、山林を買いたい人は少なく、購入を検討するにしても現地の案内に手間がかかるため、山林を取り扱う不動産会社は限られます。
そのため山林を売却する際は、リビンマッチのような不動産一括査定サイトを利用するのがおすすめです。
リビンマッチであれば、全国約1,700社の不動産会社の中から売却する不動産に適した不動産会社を紹介してもらえます。山林の売却では、まずリビンマッチを利用することをおすすめします。
⇒不動産一括査定サイト【リビンマッチ】はこちら
自治体や個人・法人に寄付する
いらない山林の買い手がなかなか見つからない場合は、無償での寄付も検討しましょう。
市区町村などの自治体や、山林を欲している個人・法人がいれば、寄付を受け入れてくれる可能性があります。主な受け入れ先としては、以下のような選択肢が挙げられます。
- 自治体
- 個人・法人
- 自治会・町内会
ただし、立地が悪い場合や活用の見込みがない場合、長く放置していた山林などは、受け入れてもらえない可能性が高いため注意してください。
相続土地国庫帰属制度で国に引き渡す
相続土地国庫帰属制度とは、一定要件を満たした土地を国に引き渡すことができる制度です。制度名に「土地」とありますが、要件さえ満たしていれば山林も引き取ってもらえます。
ただし、制度を利用できる土地や山林には、以下のように厳しい要件が付けられており、適切に管理されていない山林は受け入れてもらえない可能性が高いです。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
引用:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
また、無料で引き取ってもらえるわけではなく、一筆あたり1万4000円の審査料と、審査通過後に20万円以上の負担金が必要になります。
「国に引き取ってもらえる」という安心感はありますが、実際に利用するのは難しいケースがほとんどでしょう。
参考文献:
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
相続時に相続放棄を行う
相続開始を知った日から3カ月以内に山林の相続放棄を行えば、山林の相続手続きや大きな負担を抱えるリスクを避けられます。
相続放棄とは、相続財産に対する権利や義務責任を拒否することです。相続することによるメリットとデメリットをよく吟味し、負担のほうが大きいと感じる場合には、相続せずに放棄することをおすすめします。
ただし、相続放棄した場合はその山林だけでなく、全ての相続財産を放棄することになる点に注意が必要です。山林以外にも相続財産がある場合は、その他財産とのバランスや利益を考慮して慎重に判断しましょう。
いらない山林の相続放棄手続き方法

いらない山林を相続放棄する場合、相続開始を知った日から3カ月以内に、被相続人が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申述します。
相続放棄を申述する際に必要な書類・費用は以下のとおりです。
| 必要書類 | 取得費用 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 収入印紙代800円(申述人1人につき) |
| 連絡用の郵便切手 | 500円ほど |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 450円 |
| 相続放棄する本人の戸籍謄本 | 500円ほど |
| その他(被相続人の死亡記載のある戸籍・除籍謄本など) | 書類による |
相続放棄手続きを自分で行うと、ケースにもよりますが3000〜5000円ほどで申述可能です。弁護士や司法書士などの専門家に代行してもらう場合は、3万〜5万円ほどが相場となります。
なお、申述人の続き柄や相続順位によっては、その他にも必要な書類があるためご注意ください。
申述後、相続放棄に関する照会書が裁判所から届くため、必要事項を記入して返送してください。申述が受理されれば、数週間ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは無事完了となります。
参考文献:裁判所「相続の放棄の申述」
いらない山林を相続放棄するときのポイント・注意点
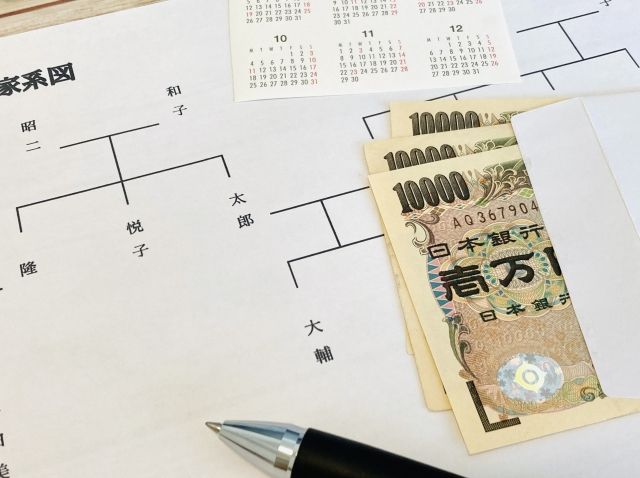
いらない山林を相続放棄する場合、全ての財産を放棄する必要があることだけでなく、以下のような点にも注意が必要です。
- 相続放棄しても管理義務は残る
- 死亡保険金などの非課税枠が使えない
- 相続放棄後に撤回はできない
相続放棄後に「相続しておけば良かった」と後悔しないように、前もって注意点を理解しておきましょう。
相続放棄しても管理義務は残る
いらない山林を相続放棄すると、次の順位の法定相続人に相続権が移ります。
常に相続人となる配偶者以外の法定相続人の順位は下記のように定められています。たとえば子が相続放棄した場合は亡くなった人の親に、その親も相続放棄した場合は亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が移転します。
| 常に | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(孫など直系卑属) |
| 第2順位 | 親(祖父母など直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) |
この際に相続人全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所を通じて相続財産管理人を選任する必要があります。
民法第940条によると「自己の財産におけるのと同一の注意義務を持って財産を保存しなければならない」とされており、相続財産管理人が選任されるまでは、相続人全員に管理義務が残るのです。
参考文献:民法第940条
死亡保険金などの非課税枠が使えない
いらない山林を相続放棄した場合、その山林だけでなく、その他の全相続財産を放棄することになりますが、相続放棄しても死亡保険金や死亡退職金の受け取りは可能です。
死亡保険金や死亡退職金を受ける際、通常では「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用され、その金額を差し引いた分にのみ相続税が課されます。
しかし、相続放棄をした人には上記の非課税枠が適用されません。死亡保険金や死亡退職金を受け取るときに、多額の相続税がかかる可能性があるため注意が必要です。
相続放棄後に撤回はできない
山林の相続放棄にあたって、家庭裁判所への申述が受理された場合、その後に相続放棄を撤回することは原則できません。
相続放棄をした後に、利益となる相続財産が見つかったとしても、一度相続放棄した人は二度と相続人に戻れないため注意してください。
相続放棄する際には、全ての相続財産をしっかり把握したうえで、山林の価値や維持管理にかかる負担を考慮して慎重に検討する必要があるのです。
とはいえ、相続や山林に関する知識を持たない方が、山林の価値を適切に判断するのは非常に困難なため、専門家による無料相談を活用しながら検討することをおすすめします。
「相続ナビ」なら自宅にいながら無料で相談や相続の専門家に手続きを依頼することができます。
「何から始めたらいいのかわからない」「多くの書類を作成する時に間違えそう」「仕事が忙しくて手続きに時間がなかなか割けない」そのような方におすすめです。
まずは無料での相談をしてみてはいかがでしょうか。
参考文献:民法第919条
いらない山林が相続放棄できない場合の使い道・活用方法

山林以外にも相続財産があって相続放棄できず、売却や寄付の見通しも立たない場合には、たとえば以下のような使い道・活用方法が考えられます。
- 農林業地として経営・貸出を行う
- キャンプ場などの行楽施設を経営する
- 太陽光発電を行う
- 趣味や私有地として活用する
山林の立地が良く、周辺地域に需要が見込まれる場合は、事業用地として活用し収益化が望める可能性があります。
しかし、相続した山林が需要の少ない田舎にある場合などは、経営できる事業は限られてしまい、失敗したときのリスクも非常に大きいため注意が必要です。
「山林を放置したくないけど、事業などのリスクは冒したくない」という場合は、収益化目的ではない、趣味や私有地としての活用方法を検討してみましょう。
たとえば、別荘や専用キャンプ場を造ったり、昆虫採取や山菜・キノコの収穫をしたりなど、ほかではできない自然を生かしたアクティビティや体験が楽しめます。
いらない山林の相続放棄はプロに相談しながら検討しよう
本記事では、いらない山林を所有するデメリットや処分方法、相続放棄の手続きやポイント、相続放棄できない場合の使い道などを解説しました。
山林の放置は、土砂崩れや不法投棄などのリスク、管理にかかる労力・金銭的負担などの大きなデメリットを伴います。
特に相続した山林が田舎にある場合は、売却や活用が困難なケースも珍しくないため、基本的には相続段階で相続放棄することをおすすめします。
⇒自宅にいながら専門家に相談するなら【相続ナビ】公式サイトはこちら
すでに相続している場合や相続放棄ができない場合は、売却や活用が選択肢になりますが、まずは売却できないか相談してみるとよいでしょう。
特に山林を売却する際は、山林の売却実績が豊富な不動産会社を見つけることが大切です。そのためには、山林の情報を入力するだけで複数の不動産会社の紹介を受けられる不動産一括査定サイトを利用するとよいでしょう。
特に リビンマッチは全国の約1,700社から紹介を受けられるため、自分の山林に合った不動産会社を紹介してもらえる可能性が高いのでおすすめです。
ぜひ、ご検討してみてください。
⇒不動産一括査定サイト【リビンマッチ】はこちら