【プロフィール】
■伊藤秀雄さん
 |
有限会社伊豆沼農産 代表取締役 1957年生まれ。75年就農。88年に伊豆沼農産を創業。養豚・水稲を中心に、ハム・ソーセージの加工、農家レストランおよび直売所の運営を行う。現在はキャンプ場なども展開し、地域の人々の協力のもと「農村産業」を実現させる活動を行う。 |
■岩佐大輝さん
 |
株式会社GRA代表取締役CEO 1977年、宮城県山元町生まれ。大学在学中に起業し、日本および海外で複数の法人のトップを務める。2011年の東日本大震災後に、大きな被害を受けた故郷山元町の復興を目的にGRAを設立。著書は『99%の絶望の中に「1%のチャンス」は実る』(ダイヤモンド社)ほか。 |
■横山拓哉
 |
株式会社マイナビ 地域活性CSV事業部 事業部長 北海道出身。国内外大手300社以上への採用支援、地域創生事業部門などで企画・サービスの立ち上げを経験。2023年4月より同事業部長就任。「農家をもっと豊かに」をテーマに、全国の農家の声に耳を傾け、奔走中。 |
規模拡大に挫折した創業期
横山:マイナビ農業の横山です。今回は第2弾ということで、伊豆沼農産にやってきました。
岩佐:我々の大先輩である伊藤さん。もともと宮城県の出身ですか。
伊藤:そうです。おやじが亡くなって18歳で家業を継ぎ、30歳の時に伊豆沼農産を始めました。創業にあたって、まずは「農業って何なんだ」と考えたんですよ。広辞苑を引いてみたら「大地に種をまいて植物を育てて、育てた植物を家畜に食べさせて家畜を育てる」と。我々はずっと「生産者」と言われてきて、モノを作るだけ。加工したり販売したりするのは農業がやることじゃなかったんですね。そういう「農業」という言葉の意味に違和感がありました。
さらに農家は自分で作ったものに対して、自分で値段をつけることができない。でも我々は誰のために供給しているのかと考えたら、「最終のお客様」なんですよ。人に対して、何を供給しているかというと「食べ物」。それで「農業を食業に変える」というコンセプトが生まれ、伊豆沼農産が始まりました。
岩佐:当時からそういう発想だったんですね。今でいう6次産業化というか。
伊藤:言葉はありませんでしたけどね。
20代の頃は規模拡大型の農業を目指しました。当時、豚30頭の一貫経営と30haの水稲受託生産組合をやっていて、それを100頭の一貫経営と受託面積を100haにする事でした。でも最終的には「経営的に難しい」という結論に達しました。水稲の場合は、例えば30haから100haにしようとしても、当時は基盤整備が追いついていなかったんですね。そうすると機械化も大きくできません。養豚に関しても、ふん尿処理にお金がかかりすぎる。そこで付加価値型という農業スタイルに切り替えることにしたんです。

挫折を経て「付加価値型農業」に転換
岩佐:30代から一気に付加価値型に。
伊藤:「30歳になったら、自分の一生の仕事を決めよう」と思っていました。当時は26歳で、まだ4年あると。その間に考えることにして、「付加価値型農業」と豚肉の加工をやろうと決めました。あとはレストランも一緒にやったんですよ。例えば豚肉を100円で売るとします。それを加工してパックに入れると300円になるわけです。それをさらに調理してお皿に乗せたら1000円になるじゃないですか。「じゃあ究極の付加価値でレストランまでやろうじゃないか」と決めたのが28歳。そこから具体的に場所やお店の規模を決めて売上計画を粛々と作り、30歳でオープンしました。
岩佐:「農家レストラン」という言葉もない時代に、それを始めたんですね。
伊藤:ただ、自分で調理をしたこともなければ、経営もやったことがありませんでした。社員として人を雇うことも全くの初めて。組織づくりから手探りでしたね。コンセプトとしては「全部うちでとれたものを使う」。野菜もおふくろが作ったものを使っていました。でも当時はバブルの時期で働き手は金の卵みたいな状態。農家の小倅(こせがれ)がやっている経営なんかに人は集まってこないですよ。シェフもなかなか見つからなくて、近くのレストランの経験者に来てもらってメニューを一緒に考えてもらったり。
岩佐:ベンチャー企業ですね。

自家製ハムも製造している。
伊藤:どうにかオープンしました。そしたら面白い人たちが集まってきたんですよね。
伊藤さんを変えた、ある編集長の言葉
伊藤:ある時、レストランに来たお客様に「ここの社長はいるか?」と言われて、出て行ったんですね。その人は、ある出版社の編集長でした。そして「あなたのやってることに協力したい」と。当時は新しい商品を作りたかったので「どなたか工場長を紹介してもらえますか?」と言ったら、えらい怒られました。「あなたは経営者なんだから、まずは経営者と会いなさい」と。
岩佐:なるほど。
伊藤:それから「伊豆沼農産が作ったものだけを使う」というコンセプトも「私たちには必要ない」と言われたんですよ。やっぱり食材が限られると、料理の3原色がそろわない時も出てきます。「もうちょっと地域に広げたらどうか」「あなたが信頼するところから仕入れたものなら、私たちも信頼できる」と言われて、ぐっと気持ちが楽になったんですよね。できないところを他の人に頼めば、自分にしかできない分野を追求できると気づきました。
岩佐:伊藤さん自身、非常に柔軟だったんですね。
伊藤:当時はものすごい葛藤がありましたよ。「うちだけではしんどいから、他所のものを入れました」では、格好がつかないじゃないですか。自分を納得させ、お客様にも理解してもらうにはどうすればいいかを考えました。それで思いついたのが「地域6次産業化」。今の農商工連携みたいなもので、地域の中でみんなで分業しようと。2006年には「新田(にった)あるものさがしの会」を立ち上げ、地域資源を探す活動も始めました。

お金をかけない情報発信こそが信頼を築く
岩佐:伊藤さんはレストランやキャンプ場なども運営していますが、どうやってお客さんを呼び込んでいったんですか。
伊藤:情報発信ですね。情報は、お金があればうまく届けられるわけではありません。逆にお金をかけない情報の方が信頼できます。一番は口コミだと思うんですよ。知り合い同士の会話が一番波及度が高いわけです。
私はテレビや新聞で取り上げてもらいやすくするため、ニュース性のある話題を常に提供するようにしています。また、官公庁が発行する広報誌の取材にもできるだけ協力してきました。お金をかけずに媒体に出ることで、逆に信頼性は高くなります。
岩佐:最初はコツコツとやってきたんですね。
伊藤:農家の場合、情報発信は控えめにする傾向があるというか、東北人ならではの性格もあるかもしれません。でもそこは自分たちの悪いところだったなと思うので、改善していこうと思っています。それから伊豆沼農産のコンセプトや理念も、パンフレットや名刺にわざとらしく書いています。
岩佐:組織としてぶれないためにも理念は必要ですよね。
伊藤:私の考える地域とは、昔の「村」ぐらいの規模。ここでいうと、登米市迫町の新田(にった)というエリアが「おらほ(私たちの)」地域です。今はその地域の中で何ができるかを考えています。地域のみなさん=高齢者。彼らは生産人口ではありません。ものづくりはうちの会社でしっかりやりますから、地域のみなさんには「会話」を通じて、ものを伝えてほしい。それによって新田が、インバウンドをはじめ都会に住んでいる方々が他ではできない経験ができる場所になります。「あのおじいちゃん、おばあちゃんに会いに行きたい」というイメージで来てもらう。そういう産業を構築していきたいと思っています。
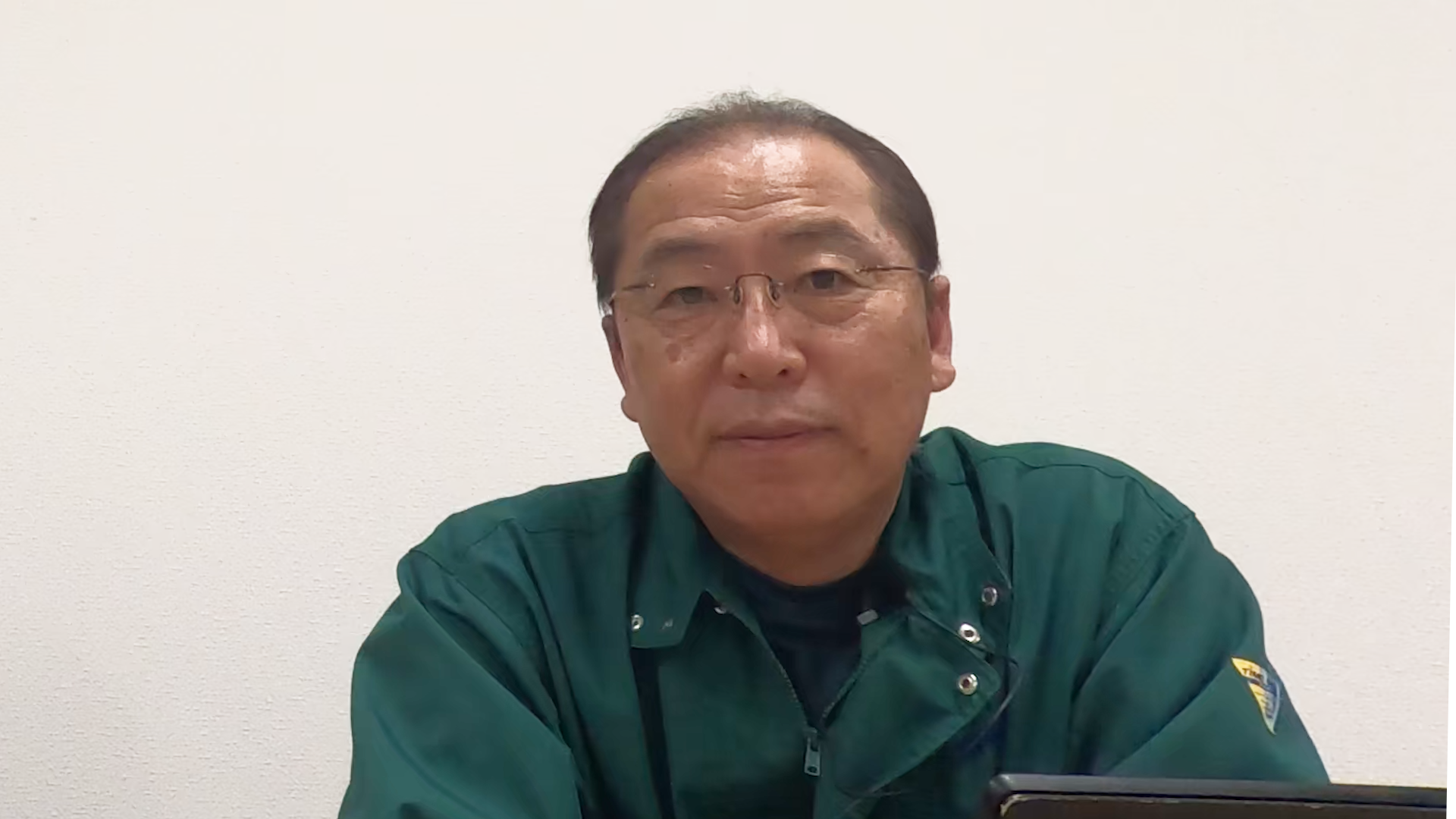
地域資源を活用し産業を創造する
岩佐:伊豆沼農産のビジネスで象徴的なものは何ですか。
伊藤:農村産業研究所ですね。農村ではどんな産業が最適なのか、何が必要とされているかを研究する部門です。創業当時から伊豆沼農産は、地域の資源を使って産業を起こし、持続可能なビジネスをしようと考えてきました。高齢者が多いこの地域で、高齢者が担い手となる産業を作れば、地域全体が面白くなるはずです。
岩佐:まさに「農村産業」をつくる部門ということですね。
伊藤:研究所では、高齢者ができる仕事は何かを考えています。例えば、高齢者は田んぼを耕すことは難しいですが、田植えの仕方を教えることはできます。都市部に住んでいる方が田植え体験をする時に、指導者になれるわけです。そういったことを引き金にしながら、どんどんお客様を招いていきたいと考えています。また「こんなこともやってみたい」という意見もあるはずなので、そういった場を提供していこうと。
岩佐:具体的にはどう提供しているんですか。
伊藤:市に「伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター」という施設があって、うちはそこの指定管理者になっています。あとは直売所にも生産会員が約100名います。人材はいっぱいいるんです。でも我々同輩が「やってください」「教えてください」とお願いしてもダメなんですよ。やっぱり地域外の「よそ者」「女性」が言ってくれた方がスムーズに事が通る(笑)。
岩佐:高齢者にとっては、自分の活躍を披露できるプラットフォームがあるのはいいですね。
伊藤:そこはまさに私がやりたい「農村産業」の取り組みの一つです。改善点もありますが、まずは組織立ててやってみる。今がそのスタートの年だと思っています。
(編集協力:三坂輝プロダクション)



























