障害者雇用、DEI推進の手立てを先進事例から学ぶ
スタディツアーは、一般社団法人日本農福連携協会が主催。千葉県いすみ市で食用菜花の栽培や販売の他、農産物加工などを農福連携で手掛けている社会福祉法人土穂会の障害福祉サービス事業所ピア宮敷(以下、ピア宮敷)が運営する圃場(ほじょう)や加工場などを巡り、参加者に農福連携による雇用創出のヒントをつかんでもらうことが目的だ。
ピア宮敷は障害を持っている人の就労支援や社会参加の機会を提供している福祉施設。2019年からは、施設利用者や特例子会社の企業に務める障害のある社員らが農業現場で活躍できる仕組みを敷いており、市内で食用菜花の栽培の他、農産物加工品の製造や販売も手掛けている。

ピア宮敷が手掛ける加工品。直営する飲食店では「ごま油」や「ハチミツ」などのラインナップが顔をそろえる
農福連携等応援コンソーシアムによる「ノウフク・アワード2022」では、新たに取り組みを開始して5年以内の団体などに贈られるフレッシュ賞を受賞するなど、障害者雇用の創出によって地域農業の活性化につなげる取り組みが評価されている。
菜花栽培のきっかけは、貸主からの思わぬ逆提案

イベント当日、大型バスに乗り込んだ参加者一行は、最初の視察先である有限会社高秀牧場へ向かった。約150頭の乳牛を飼育し、牛乳を使った加工品の製造や販売も行うなど多角的な経営を実践している同牧場。ピア宮敷では3月から9月までの間、同牧場から1.3ヘクタールの畑を借り受け、食用菜花を栽培している。主な出荷先は管内のJAで、直営の飲食店「うどん屋 どんちゃん」やJA全農のECサイト「JAタウン 」でも販売している。

緑広がる菜花畑
「もともと菜花栽培は高秀牧場さんが20年以上続けてきたことですが、人手不足のために栽培をやめたことを聞きました。一度も赤字を出したことのない品目で、非常にもったいないと考えて人手の応援を提案したところ、『忙しくて手が回らないので、あなた達でやってみないか』という話をもらったことが農福連携のきっかけです」。ピア宮敷地域支援担当の内野美佐さんは自社での菜花栽培に至った背景について、こう説明してくれた。
「場所代は要らない、トラクターも好きに使って良い」という同牧場の厚意もあって、2019年からピア宮敷による栽培がスタート。事業計画も無いまま始めたこともあり、初年度の収穫量は6.6トンにとどまったが、同牧場や近隣農家で構成される「菜花ガールズ」の助けもあって、2023年には13.6トンにまで伸ばしている。栽培初年度から、経営は黒字を推移しているといい、圃場を統括する平林大裕さんは「土の状態も今年が一番良い」と胸を張る。

ツアー当日は4人の施設利用者の他、「菜花ガールズ」の10人が収穫や箱詰めなどの作業に当たっていた。圃場見学ののち、参加者らは平林さんの案内のもと、菜花収穫作業を体験。「つぼみが膨らんでいるものを収穫し、頭から数えて15センチから18センチのところで折るように」とのレクチャーを受け、利用者らと共に汗を流した。

収穫の仕方を説明する平林さん
大塚製薬株式会社の特例子会社、はーとふる川内株式会社(徳島県)でアグリビジネス部門の所長を務める竹内淳さんは「見学を通して、特に事業として成り立っている構造が勉強になりました。作業もシンプルで初心者の方でもやりやすいのでは。弊社では水耕トマト栽培で8人の障害を持つ方を雇用していますが、今後の品目選定やマニュアル作りのヒントになりました」とうなずいた。
福祉の時間で動く事業者、作物の時間で動く農業にどう取り組む?
「うどん屋 どんちゃん」での休憩ののち、見学場所を就労継続支援B型事業所「ピア宮敷第1工房」に移した一行。ここでは近隣の農家らから寄せられた青果物を使った加工品製造の他、他社ブランド製品の製造なども請け負っており、参加者らは施設利用者の能力や特性に応じたさまざまな就労支援の様子に触れた。
施設見学後は、ピア宮敷による農福連携の取り組みなどについて、内野さんが講演。菜花栽培を始めて以来、黒字で推移している理由についても明かした。

講演する内野さん
「私たちは福祉の時間で動いていますが、農業は作物の時間で動いている点が難しかった。そこで、一部の職員と『菜花ガールズ』が朝9時から収穫を行い、9時半ごろに利用者さんたちが畑の一画にたまった菜花の出荷作業に当たるようにしました。職員の工夫や利用者の成長もあり、当初一日10箱くらいだった出荷量は昨年、1日に40箱ほど出せるようになりました」と、奏功した理由を振り返る。
「利用者さんと一緒に汗をかくことで信頼関係の構築にもつながる」と内野さん。「農福連携をはじめた当初は、農家と障害福祉のつながりのことだと思っていましたが、実際にはさまざまな人たちが関わっています。これからは社会的責任の他、社員のメンタルヘルスという面でも着目されるのではないか」と強調した。
その後、内野さんと対談したサステナブル・ビジネス情報誌「オルタナ」の編集長で株式会社オルタナ代表取締役の森摂(もり・せつ)さんは「さまざまなステークホルダーと共同で自社事業を発展させていき、社会課題を解決していくという、まさに私たちがやっていることと共通項がある取り組み」と評した。
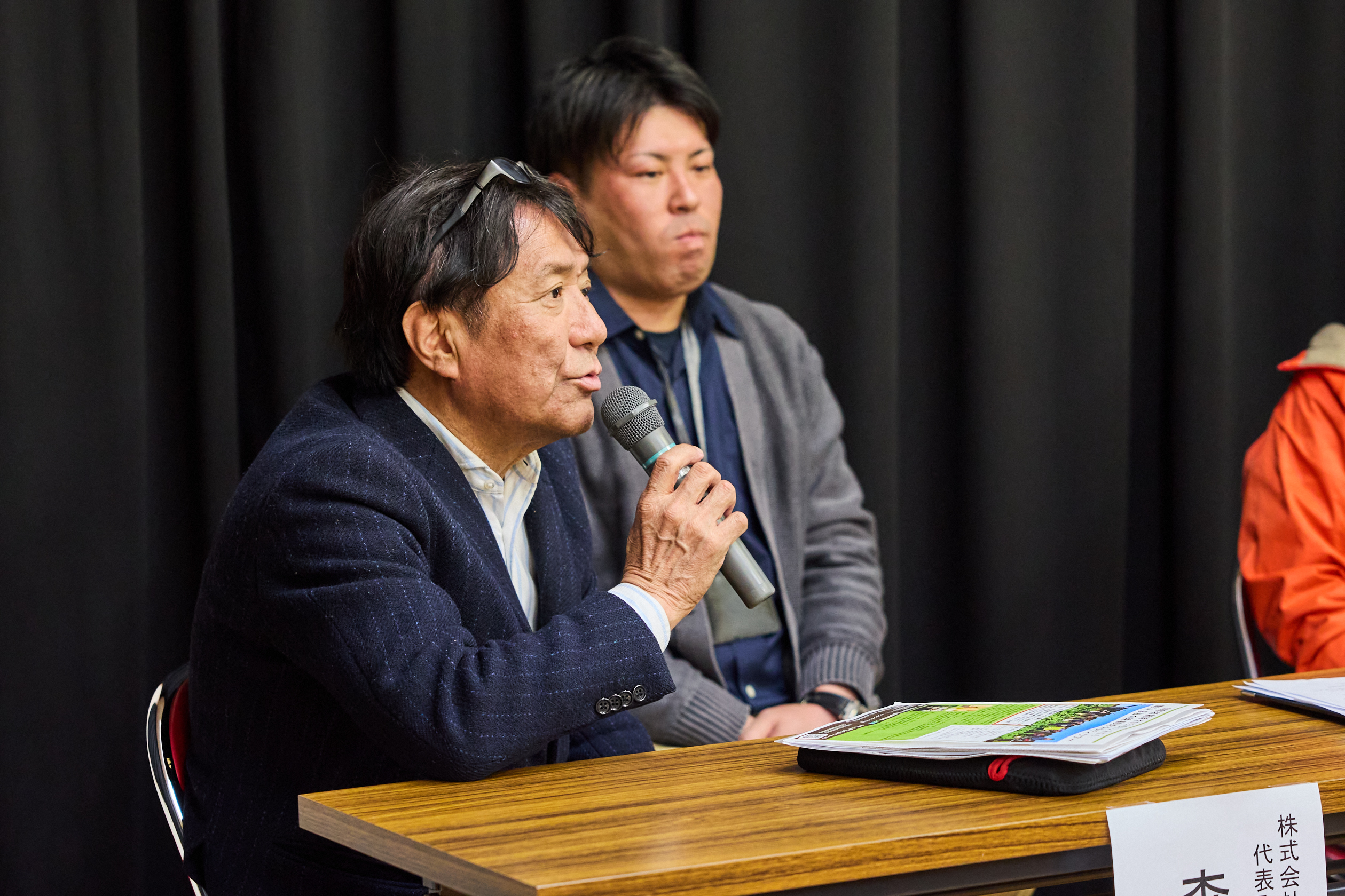
森摂さん
農福連携の課題と打開策は
最後に、参加メンバーが5人のチームに分かれてワークショップを行った。テーマは「農福連携の可能性と課題」についてだ。農業や障碍者雇用を取り巻く課題の他、本日の体験に基づいて、自社でどのようにDEIやサスティナビリティ推進につなげる余地があるかなどについて議論。代表者がそれぞれ、見解を述べた。

グループの意見をまとめる長岡さん
グループの意見を発表した、農林中金ビジネスアシスト(東京都)常務取締役の長岡正記さんは「企業と福祉の連携や、障害に対する理解が課題として挙げられます。企業、自治体間で議論の場を作ることの他、特に年配の方などから障害に対する理解を得る働き掛けもしなくてはいけない。また、農福連携の収益性だけを見ると、なかなか踏み込みにくい場合もあるでしょう。収益性を上げるためにも、ピア宮敷さんのように付加価値を創出する取り組みが求められるのでは」と総括した。
イベントを終え、NPO法人しんせい(東京都)理事の小針丈幸さんは「菜花ガールズのような、地域の資源を活用している点や、利用者が地域と関わってもらう機会を創出している点が特に参考になりました。我々は東日本大震災の避難民のうち、障害のある方を支援しており、2020年頃から農福連携に取り組んでいます。今後は体験プログラムの提供などを通して障害者理解にもつなげていきたいです」と、今後の取り組みへのヒントを得た様子だった。
取材協力
社会福祉法人 土穂会
千葉県いすみ市岩熊138-10
本イベントに関する問い合わせ
一般社団法人日本農福連携協会
東京都千代田区麹町3丁目5−5 サンデンビル 6階B室

























