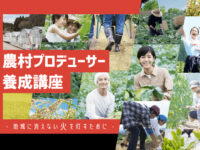【プロフィール】
■濱田健司さん
 |
一般社団法人日本農福連携協会 顧問 / 東海大学 教授 障害者・生活困窮者・高齢者等が地域の農林水産業などに従事することで地域を活性化する農福連携の取り組みについての研究が専門。 |
■北村浩彦さん
 |
一般社団法人こうち絆ファーム 代表 大阪府出身。高知県にIターンし就農。障害のある親子の雇用を機に農福連携に取り組む。2020年、就労継続支援B型の事業所を立ち上げ。地域と連携しながら障害者だけでなく生きづらさを抱えた人たちの自立支援に取り組む。就農当時は10アールだった自身の農場は、現在33アールに拡大している。 |
■小松淳さん
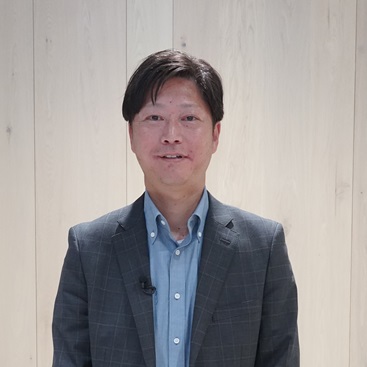 |
JA高知県 営農販売事業本部 営農企画課 課長 農繁期の人手不足解消のため2003(平成15)年に無料職業紹介所を開設。農家と障害のある労働者をつなぐ。18年に安芸市、県、福祉機関、JAで安芸市農福連携研究会を発足。農福連携の理解を深めるべく、事例や体験談などの情報交換を定期的に行っている。 |
■蒲原弥華さん
 |
子ども・福祉政策部 障害保健支援課 主幹 障害のある人が活用できるさまざまな事業や制度の取り組みを担当。高知県では農業部局と福祉部局が協力して農福連携を進めている。 |
■動画を見る
地域全体で農福連携を発展させる
濱田:今日は、農福連携のその先。JAや社会福祉協議会や企業も入って、地域全体で農福連携を発展させている取り組みを紹介できればと思います。就労継続支援の事業所を運営する北村さんから自己紹介をお願いします。
北村:自分は大阪府出身で25年、食品会社に勤めていました。「農業をやってみたい」と思い、13年前に高知県にIターンし、ナス農家になりました。「官民が連携した農福連携を」という流れから、2019年に一般社団法人こうち絆ファームを設立し、翌年に就労継続支援B型事業所を開設 しました。障害者だけでなく、高齢者、法に触れる行いをした人 なども受け入れ、いろんな人と一緒に農福連携に取り組んでいます。
小松:JA高知県の小松です。農繁期の人手不足にJAとして「できることはないか」と、2013年に無料職業紹介所を開設し、労働力のあっせんをしてきました。そこで障害のある人もいる中で、JAとしては定着支援も行っていました。2003年に安芸市農福連携研究会を立ち上げ。JA・行政・農家さんとで議論をしながら農福連携を推進してきました。私は現在、県下全域でこの広がりを持とうと試行錯誤しています。
濱田:JA高知県は、農福連携に取り組むJAの先駆け。農業サイド、福祉サイド、JAさんも動く中、高知県としてもいろいろな動きが出ていますね。
蒲原:県では農業部局と福祉部局が一緒になって、農福連携に取り組んでいます。私は障害保健支援課に所属し、2年前から担当しています。県では、地域課題や特性を生かした農福連携の取り組みが進んでいます。
失敗をためらっては人・組織の成長はない
濱田:北村さんはなぜ、さまざまな人たちを受け入れるようになったのですか。
北村:そもそも県の職員さんからの問い掛けがあったんですよ。「北村さん、困った人が居たら、どうします?」「助けたいよね」「じゃあ一緒にやりましょう」って。そこで障害がある人を受け入れたことが農福連携のきっかけ。ただ、人が増えるにつれて自分たちだけでは難しくなり、同じように障害者を雇用する農家が3軒集まり、事業所を立ち上げ、職員を雇って、見てもらうようになりました。
濱田:最初、障害のある人を雇うときに「作業効率が落ちるのでは?」などの心配はありませんでしたか?
北村:福祉に関しては全くの素人でしたが、結局は「人と人」。感覚的に教えたりしていました。けれど専門知識もあったほうが良いと考え、JAに雇用されているサポーターから、支援の仕方は学びました。こちらの負担は少なく、とても助かりましたね。
小松:JAではもともとサポーターが居たわけではありません。私が無料職業紹介所の担当だった頃に農福連携のサポートの仕方に悩んでいたんです。そこで当時、安芸で行われた農福連携サミットに、サポートに関心のある参加者が居たことから、お声掛けしました。その人は農業に関する知識や技術は無かったため、現場で学んでもらうところから。やり方が分かっていないと、障害者へも教えられないので。
濱田:新しい取り組みには、大抵の場合、二の足を踏みそうですが。

小松:最初は反対されましたよ(笑)。けれど「やってみないと分からないでしょ」と。
濱田:「失敗しそうだから」と言ってやらなかったら、人間の成長も組織の成長も無いですよね。北村さんもノウハウが無いところから始めましたし。こうち絆ファームでは、どのくらいの公的な福祉サービス(支援)を受けながら就労されている障害者がいるのですか。
北村:利用者さんの登録は今60名ぐらいです。
濱田:さらにかつてのその利用者の中から農家さんのところへ一般就労を果たしていますね。要するに農家さんのところでの障害者雇用に繋がっている。その数は4、50軒に上っていますね。雇われる先が農家であって、農業法人でないところも特徴的ですよね。
小松:JAも無料職業紹介所としてマッチングしていますが、農家さんと障害者との直接雇用契約はどうしてもハードルが高くなってくるんですよね。サポーターの役目が大きい。県下の出荷場では、40名雇用してもらっていますが。
濱田:JAさんで40名の雇用は日本でもトップクラスだと思います。
農業と福祉をつなぐ行政の役割
濱田:行政の立場からは、サポーターや雇用について、どのように見ていますか。
蒲原:私もサポーターさんとは頻繁に関わっています。本当にきめ細やかな支援をされていて。なかなか他に無い制度なので、他の地域の人からは「うちの地域にも居てほしい」というお声もたくさん聞きます。ただ現状は、実際にそういう人が居るか、どこで雇用するかがなかなか難しいと思います。
濱田:JAさんが雇用していること自体がすごいことですからね。本当は、他でもまねしてくれるとうれしいですけれど。一方で、雇用型ではなく作業受委託型では高知県はどんな取り組みをされていますか。
蒲原:高知県でも農福連携の取り組みは年々増えていますが、その多くが作業受委託型です。就労継続支援の事業所に通い、作物の袋詰めや、ビニールハウスでの作業などです。作業受委託型であれば、事業所の支援員さんが作業の指導をしてくれたりもしますので、比較的取り組みやすいと思いますし、今後も増えてくるかなと考えています。ただし単純なマッチングでは継続していきませんので、コーディネートする役割の人が重要だと思います。そのため県では現在、県内の3カ所(中部・東部・西部)に「農福連携促進コーディネーター」 を配置しています。農業者と福祉事業所の両方のニーズを聞き取り、具体的な作業を決める際のコーディネートをしていただいています。こうち絆ファームさんには、東部地域を担当していただいています。
生きづらさを抱える人たちを取り残さない支援

北村:農福連携の相談を受けていると、他の地域の課題も聞こえてきますよね。高齢化なども農福連携で解決できることもあります。農作業が社会的役割になり、生きがいづくりや、介護の予防につながるケースがどんどん出てきています。
濱田:農的な活動によって、例えば高齢者の健康づくりや孤立を防ぐことにもつながってくるということでしょうか。
北村:高知市の隣にある、いの町で、去年から高齢者のデイサービスやデイケア(※1)で、野菜の袋詰め作業をやってもらう取り組みが始まっています。認知機能の進行の緩和につながったりして、本当にびっくりしますね。みんなが元気になりますね。
濱田:他にはいかがでしょう。
北村:最近は引きこもりの事例も多く出てきてます。例えば30年引きこもっていた人が出てきて、最初は言葉も発しませんでしたが半年後には笑い出したり、数年後には冗談を言い出したりするんですよね。2年前からは臨時の職員になりました。他にも法に触れてしまった人についても、法務省とも連携しながら受け入れを進めています。
濱田:断るということはないのですか。
北村:断りませんね。そもそも安芸市では自立支援協議会の下部組織として就労支援専門部会を2017年に発足 して「断らない支援」を全面に押し出しています。
濱田:困ってる人なら、例えば生活保護受給者や生活困窮者も受け入れていくわけですね。
北村:はい。ワンストップの相談窓口ですね。社会福祉協議会やハローワーク、法テラス(※2)、不動産屋さんまでネットワークでつながっています。
※1 デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)。利用者が施設に通い、自立した日常生活を送れるように支援を受けるサービス。デイケアではリハビリテーションが中心となる。
※2 法テラスは、日本司法支援センターの通称。国により設立された法的トラブルを解決するための総合案内所。

農業だけにとどまらない、さまざまな地域課題と福祉の連携
濱田:農業以外の、林業や水産業などの話も来たりしますか。
北村:どんどん広がってますね。「林福連携」「水福連携」、また商店街の活性化を目的とする「農福商連携」「農福商工連携」などもあります。高校生・大学生も参加してワークショップで「地域の強み・弱み・追い風・向かい風」を話し合い、こうち絆ファームの前で「軽トラマルシェ 」というイベントも開いています。マルシェでは中学生のボランティアさんが「安芸地域では農業と福祉で連携をしながら頑張っています」とプレゼンテーションをします。中学校に募集をお願いして、手を挙げてもらった生徒ですね。
濱田:教育的な連携まで生まれているのですね。連携では、お寺さんとの「仏福連携」などの事例も出てきていますよね。
北村:「農福連携は地域づくり」として、安芸地域では広がっています。
濱田:「農業と福祉の課題を解決する」ということよりも先に進み、「町をつくっていく」ということに取り組んでいるのですね。個人や団体が“点”として活動するのではなく、線や面としてつながって、一体になっている。それまであったいくつもの銀河が混ざり合い、新しい“銀河”ができていますよね。“安芸銀河”が。更に他の組織にも、そのマインドなどを持ち帰ってもらいたいと思いますよね。
小松:必ず新しい銀河ができます。他の地域では、まだ小さい組織もあります。けれど困っている人に対して「構ってあげたい」「何かしてあげたい」という人たちの集まりなので、みんな同じ方向を見ています。JAでも同じ。縦割りにせず、横のつながりを広げることで、風通しの良い職場になり、地域づくりにもつながっていく。みんな「高知県は1つの家族だ」みたいなことを言いますけれど、ある意味で本当の話です。

農福連携の広がりとこれから
濱田:最後に、今後どうしていきたいかなどをお一人ずつお願いします。
蒲原:県内では農福連携の支援組織である「農福連携支援会議」が増えていて、34市町村のうち13地域21市町村 にあります。各支援会議が情報共有などができる横のつながりを持てるように、県全体で取り組んでいきます。現在は、活動報告や交流の場として「農福連携支援調整会議 」を年に1回開催しています。まずはこの会議を充実させたいですね。
小松:高知県でも農家や耕地面積が減っています。「どうしたら働きやすいか」「楽しく暮らしていけるか」「地域を守り活性化できるか」を考える中で、農福連携や林福連携・水福連携などがかみ合ってくると思います。すると、農福連携という言葉も将来的に無くなるかもしれません。
濱田:福祉制度が進んでいるといわれるスウェーデンでは、福祉という言葉はほとんど使われない そうです。日本もそうなっていくと良いですよね。障害の有無ではなく、同じ地域で社会をつくっていく対等な仲間として。「一人は万人のために、万人は一人のために」 。それはJAの理念につながりますよね。また、私は将来的には障害のある人が自分で出資、経営、労働をするモデルが増えてほしいと思っています。
小松:独立して、会社をつくるという可能性は十分にありますね。
北村:2022年には、こうち絆ファームの福祉事業所で働いていた人が独立就農した例もあります。「これまでは僕が助けてもらった。今度は僕が『助ける』という役割を果たしたい」と。今は10アールですが、来期は規模を倍にします。肥培管理や経営まで伝えて、農林課につなぐ。その後もほったらかしではダメなので、市にあるANA(安芸ナスアソシエーション) という新規就農のグループにつないでるんですよ。私もANAに入っていますし、そういう体制が整ってるから独立しやすいのだと思いますね。他にも独立就農を目指す人は居ます。
濱田:すごいことですよね。法に触れてしまった人なども、そうやって就農していく可能性もあるかもしれない。
北村:ありますね。特に出所者は帰る場所も無い人も多い。その中で、地域に必要とされるとなれば、きっとすごく活躍してくれますよね。地域の活性化にもつながる。生きづらさを抱えている人には、いろんな特性の人が居ます。屋外作業が好きな人も居れば、屋内作業が好きな人も居る。営業が好きだったり、人と何かをやることが好きな人も居ます。いろいろな場が用意されると、より多様な人が地域の中に入っていけますよね。
濱田:農福連携を起点に、いろいろな生きづらさを抱えた人たちと町をつくっていく。私も期待して、ワクワクしております。

(編集協力:三坂輝プロダクション)