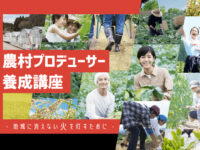闘病生活中に経営を思案。95%だった市場出荷をゼロに
2015年から「うつみ農園」の3代目として、生産から配達、缶詰やアイスなどの加工食品の開発、キッチンカーの導入、イチゴ狩りと八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍をしている内海彰雄さん。畑もハウスも住宅地に囲まれた所にあり、すぐ近くに国道が走っている。

「さっきまでスタッフとキッチンカーのメニュー作りの会議をしていたんです」と内海さん。スタッフは女性が中心で、加工や販売を担ってくれているという。
内海さんは大学を卒業後、「売り方を知らなければこれからの農家は続けられない」と考えて商社に入社。営業職を9年間経験した。売るものこそ違うが、商社ではポリシープライスを伝えられる営業能力を身に着けたと振り返る。退職後は、滋賀県近江八幡(おうみはちまん)市にある農業大学校で、興味のあったトマトやキュウリ、イチゴの栽培を学んだそうだ。
「農業大学校まで、距離が60キロほどあるんですが、サラリーマン生活で体力が落ちていたこともあり、体作りのために片道2時間半掛けて自転車で通っていました」
ところが、2014年3月に卒業が決まり、さあ農業を本格的に開始しようというタイミングで、内海さんに病魔が襲いかかる。
詳しくは差し控えるが、5月には5年生存率50%、7時間に及ぶ大手術を経験したという。しかし、内海さんは闘病中も農業経営のイメージを描きながら勉強を重ねたと、当時を振り返る。
「たぶん、体力作りをしてきたお陰で人より回復力があったので助かったなあと思っています」
手術した翌年には晴れて、「うつみ農園」の3代目としてのスタートを切った。これからどんな農業のカタチにしていけばいいか、このとき既に、大枠の構想は固まっていたようだ。ハウスを増やし、トラクターも新調したそうだ。
先代の父が経営していた当時は、95%を京都の卸売市場へ出荷していたが、内海さんは自分で価格を決められる販売方法にチェンジしていった。
「今は卸売市場への出荷はゼロです。百貨店や大手スーパーに価格を伝えて出荷をしているので販売価格を上げることができました。今後は直接お客さんに販売する機会を増やしていきたいです」
加工品・キッチンカーのテーマは「規格外を材料に」
「うつみ農園」の畑は自宅のすぐ近くにあり、キッチンカーで販売するメニューを作る工房や箱詰めなどを行う作業場も自宅内にある。山科の農地はハウスと露地を合わせて4反あり、キャベツなどの大物野菜が多くなる冬場は更に1反を借りる。そこで年間約60品目から70品目もの野菜をそれぞれの気候に合わせて栽培し、ハウスではイチゴ、トマト、キュウリをメインに、京野菜の代表的な九条ネギ、山科ナスなども栽培している。また、滋賀県守山市にある6反の圃場(ほじょう)で水稲も栽培しており、協力農家からも仕入れた米の販売も行っている。
内海さんには、農業を始めた時から大切にしていることがある、”畑が食卓に近づくこと”だ。採れたて野菜の宅配、キッチンカーでのイベント出店、共同マルシェの開催などを積極的に行うことでお客さんと直接接する機会を増やし、イチゴや米の収穫祭、出張イチゴ狩りなどを行なうことで消費者と農家の距離を縮めている。
「キッチンカー、加工品のテーマは、規格外の野菜や果物を使用することをテーマにしています」

キッチンカー付きフードトラックでイベント出店
キッチンカーの愛称は”うつみファームボックス”だ。調理スタッフとメニュー開発をし、少量多品目を栽培している農家であるからこそできる多彩なメニューを生み出している。自社の米を使用した米粉のチェロス、アイスに使用しているメロンもイチゴもうつみ農園が生産したものである。
「冬場でもフルーツがたっぷり入ったアイスは人気なんです」
キッチンカーは農園のファンづくりにも貢献している。

キッチンカーの人気メニュー。材料は「うつみ農園」で生産
オリジナル加工品も、規格外野菜を無駄にしないための手段だ。ビーガンやアレルギーに配慮したオリジナル缶詰は、日本各地のさまざまな生産者と連携しながら、高付加価値なメイド・イン・ジャパンの商品を製造・販売しているブランド「カンナチュール」との共同開発で誕生した。トマトを約70パーセント使用したトマトカレーペースト、ナスを使用した「タプナード」(南仏・プロヴァンス発祥のオリーブペースト)、ナスと、大豆ミートを使ったヘルシーキーマカレーなどがある。どれも料理用途が多く、調味料としても使用できる普通の缶詰とは一味もふた味も違うものである。

イチゴジャム作りの様子
「缶詰商品は、フードロスを農家から発信するということを意識しています。僕らも規格外の野菜をちゃんとお金に変えていくことができるので事業継続につながります。製造に関しては農福連携をやっており、加工の作業だけでなく、最近はキュウリの袋詰めなども手伝っていただいています。外注化することで慢性的な人手不足が少しでも解消できればと思っています」
更に農業と福祉を連携させられるよう、京都府の協力の元、マニュアルづくりも進めているそうだ。
加工品のラインナップにはアイスもあり、自家製のメロンとイチゴの豆乳アイスを作っている。また「京都・本くず氷」とのコラボ商品として吉野本葛を使用したトマト、イチゴのアイスキャンディーがある。内海さんは他にも加工品の構想があるそうだ。
「今後は漬物を考えています。少し前まではこの辺りの農家に行けば漬物を買えたんです。農家はぬか床を持っていて、おばあちゃんが軒先で販売していました。食品衛生法の関係で今は販売できなくなったんですが、端境期に野菜が売れる仕組みを作りたいので、検討しているところです」
これも規格外野菜を使用でき、農家と消費者が身近になることができる加工品である。

その日に収穫した野菜が入っている販売している自動販売機
「うつみ農園」の敷地には、野菜の自動販売機がずらりと並んでいる。バス停のすぐ近くにある便利さもあり、昼過ぎには売り切れていることも多いそうだ。お昼過ぎに取材に伺ったのだが、ほとんどの野菜が完売していた。
こうした販売方法の改革もあり、先代のときに比べて売上は5倍に増加したそうだ。
消費地と生産地が一緒である強みを生かし、スーパーに行く前に立ち寄ってもらえる場所作りへ
農業を始めて10年、今後は売り場環境を整えていく計画を立てている。
「野菜の自動販売機を設置している場所で野菜、自社の加工品だとかを販売できる仕組みを作っていく計画を立てています。消費地と生産地が一緒なのが強みだと思っているのでスーパーとかに行く前にお立ち寄りいただけるような場所にしたいと思っています。お米も野菜もフルーツもそろっているのと、なおかつキッチンカーがあるので、飲食店で出すようなスイーツも提供できます」
うつみ農園発のミニ道の駅というイメージだそうだ。”まちと農業の関係をあたためる”という「うつみ農園」の理念は、今後、農業を残していけるようにという思いも込めての理念である。”まちと農業の関係”が今後、どれだけ密になっていくのか楽しみである。