動画で見る
大手企業との取引で個人農家の域を超える
舞台ファームは、2003年に針生さんが設立しました。野菜やコメの生産・販売の他、カット野菜などの加工品の製造・販売、農業経営に関するコンサルティングなども行っています。
針生さんは、江戸時代から続く農家の15代目として家業を継ぎました。もともと売上3000万円ほどの個人農家でしたが、法人化して大手企業と取引をすることによって、規模を拡大してきました。
転機となったのは、2003年から始まったセブンーイレブン・ジャパンとの取引。生産したレタスを加熱用カット野菜として納品し始めました。個人農家だった針生さんにとって、年中無休で食材を安定供給することは大きなプレッシャーだったそう。「でも、それができなければ個人農家の域を超えられないと思っていました。不可能を可能にする努力こそ最大のエンジン。利益を生み出すためには、できないことでもやらないと」と振り返ります。

国内最大級のカントリーエレベーターを設立
その後、約7億円の初期投資をして自社工場を設立。2014年には、生食用カット野菜も直接納品するようになりました。
2025年3月現在、舞台ファームの売上高は約61億円に上ります。「5年以内での200億~300億円を目指して、一気に成長していきたい」と針生さんは語ります。
ハード面だけではなく、ソフト面の組織づくりにも力を入れています。社員が働きやすく、意欲的に業務に取り組めるよう、2025年には福利厚生の一環として「お米配布プロジェクト」を始めました。希望者は毎月アンケートフォームを通じて申し込めば、2キログラムのコメを受け取ることができる制度です。
この仕組みには二つの目的があります。一つは、社員が自社の食材に触れる機会を提供すること。もう一つはアンケートを通じて社員の声に耳を傾け、経営陣や事業担当者に届けること。これまでに実施したアンケートでは「より働きやすくなるためのアイデア」「カットサラダの新商品アイディア」などを募集しました。社員の意見が今後の職場環境や、商品の企画に反映される、参加型の福利厚生です。
不可能への挑戦の原動力は夢
いつも前向きに取り組んできた針生さんですが、最もつらかったのは、東日本大震災で被災した頃でした。何十年も掛けて積み上げてきたものが一瞬で失われ、借金も膨らみました。しかし「だからこそ、もっと大きなことをやらなきゃいけない」と針生さんは決意します。
針生さんを農業高校の頃から知り、社員でもある加藤さんは、「みんなの前で『俺はもう駄目だ』という姿を見たことがありません」と言います。「津波で何もかも流されて、電気も止まってしまいました。でも、冷蔵庫にある食材が腐るともったいないからと言って、すぐに炊き出しを始めたんです」
農業を始めた頃から「日本一の農家になる」という夢を抱き、「日本の農業を変えたい」「ビジネスモデルをつくりたい」と考えていた針生さん。夢とは、「過去」の実績を「現在」と掛け算して、やるべきことを決めることだと言います。「夢や浪漫がないと、不可能への挑戦はできません。お金をもうけて社会に循環させていくために、絶対に頑張らなきゃいけないと思っていました」
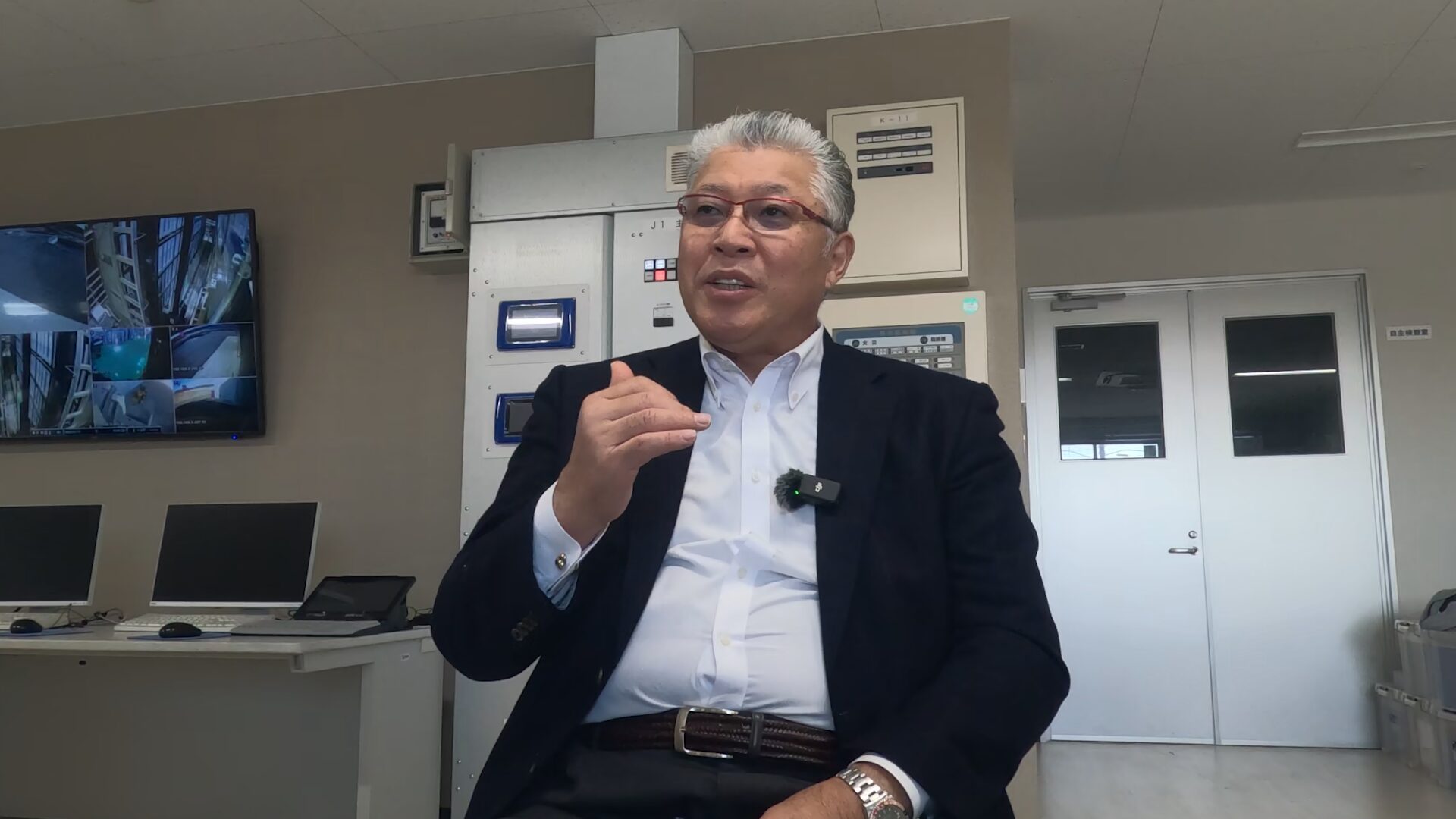
「食卓イノベーション」で更なる成長を
舞台ファームの今後の成長戦略となるのが「食卓イノベーション」。農業のDXにより、イノベーションを起こしていく考え方です。2021年10月には、総工費約34億円を掛けて、次世代型植物工場「美里グリーンベース」を竣工しました。建屋の広さは約5ヘクタールで、1年を通じてレタスを生産しています。
「10年後には人型ロボットもしくは無人型の機械が食料を作る時代が始まる」という針生さん。今後は作り方や面積の大小ではなく、エネルギー・食料・ロボットのバランスをどう経営に組み込んでいけるかが重要だと言います。
美里グリーンベースでは、育苗から栽培まで自動化されており、定植作業などはロボットが行います。更に、土地面積を最大限に活用する独自のシステムにより、露地栽培の約80倍もの生産効率を実現しました。土耕栽培と水耕栽培を掛け合わせた生産方法で、自然栽培や有機栽培に近い環境を用意し、根張りが良くなることで高品質のレタスを生産できます。

1日4〜5万株のレタスを生産する美里グリーンベース
規模を大きくしていくことを前提に考えて行動できることが、舞台ファームの強みだという針生さん。そのため、営業とマーケティングや、採用と育成など、一つの領域に特化するのではなく、複数を組み合わせて強靭(きょうじん)な一つの組織につくり上げていくことを重視していると言います。今後も「農業以外の業界の皆さんから学び、それを農業業界に応用していきたい」と、針生さんは言います。
ビジネスモデルを日本全国に広げたい
最後に、針生さんに今後の展望を聞きました。
「日本は、誰かが強いリーダーシップで象徴的なビジネスモデルをけん引していっても、その情報が開示されないと思うんです。日本の農業がしっかりもうかって、消費者である国民の皆さんにとってもコストパフォーマンスの高いものを作る。そのためには、ビジネスとしての成功モデルを全国に広げていかなければいけません。誰かがもうかっていれば良いのではなくて、成功例を日本全国に広げていく。だから私たちは日本農業の課題解決を目指す“アグリソリューションプロジェクト”を展開していきたいと思っています」
(編集協力:三坂輝プロダクション)
























