■横浜市場センター株式会社プロフィール
 |
神奈川県横浜市に本社を構える横浜丸中グループ。横浜市中央卸売市場の指定卸売会社である横浜丸中青果株式会社が産地で集荷した青果物を販売することを目的として2000年に設立。市場から仕入れた青果物を、首都圏を中心とした全国の量販店・コンビニ・外食・中食・総菜工場などに販売するほか、近年は、産地と直接契約し、出荷全量を販売に結び付ける「畑まるごと買い」にも力を入れる。 |
インバウンドの影響を受けるコンビニ業界
-相澤さんの部署では主にどのようなところ向けに青果物を扱っているのでしょうか。
私が属している部署ではコンビニ向けに青果物を卸しています。ただ、ひとまとめにコンビニ向けといっても、店内にそのまま置かれる青果物と惣菜や弁当に使われる青果物では取り扱い部署が変わってきます。その中で、私が担当しているのは、店頭に置かれる青果物になります。
この違いは、私の部署では、コンビニと直接取引を行い納品をしていますが、もう一方の惣菜や弁当に使われる青果物を取り扱う部署では、デイリーメーカー(ベンダー)と呼ばれる惣菜や弁当を作る工場と取引を行い、デイリーメーカーがコンビニと取引を行っています。コンビニ各社が工場を運営している訳ではなく、各社ごとに連携しているデイリーメーカーがある形です。
-青果物というとスーパーをはじめとした量販店のイメージが強いですが、コンビニで青果物を買う需要は増えているのでしょうか。
皆さんも想像するように、コンビニは青果物を買う場所という認識が世の中的にも薄いです。スーパーだと、肉、魚、野菜、調味料といった家で料理する材料がワンストップでそろいますが、コンビニだとそうはいきません。買ってすぐに食べることのできるサラダや弁当がメインになってきます。
ただ、そうは言っても、ミニトマトのように一定数の需要がある野菜はあります。更に、弊社の場合は取り扱うコンビニが約1万店舗と多いので、1店舗当たり2~3個納品でも1万店舗へ納品となるとかなりのボリュームになります。
-主に、どんな人からの需要があるのでしょうか。
都内のホテルに併設しているようなコンビニやインバウンド需要のある観光地のコンビニでは、ホテルでそのまま食べられるような果物や野菜、カットフルーツの売れ行きが好調です。購入しているのは、ほとんどが旅行などで来日した外国人になります。
例えばイチゴでは、価格帯が6粒1600円と、スーパーなどと比べて高単価ですが、コンビニで購入できる手軽さもあってか、かなりの数が売れています。こういった時代の流れや需要の変容もあり、半年前から弊社で納品しているイチゴのパッケージを英語に変えました。

筆者が某コンビニで買ったカットフルーツ
コンビニ業界で扱われてきた青果物、求めている青果物
-ここからは業界で扱われる青果物について伺いたいと思います。現在の取り扱い品目上位にはどのようなものがあるのでしょうか。
現在、私が扱っている品目は約60種類あるのですが、一番多いのがミニトマトです。売上で言うと全体の約30%を占めています。その次にキュウリやジャガイモ、タマネギ、ニンジンが続くようなイメージです。
あとは、果物の取り扱い量がここ1年でかなり増えています。具体的には、そのまま食べることのできるイチゴやシャインマスカット。あとは、カットされたメロンやスイカ、カキ、ナシといった旬の果物が売れている現状です。
弊社だけでなく、他社からもカットフルーツと呼ばれる商品が、コンビニ各店へ多く納品されているかと思います。
-コンビニで扱われるものには、果物はそのまま食べられることやすぐ食べることのできるカット済みが特徴として挙げられるかと思いますが、野菜では、どのような特徴を持つものが扱われるのでしょうか。
キュウリやジャガイモ、タマネギ、ニンジンといった品目は、スーパーなどで販売されているものとさほど変わりありません。ただ、一番取り扱い数量が多いミニトマトの場合は、スーパーと違ってヘタが付いてない商品が好まれます。
一般的に、スーパーなどではヘタが付いている方が新鮮だと感じられて売れ行きが良い傾向にあります。それに比べて、コンビニで取り扱うミニトマトは、その場ですぐに食べるという需要が強いため、ゴミが出ずにそのまま食べることのできるヘタ無しが選ばれる傾向にあります。

写真は一般的なミニトマトになるが近年はヘタが取れやすい品種もある
生産者から寄せられた質問をぶつけてみた
-ここからは、あらかじめ生産者から募った質問に回答いただきたいと思います。まずは、コンビニ関係に出荷する場合の最低出荷量について教えてください。
一定の規模があった方が話を進めやすいのは確かですが、コンビニでも店舗を絞った限定販売という売り方も可能なので、物が良くて味もおいしくて是非やりたいと思える商品でしたら少量で話をすることは可能です。そこから、売れ行きを見て増やしていくなどの展開も狙えるかと思います。
コンビニでは、一定価格の安定商品しかやらないというイメージを持つ人がいらっしゃるかもしれませんが、意外とそうではありません。ただ、スーパーと比べたら売れる回転のスピードが遅いので、納品周期など事前の話し合いが必要にはなります。
-これまで取引に至った生産者と至らなかった生産者。取引してみたけど続かなかった生産者が居るかと思います。その原因について教えてください。
やっぱり、信頼関係ですね。どうしても青果物は、夏ごろなど品質が悪くなる時期があります。そういった時、「バレないかもしれないから、とにかく出してみよう」という生産者さんでは、いざ届いたとしても出荷できない、納品までに時間が無いため新しい物を集める対応ができないといった負の循環が生まれてしまいます。
それならば、「畑見て貰っても良いが、物が出せないんです」と、正直に申告してくれる生産者さんの方が、私どもとしても安心します。早めに言っていただければ対応できる場合もありますので。
-生産者に求めるスキルや知識はありますか。
生産者が物流についての理解があると取引につながりやすいなと思います。
どうしても取り扱う上でネックになってくるのが物流。私どもで言うと、農作物を横浜までどのように鮮度を保ってお送りいただけるかです。話がまとまり、これから売っていこうとなった後に、鮮度良く運べる物流会社をこれから探すというのではいけません。そう簡単に見つかるものではないためです。
地方から荷物を運ぶ時に重要になってくるのが地域の物流会社です。私たちも既存の物流会社などを含め、一緒に探しはするのですが、生産者の方で普段から近辺の物流会社とつながりを作っていたり、農協と関係を築いていて市場便を使えたりする環境を持っていて、商談の時点で運べるとなると、取引に至るケースが増えてくると思います。
物流会社も、少量よりもまとめて運びたいので、そういった意味では生産規模や物量があると運んで貰いやすく有利にはなりますよね。
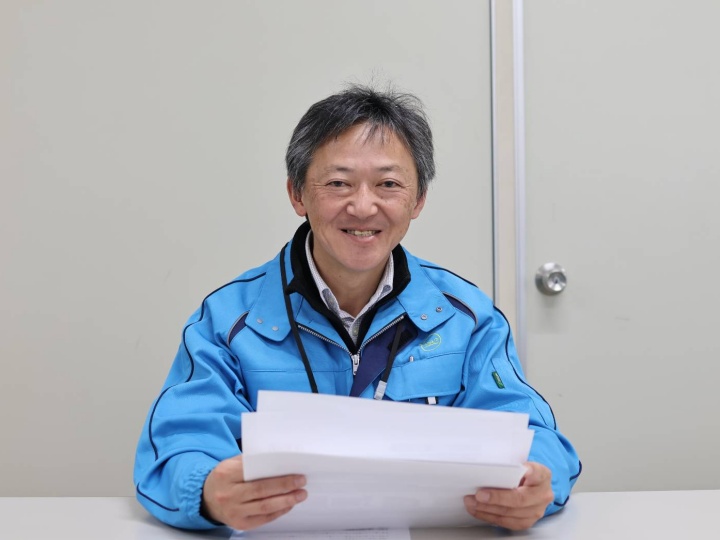
取材時の相澤さん
今後のスーパーマーケット業界は
-最後に今後予想される業界の動きについて教えてください。
これまで、コンビニで青果物を買う人は少なく、ごく一部のニーズとなっていました。
しかし、少子高齢化が進む日本において、24時間営業で徒歩圏内で野菜が買えるコンビニは、スーパーに足を運ぶことが難しい高齢者にとって非常に重要な存在です。移動が難しい人々にとって、いつでもどこでも必要な食材が手に入る環境はある意味、ガス、電気、水道のように生活インフラとして不可欠なのではないでしょうか。コンビニ側とも宅配なども含め、そこに対応していかないといけないという話も出ています。
長期的には、コンビニで青果物が買える環境は今以上に需要が増えると思っています。
取材協力
横浜丸中グループ
横浜市場センター株式会社




























