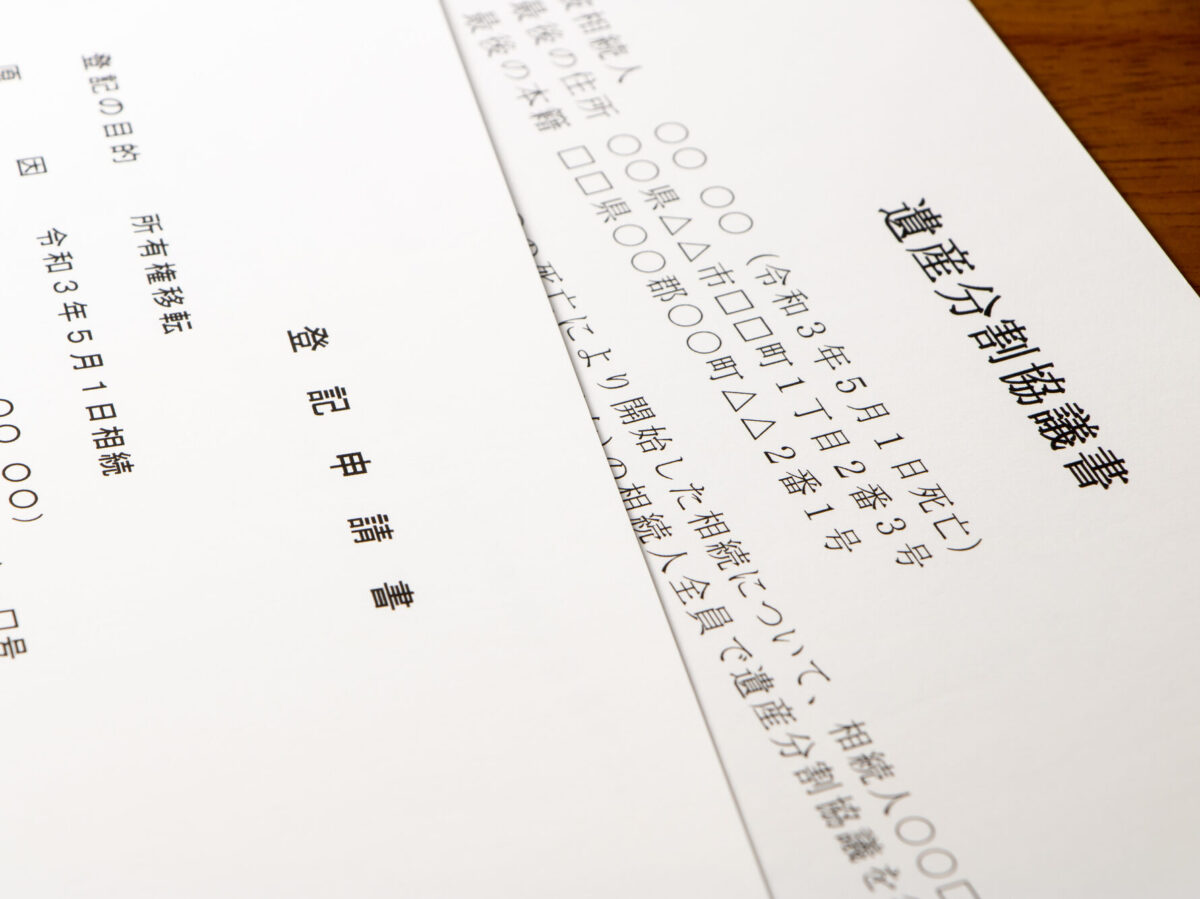農業にほとんどノータッチだった兄弟からの遺産相続の要求

都市近郊で農業をしていた父がこのほど、預貯金と自宅のほか、所有する2カ所の農地(計約50アール)を遺して急逝しました。まだ60歳になったばかりとあって遺言の類はありません。どのように遺産分割を進めるべきか悩んでいます。
父の家族は、長女である私のほかに、自宅に住む母、県外に住む次男と次女の計4人がいます。長女の私は実家の近くで専業主婦として夫と子どもと暮らしています。ゆくゆくは父の土地で農業をしたいと考えていたため、たまに母と一緒に農業や事務の手伝いをしてきました。
次男、次女は共に他県で生活しており、実家に顔を出すのは盆や正月くらいでした。
私は母と一緒に農業を続けていきたいと考えているのですが、次男と次女が現行民法の相続分に従って6分の1の農地をそれぞれ渡すか、農地を売却して、相続分相当の金額を支払ってほしい旨を求めています。
個人的には、金銭の支払いはもとより、生産能力が下がってしまうため農地の分割も避けたいところです。何より父の農業にほとんどノータッチだった2人のこうした主張に承服しかねる気持ちもあります。
こうしたケースの場合、どのように遺産を分割するものなのでしょうか。
弁護士の見解
A ご兄弟の請求を拒否することは難しいものと言えるため、ご兄弟及びお母様と具体的な遺産の分割の方法について協議する必要があります。
相続の原則ついて
遺言書が存在しない場合、遺産は、民法に定められた相続人の範囲や順位、それぞれの相続分に従って相続されるのが原則となります。民法の規定に基づくと、ご質問いただいた事例では、亡くなられた方はご質問者様のお父様であり、ご質問者様のほかにご存命のご家族としてお母様とご兄弟2名がいらっしゃるという事になります。従って、相続人は、ご質問者様、お母様、ご兄弟2名の合計4人であることとなり、それぞれの相続分は、お母様が2分の1、ご質問者様とご兄弟がそれぞれ6分の1という事になります。
従って、ご質問いただいた事例において民法の原則に従うと、遺産である預貯金及び自宅の不動産並びに2カ所の農地全てについて、お母様が2分の1、ご質問者様及びご兄弟が6分の1ずつ相続することになり、自宅及び農地は相続人全員の共有となることとなります。
遺産の分割の協議又は審判
遺言が存在しない場合、相続分による相続と異なる形で遺産を分割するためには、相続人全員で遺産の分割に関する協議又は審判を行うしかありません。遺産の分割に関する協議の方法としては、相続人だけで協議する方法と家庭裁判所において調停委員などの中立的な第三者を加えて協議する調停という方法の2種類の方法があります。どちらの方法においても、相続人の全員の合意がなければ具体的に遺産を分割することはできません。相続人間で協議がまとまらない場合、調停を申し立てた上で家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。この場合、最終的には裁判官(家事審判官)が具体的な遺産の分割の方法について判断することとなります。裁判官による遺産の分割の方法としてはいくつかの方法ありますが、ご質問いただいた事例における農地の具体的な分割として裁判官が採用する可能性が高い方法は、農地を現実に分割してそれぞれの相続分に応じて取得させるという方法又はご質問者様が農地を取得して、ご兄弟に一定の金銭を支払うという方法のどちらかであると考えられます。従って、審判による分割の場合において、ご質問者様のご希望に沿う方法で裁判官が遺産を分割するという判断を行う可能性は、残念ながら、低いものと考えられます。
以上を踏まえると、結論的には、ご兄弟が農地の取得又は農地の相続分に相当する金銭の取得を希望している以上、それをご質問者様が拒否することは極めて難しいものと考えられます。
現実的な対応としては、ご兄弟を説得し、ご質問者様(及びお母様)が農地の全てを取得する一方、ご兄弟に対して、遺産である預貯金を多めに渡す又は遺産とは別に金銭を支払うとなどの条件を提示した上で、ご兄弟に農地の取得を諦めてもらう形での遺産分割協議を成立させるというのが最も実現可能性のある対応であると考えられます。
遺言書がある場合
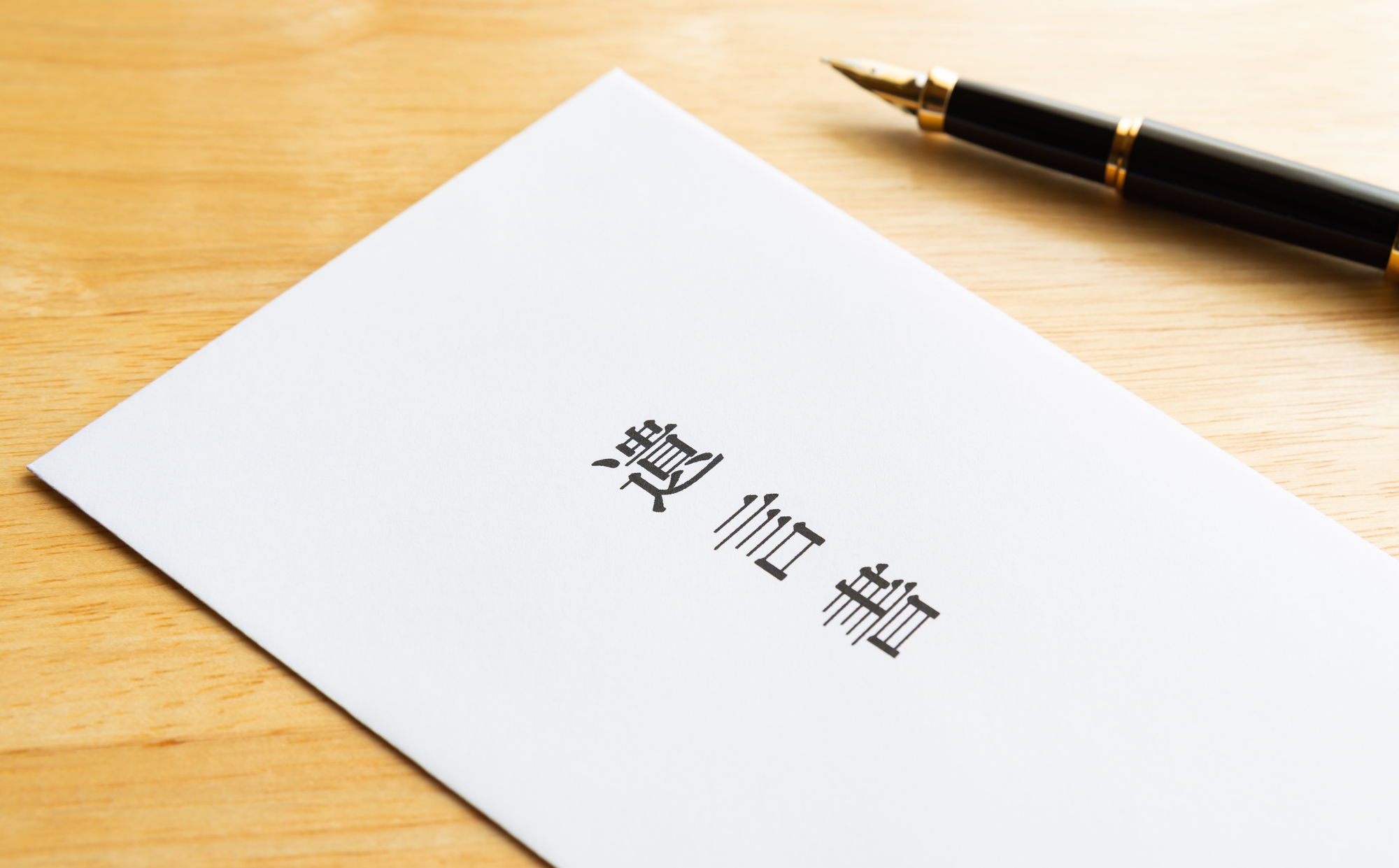
仮に、ご質問いただいた事例において、遺言書が存在していた場合において、その遺言にご質問者様一人に農地の全てを相続させると記載されていたときは、ご質問者様は遺言に基づいて農地全てを一人で相続することができます。もっとも、民法は、それぞれの相続人に対して最低限相続できる遺産の割合(これを遺留分といいます。)を定めています。従って、この場合でもそのような遺言がご兄弟の遺留分を侵害するときは、ご質問者様がご兄弟に対して、遺留分に相当する金銭を支払わなければなりません。
まとめ
上記の通り、相続となった場合において、特定の人物に特定の財産を相続させないようにすることは難しい場合が多いものと言えます。従って、相続により農地がきちんと農業を引き継ぐ方に相続されるように、生前において遺言書の作成や生前贈与などの手法を検討しておくことが重要であると言えます。
本事案のポイントを整理
✅遺言がない限り、遺産は相続分に従って相続され、共有となる。
✅相続分と異なる形で遺産の分割を行うためには、遺産の分割の協議又は審判を行う必要がある。
✅遺言書がある場合には、特定の財産を特定の人物に相続させないことができる。ただし、遺留分に相当する金銭を支払わなければならない可能性がある。
✅本人が納得しない限り、同人に特定の遺産を所得させないことは極めて難しいため、特定の遺産を特定の人物に相続させたい場合、生前から準備を行うことが必要である。
弁護士プロフィール
杉本隼与
2003年早稲田大学法学部卒業。2006年に旧司法試験合格(第61期)
2016年東京理科大学イノベーション研究科知的財産戦略専攻卒業 知的財産修士(MIP)
同年に銀座パートナーズ法律事務所を開設し、現在に至る。
銀座パートナーズ法律事務所