相続しても、ヨメはもらえません!?

義両親と長年同居し家業に尽くしてきた。それにもかかわらず、いざ相続となると「嫁には相続権がない」と告げられる。このような話は、決して珍しいことではありません。民法では、相続人は配偶者および子供、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹とされています。つまり、義理の娘である嫁には原則として法定相続権がないのです。
家族の一員として支え合ってきたという事実だけでは、法律の壁を越えることはできません。こうした現実を知っておくことが、相続トラブルを未然に防ぐ第一歩と言えるでしょう。
「介護したら相続できる」は半分正解。ただし条件は厳しい
「嫁として20年間も義父母を介護した。それなら当然、財産の一部はもらえるはず」と考える人は少なくありません。確かに令和元年の民法改正により、法定相続人でなくても「特別寄与料」として相続を得ることがようやく認められました。しかし、寄与分を得るには他の相続人すべての合意か、家庭裁判所での調停・審判が必要です。
調停には労力と費用が必要ですし、寄与を認めてもらうための証明となる資料や証言が必要と、認定のハードルは高いものとなっています。遺言書に書いてもらえれば良いのですが、そもそも遺言書を書く人は全体の10%未満と低い割合。感情的な主張だけでは、法的には通用しないのが現実です。
実家に住んでいたのに「出ていって」と言われる現実

相続にまつわるシナリオで最も怖いのは、実家に同居していた人たちが相続後に住む場所を失うケースです。例えば3人兄弟で、長男家族が両親と同居していたとします。実家と土地を長男が相続したいと考えても、法定相続分に従えば、兄弟それぞれが3分の1ずつの権利を持つことになります。その結果、「自宅評価額のうち2/3分を現金で払ってほしい」と他の兄弟から請求されることに。長男に貯金があればいいのですが、支払い能力がなければ「家を売って現金で分けよう」という話になるのは当然の流れです。高齢になってから、突然住み慣れた家を手放し、引っ越しを余儀なくされる―そんな事態も現実に起こっているのです。
分けにくく、売れにくい。田舎の不動産が残すもの

預金や有価証券といったきっちり分けられる財産に対して、自宅・農地・山林などの不動産は簡単に分けることができません。さらに現金化しようとしても特に田舎の場合は「売れない」という問題が起こることもしばしばあります。
管理が必要な空き家を相続してしまうと、定期的な風通しや倒壊防止のための補修など、多くの手間と費用がかかります。農地の場合は草刈りでさらに頻繁に通わなくてはならない場合も。遠方に住んでいればとても自分だけでは対処できず、費用を払って委託する必要がでてきます。
加えて、以下のような問題もよく見られます。
● 先代名義から名義変更されていない
● 土地の境界が不明確で売却できない
● 農地法による利用制限がある
これらは資産というより、むしろ「負動産(ふどうさん)」とも揶揄されるほど、自らの首を絞める可能性があります。相続しても使えない、売れない、管理ばかりが増える土地が残るリスクを忘れてはいけません。
相続放棄という選択肢と、その注意点
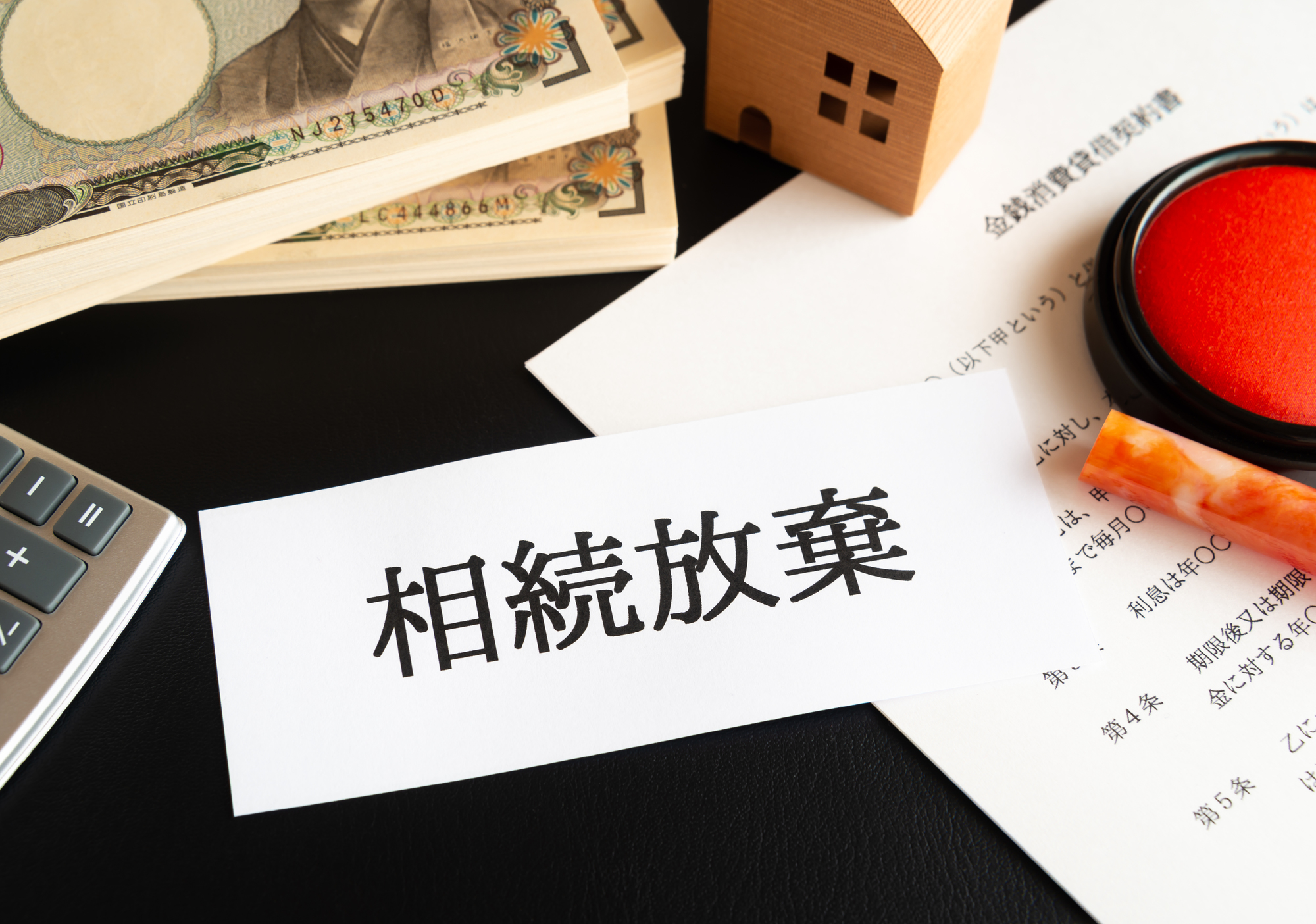
相続財産が明らかに価値のない土地や空き家である場合、「相続放棄」を検討するのも一つの方法です。家庭裁判所に申述し、認められれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。ただし、相続開始から3か月以内に手続きが必要なため、迅速な決断が求められます。放棄の判断は慎重に行うべきですが、放棄するほうが合理的な場合もあるという点は、頭に入れておきたいところです。特に、相続した空き家が「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がることも。家を持つことが、逆に家計を圧迫するリスクも存在します。
対策は早いうちに。避けてはいけない「相続の話」
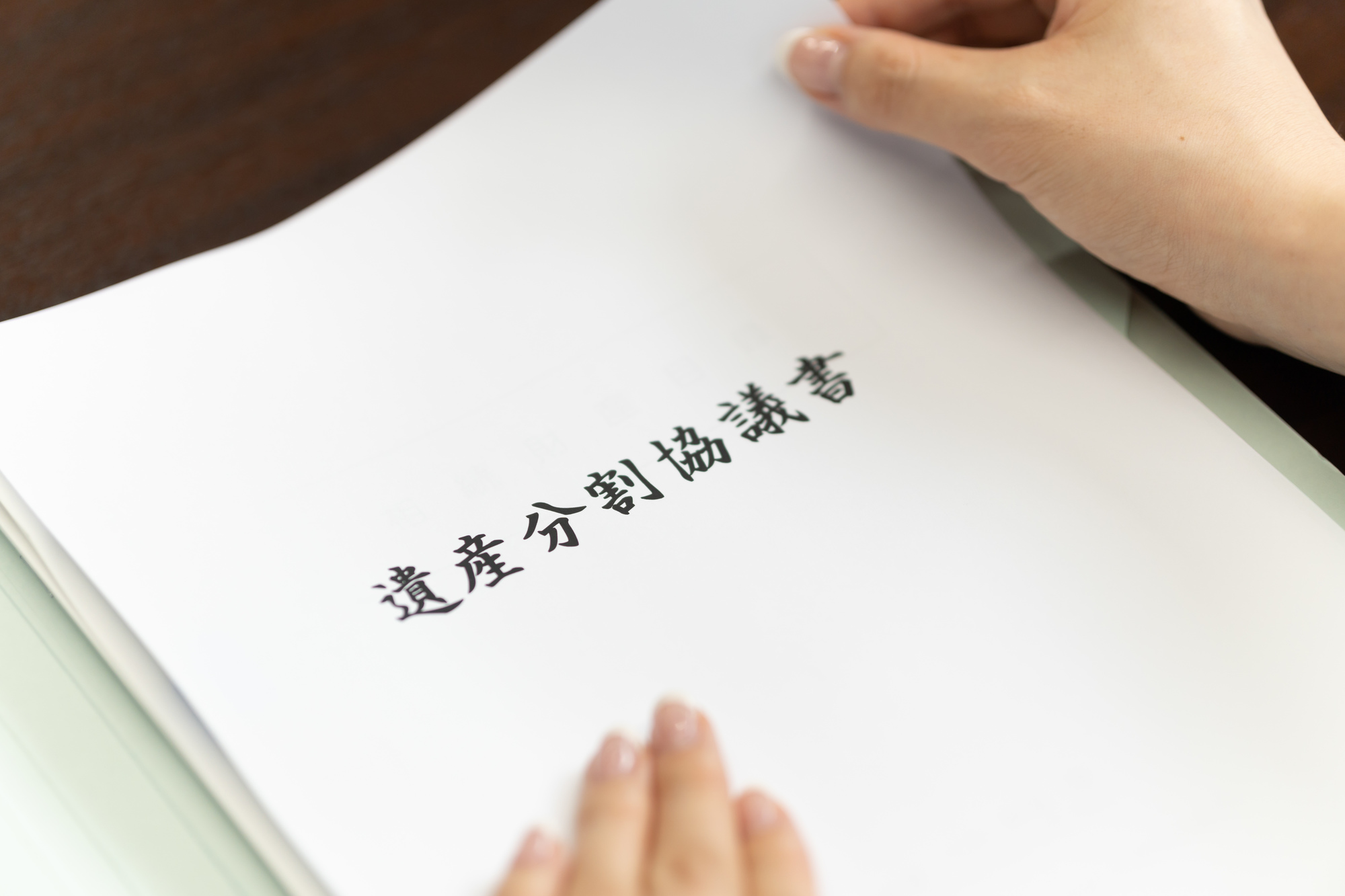
相続で揉めないために最も有効な方法は「元気なうちに、家族みんなで話し合っておくこと」です。「縁起でもない」と話を遮られたり、「遺産を目当てにしているのか」と疑われたりと、話題にしにくいのも事実でしょう。しかし、相続が“争族”になるのは、こうした“取り決め”をしないままにしてしまうからこそ。相続についての情報を集め、必要に応じて市役所の空き家対策窓口や、司法書士・行政書士による無料相談などを利用するのも有効です。
実際、我が家でも調べてみると、50年以上前から農地として使っていた土地が未だに「原野」として登記されていたり、隣との境界が曖昧だったりと、意外な問題が見つかりました。聞いた話でも、自宅のある土地の一部が実は市有地だった、農地を親戚が分割して農業が続けられなくなり離農した、などの深刻な話がいくつもありました。
経験者の多くが口をそろえるのは、「もっと早く動けばよかった」という言葉です。特に土地に関しては「売るにしても、名義を変えるにしても、親が生きているうちにしてくれればこんなに大変なことにならなかったのに」という声をよく聞きます。相続はいつ起こるか誰にもわかりません。「始めるなら今!」と思って重い腰をあげてみませんか。
農家嫁の鉄則。感情論に頼らず、今のうちから準備を
田舎の相続は、「家がもらえる」「土地があるから安心」といった話ばかりではありません。実際には、相続権の有無や土地の管理、放棄するかどうかの判断など、事前に押さえておきたいポイントがいくつもあります。
特に、実子でなくても、嫁として長年介護や家業に関わってきた人にとっては、自分の立場を守るための知識が大切になります。感情だけに頼らず、法律や制度を味方にすることが、将来の安心につながります。今のうちから少しずつ準備を始めてみましょう。




























