日本農業検定とは?

日本農業検定は、農業への理解を促進するために作られた検定で、年に一度実施されます。一般社団法人全国農業観光協会が検定事務局となり、後援団体には農林水産省や全国農業協同組合中央会などが名を連ねています。
日本農業検定の概要
日本農業検定は年に一回のみです。試験期間は例年1月上旬~1月中旬に設定され、合格発表は例年2月下旬に行われます。「農検」「農業検定」とも呼ばれています。名称が似ている「日本農業技術検定」は、日本農業技術検定協会が実施する別の検定ですので注意してください。
テストは4つの選択肢からの選択式です。
検定の目的と意義
農業への関心が高まる中、正しい知識を身に着けたいと考える人にとって日本農業検定はひとつの指標になります。日本農業検定を通して農業への理解を深め、食の安全や安心について高い関心と必要な知識を持った人たちが農業の担い手、あるいは農業の理解者となることには大きな意義があります。
「栽培」「環境」「食」に関する基礎知識の重要性
農業の技術・知識は複雑で多岐に渡りますが、日本農業検定では農業全般・環境・食・栽培の4つの分野が設定され、それぞれの基礎知識が問われます。農業の根幹を成す分野として、必要な知識をしっかりと身に着けましょう。
検定試験の仕組みと受検資格
日本農業検定の受検資格は特にありません。実務経験や農業系の学校で学んだ経験などは問われないため、誰でも受検できます。
1級から3級までのレベル設定
日本農業検定には1級から3級までありますが、どの級からでも受検でき、併願も可能です。各級の合格率は、1級で8.4%、2級59.7% 3級75.6%となっています。
出題分野はすべての級で共通ですが、範囲はそれぞれ異なります。
・3級の出題範囲
| 1 | 農業全般分野 | 農業のたいせつな役割 農業・農村の現状 食料自給率 耕作放棄地の増加と対策 農業の新しい取り組み |
| 2 | 環境基礎分野 | 地球温暖化の原因と影響 自然環境と農業のかかわり 地産地消の取り組み 都市農業の役割 |
| 3 | 食の基礎分野 | 肥満と食習慣 食生活と必要な栄養素 健康な食生活を支える日本の食文化 和食の基本 旬を楽しむ食生活 伝統的発酵食品 食品選び・表示の見方 和食と箸 盛り付けの基本 食の安全管理 |
| 4 | 栽培分野(1) | 種子と発芽の条件 野菜の生育に適した環境 光合成と呼吸作用 葉の気孔と蒸散作用 作物が育つための養分の補給 野菜の病気と防除 野菜の害虫と防除 プランター栽培の基本 |
| 5 | 栽培分野(2) | ・イネ ・カブ ・コマツナ ・シソ ・レタス ・イチゴ ・エダマメ ・ジャガイモ |
・2級の出題範囲
| 1 | 農業全般分野 | 農業とはなにか 世界の食料農業事情 日本農業の現状 農畜産物の需給状況 農業・農村の多面的機能 スマート農業への技術革新 |
| 2 | 環境基礎分野 | 生態系の基礎知識 地球規模の環境問題 農業の環境への負荷 農業が守る自然環境 環境にやさしい生活 |
| 3 | 食の基礎分野 | 食生活と健康 日本の伝統的食生活 食の表示と安全 日本人と食の実態 調理の基本 食品調理・加工と保存 |
| 4 | 栽培分野(1) | 植物の成長 栽培環境の管理 栽培作業の基礎 |
| 5 | 栽培分野(2) | ・イネ ・サツマイモ ・ジャガイモ ・ダイコン ・ニンジン ・ネギ ・ハクサイ ・ブロッコリー ・ホウレンソウ ・カボチャ ・キュウリ ・スイートコーン ・トマト ・ナス ・ピーマン ・ラッカセイ ・メロン ・果樹全般 |
・1級の出題範囲
| 1 | 農業全般分野 | 日本農業の始まり 世界の農業と食料情勢 日本の農業と食料を取り巻く現状 国内農業生産の動向 農業・農村の多面的機能 これからの農業革新の方向 |
| 2 | 環境基礎分野 | 地球規模の環境問題 農業と環境の保全と整備 |
| 3 | 食の基礎分野 | 日本人と食の実態 日本型食生活と健康 食品の安全・安心 和食と伝統的食文化 食育のすすめ 食材の基本 |
| 4 | 栽培分野(1) | 植物の基本的生理作用 栽培植物の成長と繁殖 栽培環境とその管理 |
| 5 | 栽培分野(2) | ・イネ ・サツマイモ ・ジャガイモ ・ダイコン ・ニンジン ・キャベツ ・タマネギ ・ホウレンソウ ・キュウリ ・トマト ・ナス ・果樹全般 ・ネギ ・レタス ・カボチャ ・スイートコーン ・ソラマメ ・イチゴ ・花き ・畜産 |
CBT方式による受検の柔軟性
日本農業検定はCBT方式の試験です。CBTとはComputer Based Testingの略で、申込みから当日の受検まですべてパソコンで行える仕組みです。試験会場は47都道府県にあり、設定された試験期間の中で、都合の良い日時・試験会場で受検することができます。
合格基準と試験時間・問題数の違い
試験時間:【3級】50分、 【2級】70分、 【1級】70分
問題数 :【3級】全50問、【2級】全70問、【1級】全70問
合格基準:【3級・2級】正答率原則60%以上 【1級】正答率70%以上
※若干の得点調整が行われる場合あり
日本農業検定を受検するメリット

日本農業検定の受検には、さまざまなメリットがあります。合否に関わらず、自身の成長につながる面も見逃せません。
就職活動でのアピールポイント
日本農業検定に合格していると、農業に関して一定の知識と関心があることを客観的に証明できます。就職活動においては、農業や食品に関連する企業のほか、自治体やJAなどの採用試験を受ける際に強みになります。
農業への理解を深める
合格するまでの学習を通じて、農業に関する基礎知識を幅広く身に着け、農業への理解を深められます。すでに一定の農業経験がある場合も、知識を補完したり関わりのない分野に関して学んだりする機会となります。
検定試験を通じた自己成長
検定の合格という目標を立て、計画的に受験勉強を進めていく過程において、自分自身の成長を促すことができます。コツコツと努力し、実際に合格という結果を出せれば自信につながります。
日本農業検定の受検準備
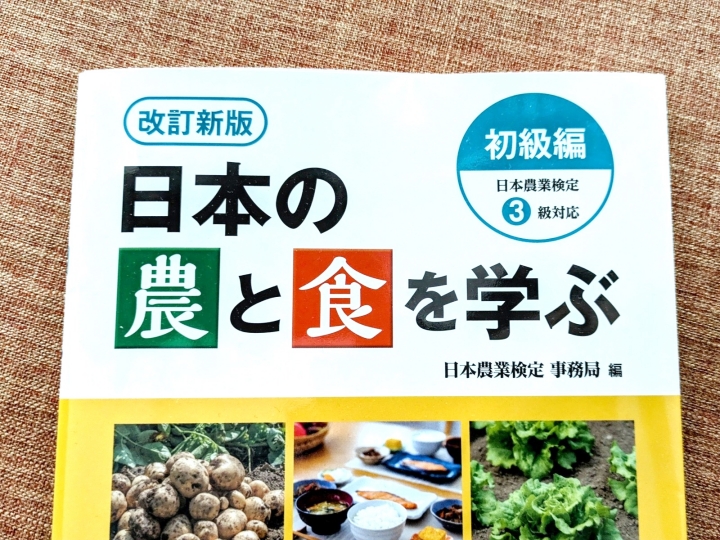
事前に試験の実施要領に目を通し、日程や受検料、必要なものを確認しておきましょう。初めて個人受検を申し込む際は、公式サイトにて新規受検者登録を行う必要があります。
試験日程と申し込み期間
申込期間:2025年12月1日(月)~ 2025年12月26日(金)
試験実施期間:2026年1月6日(火)~ 2026年1月15日(木)
受検料の詳細(1級~3級)
受検料(税込):【3級】4,400円、【2級】4,900円、【1級】5,800円
支払方法:クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済・Pay-easy(ペイジー)決済が可能です。
公式テキストと問題集の活用
最新版テキストの入手方法
最新版の日本農業検定テキストを購入して学習しましょう。書店の店頭にない場合は、注文して取り寄せになります。検定の公式サイト内からも購入できます。
訂正表の確認で正確な情報収集
試験は改訂新版のテキストより出題されます。農業に関して一定の知識がある場合も、テキストに沿って学ぶのが効率的です。訂正表・正誤表の有無も確認しておきます。
効果的な学習方法
改訂新版のテキストを使った学習と、過去問題を解く演習が基本です。さらに深堀りしたい事柄がある場合には書籍やインターネットで調べたり、生産者に直接聞いたりするのも楽しいものですが、日本農業検定の合格という観点では、公式テキストと過去問題が最も効果的です。
試験範囲の理解と重点的な学習
4つの出題分野はすべての級で共通ですが、範囲は異なります。栽培分野に関しては、対象となる品目が級によって異なるため、特に注意が必要です。
過去問題の活用と自己採点
過去問の問題集は販売されていません。日本農業検定の公式サイトに2019年から2024年までの過去問題が公開されているので、受検までに挑戦してみましょう。回答も公開されているので、自己採点ができます。
団体で受検する場合
学校や企業その他の団体で日本農業検定を受ける場合には、団体受検の制度が利用できます。受検者人数が5名以上で、検定会場や試験監督を準備・提供できることなどの要件があるため、詳細は公式サイトなどで確認してください。
合格への5つのステップ
日本農業検定の合格までの過程には、以下の5つのステップがあります。

ステップ1:目標級を決める
公式サイトに掲載されている過去問題の難度などを参考にして、1~3級までの中から目標とする級を決めます。2級と3級など複数の併願もできます。
ステップ2:スケジュールを立てる
出題範囲である農業全般・環境・食・栽培の4分野をもれなく学習できるよう、スケジュールを立てます。テキストを見て学習する期間に加えて、複数年分の過去問題を解いて復習する期間を想定します。
ステップ3:教材をそろえる
受検する級に合わせてテキストを購入します。書店あるいは日本農業検定の公式サイトからも購入できます。基本的にはテキストに沿って学習し、必要に応じて農業に関する書籍やインターネットも使って知識と理解を深めるのが効果的です。
ステップ4:模擬試験で実力を測る
一通り学習が進んだら、公式サイトに掲載されている過去問題を使って模擬試験に挑戦します。自己採点をして、試験の傾向や自分の苦手分野を確認してください。
ステップ5:試験当日の準備
個人受検の場合は、申し込み時に選んだ試験会場での受検となります。開始20分前までに到着するよう、時間に余裕を持って出かけましょう。また、当日は本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を持参する必要があります。
日本農業検定事務局からの最新情報

日本農業検定の公式サイトのトップページには「Informaton」のカテゴリがあり、さまざまな最新情報が公開されています。特に試験の直前には忘れずにチェックし、試験の日程や変更点などがないかを確認してください。
日本農業検定を活用しよう
日本農業検定では、栽培や管理、環境や食など農業の基礎知識を幅広く体系的に学ぶことができ、その知識があることを客観的に証明できます。農業への関心と知識をアピールできるため、就職活動でも役に立ちます。
食料品の価格上昇や備蓄米の流通に関するニュースが毎日のように報じられている現在、日本全国で農業への関心が高まっています。農業は食の安全・安心をはじめ、さまざまな社会的課題と関係が深い分野です。日本農業検定への取り組みは、農業に対する理解を深め、将来の可能性を広げるきっかけになるでしょう。
参考:日本農業検定公式サイト

























