コメの先物市場とは。日の目を浴びない理由
コメ全体の価格変動を回避するリスクヘッジとしての場だけではなく、将来価格がわかることで、売り手の生産者にとっても買い手の流通業者や実需者にとっても大きなメリットをもたらし、産業としての礎を築く存在であるコメの先物取引市場。
しかしながら、原油先物市場や大豆、小麦、トウモロコシなど穀物の先物市場などは世界的な中心市場の価格が毎日ニュースで取り上げられる一方、堂島取引所で毎日形成されるコメの先物価格がニュースで報じられることはほとんどない。
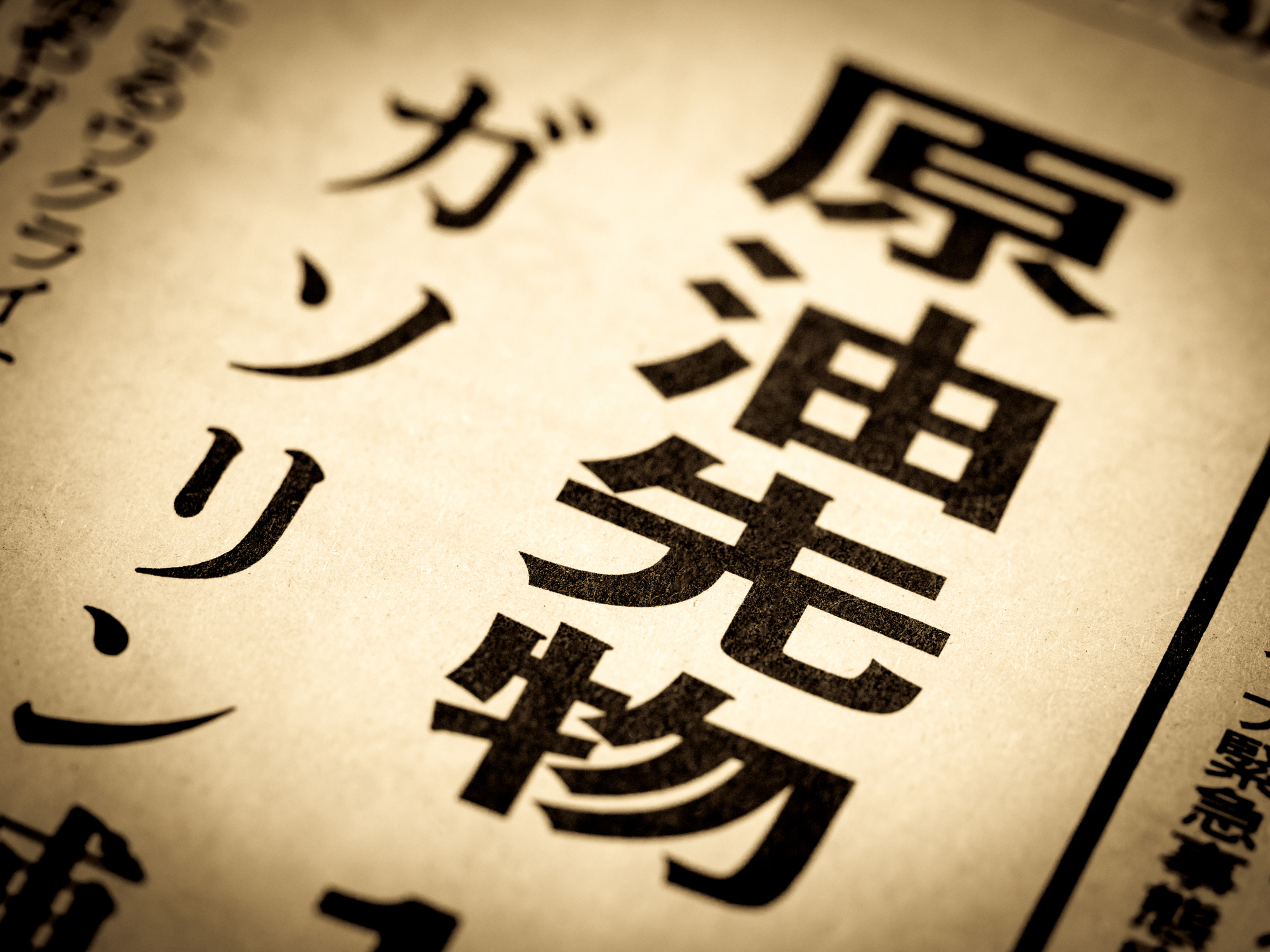
その理由として考えられるのは、取引開始からまだ日が経っていないこと、市民権を得られるほど価格形成市場として認知されていないことが挙げられる。
売買対象がコメの現物そのものではなく「指数」と言う商品であり、コメの生産者や流通業者、実需者にとってわかりにくいことなども理由の一つだろう。
それでも、特定の産地銘柄の売買においては、先駆的な取引事例も生まれている。
例えば、試験上場中の「新潟コシヒカリ」は、売買対象が新潟県で生産されるコシヒカリで検査を受けたもので、シンプルでわかりやすかった。実際、新潟県のコメの生産者の中には田植えが終わった後、収穫時の10月限に生産数量の何割かを先物市場で売る人もいた。また、集荷業者の中には先物市場でも納会日に現物を買い受けることができたので、将来の現物を確保するために先物市場で買い建て玉を立て、実際に現物を受けた業者もいた。こうした先渡し市場的な使い方をして売り手、買い手ともにメリットを感じていた。
コメ先物の歴史と仕組み
コメの先物市場をよく理解するためにお勧めしたいのが、YouTubeで無料で見られる日本取引所グループ公式チャンネル「堂島米市場」だ。10分程度の動画が6回に分けて編集されているので、時間のある時に繰り返し閲覧できる。
この動画を見ると、江戸時代に生まれたコメ先物市場が優れた取引手法で、世界のデリバティブ取引の先駆けになったことがよくわかるように紹介されている。しかも現物そのものではなく「米切手」という証券を売買、しかも取引に流動性を持たせるために具体的な特定産地の銘柄ではなく「立物米」という名目的なコメ証券を売買するなど堂島のコメ商人たちの柔軟な発想と先進性に驚くほかない。
取引上の最大の発明は「やりくり両替」(消合場)と言う日々の取引を清算する仕組みが作られたことで、これによって先物市場の肝と言うべき「反対売買による清算取引」が可能になった。現在、世界中で隆盛を誇っているあらゆる商品の先物取引はこの「反対売買による清算取引」が発明されたから可能になったのであり、まさに堂島はデリバティブ発祥の地として称えられている所以である。

コメ先物取引市場の多様なメリット
コメ先物取引市場のメリットを端的に示すと、以下のようなことが挙げられる。
1、 先行きの価格がわかる
現在、堂島取引所で売買されているコメ先物取引は偶数月の最長1年先まで取引が行われている。今年、6月時点であれば来年6月までの売買が可能である。今年10月の売買もできるので令和7年産米の価格がわかる。先行きの価格がわかることによって経営計画が立てやすくなる。
2、 安全に将来の所得が確定できる
先行きの価格がわかるだけでなく、コメの生産者は先物市場で売買される1年先の限月で売ることによって将来の所得が確保できる。先物取引所は毎日、売り買いの清算を行っており、売ったものの代金が入って来ないということはない。所得が確定しているということは金融機関との借り入れ交渉に役立つ。
3、 価格下落時に差損をカバーできる
先物市場で売りつないでおけば、収穫時期になって豊作で価格が値下がりしても売ったものを買い戻すことで利益を確保できるので現物の値下がりによる損失をカバーできる。
4、 先物市場には価格の平準化作用がある
先物市場で形成される価格には平準化作用があり、現物市場しかない場合に比べ価格の乱高下が抑えられる。
5、 買い手の実需者は先物市場で買い建て玉を建てることによって先行きの仕入れ計画に役立つ
買い手のコメ卸や外食・中食企業にとって先物市場で2カ月おきに1年先まで買い建て玉を建てることによって先行きの仕入れ計画に役立つ。現物を倉庫に保管して先行きの需要に備えるより、保管料や金利がかからない。
6、 少ない資本で大量の売り買いが可能になる
先物取引は売買代金の1部を証拠金として預託することによって約その10倍の数量を売り買いできる。
以上が先物市場活用の主だったメリットだが、派生的に情報発信機能などのさまざまな恩恵がある。
次回はより具体的に取引の仕組みを解説してみたい。



























