米の小売価格は、概ね概算金・相対取引価格で決まる
そもそも米生産者が収穫した米の価格は、どうやって決まっているのか、その仕組みを簡単に説明しておこう。

2023年産米について、米流通経路別に米の流通量を図示したもの。肌感覚より遥かに集出荷業者向けが少なく、農家直売等と農家消費が多い。農水省「米をめぐる状況について(令和7年5月)」より
農水省が公表している資料によると、2023年産米の主食用うるち米は、717万t-74万t=643万tが生産された。そのうち農家直売等が233万t、自家消費や無償譲渡された「農家消費」が110万t、残る300万tが「集出荷業者」に回っている。集出荷業者からは、全国集出荷団体等を経由して卸・小売り等へ218万tが流れていた。
米生産者から集荷業者のうちJAなどが集荷する分は、概算金が支払われる。概算金とは、出荷時に集荷業者が生産者に仮で支払う仮渡金であり、その金額は県単位で全農県本部・経済連が決めている。全農県本部・経済連は販売の見通しが立った時点で、販売見込額から経費・概算金を除いた額を生産者に追加払いする。集荷業者から見れば、概算金は仕入値だ。
集荷業者から卸業者に売り渡される価格を相対取引価格という。相対取引価格は、全農、県経済連、県単一農協、県出荷団体(年間の玄米仕入数量が5,000トン以上)、出荷業者(年間の直接販売数量が5,000トン以上)から農水省に報告され、発表される。集荷業者から見れば、相対取引価格は売上に当たる。
米生産者にJA等が支払う概算金は、銘柄により少なからず上下あるものの、概ね12,000円/60kg程度で推移してきた、と言われている。それに対して相対取引価格はというと、これも14,000円/60kg前後で推移してきた。
集荷団体における米の集荷・流通等に要するコストは(県や銘柄により異なるものの)概ね2,000円/60kgであると言われているから、JAの立場に立つと、売上(14,000円)から仕入価格(12,000円)と経費(2,000円)を引いて残るのが利益だが、それはなんとゼロ。長年JAは、米からほぼ利益を上げていないことになる。

相対取引価格が跳ね上がったのは2024年産米。12,000~16,000円の間で推移していた相対取引価格は一気に24,500円へと跳ね上がり、同時に小売価格も急上昇した。
相対取引価格で買われた米は、精米・パック詰め・輸送にかかる経費と利益を上乗せされて小売店に販売され、それが消費者に販売される。この時の価格が小売価格だ。
米の価格は、集荷業者(全農県本部等)が決める概算金が起点となる。これに応じて相対取引価格・卸売価格・小売価格が決まって行く。これが基本的な米価格の決まり方だ。
高米価の背景にあった、スポット価格の高騰
前回の記事で熊野さんは「米価高騰の根本的な原因は米不足=民間在庫量の不足。JAが買い負けし、スポット価格も上昇した」と説明した。
スポット価格とは、実需との契約が済んでいない米の取引が行われるスポット市場での価格。米を十分に集めることができなかった卸業者が、スポット市場で競って米を集めたことから、スポット価格が高騰。それが小売価格の暴騰を誘発した、という説明だった。この熊野さんの主張が正しいことを裏付ける資料を、農水省が公表した。

集荷業者への出荷が前年と比べ31万トン減少。集荷業者以外の業者の取引が44万トン増加している。集荷業者から大ロットで契約して購入していた卸売業者・実需者は、不足分を他の事業者から小ロットで 比較的高い価格で入手した。農水省資料「小売価格の上昇の背景(令和7年7月14日)」より
熊野さんは前回、スポット取引では集荷業者から先の売先が決まっていない米が、卸・小売り等へと売られて行く、と教えてくれた。これはわかる。一方で、米市場の部外者である筆者にとって理解しがたいのが、相対取引価格だ。これは一体どうやって決まるのだろうか?
「ここは外部からは見えません。集荷業者から卸業者に売られた後に農水省に報告される、という形になっている」(熊野さん)
卸業者では、自社の契約量(販売予定)を確保すべく、民間在庫量や小売店の動向(小売価格や販売数量の推移)、次作の作況などを勘案しつつ、集荷業者と交渉して決めているのだろう。
透明性の高い市場を構築して米を適正な産業にすべし!
では、こうした現在の米流通構造のどこに問題があるのだろう? 熊野さんは以下のように指摘した。
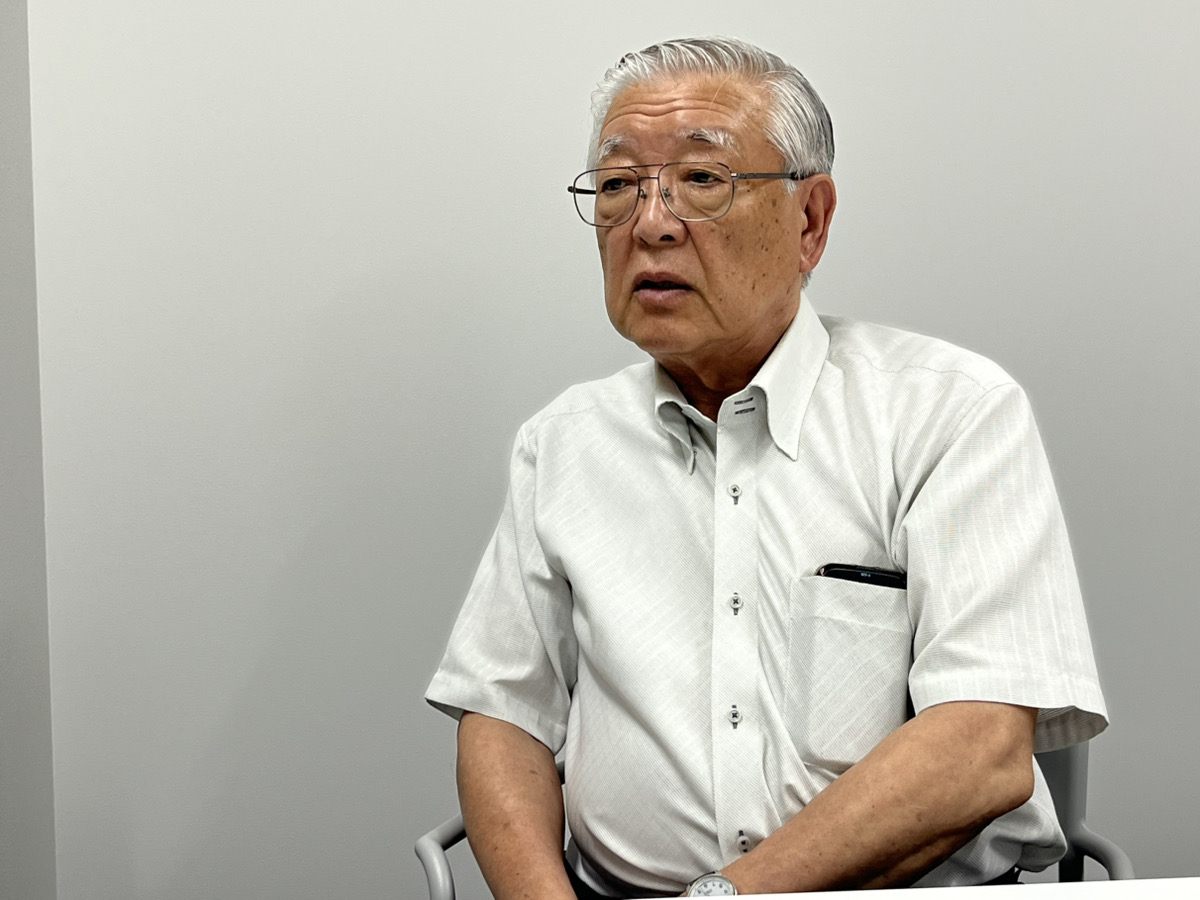
「相対取引価格は、なぜその価格になったのか、外から見ることができない。まず、それが問題。ただし、系統の集荷割合が減少し大手商社が単位農協との直接契約を進めていることから、相対取引価格が米価全体を大きく左右することはなくなる」。
また、令和の米騒動を引き起こした一因に、米の区分けのいびつさがあったと、熊野さんは言葉を続ける。
「農水省は米について、子実用と主食用という2つの統計を出しているが、『これは主食用米』『これは違う』、と言えば、そうなる仕組みがある。米市場のあるべき姿とは、まずは加工用や輸出用も全て需要と認めて、それぞれの品質に見合った価格を市場で形成する。そうした仕組みを作ることが、米を適正な産業にする第一歩になる」と述べた。
熊野さんによると、令和の米騒動で最初に米不足を訴えたのは、加工用米を大量に消費する米菓業界であるという。2023年9月、備蓄米の放出を含めた意見を農水省に提出した。これは2023年産の主食用米の不足を受けて、それまで加工用米として流れていた、ふるい下米が激減したためだ。
「私が入手したデータでは、2023年産米のふるい下米発生量は32万tで、これは2022年産米に比べて19万tも少なかった。これでは、米生産の下流にある食品産業が、安心して事業を継続するのは困難」
そのうえで熊野さんは、品質に見合った価格を市場で形成するには3つの市場(①現物市場、②相対市場、③先物市場)が必要であり、これまで裁定市場の役割を果たす先物市場が未整備だったことが問題だった、と指摘した。
「先物市場があることで、将来の米価格に関する市場の予測や需給見通しが反映された先物価格が常に公開されることになる。これにより、米生産者、流通業者、実需者(卸・外食・小売など)は、市場価格を客観的に把握しやすくなる。つまり、不透明な相対取引が中心だった米市場に価格指標ができ、交渉の基準が明確になる。価格が『見える化』することで、米生産者は適切な作付判断が可能になる」
さらに、先物市場があることで価格変動リスクへの対応ができる、いわゆるヘッジ機能を、先物市場のメリットにあげた。米生産者や流通業者は、将来の米価下落に備えて、先物市場で価格を「今の水準で固定」することができる。作付前や収穫前に、先物市場で一定の価格で売りを立てておけば、米価が暴落した時のダメージを軽減できる、という理屈だ。
「先物市場には、裁定市場として現物市場との価格乖離を是正する機能がある。先物市場が裁定市場として機能すれば、先物価格と現物価格の間で価格調整(裁定取引)が起き、市場全体がバランスを取る。その結果、先物市場は、現物価格が不当に吊り上がったり、暴落したりするのを防ぐ『安定装置』になる。言葉を変えれば、実需に基づく適正な価格形成が進む、と考えられる」
熊野さんは決して、相対取引市場を全否定しているわけではない。また、米の先物市場は、堂島コメ平均として既に立ち上がっている。先物市場への参加者が増えることで、熊野さんが指摘する価格の見える化が実現し、価格の安定装置として機能するようになるはずだ。
今回熊野さんにインタビューして感じたのは、米流通は極めて奥が深い、ということ。これまでの系統を中心に構築された相対取引は、(そこそこ)米価を適正に保ち、米生産者を守るのに役立って来たと思う。一方で、部外者からみたとき、加工用や飼料用を含めた米市場・米流通は分かりにくい。これが「JAが農家を食い物にしている」「農家は補助金漬けだ」「卸が米を隠し持っている」などといった誤った理解を生む原因ではないかと思う。
ブラックボックスを透明にして行く作業を、米流通関係者には望みたい。米流通の透明性が高まれば、消費者の米生産・流通への理解が進む。そうなれば、今のように「米価が上がった・下がった」といった近視眼的な視点からだけでなく、食料安全保障を含めて米生産に関する国民的議論ができるのではないか? 一定程度の米価の上昇だって理解されるはずだ。何より、米生産者が将来を見通して、安心して生産を続けることができるようになるだろう。





























