五味とは?

酸(さん)・苦(く)・甘(かん)・辛(しん)・鹹(かん)の5つの味に食べものを分類し、味と臓器が密接な関係にあるとした考え方です。
漢方の古い書物には、酸は肝・胆、苦は心・小腸、甘は脾(ひ)・胃、辛は肺・大腸、鹹は腎(じん)・膀胱に入るとあり、口から入った食べ物は味の違いによってそれぞれ違う臓器に働きかけると書かれています。
五味の作用について
酸(酸味)

酸には収斂作用(しゅうれんさよう)と固渋作用(こじゅうさよう)があり、五臓では肝に関連します。例えばシメサバは、酢の持つ収斂作用を利用してサバの身を引き締めた調理法です。また、ウメ干しの酸味には物を固め出して渋らせる作用があり、下痢の改善に効果的だと言われています。その他、汗腺を引き締めて発汗を抑える作用もあります。
肝は、漢方においては肝臓だけでなく精神をコントロールする作用もあると考えられています。そのため、イライラした時などには酸味の強いものを口に入れることでストレスを発散させることができます。
苦(苦味)

苦には余分な熱を取り去る清熱作用と余分な水分を取り除き、柔らかくなりすぎたものを固くする燥湿堅化作用があり、五臓では小腸に関連します。
苦の食べ物の代表としてはゴーヤが挙げられます。ゴーヤが暑い沖縄において夏に食べられる野菜であるように、体の熱を取り去ってくれる効果があります。また、実を乾燥してお茶にしたゴーヤ茶には、小腸の過剰な水分を取り除き、下痢を止める作用が期待できます。ジャガイモの黒焼きにも出血性疾患や下痢止めの効果が期待できます。
甘(甘味)

甘には滋養作用と弛緩作用があり、五臓では胃に関連します。滋養作用とは、栄養を与える作用のことであり、弛緩作用とは緊張した状態を和らげる作用のことをいいます。身体が疲れた時に甘いものを食べたくなるのは体がこの滋養作用を求めるものであり、緊張状態のときに甘いものを口に入れると緊張がほぐれるのは、弛緩作用があるからです。
甘の食べ物であるハチミツは、のどの緊張を和らげてのどの痛みを改善したり、のどにささった骨やとげを抜けやすくする効果があります。
辛(辛味)

辛味には、汗をかくことを促進する発散作用と、気血の巡りを良くする運行作用があります。
辛い食べ物の代表的な存在であるトウガラシを使った料理を食べているときに、徐々に体が熱くなっていき、鼻の頭などに汗をかいたことがある経験はないでしょうか。これはトウガラシの辛味の発散作用で毛穴が開いて汗をかき、運行作用によって全身の気や血のめぐりがよくなって、体が温まったということになります。
また、風邪のひき初めには、同じく辛味成分が含まれるネギやショウガを用いた料理を食べると辛味の持つ発散作用で汗をかき、風邪を悪化させずに初期段階で治すことが期待できます。
鹹(塩味)

鹹味(かんみ)とは聞きなれない言葉ですが、塩辛い味のことです。鹹には軟化作用と散結作用があり、これらはどちらも固いものをやわらかくする作用のことです。
また、便通を良くする瀉下(しゃか)作用もあるため、便秘の時には食塩水などで塩を摂取すると、軟化作用と相まって便が柔らかくなり便通を良くします。
また、コンブは鹹の軟化作用によってしこりを柔らかくする作用があり、甲状腺腫に良いとされています。
五味と五臓の関係

五味は五臓を補う働きがあるとされています。そのため、体のある部分が疲れていると五味のいずれかの味を欲するようになります。
腎が弱っているときは塩辛い鹹、肝が弱っているときは酸、心が弱っているときは苦、胃が弱っているときは甘といったように、欲する味によって体のどこが疲れているのかが分かるようになります。
しかし、五味は五臓を補う一方で、過剰に摂取すると逆に五臓を弱らせてしまうこともあります。塩辛いものを食べ続けるとさらに腎が弱ってむくみが出たり、甘いものを食べすぎると胃腸障害が起きて口の周りに吹き出物ができます。辛い食べ物の摂りすぎは気管支に悪い影響を与え、咳を誘発したり気管支炎を悪化させることもあります。
ただし、辛の食べ物であるネギやショウガなどの発汗作用は、風邪の初期症状に効果的であり、風邪のひき初めには積極的に摂取した方がよい食べ物です。また適度な酸味には、ストレスを発散させるなど肝の機能を高める働きもあります。
漢方を支える基本理論である五行説においても、バランスを鑑みることを非常に大切に考えています。その思想はこの五味においても同様であり、五味のバランスを考えた食事をとることが五臓の調子を整え、健康を維持するとされています。
日常生活における食事でも、甘いものと酸っぱいものや辛いものと苦いものなど、反対の作用をもつ食べ物を組み合わせて作る料理が多くなっています。五味のバランスを整えて食事をとることが大切ですが、実は人間の長年の経験と習慣から生まれた知恵なのかもしれません。私たちも知らず知らずのうちに自然と五味のバランスの取れた料理を食べているようです。
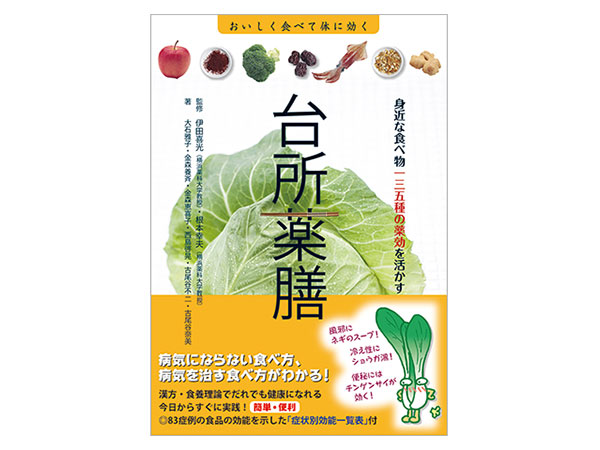
参考書籍:『台所薬膳 身近な食べ物135種の薬効を活かす』(万来社)




























