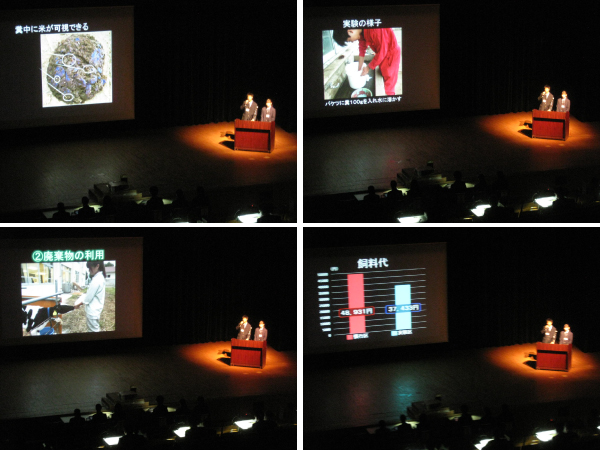農業高校生たちの学び・活動の発表の場
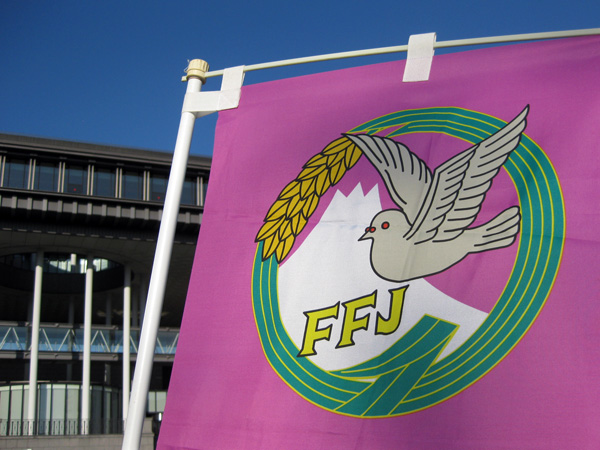
日本学校農業クラブ連盟(Future Farmers of Japan)のシンボルマーク。
鳩は平和と友愛と協同を、富士山は日本を、稲穂は日本の農業を表す
1日目はプロジェクト発表会、2日目は最優秀者発表と表彰式
第69回を迎えた日本学校農業クラブ全国大会(以下、全国大会)。その1日目、10月24日にプロジェクト発表会は行われました。
Ⅰ類(生産・流通・経営)、Ⅱ類(開発・保全・創造)、Ⅲ類(ヒューマンサービス)について、専門分野ごとにそれぞれ全国9ブロックの代表校が1校ずつ発表を行いました。一日かけて全27校が発表を行い、この中から各類ごとに優秀賞、そして最優秀賞が決定します。
優れたプロジェクト発表が選出

細かく定められた発表要領に合わせてプロジェクト発表は進められる
Ⅰ類:ウイルス病対策からイチジクの秀品率を上げる
Ⅰ類の最優秀賞(農林水産大臣賞)は、兵庫県立農業高等学校による「ウイルス病対策によるイチジクの秀品率向上」。
イチジクの病害であるイチジクモザイクウイルスの対策のため、生徒が技術開発と地域連携の中心となり、農家・行政・JA・大学などと一緒に取り組んだプロジェクトです。
ウイルス検定を行い非感染を確認した無病苗であり、かつ糖度が高く食味も良い優良苗を供給できることを目指し、実際に2018年3月には87本の優良苗を提供しました。優良苗により、贈答用として取引される秀品が収穫できる“秀品率”が高まり、さらに早期出荷ができるという経営メリットもあるそうです。今後も年間1万2000本の苗を生産・供給することを目指すとのことでした。
Ⅱ類:下水処理の汚泥から肥料を生む
Ⅱ類の最優秀賞(文部科学大臣賞)は、京都府立桂高等学校による「植物の隠れた能力を引き出す!! ~未利用資源MAPを活用した新技術の開発~」。
下水処理場で汚泥を浄化する際に発生するリン酸マグネシウムアンモニウム(MAP)を肥料として使用するプロジェクトです。企業と地元下水道局の協力の下、研究開発を進めたそうです。
麦で実証試験を行い、追肥せずに元肥だけで収穫量が増えるという結果となりました。
「化学肥料を減らしながらも生産量を安定させるイノベーションです。今後も研究を続け、化学肥料の削減だけでなく持続可能な土壌環境の創出を目指します」と発表は締めくくられました。
Ⅲ類:廃棄処分するツルを加工し伝統工芸に活かす
Ⅲ類の最優秀賞(文部科学大臣賞)は、長崎県立諫早農業高等学校による「長崎伝統文化を守れ! ~廃棄カボチャ蔓(つる)で和紙文化の再興と普及~」。
これまでもカボチャの規格外品から作る加工品として、餡にカボチャを練り込んだ中華菓子の「月餅」を商品化してきた同校。今回は焼却処分されていた蔓の加工について研究し、蔓を利用した伝統和紙作りで、地域のイベントなどでのべ1万5000人以上に直接PRしてきました。
開催県の鹿児島県勢からは14年ぶりの入賞も

市来農芸高等学校の発表者の生徒たち
今大会の開催県である鹿児島からは、Ⅰ類に市来農芸高等学校が「ツバキプロジェクトパートⅡ アニマルウェルフェアと鶏卵有利販売の確立を目指して」というテーマで発表。
消臭効果があると言われるツバキに着目し、その活用方法を検討するプロジェクトとして、2年にわたり調査研究を続けてきました。ツバキにより臭いが減る効果を明らかにした1年目に続き、さらなる活用法を模索した2年目。ツバキ茶の茶葉をニワトリに与えることで、フンの臭いが減ったり鶏卵の品質が向上したりするなどの効果を確認しました。ツバキは火山灰にも強いことから、桜島が活発に活動を続ける地元鹿児島県に適しているのではとも生徒たちは考えています。
この発表が優秀賞を受賞し、県勢としては14年ぶりの入賞となりました。
発表をした生物工学科の2年生、福滿陽菜(ふくみつ・ひな)さんは「足がガクガクするほど緊張しましたが、私たちのプロジェクトを伝えられて良かったなと思います。まずは地元に普及させていきたいです」と話しました。
これからの農業の担い手同士に刺激

会場では各校のプロジェクト活動記録簿も公開された
審査員は、こうしたプロジェクト発表の数々について「地域の課題解決のために、取り組む姿が印象的」と講評しました。
プロジェクト発表会の担当校として運営に当たっていた、鹿児島県立市来農芸高等学校の教員・栗山典友喜(くりやま・のりゆき)さんは「選手の発表は本当にレベルが高かった。地域の垣根を越えて、生徒同士でも刺激を受けていたようです」と話しました。
創意工夫に満ちた、科学性・社会性・指導性のあるプロジェクトの数々は、この先の農業に役立つであろう期待にあふれています。
【前編はコチラ】学校農業クラブ全国大会 2018年のプロジェクト発表ダイジェスト(前編)