ビーツとは
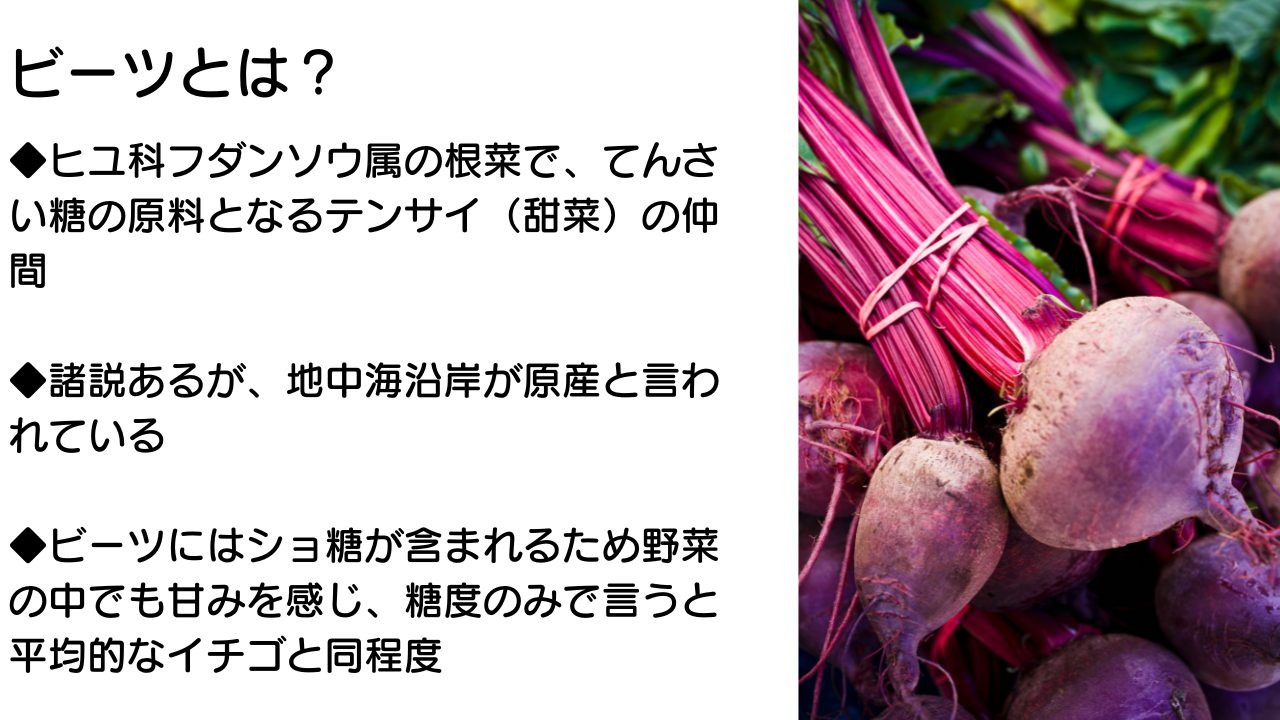
ヒユ科フダンソウ属の根菜で、てんさい糖の原料となるテンサイ(甜菜)の仲間です。
ショ糖を多く含むため、食べるとほんのりと甘みがあります。テーブルビート、カエンサイ(火焔菜)などの呼び名もあります。一見すると赤く丸い根が赤カブに似ているようですが、アブラナ科であるカブとは別の種類です。
欧米では一般的に食べられており、ロシア料理で有名なボルシチに代表されるように、東欧を中心にさまざまな料理に使われています。
主な原産地
諸説ありますが、地中海沿岸が原産と言われています。日本には江戸時代の初め頃に渡来し、江戸時代の書物「大和本草(やまとほんぞう)」では、現在のビーツとよく似た特徴の暹羅(しゃむら)大根として紹介されています。
ビーツの味
ビーツは、一般的にはあまりなじみのない野菜ということもあり、味の想像がつきにくいかもしれません。ビーツにはショ糖が含まれるため野菜の中でも甘みを感じ、糖度のみで言うと平均的なイチゴと同程度と言えるでしょう。
じっくりと加熱調理されたビーツは、特有の土のような香りが和らいで優しい甘みが引き出され、ホクッとした食感の中にもみずみずしさが感じられます。
ビーツの旬な時期
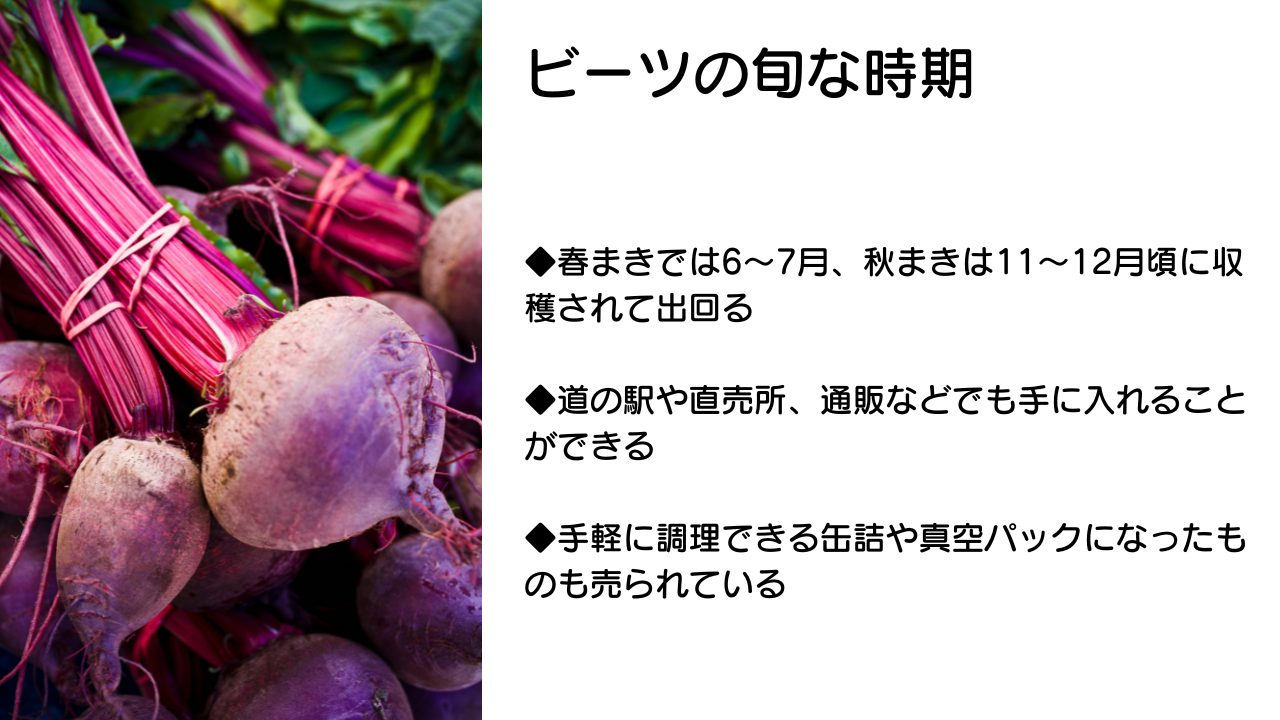
国内では主に埼玉県や北海道、長野県、茨城県、熊本県などで生産されており、春まきでは6~7月、秋まきは11~12月頃に収穫されて出回ります。輸入物は通年出回っています。
現在は、スーパーなどで身近に見かけることは少ないですが、道の駅や直売所、通販などでも手に入れることができます。手軽に調理できる缶詰や真空パックになったものも売られています。
ビーツの食べ方
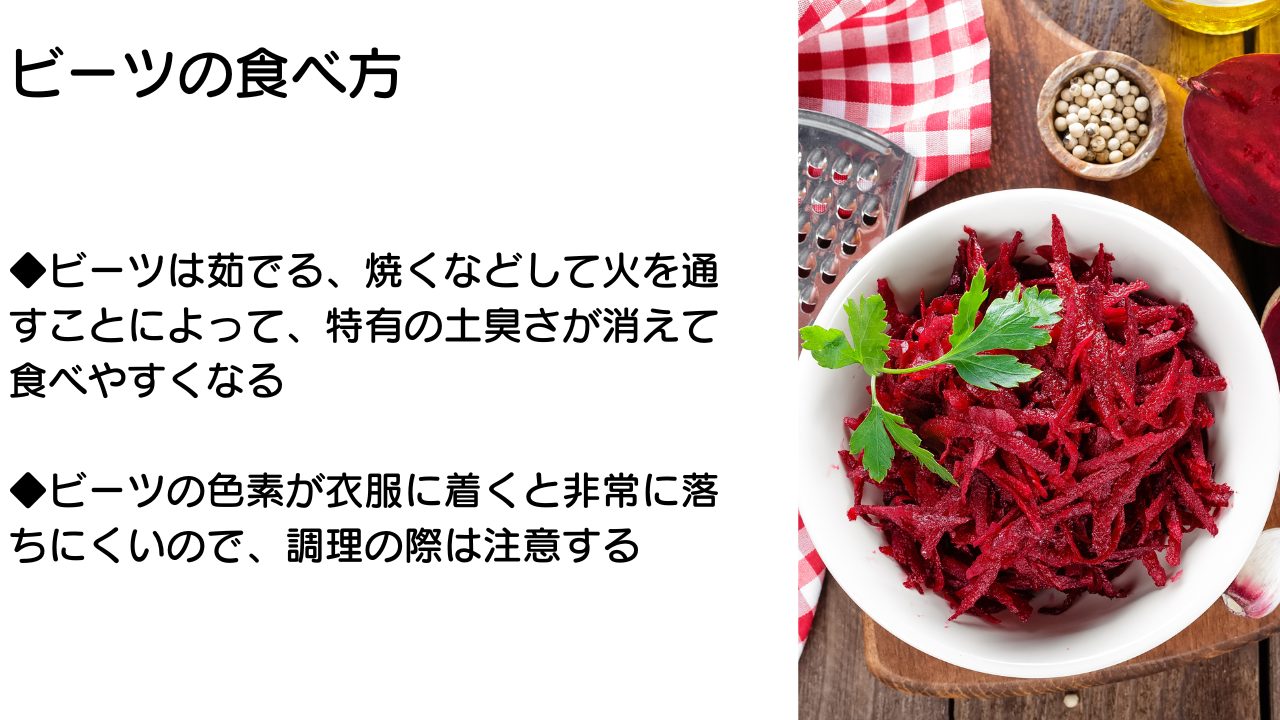
ビーツは茹でる、焼くなどして火を通すことによって、特有の土臭さが消えて食べやすくなります。また、最近では生食でも食べやすい品種も出てきており、さまざまな用途で活躍する食材と言えます。
皮付きのビーツを茹でる

ビーツの特徴である赤い色が抜けてしまわないように、丸ごと皮付きのまま茹でるとよいでしょう。水に少量の酢やレモン汁を入れると、より色鮮やかに仕上がります。竹串がスッと通ればゆで上がりです。食べやすい大きさにカットして食べましょう。
ビーツの色素が衣服に着くと非常に落ちにくいので、調理の際はご注意ください。まな板などにも色素が付いてしまうので、洗って乾かした牛乳パックやオーブンシートを敷いてカットするのもおすすめです。
皮付きのビーツをホイル焼きにする
皮付きのビーツに塩を軽くふり、アルミホイルで包みます。十字に切れ目を入れておくと中までしっかり加熱できます。180度のオーブンで40分~1時間ほどじっくり焼くと、ほっくりとした食感と甘みが引き出されます。

生で食べる
皮を厚めにむいて、食べやすい薄さにカットします。
最近では、生食でもアクが少なく、白地に赤い年輪模様の「渦巻きビーツ」も見かけるようになりました。シャキシャキとした食感で、サラダなどに使うと見た目にも美しいアクセントになります。
ビーツの保存方法

新聞紙やビニール袋などに入れて冷蔵庫の野菜室で保存します。根の栄養が葉の成長に使われ、水分も蒸発してしまうので根と葉の部分は分けて保存しましょう。
根は1週間、葉の部分は2日ほどを目安に食べきりましょう。冷凍保存も可能で、加熱したビーツを冷まして食べやすいサイズにカットし、冷凍用保存袋に入れて冷凍します。解凍後は崩れやすいので、スープやスムージーなどに使うのがおすすめです。
ビーツを使ったおすすめレシピ

美しい赤紫色が特徴のビーツは、その色合いや甘みで料理を華やかに彩ってくれます。ここからは、素材の味を生かしたおすすめレシピを紹介します。
ビーツのポテトサラダ

| 材料(3~5人分) | ・ビーツ 2個 ・ジャガイモ 2個 ・タマネギ 1/4個 ・パセリ 適量 ・マヨネーズ 適量 ・塩こしょう 適量 |
|---|
-
作り方
1.ビーツ、ジャガイモの順番で中まで火が通るようにゆでる
2.ビーツは皮をむいて、みじん切りにする。ジャガイモは潰しておく
3.タマネギ、パセリをみじん切りにする
4.ボールに、2と3の具材を入れて、マヨネーズ、塩こしょうで味を調えて混ぜて完成
ビーツと野菜を使ったボルシチスープ

| 材料(2人分) | ・ビーツ(ゆでたもの) 1/2個 ・ジャガイモ 1/2個 ・タマネギ 1/2個 ・ニンジン 1/4本 ・牛肉 60g ・トマトピューレ 100g ・水 200~250cc ・塩こしょう 少々 ・サワークリーム お好みの量 ・ローリエ 1枚 |
|---|
-
作り方
1.ビーツ、ジャガイモ、タマネギ、ニンジン、牛肉を食べやすい大きさにカット
2.水にローリエを入れて1でカットした具材を軟らかくなるまで煮込む
3.2にトマトピューレを加えて、塩こしょうで味を調える
4.お皿に移し、サワークリームをのせて完成
ビーツとベリーのスムージー

| 材料(2人分) | ・ビーツ(ゆでたもの) 130g ・ミックスベリー(冷凍) 140g ・牛乳(豆乳でも可)400ml |
|---|
-
作り方
1.ビーツ、ミックスベリー、牛乳(豆乳)をミキサーに入れて撹拌(かくはん)する
2.1をグラスに入れて完成
ビーツの葉とエリンギのバターソテー

| 材料(2人分) | ・ビーツの葉 2個分 ・エリンギ 1本 ・バター 15g ・塩こしょう 少々 |
|---|
-
作り方
1.ビーツの葉とエリンギは、食べやすい大きさにカットする
2.バターを熱したフライパンに、1の具材を入れて炒める
3.塩こしょうで味を調えて完成
ビーツの葉のおひたし
| 材料(2人分) | ・ビーツの葉 お好みの量 ・しょうゆ 適量 ・かつおぶし 少々 |
|---|
-
作り方
1.ビーツの葉を根元から入れて20秒ほどゆでる
2.ゆでたら、冷水にさらし、水気を切る
3.食べやすい大きさにカットして、しょうゆをかけて完成
ビーツに含まれる栄養素

ビーツには、血圧を下げる働きを持つカリウムや、お腹の調子を整える食物繊維・オリゴ糖をはじめ、ビーツの特徴である色素成分ベタシアニン、ビーツの仲間であるテンサイに由来する成分ベタイン、女性にうれしい働きを持つビタミンB6や葉酸などが主に含まれています。それぞれの期待できる効能を見ていきましょう。
カリウム
カリウムは細胞内に多く存在していて、血圧を調節したり、細胞の代謝や神経・筋肉の働きに関わる重要な栄養素です。不足すると食欲不振や倦怠(けんたい)感、むくみを招く原因になります。
食物繊維・オリゴ糖

食物繊維とオリゴ糖は、どちらも腸内の健康維持に役立ちます。オリゴ糖は善玉菌を増やして悪玉菌を減少させ、食物繊維は悪玉菌の生産物を排出させます。
ベタシアニン
ビーツの鮮やかで濃い赤紫色は、ポリフェノールの一種であるベタシアニンによるもので、すぐれた抗酸化力があります。老化や病気の原因になるといわれている体の中の活性酸素を取り除く働きがあります。
ベタイン
ベタインには、肝機能を高めて肝臓に脂肪をつきにくくする働きがあります。
ビタミンB6・葉酸
ビタミンB6は、たんぱく質(アミノ酸)の代謝に欠かせないビタミンです。神経ホルモンの代謝にも必要とされています。皮膚炎を予防することから発見されたビタミンなので、健康な肌を維持するために大切な栄要素と言えるでしょう。
また、ビタミンB群の仲間である葉酸も含まれています。
ビーツは家庭菜園にもおすすめ

ビーツの生育温度は15~21℃で、涼しい栽培環境を好みます。寒さには比較的強いですが、暑さには弱いので夏を避け春か秋に種をまいて育てましょう。気温が下がるにつれて葉の赤みが増していきます。
家庭菜園でも栽培可能で、根を浅く張り、あまり大きくならないためプランターでも育てることができ、2~3カ月で収穫することができます。乾燥に弱いので、陽当たりの良い場所で育てる場合は水切れに注意しましょう。
豊富な栄養と美味しさを兼ね備えた野菜

ビーツは見た目の華やかさもさることながら、ベタシアニンやベタインなど特有の栄養成分も多く含まれています。
「皮をむかずに加熱する」など下ごしらえのポイントを押さえることで効率よく栄養をとることができ、さまざまな調理にも応用可能です。美しい赤紫色も豊かな食生活を演出してくれるので、積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
監修:日本野菜ソムリエ協会



























