漁師の生命線を握る 造船師

漁師の船は1隻ずつ仕様や大きさが異なるオーダーメイド品。それぞれの漁法や自然環境に合わせて、こだわりを持って造られています。漁師の要望に応えて船を新しく造ったり、修繕したりするのが造船師の仕事。
新人造船師が一人前に成長するまでにはたくさんの経験が必要となるため、造船の現場でも高齢化や人材不足が問題となっています。
造船所のまわりには、鉄鋼会社、電気会社、油圧会社など、船を整備するのに欠かせない企業が集まっています。
必要な道具はお任せあれ 漁具・資材会社

漁師はそれぞれの海、漁法によって漁具が異なります。ロープひとつとっても素材や太さが異なりますし、水揚げした魚を入れる箱や樽も、海に浮かんでいる浮き玉(フロート)も、大きさや形、素材などさまざまで、用途によって異なります。
漁師のニーズに合わせ、道具や資材を用意するのが漁具・資材会社の仕事。こまめに浜に顔を出し、漁師とコミュニケーションを取りながら、必要なものを汲み取って道具を用意します。
漁師のマネージャー 漁協職員

漁業協組合とは、水産業協同組合法において組合員の相互補助を目的とした組織を言います。漁村地域の中枢的な役割を担っており、組合員のために販売、購買、信用、共済などの事業を行うほか、知事から与えれた沿岸部の漁業権の管理や組合員に対する指導を通じて、水産資源の適切な利用と管理を行っています。忙しい漁師に変わって、さまざまな仕事をこなす「漁師のマネージャー」。最近では、担い手事業や漁業者の所得向上、販路開拓を積極的に行う漁協もあります。
中継プレーで食のバトンを繋ぐ 卸売業者

漁師が水揚げした魚は、市場を通す「市場内流通」と市場を通さない「市場外流通」に分かれますが、市場内流通に欠かせないのが、仲買人、仲卸人といった卸売業者の存在です。彼らは産地市場から消費地市場へ、はたまた飲食店へと、魚を広く流通させる役割を担っています。活魚で仕入れた魚に神経締めなどの手当てを施して、魚の鮮度を保って良い状態で出荷する工夫をしている卸売人もいます。
日本の食卓を支える影のヒーロー 水産加工会社

日本の食用魚介類の国内消費の6割は加工品として供給されています。近年は家庭で魚を捌くということが少なくなっているので、家庭で気軽に魚を調理できるように水産加工会社が奮闘しています。
冷凍技術の発達により、魚の鮮度そのままに長期保存が可能になりました。水産物の付加価値の向上や魚食普及に欠かせない存在でありながら、近年は働き手不足が問題になっています。現場では海外実習生なども多く活躍しています。
安心・安全を未来へ繋ぐ 水産技術職
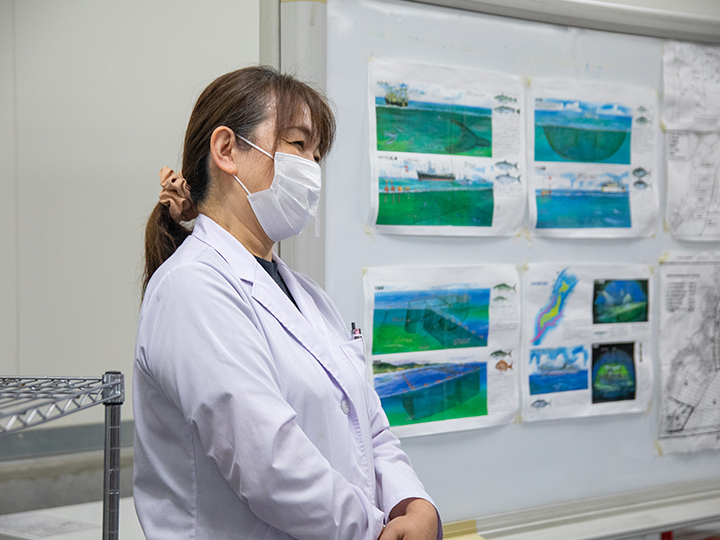
安心・安全な魚を食べてもらうため、そして未来にこの豊かな海を繋ぐことがミッション。日夜、海の環境の変化や漁獲される魚などを調べ、研究しています。
さまざまな水産技術職があり、漁獲量が減ってきている魚を養殖・放流して回復の傾向があるか調査を行う仕事や、市場や専門機関で放射能や有毒な物質がないか測定を行う仕事などがあります。漁師が水揚げした魚の安心安全を後押しし、資源が枯渇しないように豊かな海を未来へ繋ぐために奔走しています。
日本中へ魚を運ぶ 運送業者

冷蔵・冷凍技術が普及したことで、新鮮な状態の魚を日本中どこへでも運ぶことができるようになりました。大型の冷蔵・冷凍車だけでなく、活魚を必要とする料亭や飲食店もあるため、大きな水槽を搭載した活魚車も活躍しています。ほかにも、稚魚を運んだり、魚の飼料を運んだりと、水産業において「運ぶ」仕事は欠かせません。
おいしい魚を未来に繋ぐために
一次産業の仕事はどうしても生産者に目が向きがちですが、彼らの仕事を全力でサポートする人たちの存在があるからこそ、漁師たちは仕事に専念できます。ここに紹介した仕事以外にも、市場を管理・運営する職員や、おいしい魚を提供する飲食店、仕事の効率化を図るシステムを開発するIT企業など、水産業を支えるたくさんの仕事があります。
水産業の担い手不足は漁師の現場だけでなく、これらすべての現場において深刻です。海や魚に興味がある人がいたら、広い視点で水産業を見つめ、自分に合った仕事を模索してみてください。
関連サイト:TRITON JOB「【漁師入門】覚えておきたい!漁具10選」「漁協と浜と未来と」「【生産のその先】水産業の流通の仕組みを教えて!」

























