田舎の土地を相続するメリット三つ

田舎の土地は一見魅力に欠けるように感じるかもしれません。しかし相続するメリットも以下の通り存在します。
- 通常より安く土地を取得できる
- 収益化できる可能性がある
- 地価が上昇する可能性がある
通常より安く土地を取得できる
田舎の土地を相続する場合、通常の購入時にかかる不動産取得税が免除されるため、取得費用を大幅に抑えられるというメリットがあります。
また、田舎の土地は相続財産の価値を表す「相続税評価額」が低い傾向にあり、都市部の土地よりも相続税や登録免許税の負担も軽減されます。
そのため、将来的に売却や活用計画の見込みがある土地の場合、安価で資産を取得できる絶好の機会といえます。
収益化できる可能性がある
本記事の最初に触れた通り、相続した田舎の土地を上手に活用することで収入を得られるようになる可能性があります。
たとえば、駐車場や賃貸アパート、太陽光発電や事業用地などとして活用・貸し出しできれば、安定的な副収入を得られる可能性は十分にあるでしょう。また近年では、キャンプ場やグランピング施設、田舎暮らしを体験できるシェアハウスなども注目されており、田舎ならではの自然豊かな土地を生かしたビジネスを展開することも可能です。
地価が上昇し、売却益を得られることも
相続しようとしている田舎の土地周辺の再開発が行われることによって、地価が上がる可能性があります。
例えば、新しい交通機関や観光スポット、規模の大きい工場が建設されるといったケースです。相続した時点では地価が低い田舎の土地であっても、地価が上昇したタイミングで売却すれば、より大きな利益を得ることが可能になります。
田舎の土地を相続するデメリット三つ

ここまで田舎の土地を相続するメリットを紹介してきました。
しかし現実的な問題として田舎の土地の相続には、メリットよりも負担や問題が大きい場合も多く、特に以下の三つのデメリットには注意が必要です。
- 固定資産税と維持管理費の負担が大きい
- 売却・活用できない可能性がある
- 次世代への問題の先送りとなる
後悔のない選択ができるように、相続後に考えられる負担やトラブルをしっかり理解しておきましょう。
固定資産税と維持管理費の負担が大きい
たとえ何もない土地であっても、相続すれば土地を所有しているだけで税金などのコストが発生します。
代表的なものは固定資産税です。固定資産税は土地に課される税金のことで、固定資産税評価額×1.4%で算出されます。例えば固定資産税評価額500万円の土地を所有していた場合、500万円×1.4%=7万円が毎年必要になってきます。
また、空き地の草木をそのままにしておくと、近隣からクレームが来る可能性もあり、定期的なメンテナンスが必要になる場合もあります。
このように、固定資産税や維持管理費は、価値の低い田舎の土地であっても、手放さない限り半永久的に続く出費となるため、相続した際の大きな負担となります。維持管理などは業者に依頼すると手間がかからず安心ですが、その分かかるコストは増えていくため注意が必要です。
売却・活用できない可能性が高い
都市部に比べて人口が少ない田舎では土地の需要も少なく、売却先がなかなか見つかりにくい傾向にあります。
買い手が見つからない期間も上記の固定資産税がかかってくることに加え、引き取り手が見つかったとしても、無償譲渡になる場合も珍しくありません。
また、土地を活用するにしても、田舎では商業や賃貸需要が限られているため、有効的なアイデアや機会が乏しく、地域によってはそもそも土地の用途が限定されている場合もあります。
これらの理由から、売却も活用もできない土地は、コストと手間ばかりかかる荷物となるため、相続した際の大きな負担となります。
次世代への問題の先送りとなる
相続した田舎の土地を売却も活用もできず放置してしまうと、子や孫世代に問題を先送りすることになります。
土地にかかる維持費や税金は相続人が支払い続けることになり、土地所有権の問題で親戚間トラブルにつながることもあるでしょう。不要な土地の相続は、次世代にとって経済的・労力的な負担になるだけでなく、人間関係にも影響を及ぼす「負の遺産」となる可能性があります。
そのため、田舎の土地をすでに相続している場合は、なるべく早めに処分方法を検討しておきましょう。
田舎の土地は相続する? 相続の判断基準3点
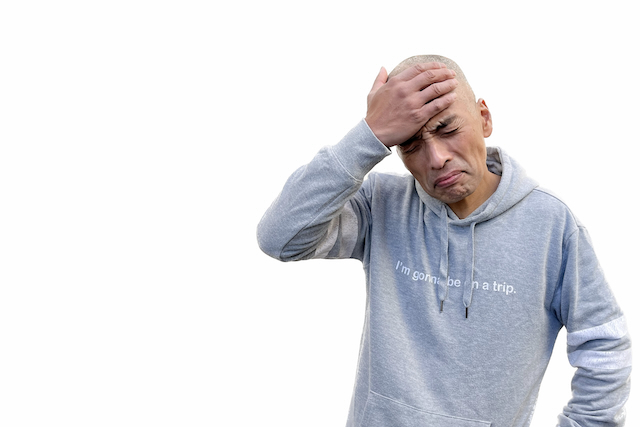
田舎の土地の相続が発生した際には、その価値を正確に見極めることが大切です。より重要な判断基準となるのは以下の3点です。
- 土地の活用・売却の可能性
- 固定資産税と維持管理コスト
- 土地とその他金融資産のバランス
土地の活用・売却の可能性を確認する
活用・売却できる見込みのある土地であれば、相続にかかったコストを上回る収益源になる可能性があるため、相続する価値があるといえます。
例えば、立地条件が良かったり周辺地域の発展性が見込めたりする場合には、賃貸や駐車場経営をはじめとする土地活用、もしくは売却できる可能性が高いでしょう。
しかし、前述した通り、田舎の土地は需要が少ない傾向にあり、活用・売却が困難なケースが非常に多いです。
そのため、相続する前に、まずは活用・売却できる可能性はあるのかについて不動産会社などと相談をしておくのがおすすめです。
中には、不動産会社というと尻込みしてしまう方もいると思います。
その場合には、インターネット上で一括査定ができる不動産一括査定サイト「リビンマッチ」がおすすめです。
不動産一括査定サイトの中には農地の査定は行っていないサイトもありますが、リビンマッチは一括査定サイトがまだ普及していなかった2006年のサービス開始時から土地や農地査定を行っています。
土地や農地査定に関して長い歴史を持ち、信頼性の高いサイトですので、活用してみるとよいでしょう。
⇒完全無料!不動産一括査定サイト【リビンマッチ】はこちら
固定資産税と維持管理コストを見ておく
前述した通り、土地を所有しているだけでも固定資産税がかかってきます。また場所に応じては都市計画税がかかるケースや、家が残っている場合は光熱費や維持費も必要になってきます。
ただし、固定資産税や都市計画税には軽減措置が設けられているため、建物の有無によって税額は変わってきます。このように、土地を所有するだけでかかるコストは所有している地域や状況に応じて変動します。
そのため、目安として相続する前の5~10年間ほどの期間に、毎年合計どれくらいのコストがかかるのかを把握しておくことが重要です。
土地とその他金融資産のバランスを確認する
上記の「固定資産税と維持管理コストを見ておく」に関連して、田舎の土地以外の金融資産も相続する場合、それらを含めた全体の資産額にも注目しておくことが重要です。
例えば土地のような不動産だけでなく、預貯金や株式なども相続する場合は、それらの資産額で固定資産税をはじめとする維持管理コストを賄える可能性もあるからです。
しかし逆にいえば、せっかく相続した金融資産が相続した田舎の土地の維持管理費に消えてしまうということにもなりかねません。
目安として「相続する金融資産が500万円以下」の場合は、土地にかかる税金や管理費などにより、わずか数年で金融資産が底を突く可能性があるといわれています。
そのため、相続する資産全体を見て、土地は早めに処分するべきなのか(負動産になってしまうのか)を確認しておくことが重要です。
相続した田舎の土地の処分方法

判断基準と照らし合わせて田舎の土地を相続するデメリットが大きい場合、手放すことも一つの選択肢として考えましょう。田舎の土地の主な処分方法は以下の通りです。
- 売却(有償での譲渡)
- 無償での寄付
- 相続放棄
売却(有償での譲渡)
土地の売却は、売却益が得られるようになるため、もっとも好ましい処分方法です。ただし繰り返しになりますが田舎の土地は買い手がつかないケースが多く、売り出し価格を下げると利益はほとんど残らない可能性も大いにあります。
とはいえ、所有し続けるコストや負担を考えれば、利益が少なくても売却するメリットは大きいといえるでしょう。そのため、相続した田舎の土地を処分する際は、まず売却から検討してみましょう。
無償での寄付
相続した田舎の土地の状況や需要によっては、買い手がなかなか見つからないことも。そのような場合には、無償で寄付することも検討しましょう。公益法人や自治体によっては、無償で土地を引き取ってくれる場合があります。
土地を寄付する場合は利益こそ得られないものの、税金や維持コストの支払いや管理の手間、精神的な不安などの煩わしい問題からは開放されます。
相続放棄
田舎の土地を相続する前であれば「相続放棄」を選択できます。
相続放棄とは、相続財産に対する法的責任を拒否することです。相続が発生した段階で家庭裁判所に申述すれば、税金を支払う義務も、自ら処分する必要もなくなります。ただし以下のような注意点もあります。
- 全ての財産を相続放棄することになる
- 申請できるのは相続開始3ヵ月以内
- 相続放棄後は相続人には戻れない
- 相続放棄後は後順位の方が相続人になる
- 次の相続人に引き渡すまでは管理義務がある
加えて書類のやり取りなど煩雑な作業も発生します。
そのため、相続放棄を行う場合は専門家のサポートは必須です。
相続した田舎の土地が売れない場合の最終手段

繰り返しになりますが、売却や活用、寄付もできない土地は、所有しているだけで固定資産税や管理の手間が発生し、毎年数万〜数十万円のコストがかかります。
このような負動産は、子どもの代まで続く重荷となってしまうため、最終手段として有償でも引き取ってもらうことがおすすめです。
まずは土地活用の可能性を考えよう
今回は、田舎の土地を相続する判断基準やメリット・デメリット、相続した土地の処分方法について解説しました。相続した土地は、資産としての活用や売却による収益化の可能性がある一方で、税金や維持管理の負担、次世代まで続く負の遺産となる大きなリスクも持っています。
将来の生活に大きな影響を与える場合もあるため、あらゆる角度から長期的な視点で判断する必要がありますが、一人で適切な判断をすることは難しいのが現実です。
そのため、相続すべきか悩んでいる方や処分に困っている方は、まずは活用方法や売却できる可能性があるのかを調査した上で、相続の専門家に相談することをおすすめします。
田舎の土地を売却する際は、リビンマッチのような不動産一括査定サイトを利用するのがよいでしょう。
リビンマッチであれば、 全国約1,700社の不動産会社の中から売却する不動産に適した不動産会社を紹介してもらえます。
土地売却では、まずリビンマッチを利用することをおすすめします。
⇒完全無料!不動産一括査定サイト【リビンマッチ】はこちら
参考URL:
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/waiver/12/
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/inaka-tochi-souzoku/
https://www.l-faith.com/service/sozoku/column/detail1962/
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/countryside-land-unnecessary-8899#23
https://souzokuplus.com/columns/fudosan/1492/
https://areps.co.jp/owner/knowledge/merit-demerit-inheriting-rural-land/#i-17
https://areps.co.jp/owner/knowledge/inheritance-rural-land-hell/
https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00210




























