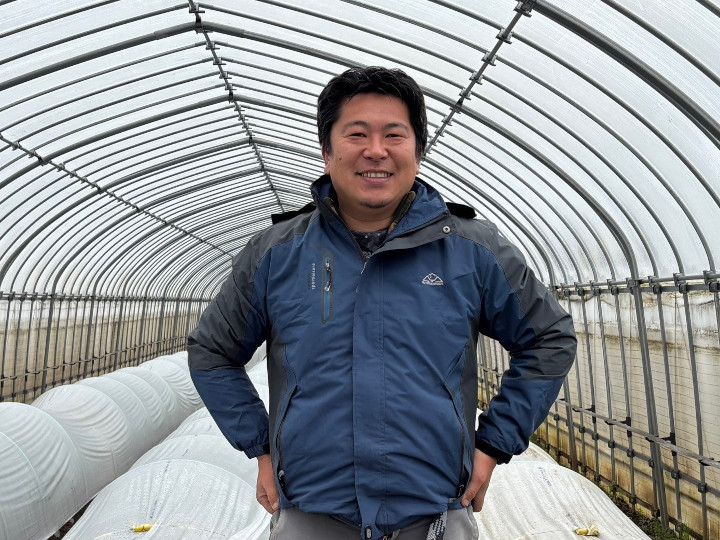政府備蓄米の大半を放出
農林水産省は100万トンをメドに政府備蓄米の制度を運用している。放出を始める前に実際に保管していたのは約90万トンだったとされる。
米価の高騰を抑えるべきだとの世論の高まりを受け、3月に2回に分けて実施した入札で放出の対象になったのは21万トン。近く実施する入札で10万トンの放出を予定しており、これで残りは約60万トンになる。
仮に5月から7月まで毎月10万トンずつ放出すれば、残りはたったの30万トンになる。米価の高騰が収まって放出すべき量が減ったとしても、備蓄制度がメドにしている100万トンを大きく下回るのは間違いない。
ではこの先何が必要になるのか。今回の混乱から導き出される答えは1つだろう。全国で足並みをそろえて生産調整するのをやめて、可能な地域はできるだけ増産する。半世紀余り続いた政策の抜本見直しだ。

緊急時にはMA米も主食へ
政府備蓄が大きく減ったからといって、目標としている量までただちに補充するのは難しい。そんなことをすればただでさえタイトな需給がいっそう引き締まって、米価のさらなる高騰を招くのは必至だからだ。
この点に関し、農水省はもし必要なら海外から輸入するミニマムアクセス(MA)のコメを主食に回す方針を示している。これまでは主食米の需給に影響するのを避けるため、一部を除いて飼料などに充てていた。
農業界にはMA制度の趣旨に反するとして反対する声もある。だが米価高騰とコメ不足への消費者の不安を考えれば、必要な措置だろう。
問題はこの先だ。緊急時への備えを確かなものにするには、備蓄制度が前提としている量を数年かけて回復させるか、あるいはそれ以上まで増やすのが不可欠。それには当然、市場の需要を大幅に上回る生産が求められる。

備蓄放出でも米価は高止まり
ここでいったん今回の混乱の原因を振り返ってみよう。発端は2023年の猛暑。高温障害で米粒が白濁したり、割れたりして、主食用で必要な量を確保できなくなった。その影響は2024年春ごろに顕在化した。
農水省は当初、2024年産米が出回り始めれば、事態は沈静化すると予想していた。だが見通しはもろくも外れ、米価はその後も上がり続けた。
もう1つの誤算は、備蓄米の放出の効果が思うように上がらなかったことだ。2025年3月31日~4月6日に全国のスーパーで販売されたコメの5キロ当たりの平均価格は前年同期の2倍超の4214円と、過去最高値を更新した。
もともと政府備蓄米は「10年に1度の不作」などに対応するのを目的にしていた。ところが2023年と2024年の作況指数はいずれも平年並みの「101」。にもかかわらずコメが足りなくなったのは想定外の事態と言える。
そこで農水省が講じたのは、放出の基準に「主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合」を加えること。ただそれは急場しのぎの手立てに過ぎない。農政がいま取り組むべきなのは流通以上に、生産の課題解決だ。

米所の増産が今後の課題
2023年の作況指数が101にもかかわらずコメが足りなくなったのは、収穫した量は平年並みだったとしても、そのうち主食に回せるコメが十分でなかったからだ。2024年は各地でイネカメムシによる深刻な被害が出た。
農家数が減り続け、ただでさえ生産基盤が弱っているのに、異常気象で生産が揺さぶられる。生産調整で需給をバランスさせようにも不確定な要素が多すぎる。生産量に余裕を持たせないと、今回のような混乱を繰り返す。