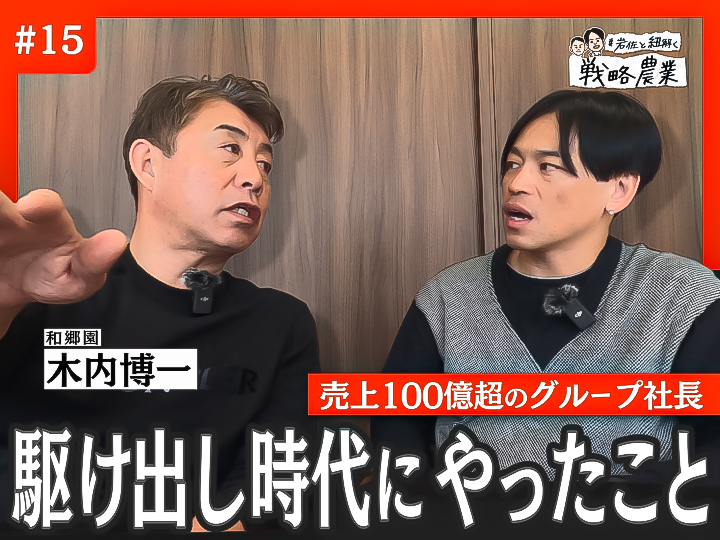■プロフィール
■木内博一さん
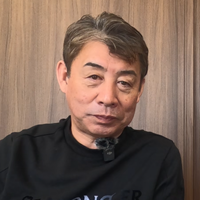 |
株式会社和郷 代表取締役、農事組合法人和郷園 代表理事 1967年千葉県生まれ。農業者大学校を卒業後、1990年に就農。翌年、有志5人で野菜の直販を開始。「和のマネジメントと郷の精神」で約90の農家をグループ化。約50社の取引先に共通ブランドの野菜を販売。事業地域に密着した循環型農業のビジネスモデルを構築している。 |
■岩佐大輝さん
 |
株式会社GRA代表取締役CEO 1977年、宮城県山元町生まれ。大学在学中に起業し、日本及び海外で複数の法人のトップを務める。2011年の東日本大震災後に、大きな被害を受けた故郷山元町の復興を目的にGRAを設立。著書は『99%の絶望の中に「1%のチャンス」は実る』(ダイヤモンド社)他。 |
■横山拓哉
 |
株式会社マイナビ 地域活性CSV事業部 事業部長 北海道出身。国内外大手300社以上への採用支援、地域創生事業部門などで企画・サービスの立ち上げを経験。2023年4月より同事業部長就任。「農家をもっと豊かに」をテーマに、全国の農家の声に耳を傾け、奔走中。 |
和郷園の“転機”
岩佐:加工分野に進出した後、次なる一手として木内さんが投資したのはアグリテックの普及ですよね。
木内:この分野への投資は、ハード面だけではなく、オペレーションをする人材にも必要です。それを考えると、そこそこの規模の農家でも足踏みしてしまうもの。でも、これをやらないと文化は変わらないと思いました。そこで和郷の子会社として、福井和郷をつくったんです。今、農業界では輸出を促進する動きがありますが、昔から僕は、素材ではなく“日本食”そのものを輸出するべきだと言ってきました。
岩佐:日本食そのものを輸出するとは。
木内:外国人観光客は「日本の居酒屋には、こんなに安くておいしいものがある」と言いますよね。それは日本に整ったサプライチェーンがあるから。極端な言い方をすれば、飲食店は良い物件を見つけて、そこでおいしいものを出せば良い。食材は電話1本で全部そろいます。だから日本でオペレーションできるんです。だけど海外に行った時には、サプライチェーン全部をつくらなきゃいけない。
横山:そうですね。
木内:例えばヨーロッパに進出して、ドミナント戦略で約100店舗出すとします。すると、それを支えるコンビナートが必要になる。その設計を福井和郷で初めてやったわけです。約8ヘクタールの敷地に人工光利用型植物工場を建てました。太陽光利用型の施設も併設されています。ほとんどの果菜類、葉物類を作ることができますよ。
岩佐:大きいですね!
木内:もう一つ、食材のカット、冷凍、乾燥までを一気に行うフリーズドライ工場もあります。ここをアッセンブリー工場と考えれば、店舗で販売する商品を全てマネジメントできることになります。そういう日本のテクノロジーと、きめ細かな管理能力を組み合わせて飲食店を展開すれば、日本食ブームが起きると考えています。
岩佐:日本食を展開したい場所に、福井和郷のような施設を持って行くということですね。
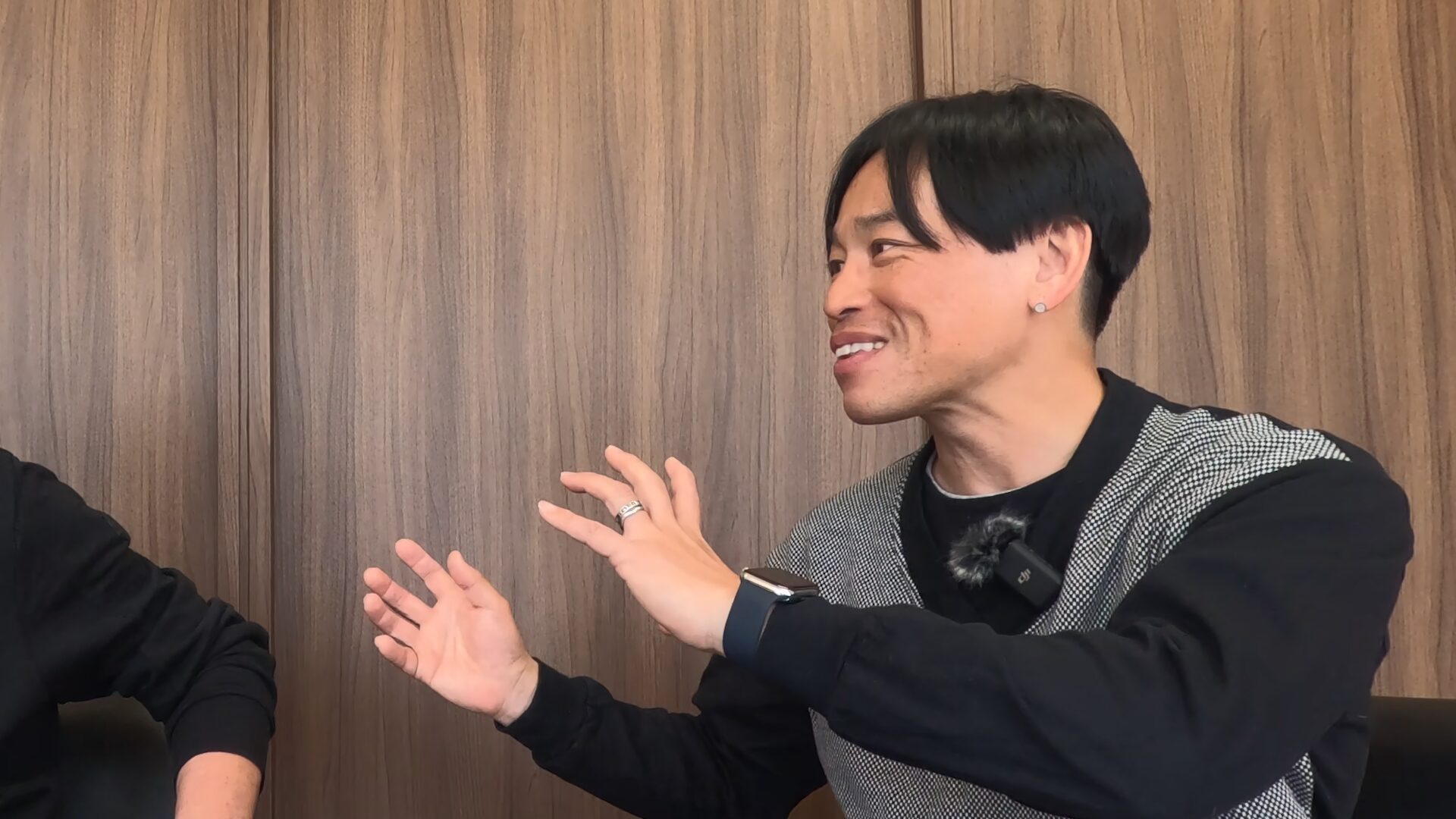
利益を上げるために行っている「コストのトレーサビリティー」
木内:僕は約10年前から、安心安全のトレーサビリティーではなく、コストのトレーサビリティーを基に、“あるべき価格”の目安を出すべきだと主張してきました。それで最近、感動したことがあるんです。2025年2月、東京・丸の内のある商業施設で行われた「値段のないスーパーマーケット」というイベントです。これは農水省のプロジェクトの一環で、消費者に食品の適正価格を理解してもらうことを目的としています。
岩佐:どうやって商品を購入するんですか。
木内:牛乳やタマネギなどの食品が値札の無い状態で販売されています。お客さんは商品をレジに持って行って、売り手・買い手・作り手みんなにとってフェアだと思う値段を自分で入力し、購入します。答えはレシートに「高め」「低め」「ぴったり」の3段階で表示される仕組みです。
岩佐:面白いですね。
木内:僕がやっている約50品目の生産原価を算出してみると、ほとんどは2~3割、原価割れしています。これが市場の基準となる価格になってしまっているんです。その価格を基にバイヤーは、例えばどれぐらい農薬を減らしたか、どれぐらいおいしいかといった点を考慮して値段を付けてくれます。しかし、それで上乗せされるのは、最大でも2割ほど。これだけでは原価割れを補うことはできても、成長はできません。
岩佐:では和郷が成長できているのはなぜですか。
木内:農業はインフラ産業。補助金などを活用し、かつ大きなスケールでインフラ投資を行ってきたからです。スケールが大きければ、初期投資のコストもぐっと抑えられます。更に産直などの市場を通さない仕組みづくりや、物流の整備など、細かく無駄な手数料を省いていけば、何とか10%弱の成長を目指せます。

人工光型の植物工場がうまくいっていない理由
岩佐:グローバルで見ても、人工光型の植物工場はあまりうまくいっていないと聞きます。木内さんから見て、問題はどこにあると思いますか。
木内:小売のマーケットをベースに考えているからだと思います。価格的にも露地やグリーンハウス(温室)で作ったものが主流であるマーケットに、植物工場のものを並べたら、どうしても差が出てきますよね。ただ、面白いデータもあります。一時期レタスがすごく安くなって、あるスーパーでは、うちの植物工場のレタスが100~120円、玉レタスが一つ70~80円で売られていたことがありました。でも、注文はほとんど減らなかったんです。
岩佐:なぜですか。
木内:うちの植物工場のレタスは、菌がほとんど付着していないので、冷蔵庫の中で日持ちします。例えば、ハンバーグに添えたいときも、1枚だけ剥がして使えて便利なんです。使い切れなくても茶色くなったり、弱ったりしないので衛生的にも安心です。こうした利便性があって、30~40円ぐらいの価格差であれば、うちのレタスを選んでくれる人の数は変わらないんだと気付きました。
岩佐:価格差を広げないためにも、一定の量を作るのは最低条件ですね。
木内:そこが生産技術なんですよ。作物の生産には、「成長のカーブ」というものがあります。これは縦軸を作物の「重量」、横軸を「日数」としてグラフにしたときに出てくるものです。生産者は、できるだけ日数を短くして重量を上げたい。そのために光の量や肥料、温度、湿度、CO2などを全て調整していきます。すると、ずっと横ばいだったグラフが、ある時期からぐっと上に伸びていきます。
岩佐:「J」の字のようなカーブになるんですね。
木内:その時、技術が無ければチップバーン(葉先が黒くなる生理障害)で商品がダメになる。すると売り物になりません。チップバーンを出さないで作ることができれば、重量はしっかりと上がります。これができないとダメなんです。だから植物工場って、プラントを買えば良いんじゃなくて、圧倒的にソフト。栽培技術なんですよ。
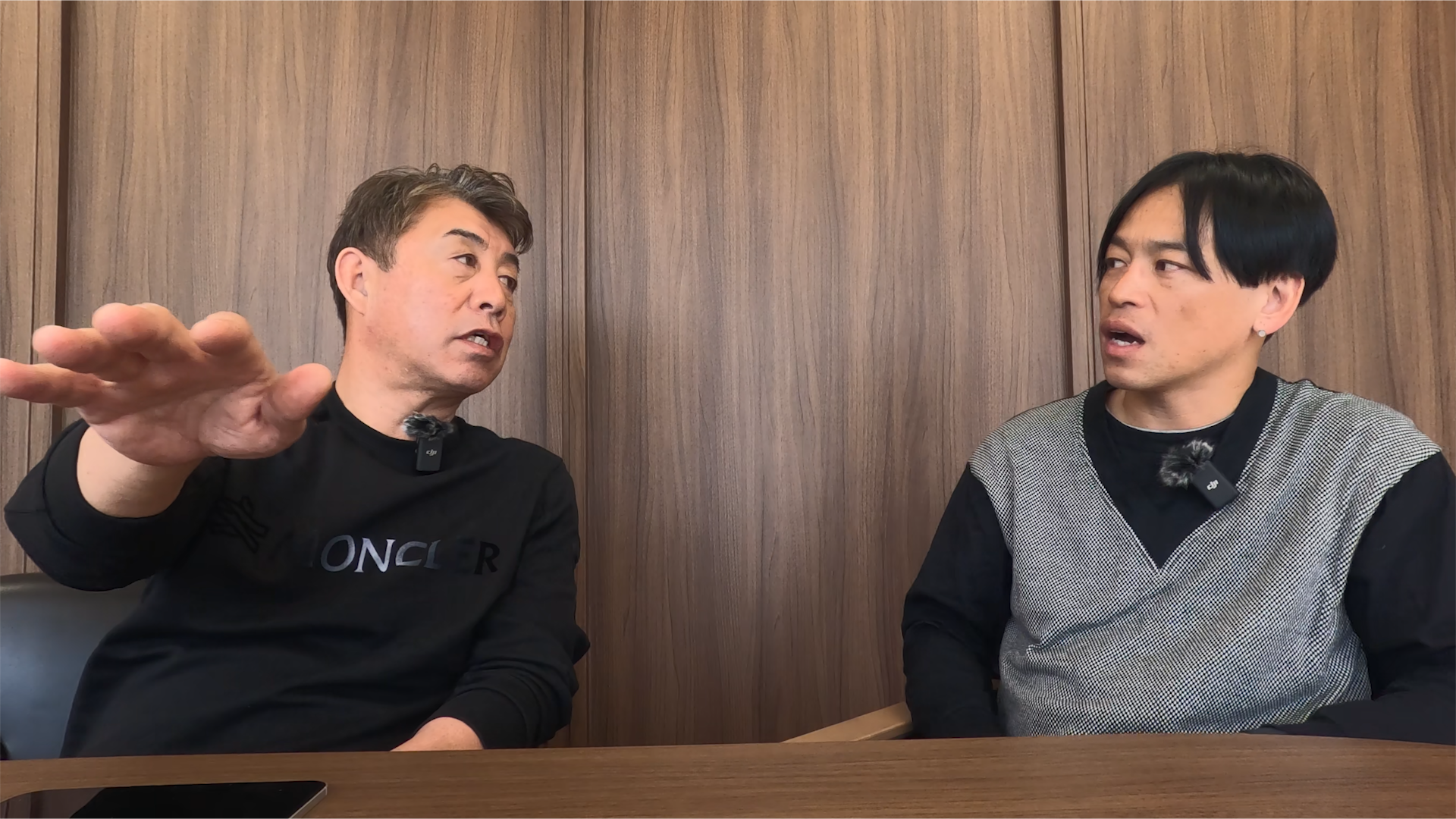
農業者へメッセージ
岩佐:これから農業を始める人や、今苦戦してる方にメッセージをお願いします。
木内:農業は投資産業だから、まずはある程度技術をしっかり磨いていくことが大切だと思います。あとはグローバルに視野を広げること。日本には四季がありますが、例えば東南アジアの高原地帯には一年中春のような気候の場所もあります。そういう場所に輸出するだけでなく、出て行ってみる。そして日本の技術でものづくりをして、できたものを第三国に輸出する。その所得収支で日本に貢献するというのも、立派な農業経営者だと思います。これからの若い人たちには、そういうグローバルな挑戦もしてほしいです。
岩佐:Go Globalということですね。ありがとうございました。
まとめ
岩佐:和郷のすごいポイントを4つ、振り返りたいと思います。
| 和郷グループの農業戦略のポイント | ||
| ① | 四の五の言わずにどぶ板い営業 | 現場に行くからこそ潜在的ニーズを掴める。まずは現場に行き、課題解決に取り組む。 |
| ② | プロダクトアウトではなくマーケットイン | 消費者目線のニーズに合わせた付加価値を考える。マーケットの変化を把握した投資により新たな雇用も生まれる。 |
| ③ | 圧倒的な投資で構造優位を作る | ここぞという時は思い切って投資を行い、二番手の追随を許さないレベルまで上がる。正しい投資判断が出来るための目を養っていくことも大事。 |
| ④ | とにかく行動して常に学ぶ | 農業経営を客観的に判断することで、その先の行動が変わってくる。また行動の量・早さが売上につながっている。 |
岩佐:以上、4つが和郷のポイントでした。ぜひ皆さん参考にしてみてください。
(編集協力:三坂輝プロダクション)