【プロフィール】
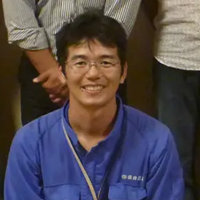 |
■横田修一さんプロフィール 有限会社横田農場 代表取締役 茨城県龍ケ崎市で800年以上前から続くコメ農家。茨城大学農学部で農業経営を学び、卒業後の1996年、父が法人化した横田農場に就農する。約20ヘクタールだった農地は、約177ヘクタール(2025年現在)に拡大。コメの生産以外に、米粉のスイーツ作りや、田植え体験、料理教室なども行う。 |
■岩佐大輝さん
 |
株式会社GRA代表取締役CEO 1977年、宮城県山元町生まれ。大学在学中に起業し、日本及び海外で複数の法人のトップを務める。2011年の東日本大震災後に、大きな被害を受けた故郷山元町の復興を目的にGRAを設立。著書は『99%の絶望の中に「1%のチャンス」は実る』(ダイヤモンド社)ほか。 |
■横山拓哉
 |
株式会社マイナビ 地域活性CSV事業部 事業部長 北海道出身。国内外大手300社以上への採用支援、地域創生事業部門などで企画・サービスの立ち上げを経験。2023年4月より同事業部長就任。「農家をもっと豊かに」をテーマに、全国の農家の声に耳を傾け、奔走中。 |
消費者との信頼関係を築く、横田農場のビジネス
岩佐:まずは経営の全体像について教えてください。
横田:2025年の作付面積は177ヘクタールで、全てコメを作っています。うちの特徴は、少ない機械・少ない人数で広い面積を管理し、コストを下げていること。実際に使っているのは田植え機1台、コンバイン1台です。
岩佐:販路はどう確保していますか。
横田:今は一時中止していますがネット販売で各家庭に直接発送したり、スーパー6店舗で販売したりしています。「消化仕入れ」という取引形態をとっていて、直売所のように自分でスーパーの棚にコメを並べ、売れたら追加しています。あとは業務用や加工用として、飲食店や食品メーカーに卸しています。
岩佐:横田さんが全て値決めできるということですね。農協に卸すのと比べて、販売単価はどれぐらい変わるものなんでしょうか。
横田:基本的には、自分たちでコストや取りたい利益を設定した上で値段を決めます。農協の相場を基に設定すると、それが変動した時に、私たちも値段を変えなければいけません。そういう売り方をしたくなかったので、私たちは一度決めた値段で売ることを目標にやってきました。世の中の相場が安くなれば利幅が大きくなるし、高くなればもうかりません。
岩佐:どうしても価格を下げざるを得ないことはありましたか。
横田:下げたことはないですよ。信頼関係を結べるお客さんをどれだけ増やせるかだと思っています。そのために情報発信や稲刈り体験などを行っています。うちは今年、1000トン弱のコメを収穫できる見込みです。これは2万人弱が1年間に食べるコメの量です。2万人の中には子供も含まれますから、実際に買うのはその4分の1。つまり5000人が横田農場のコメを買うと決めてくれれば、うちは売り先に困らないと考えています。

規模の不経済の可能性
岩佐:今の設備でできる最大規模はどれぐらいですか。
横田:おそらく250~300ヘクタールが限界です。
岩佐:300ヘクタールまでは規模の不経済が働かないと考えていいのでしょうか。
横田:地域によって全く違うので、一概には言えません。ただ、常識に縛られているところも大きいと思います。例えば、作付面積が約3ヘクタールの農家が、規模を拡大していくと、15ヘクタールぐらいまではコストが下がります。でも、それ以上は更に設備投資をしないとコストが下がらないという統計があります。そうした数字に、みんな縛られていると思います。
岩佐:なるほど。
横田:農家をやめる人は増えていますから、農地が増えても受け入れに困る。だから、やり方を変える必要があります。私たちはいろんな品種を作って、作期分散させるなどして、規模拡大に対応してきました。ただ、言うのは簡単ですが、実際にやるのはかなり難しいと思います。
岩佐:それはなぜですか。
横田:一番の課題はオペレーションだと思います。人間はもう何千年もコメを作ってきたのに、なぜこの時期に種まきをするのかと言ったら、「これまでこの時期にしてきたから」というぐらいです。私たちは、いつ種子の取得を始めて、いつまいて、いつまでに植えて、いつまでにハウスに並べて……といったことを、びっちりスケジュールを立てて、種まきをする時期を決めます。
岩佐:ガントチャート(線表)を作って、やるべきことを洗い出すということですね。オペレーションマネジメントをする上で、最初にすべきことは何ですか。
横田:あらゆる数字をつかむことが大事だと思います。それは農機メーカーから言われるものではなく、自分がなんとかしたい課題の解決につながるような数字でなければいけません。課題を解決するためには、どんな数字が分かればいいのか。そこを自分で見つけて、一つでも改善することだと思います。

令和の米騒動から考える“需要に応じた生産”の在り方
岩佐:いわゆる“令和の米騒動”といわれる今、消費者や農家、国、さまざまな立場の思いが交錯しています。この現状をどう打破すればいいと考えますか。
横田:例えば大手コンビニチェーンや外食チェーンは、1年間に使用するコメの量をあらかじめ算出して調達していますよね。そうでないところは、その都度買うか、安くなった時に買うという調達の仕方をしていました。後者は、コメがたくさんあった時代が長く続いていたからできたことです。でも、コメがなくなれば「もう買えない」「高くて買えない」と大騒ぎになります。
岩佐:そうですよね。
横田:あらかじめ必要な量が分かるのであれば、前もって調達しておくことが必要だと思います。それはいち消費者も同じです。うちも年間契約を結んで、毎月決まった量を発送する取り組みも行っています。コメの消費量は、そんなに極端に増えたり減ったりしないと思います。うちも、そういうファンに向けてしっかりと作って販売していきたいと考えています。それこそが、農林水産省のいう“需要に応じた生産”なのかもしれません。
岩佐:すごく素敵なスタイルだと思います。
横田:これだけ異常気象が起こると、今後正確な作況を測るのは難しくなります。一方で、最近のインバウンド需要も読みにくいわけですよね。コロナ禍のようなことも起こり得ますから。需要と供給のバランスを推測するのは難しくなっているからこそ、あらかじめ必要な量を販売してくれる人を見つけて、そこから買う約束をしておく。そういう取引の割合が高くなれば、今のような混乱は起きにくくなるだろうと思います。

重要なのは、コスト・販売先・利益・持続的な経営
横山:横田さんの長期的な目標を教えてください。
横田:「●●ヘクタールまで拡大したい」という目標はありません。積極的に規模を拡大しようと思ったことは一度もないんですよ。ただ、この地域には約500ヘクタールの農地があり、最終的には私がやらなければいけないとは思っています。
横山:なるほど。
横田:私が就農した頃は、規模拡大よりも販売単価を上げようと思って直接販売を始めました。一方で、残念ながらこの地域で農業をやめる人がどんどん増えていきました。「同じ地元だから」「うちの田んぼの隣だから」「この農道沿いだから」といった理由で、彼らの農地を集めていった結果、面積が増えていきました。
岩佐:自然と集まったんですね。
横田:この地域の圃場(ほじょう)は一区画が小さいところがほとんどです。もし仮にこの地域の田んぼを全部うちがやることになったら、あぜ抜きをして区画を大きくすれば、今のコストの限界を1段超えられる可能性があります。その必要があれば、やる意味はあると思っています。更に地域の枠を超えることになれば、1000ヘクタール、2000ヘクタールになるかもしれません。ただ、規模拡大は私にとってあまり重要ではありません。
岩佐:規模拡大が目的ではないと。
横田:より重要なのは、その時々でどういうコストで作って、どういう販売先に売って、どれだけの利益を出して、次の投資に回せるか。それによって持続的な経営ができるかです。
まとめ
岩佐:最後に、横田農場の経営のポイントをまとめます。
| 横田農場の農業戦略のポイント | ||
| ① | オペレーショナル・エクセレンスの構築 | 全ての農作業をガントチャートで管理し、作業の無駄を一切なくす。それによって最小限の人数・機械に抑え、製造原価に占める減価償却費を最小限にする。 |
| ② | 地代の契約をコメの相場連動制にする | 米価に応じて地代を払うことで、貸し手もモチベーションが上がり、信頼関係を構築できる。地域と共に取り組む姿勢が、規模拡大の基礎を築く。 |
| ③ | 直接販売で消費者との信頼関係を構築 | 消費者との接点をつくり、時間をかけて信頼関係を築く。ブランドの価値を高めることで、販売管理費や広告費をかけなくても、マーケットより高価格・安定価格で販売できる。 |
岩佐:横田さんは、自分の経営が良くても悪くても、絶対に外部環境のせいにしません。全ての環境が経営の責任だと思って会社を経営している、「ザ・農業経営者」です。なれるようで、なかなかなれない存在だと思います。
(編集協力:三坂輝プロダクション)





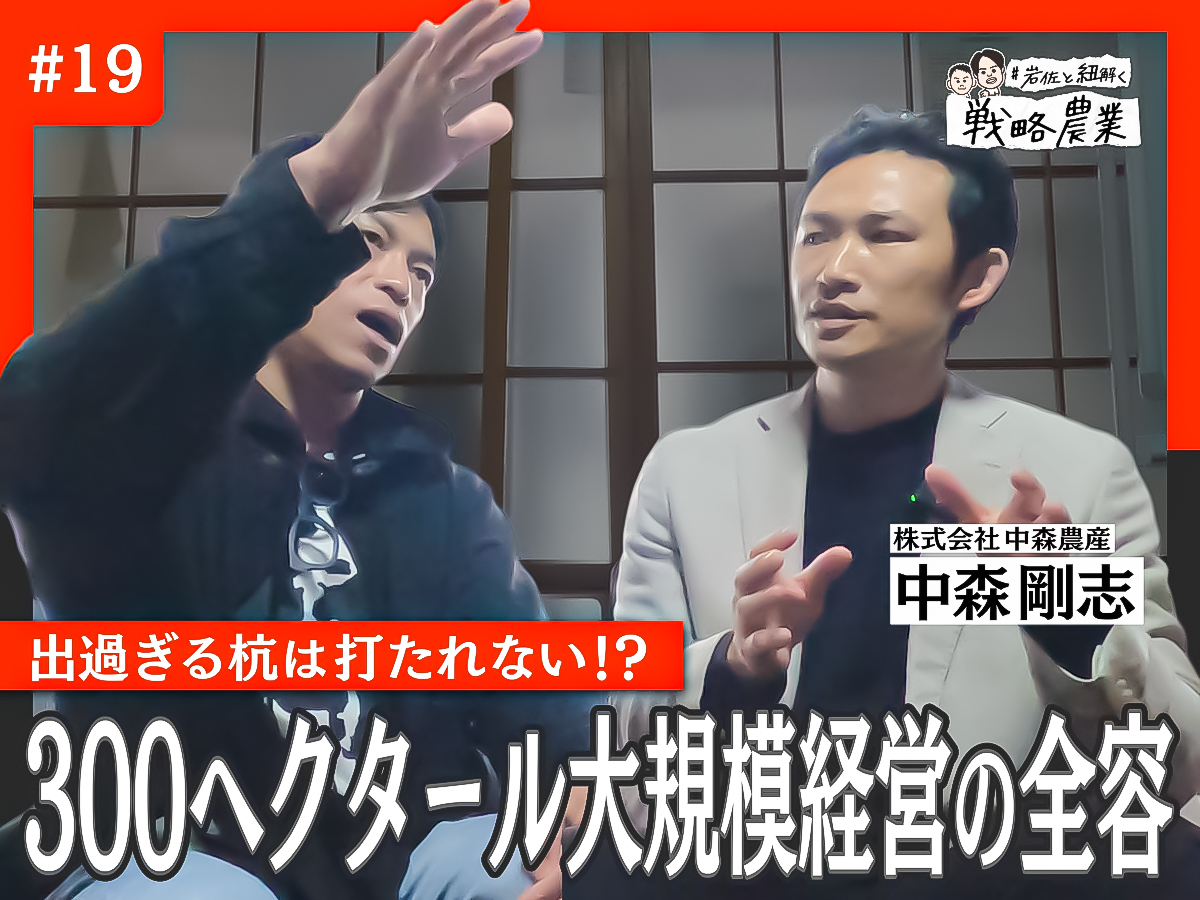






















読者の声を投稿する
読者の声を投稿するにはログインしてください。