無謀!? イチゴハウスの暖房を封印
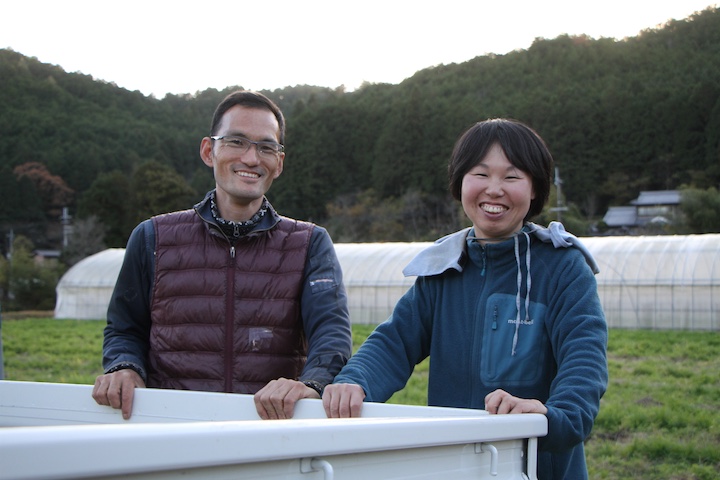
左から、吉村農園の吉村次郎(よしむら・じろう)さん、吉村聡子さん
就農10年目の2021年、吉村聡子さんはイチゴハウスの暖房を封印することに決めました。その決意を表わすように、灯油式の暖房機はブルーシートでぐるぐる巻きになっていました。
聡子さんが住む大阪府能勢町は、標高300メートルに位置する山に囲まれた町です。山間地ゆえに真冬は大阪とは思えないほど寒く、冷え込む早朝には氷点下8度程度まで下がることもあります。そんな能勢町で無加温イチゴを作るというのは、聡子さんいわく「無謀な挑戦」。
収穫量が大幅に減少する可能性も
聡子さんのイチゴは、3.6アールの小さな連棟ハウスでの促成栽培(12〜5月まで収穫する日本では一般的な作型)です。9月下旬に定植するイチゴは、極端な寒さに遭遇すると休眠してしまったり、低温で花粉が傷むと黒っぽくなって受粉がうまくいかなかったりと、真冬の収穫量が大幅に減少してしまいます。
そのため、2019年までは吉村さん夫婦も灯油式の暖房を使って、冬場のハウスを5度前後に保つようにしていました。暖房なしでは最悪の場合、株が休眠して、4〜5月からしか収穫できないという事態にもなるのだそうです。
だから、「無謀な挑戦」ーー。しかしそれでもなお、吉村さんには無加温栽培に挑みたい、強い思いがありました。
イチゴ農家としてCO2排出量を抑えたい
聡子さんがイチゴハウスで使っていた灯油は年間約500リットル。2年前までは1リットルで80円ちょっとでしたが、ここ2年は120円ほどにまで高騰しています。灯油の使用をなくしたことで6万円ほどのお金が浮いたということになりますが、吉村さんの狙いはそこではありませんでした。
「うちが暖房をやめると、だいたい1トン245キロのCO2が削減できるんです。そんなんいうても、小さい小さい取り組みなんですけど」と、聡子さん。ちなみに、日本人が1人当たり1年間に排出するCO2の量は8トンほどだそう。
よくいわれる経費削減よりも、むしろ二酸化炭素排出量を減らすことに主眼を置いているのです。そのため、聡子さんは暖房だけでなく、冬場の生育を促すために使う電照もやめてしまいました。
聡子さんが環境問題について真剣に考えるようになったのは、2018年の西日本豪雨がきっかけでした。豪雨の影響で、吉村農園でもトマトのハウスが水没してしまい、壊滅的な被害を受けました。豪雨増加の原因の一つは、地球温暖化にあるともいわれています。この出来事を通じて、地球規模の環境問題は他人ごとではなく、自分の暮らしと密接につながっていると感じるようになりました。もう一つの転機は、2020年に長男を授かったことでした。妊娠中、地球環境のことや地球温暖化に関する本を読んでいたところ、自分の農業はこのままでいいのか、改めて考えるようになったといいます。
「地球全体の平均気温が産業革命前より1.5度以上上昇すると、地球のシステム全体にとって、後戻りできないほど急激な変化が起こりうる、と書かれていました。魔のドミノ倒しっていうんですかね。早ければ、2030年にはこのレベルに達するといいます。自分らがひどい目に遭うのはまだええんですけど、これから生まれてくる子供たちのことを考えると、すごくモヤモヤしたんです」(吉村さん)
自分の子供のことだけではありません。ハウスでの摘み取り体験には子供連れのお客さんたちもたくさん来て、喜んでくれています。子供たちがおいしそうに頬張るイチゴは灯油を使いながら作ったもの。「それでいいんやろか」という思いが聡子さんの中で日々強くなっていきました。
地下水でイチゴを守る!
「思い立ったらあんまり何も考えずに突き進むほうなんです」と笑う吉村さんですが、ただ無謀に無加温イチゴに挑戦しているわけではありません。
暖房を使わなくてもイチゴが十分収穫できる程度に育つような環境をつくるべく、自然の力を活用することにしました。最初の年に吉村さんが着目したのが、年間を通じて12〜13度と温度が一定の地下水でした。
地下水でクラウン加温

マルチの下に見える白いものが密閉式チューブ。地下水を流して、生長点をスポット的に加温する
聡子さんのイチゴの畝には、2本の密閉式のチューブが株を挟むようにはっていました。
イチゴは、「クラウン」と呼ばれる地表にある生長点で温度を感じ取っています。チューブに温度が一定の地下水を流すことで、ハウスの温度が高まる夏には、クラウンをひんやり冷たい地下水で冷やすことができ、冬場はぬるい地下水で暖めることができます。
ハウス全体を暖めずとも、局所的に温めることによって休眠を防ぐ、というのがクラウン加温の狙いです。

コンテナの上に散水チューブを置いて、夕方に散水。わざと凍結させることでイチゴを寒さから守る
夕方散水
外気温が氷点下3度以下になると予想される場合には、地下水を使って「夕方散水」をすることにしました。これは、かん水チューブをコンテナの上に置いて、夕方に散水するという方法。
水をまくと、夜間にはその水分が凍ります。なんだか、余計に冷えそうな気がしますが、そうではありません。じつは、水が凍るときには「凝固潜熱」という熱を放出するそうです。気化熱を利用して周囲を冷やす「打ち水」の反対の原理です。
寒冷地の果樹栽培でも「散水氷結法」という技術があります。低温に弱い花芽を散水して氷で覆うことで、外気温がマイナスでも花芽は0度前後に保たれ、凍霜害から守ることができる、という技術です。
「朝方、ハウスに行くと、葉っぱが凍ってるんです。それを見て、この氷がイチゴを守ってくれてるんやなぁって……」と、吉村さん。

外気温とハウス内部の気温をメモして、夕方散水のタイミングを模索した
減収を防いで、もっと稼ぐ
初年度は地下水を駆使して無加温に挑んだ聡子さん。地下水の利用前と比較して実験したわけではないので前述した二つの対策にどれだけの効果があったかわかりませんが、やはりそう簡単ではありませんでした。
2〜3月の収量が少なくなる一方で、4月下旬から急に増えたので「仕事量が偏ってめちゃめちゃしんどい」ということになってしまいました。結果、収量は3割減。正直、大きな痛手でした。
それでも聡子さん、そう簡単には諦めません。
徹底被覆

イチゴの畝をワリフで覆い、保温力を高めた
地下水利用と組み合わせ、内張りカーテン(「快晴カーテン」)はもちろん、イチゴをがぼっと覆うワリフで、保温効果を狙うとともに、放射冷却を防ぐことにしました。二段構えで徹底保温するわけです。
夜は覆い、朝には剥ぐ。大きなワリフですが、聡子さん1人でもかけたり剥がしたりできるように、工夫もしました。
散水時には手作り菌液も
じつは、夕方散水には弱点がありました。気温が暖かくなってくると、ハウス内の湿度が高いせいか、灰色カビ病が出やすいように感じたのです。
そこで、散水時に「えひめAI」を混ぜることにしました。納豆とヨーグルト、ドライイーストを発酵培養させた菌液です。微生物の作用でカビを抑えるのが目的です。
「えひめAI」は、聡子さんも家庭で愛用しており、効果を感じていたところ。例えばこれを生ごみにかけると、不快な腐敗臭がせず、ぬか漬けのような酸っぱい、良いニオイになるそうです。
外気温マイナス6度でも、畝の上は4度に
そして、2022年12月20日。強烈な寒波がやってきて、ハウス外の最低気温が氷点下6度まで下がりました。ところが、内張りと夕方散水のおかげか、ハウス内は2度前後、畝の上は4.5度程度に保つことができたそうです。「今のところはすぐに休眠してしまうこともなさそう」とのこと。

聡子さんの取り組みに共感した技術者の夫婦が、温度や湿度を逐一データ化する機械を提供してくれた
単価を上げるために天敵活用開始

コレマンアブラバチに寄生されたアブラムシは、白っぽくなって動かなくなる
「無加温にして収量がかなり減ってしまったので、もう少し高く売れるようにしたいけれど、『無加温栽培』だけではピンとくるお客さんはたぶん少ないように思います。なので、農薬や化学肥料を極力減らした栽培をすると、消費者もわかってくれて、もう少し単価があげられるんじゃないかと思いました」と聡子さん。そこで、化学農薬を使わずに害虫を防ぐ方法に取り組みました。
化学農薬を減らすことが環境負荷を抑える農業だということは消費者にも浸透していますが、暖房機を使わないことが環境保全につながるといってもわかりづらく評価がされにくい、という現状があります。
イチゴの場合、問題となる害虫はアブラムシ。この対策に、アブラムシを捕食する天敵「コレマンアブラバチ」を導入しました。
「この白っぽくなっているのが、コレマンアブラバチに寄生されたアブラムシです」と、イチゴの葉裏を見せてくれる聡子さん。
雑草の取り残しのように見えるムギも、じつはタネをまいて育てているもの。ここにはイチゴには悪さをしないムギクビレアブラムシが住んでおり、コレマンアブラバチの数を増やすのに一役買います。

コレマンアブラバチを温存するために生やしたムギ。黒いムギクビレアブラムシのすみかになる
イチゴの暖房をやめた。そのことをきっかけに、聡子さんの小さなイチゴハウスはたくさんの工夫やアイデアでいっぱいになりました。
ハウスの外では省電力、脱マルチ
脱炭素のアイデアは、ハウスの外にもあふれています。

ソーラー化したポンプ
用水路には1枚のソーラーパネルが置いてあります。ハウスのかん水に使う水中ポンプの電源を太陽光に置き換えました。

露地では脱マルチ。そのかわり地力を高め、泥はねを防ぐためにワリフを使うことにした
また、聡子さんの夫で、トマトや露地野菜を担当している次郎さんは、聡子さんいわく「私よりもずっと前から環境問題について考えてきた人」だそうです。
次郎さんの場合、露地野菜でマルチを使うことを少し前にやめました。今は規制が強化されているようですが、日本で使ったビニールマルチなどのプラスチック廃棄物をアジア諸国で処分していると聞いて「果たして、マルチは必要か」と考えたところ、「効果や手間など総合的に判断したら、いらん、となりました」とのこと。
また、トマトの栽培方法も2本仕立てにすることで、必要な苗数が減ったため、電熱温床の面積が狭くなりました。さらに、温床にかける保温資材を何重にもすることで、保温するのに使う電気の量がおおよそ半分に減ったそうです。
取材中、聡子さんは「私がこんなことしても、どんだけ意味があるんやろか」と時々言っていました。吉村夫妻の「(環境に負荷をかけるのは)いやだ」だから「使うのをやめた」から農園中に知恵や工夫があふれている様子をみると「そんなことはない」と言いたくなります。
「農薬や化成肥料の使用」と同じく、吉村夫妻のような「脱炭素」の取り組みについても、消費者から評価される時代が来るといいな、と思わずにはいられません。




























