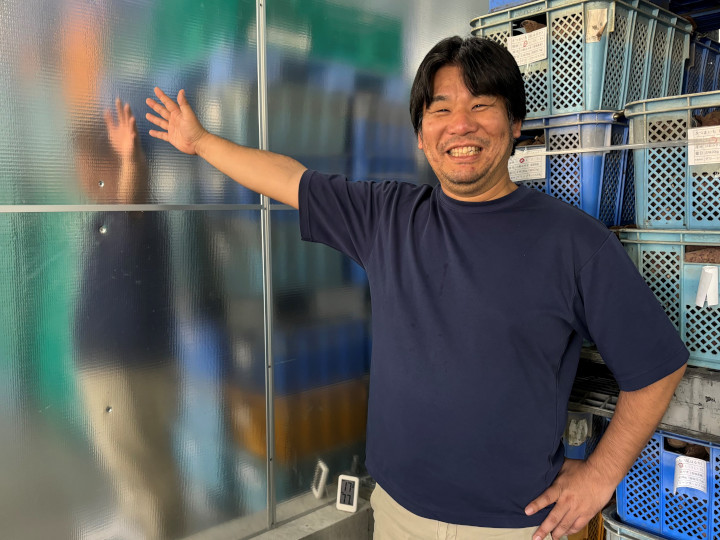民主党がかつて創設した戸別所得補償
直接支払いの補助金は、設備や機械の購入費を補塡するタイプの補助金と違い、農家の所得をじかに増やす点に特徴がある。現行制度では、麦や大豆などの畑作物、飼料米を含めた水田の転作作物などが対象になっている。
民主党が2009年に政権の座に就いたとき、戸別所得補償制度という名称で主食米を対象にした直接支払いの補助金を創設した。民主党が同年の衆院選で公約に掲げ、農村票を自民党から奪うきっかけになった制度だ。
金額は10アール当たりで一律に1万5000円。主食米の生産で発生する平均的な赤字を補塡するのが算出根拠だった。
2012年に自民党が政権に返り咲くと、制度の廃止を決めた。野党に転落していたとき、「ばらまき」と批判していたためだ。稲作の振興にとって、直接支払いが必要かどうかを突っ込んで議論した形跡はない。

生産者と消費者の利害を一致させる補助金
今回の衆院選でも、自民党は主食米に対する直接支払いの補助金を復活させることを公約に盛り込まなかった。政権に復帰して以降の農業政策の流れを踏まえると、当然予想されたことだった。
野党はこれに対抗した。立憲民主党は戸別所得補償を農地に着目した制度に衣替えして復活させることを提起。国民民主党は食料安全保障の確保を目的にした直接支払いの制度を創設することを公約に掲げた。
政策課題が山積する中で、与野党の協議で農政がどこまで焦点になるかはわからない。だが与党が野党の意見に耳を傾けやすい環境が整ったことで、これまでの主張の垣根を越えて農政の議論が進むことを期待したい。
主食米への補助金はその1つ。立憲民主党も国民民主党も公約で掲げた内容は主食米だけを対象にしたものではないが、ここではあえて主食米の生産にとって直接支払いの補助金が持つ意味を考えてみたいと思う。
論点にすべきなのは誰のための補助金かだ。民主党時代の戸別所得補償制度は、主食米の生産調整に参加することが支給条件だった。
生産調整は米価の下落を防ぎ、可能なら上げるのが政策の目的だ。消費者の目から見れば、税金が原資の補助金で米価を上げ、家計を圧迫するという制度に映る。ここで農家と消費者の立場は対立する。
10年余りの時を経て、状況は劇的に変わった。稲作農家の減少が加速し、いずれコメが足りなくなることも視野に入ってきた。計画では足りるはずでも、異常気象で需給バランスが崩れるリスクも高まっている。
もしコメが足りなくなれば、米価は一気に高騰する。困るのは消費者だ。コメ余りが前提だった民主党政権の時代との違いがここにある。今夏のコメ不足と米価の上昇で、国民はそのリスクを感じたのではないだろうか。
高齢農家の引退は今後も確実に進む。直接支払いの補助金があれば、担い手の規模拡大や稲作への新規参入を後押しすることにつながるかもしれない。そうすることで、コメ不足や米価の高騰を防ぐ。
農家への政策支援が、主食米の安定供給の確保という形で消費者のメリットにもなる。そのことを、考えるべき時期が来たように思う。