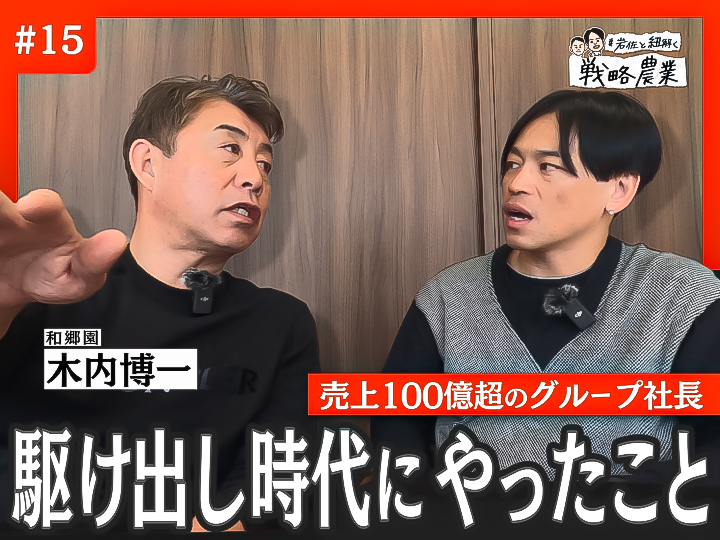【プロフィール】五十音順
■加藤博久さん
 |
株式会社カトウグリーンファーム 加藤農園代表 2011年に家業の農業を受け継ぎ、2015年からイチゴの栽培を開始。現在は東京都練馬区と埼玉県滑川町に圃場(ほじょう)がある。収穫のタイミングを限界まで遅らせ、樹上で真っ赤に完熟させてから収穫したイチゴを「あまどりいちご」としてブランド化し販売している。 |
■新井孝一さん
 |
株式会社ベリーズバトン 代表取締役 栃木県真岡市のイチゴ農家の3代目。東京農業大学を卒業後、栃木県いちご研究所での研修を経て、2008年新井農園に就農。2019年に法人化し、代表取締役に就任。2022年に栃木県農業大賞の「農業経営の部」で大賞を受賞。新規就農者の支援や観光農園事業にも取り組む。 |
■近藤克成さん
 |
掛川中央茶業株式会社 部長 大学卒業後、約20年間農協でイチゴの営農指導や新規就農者への研修、独立支援を担当。その後、佐々木製茶株式会社の生産部門、掛川中央茶業株式会社に入社し、イチゴの生産に携わる。 |
■岩佐大輝さん
 |
株式会社GRA代表取締役CEO 1977年、宮城県山元町生まれ。大学在学中に起業し、日本及び海外で複数の法人のトップを務める。2011年の東日本大震災後に、大きな被害を受けた故郷山元町の復興を目的にGRAを設立。著書は『99%の絶望の中に「1%のチャンス」は実る』(ダイヤモンド社)他。 |
■動画で見る
多すぎる!イチゴの品種
栽培する品種はどうやって決めた?
横山:イチゴは品種がすごく多いですよね。素人目には、なぜその品種を作っているのかが気になります。
岩佐:皆さんは、これまでどんな品種を栽培してきましたか?
新井:僕が就農した18年前は、「女峰」から「とちおとめ」に切り替わり始めた時期でした。ずっと「とちおとめ」を作っていたのですが、令和7年産では栃木県の約8割 が「とちあいか」に変わりました。
岩佐:「とちおとめ」「とちあいか」品種としての違いは何ですか。
新井:一番の違いは、同じ作り方をしても「とちあいか」の方が収量が多い ことだと思います。食味に関しても本当に甘味が際立っていて香りが良く、形も奇麗。欠点があまり無くて、非常にポテンシャルが高いです。
加藤:うちは今練馬で「スターナイト」「ほしうらら」「紅ほっぺ」「おいCベリー」を、それから埼玉県の圃場で「あまりん」を栽培しています。約2年前から人気なのが「スターナイト」ですね。甘味と酸味のバランスが良く、はっきりとした味わいが特徴です。
近藤:うちは今「紅ほっぺ」のみを栽培しています。今後は「きらぴ香」も入れてみようと考えています。「きらぴ香」は果皮がやや硬くて扱いやすく、連続出蕾(しゅつらい)性に優れていて安定的に取れることが特徴です。あとは花数も、「紅ほっぺ」に比べてそこまで調整しなくても良いので、作業が省力化できます。また「きらぴ香」の方が今売れているので単価も良いですね。

出荷先もさまざま
岩佐:出荷先としてはどこが多いですか。
新井:僕が就農した時はJAの市場出荷が100%でした。面積が倍になってからも、当初の作付面積の分はJAにそのまま卸して、増やした面積分は自分で新しく販路を広げていきました。3〜4割ぐらいはふるさと納税、あとはECサイトと、今年から輸出を始めました。
加藤:うちは売り上げの7〜8割が直売所やECサイト、マルシェで、2割弱が観光農園での摘み取り。残りは輸出加工品、キッチンカーです。なので、どうしても味で見られるんですね。そこでまずは味を追求しようと考えて、それぞれ特色のあるイチゴで作っています。
岩佐:東京は摘み取りが多いイメージでしたが、意外と直売所の割合が高いですね。
加藤:摘み取りになると、どうしてもイチゴを赤くしなければいけません。でも自分がイチゴ農家になる時、まずはおいしさを追求しようと決めたんです。その前提があるので、この比率になっています。
近藤:うちは9割以上が系統出荷です。あとは自社で経営しているカフェや、地元のケーキ屋さんに卸しています。
岩佐:将来的には6次産業化も考えていますか。
近藤:どうしても規格外のイチゴも出てきますからね。今JAにも加工用のイチゴを出荷していますが、キロ単価が安いので、自社である程度加工用として使いながら、もっと高単価で販売していきたいです。

農家によって異なる栽培の技術
栽培技術の学び方
岩佐:皆さんはどうやって栽培技術を習得していったのでしょうか。
近藤:僕は前職の農協で20年間イチゴに携わりました。先輩に付いて畑を回り、現場で話を聞きながら覚えていきましたね。県の農業試験場や地域の畑に行ったり、JAの営農指導員の勉強会に参加したり。あと農協の育苗センターでは、イチゴの生理生態を学んだり、農薬を掛けたりもしました。
新井:僕が就農した時、父親の「とちおとめ」の反収は約4トンでした。その後、10年ぐらいで7トン半まで上げました。実は僕、学生時代は野球でプロを目指していて、食事やサプリメント、トレーニングの仕方をかなり勉強したんです。その考え方をイチゴの栽培と照らし合わせて取り組みました。
岩佐:具体的には?
新井:イチゴをたくさん収穫するには、花をたくさん付かせないといけない。そのためには、どの時期にどの成分を与えて、どんな環境にすれば良いかを考えました。絶対に毎年課題は見えてくるので、その課題に対してどう対策するかを積み重ねて7トン半までいけました。
加藤:私は周りにイチゴ農家が居なかったので自分で探しました。栃木やアメリカにも行きましたが、最終的には埼玉の深谷で、1軒研修先を見つけて、約2年通いながら学んで自分で始めました。でも、まだ学んでますね。あとはシステムによっても全然違うので、同じシステムで栽培している人のところに行って、情報交換しています。

農家によって異なる設備のスペック
岩佐:イチゴの場合、農家によって設備がまるで違うと思うんです。皆さんの設備のスペックを教えてください。
近藤:鉄骨屋根型のビニールハウスで、天窓のタイプです。当然、高設栽培ですけれども、設備としてはCO2施用機「真呼吸」を導入しています。あとは保温と遮光のカーテン、加温機、複合環境制御「ウルトラエース」を付けています。フィルムは「エフクリーン」です。ミストは付けていません。
新井:栃木県は昔ながらのイチゴ農家が多数居るので、軒高のハウスより小さい単棟ハウスが多いです。僕らの地域は「ウォーターカーテン」という地下水をくみ上げて、暖を取る農家がたくさん居ますね。CO2に関しても単棟ハウスで作る場合、日中晴れていれば、自動換気で十分です。今はいろんな物の値段が上がっているので、もっと収量を上げるよりは、今のクオリティを下げないところで極力カットしていくことを突き詰めています。
岩佐:設備に投資することだけが答えでは無いんですね。
加藤:うちは今「ネオサンアップシステム」を使っています。ハウスは5種類ありますが、収量が全然違いますね。やっぱり丸屋根のパイプハウスが一番成績が良いです。カーテンは一層のものを使っています。うちは味を追求したいので、暖房もほとんど6〜7度設定で朝方しか動いていません。日中も20度ぐらいで、昼間は開いてます。今年からCO2もやめました。
岩佐:CO2施用機は使っていないんですか。
加藤:ゼロにしました。外気が入ってくるので。ただ、6畝ぐらいの小さいハウスがあって、そこは施用機も複合環境制御装置も入れていませんが、あまり他のハウスと収量は変わりません。投資した分、収量が取れて単価も上げられれば良いんですが。量が取れたから単価が下がるとなったら、意味が無いだろうなと思います。

イチゴ農家の経営戦略とは
農業経営の中で大切にしていること
岩佐:農業経営の中で大切にしていることや経営戦略について教えてください。
加藤:農業を始める時、叔父から言われた「まずはうまいものを作れるようになれ」という一言が頭に残っていて。なのでまずはおいしいものを作り、今は「あまどりいちご」という名前でブランディングしています。直売だけでなく、海外に広げたり、百貨店に置いてもらったりしていますね。次のフェーズとしては、加工品に重きを置いていこうと思っています。
岩佐:加工品とは具体的に言うと?
加藤:とあるお菓子会社と一緒にキューブケーキを作っています。それを2025年3月、FOODEX JAPANに出展して、海外への販路を探そうと考えています。
新井:僕もおいしいイチゴを追求することが大前提だと思います。それから面積が広くなるほど1人ではできなくなってくるので、今はスタッフとのコミュニケーションや評価など、“人”の部分に時間と労力を割いています。評価については昨年見直して、人の成長が会社の成長に直結するようになると考えています。
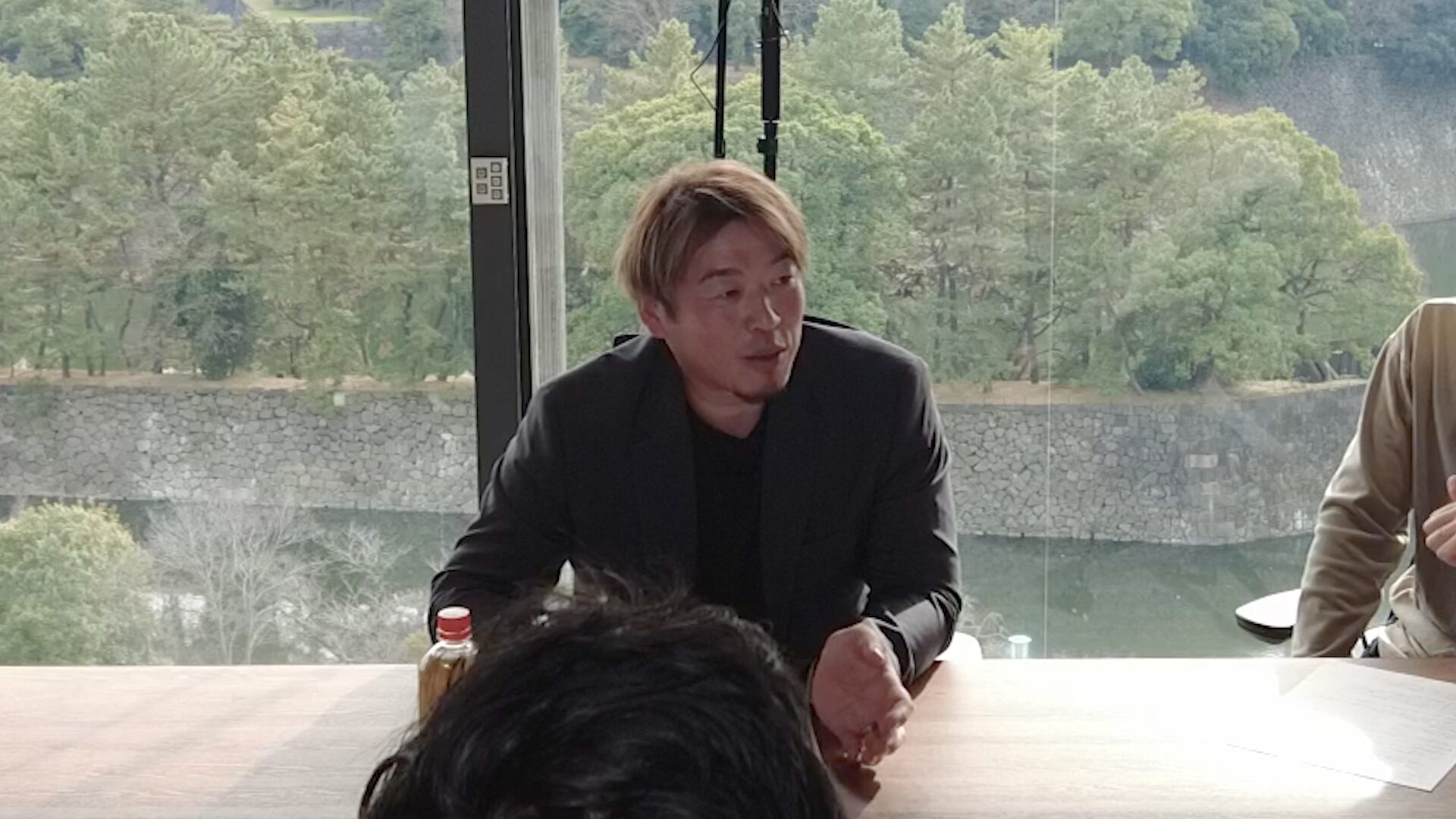
近藤:私はいち従業員なので経営戦略というよりは、個人的に観光農園に興味があります。当然、駐車場の整備やバリアフリー対応なども必要でしょうし、お客さんが来なかった時にどうするのかというリスクもあると思います。でもうちの周りにまだ観光農園がほとんどありませんし、比較的、車の通りも多いので、もしかしたら集客が見込めるのかなと。あとは自社のカフェとのコラボもできたらと考えています。
岩佐:イチゴとお茶は最強の組み合わせですよね。
近藤:単純にイチゴだけ売るよりも、会社全体でイチゴを使いながら、お茶の売り上げにも貢献していきたいですね。
売り上げの比率は?
岩佐:ちなみに加藤さんはBtoBの取引はあるのでしょうか。
加藤:ちょうど今日から、虎ノ門ヒルズのあるレストランに卸し始めました。実は直売の割合を減らす方向です。農園の直売だと、どうしても余る時が出てきます。それがストレスで、結局、不定休でずっと販売を続けなければならなくて。もうすぐ10年になるので、さすがに休みを作ろうと思って、今は卸の方との付き合いを増やしています。
岩佐:新井さんはJAにもかなり卸していますが、理想の経営スタイルを教えてください。
新井:JAを含めて3本柱があると良いんじゃないかと思っています。うちの去年の売り上げはJAで約1億3000万円、ふるさと納税で約1億2000万円、苗の事業で約3000万円なんですよ。
岩佐:随分、地域に貢献していますね。
新井:加工をやろうと思いましたが、1本600円〜1000円のジャムを1万本売るのは大変だし、設備を作るのに約2000万円掛かると言われたので、加工はストップしました。ふるさと納税だと、お客さんから直接レビューももらえて、スタッフも自分が作ったイチゴが評価されていると分かります。
岩佐:近藤さんはJA出荷がほとんどですよね。今後はどのようにしていきたいですか。
近藤:もうちょっと直売を増やしていきたいと考えています。最終的にはJAを約4割、直売を約4割、あとは加工などにしていきたいですね。リスクヘッジのためにも、JAをゼロにすることはありません。
イチゴ農家を目指す人に必要なこと
岩佐:これから新規就農を考えている人や、農家になったばかりの人に必要なことは何だと思いますか。
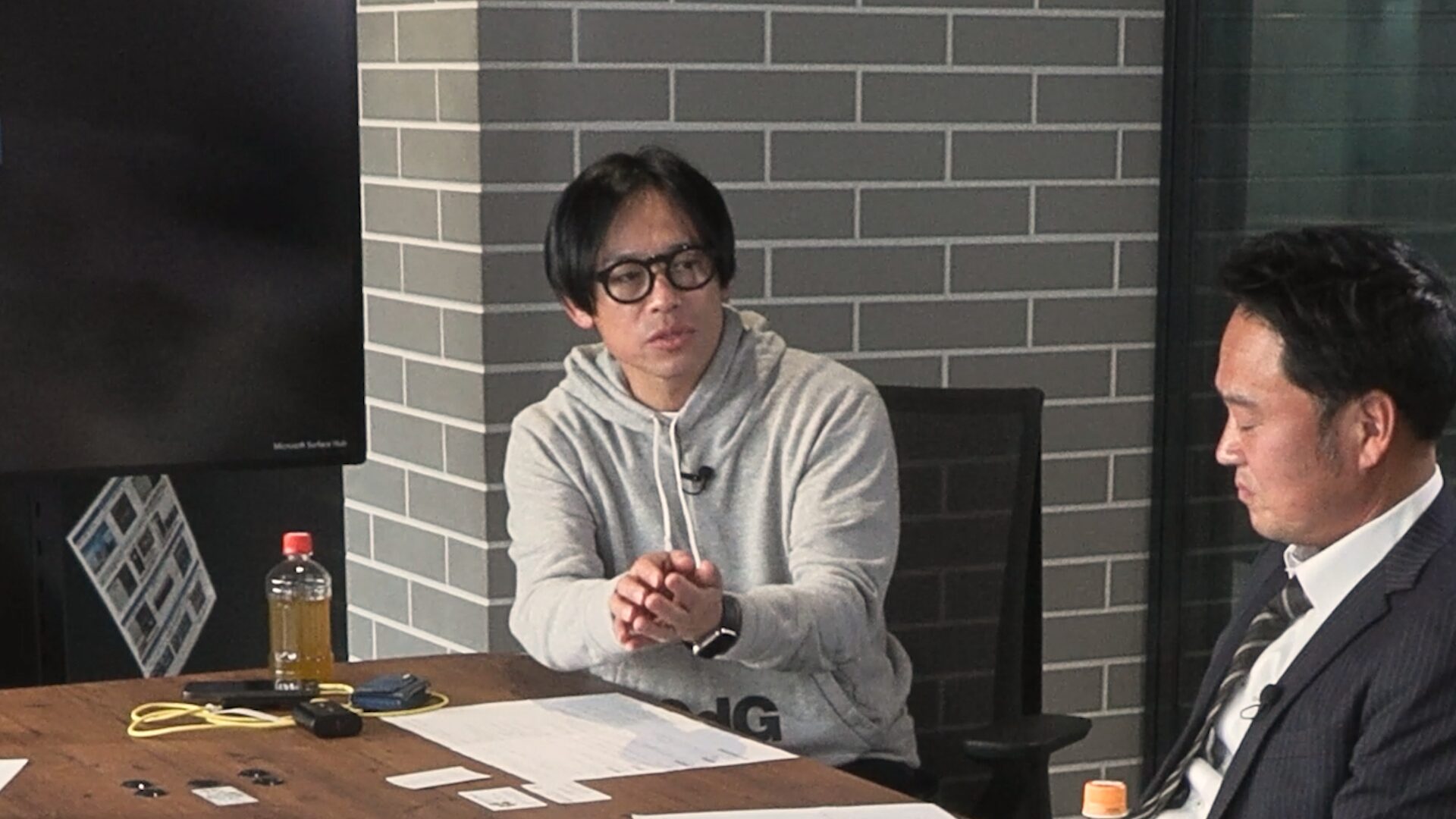
新井:いろんな農家さんを見てきましたが、生産も人事も営業も全部できる農家さんって少ないと思うんですよ。それなら絞った方が良いだろうなと。僕の場合は「おいしさ」に特化した方が良いと考えていて、そのためには組織として動いた方が良いと思っています。この業界の平均年齢が60代後半で、今後たくさんの人が離農したら、新規就農者が1人で力を発揮するのは難しいです。でも組織的に動いていれば、ベテランから新人までいろんな部門に配置して動けると考えています。今ある農業法人がより強く、よりホワイトに動けるようになることが重要ではないでしょうか。
加藤:私もイチゴ農家になりたい人の相談をよく受けます。頑張ればしっかり収益が出る仕事ですが、やっぱり大変だと思います。もうかる仕事はいっぱいあります。その中でもイチゴ農家になりたい人は、どこを目指すか、味なのか、量なのか、観光農園でサービスを充実させてやるのか。まずは自分がやりたい経営スタイルを明確にした上で始めるのが良いと思います。特に都市近郊はイチゴの観光農園が大分増えています。でも子供の数も減っていますし、お客さんの見る目も肥えて差別化も難しくなってきました。ただ、しっかり頑張ればできると思います。
近藤:加藤さんと同じく、本当に大変ではあります。それは資金面だけでなく、仕事そのものもです。冬場の収穫時期だけだと良く見えますが、夏場も暑い中、仕事をやって、やっと収穫ができます。収穫できるまでの未収益期間もありますから、プランをしっかり立てて、もしご家族が居るなら十分に理解を得てください。イチゴは地道な仕事が多いと思いますが、計画をしっかり実行していけば成功につながると思います。
まとめ
岩佐:非常に勉強になりましたね。では今回の座談会を振り返りたいと思います。
| イチゴ農家を目指す人へ、農業戦略のポイント | ||
| ① | 設備にお金を掛け過ぎない | 栽培方法のノウハウや知識を習得していくことで、収量や品質もついてくる。設備はできるだけミニマムで始めることが重要。 |
| ② | 自らのスタイル、ポジショニングをぶらさない | 生産から販売まで全部やると決めたら、徹底的に6次産業化を進める。生産と販売に特化するなら販路を絞るなど、どんな戦略をもって勝ち残るかを明確にする。 |
岩佐:やっぱりイチゴ農家はユニークで面白い人、すてきな人が多いですね。ありがとうございました。
(編集協力:三坂輝プロダクション)