一周回って間隔が重要
関さんは42歳。90アールの農場で、トマトやナス、ミズナなどを栽培している。売り先は豊洲市場(東京都江東区)などの仲卸だ。
経営を軌道に乗せるうえで決め手になったのが、オランダ型の栽培ハウスの導入。温度や湿度、日射量をセンサーで観測し、天窓を開いたり、遮光ネットを張ったりしてハウス内の環境を自動でコントロールする。
そう聞くと、データにもともとづく先端農業をイメージするかもしれない。もちろんデータは大切だ。だが本稿の読者が農家や農業に関心のある人であることを考えれば、解説をここでとどめるべきではないだろう。
「一周回っていまは感覚的なものがより重要だと思っている」。関さんはそう話す。環境制御型のハウスを使いこなした上での実感だ。
なぜ経験を積み、感覚を研ぎ澄ますことが必要なのか。オランダ型のハウスは勘に頼る農業から脱却することに意味があったはずではないのか。関さんへのインタビューを通して、その点を再考してみたいと思う。
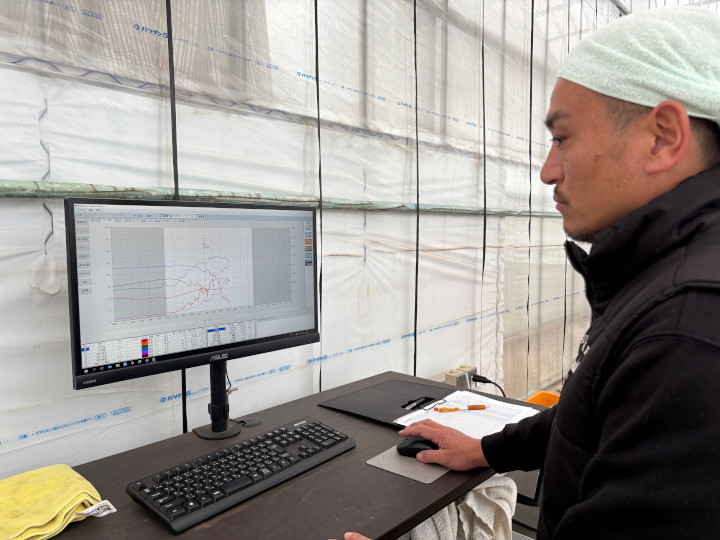
データを確認する関健一さん
遮光カーテンを閉めるかどうかの判断
2014年にオランダ型のハウスを導入して以降、3人の研修を受け入れて、全員すでに独立就農した。現在は2人の社員を雇用している。ここから先は、どんなことに力点をおいて彼らを指導してきかたを説明しよう。
例えば3月上旬にこんなことがあった。関さんが「トマトがしおれてなかった?」と聞くと、社員は「しおれてませんでした」。怪しいなあと思って自分で見に行くと、その兆しがあったので遮光カーテンを張った。
翌日、「遮光カーテンをどうセットしておいた?」と聞くと、社員は「昨日と同じ日射量で張るようセットしておきました」。関さんが前日、遮光カーテンを閉めたので、同じ条件で広がるようにセットしたのだ。
関さんは改めて社員に「しおれてるかどうか確認してみた?」と聞いたうえで、さらにこう続けた「しおれてないなら、張る必要ないよ」。

遮光カーテンをたたんだ状態のハウス
このとき関さんはこう説明した。2日前まで4日続けて曇天だった。光合成が進まないので、植物は呼吸を抑制する。昨日は晴天になったので、遮光カーテンを張らないと急に呼吸が盛んになり、水分の蒸散が進む。
関さんは「突然、スタートダッシュするようなもの。植物が脱水状態になって、しおれてしまう可能性がある」と話す。だから日が昇ってから日射量がそれほど多くならないうちに、遮光カーテンを張る必要がある。
これに対し、その日は2日続きの晴天なので、こうした混乱が置きにくい。だから、トマトがたっぷり日を浴びて光合成が進むよう促す。植物を観察し、経験を積み重ねることによって得ることができるノウハウだ。
「寺の上に雲が出たら雨が降る」
「データ上はハウスの中が植物にとってすばらしい環境になっている。ところが見に行ってみると、トマトが違った反応をしていることがある」。関さんはそう話す。重視すべきはもちろん実際のトマトの状態だ。
関さんによると、父親は「晴れの日でも、近くの寺の上に雲が出たら夕立が来るぞ」と話していたという。そしてその直感は当たる。「ヒューッと冷たい風に雨のにおいを感じ取る。そういうことを覚えながら、育ってきた」
繰り返しになるが、関さんはデータを見ることを否定しているわけではない。だが自分の感覚で確かめることを怠っていたのでは、栽培技術は向上しない。そうしたことを、独立した研修生や社員に教えてきた。

トマトの様子
売り上げはハウスのスペックで決まる
オランダ型のハウスを使った経営で、関さんが何を重視しているかについても触れておこう。「売り上げは基本的にハウスのスペックで決まる。そこからの引き算で考える必要がある」。関さんはこう指摘する。





























