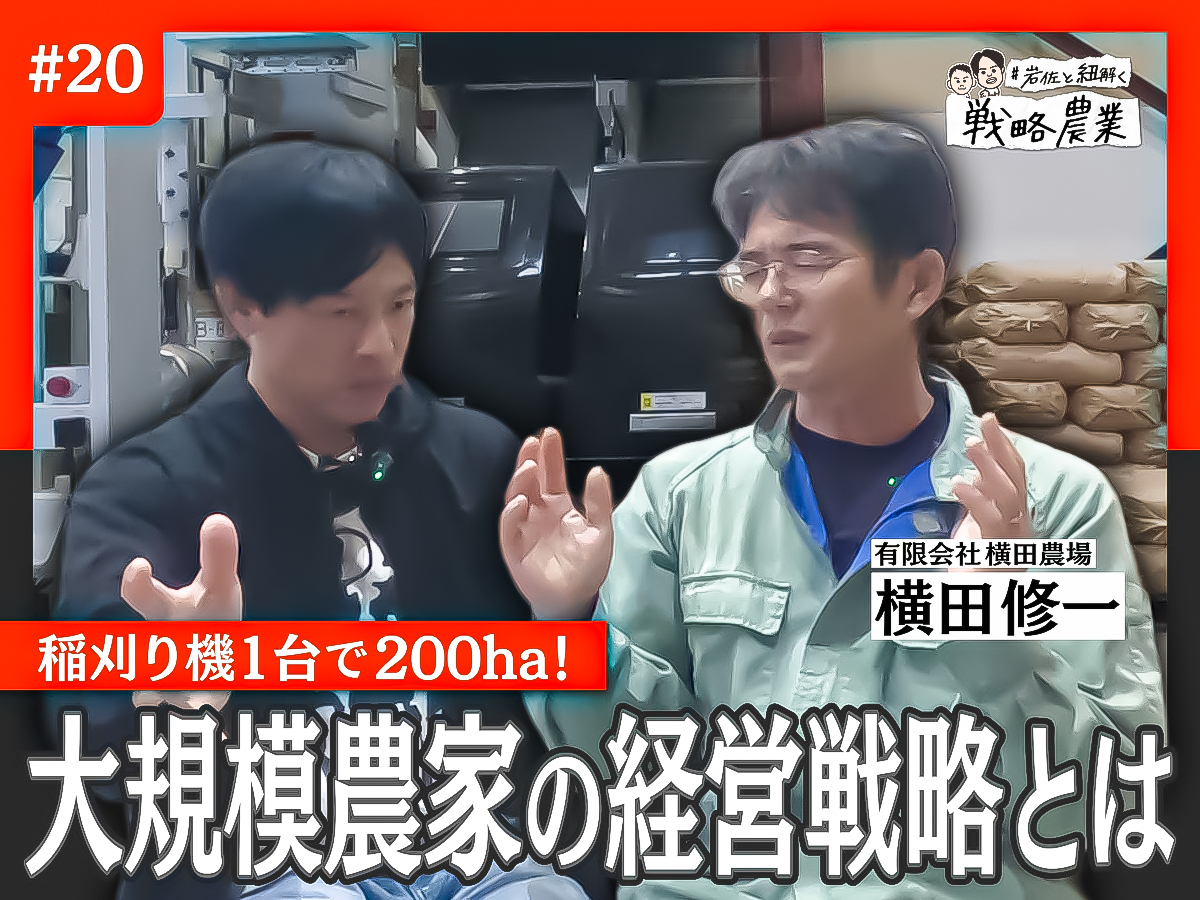【プロフィール】
■中森剛志さん
 |
中森農産株式会社 代表取締役 東京農業大学農学部卒業。農業研修を経て、2017年に「食料安全保障の確立」を企業理念として中森農産(株)を設立し、コメ、ムギ、ダイズ、ソバを生産。埼玉県・栃木県・島根県・山口県にて生産を行い、作付面積は合計330ヘクタールにのぼる。 |
■岩佐大輝さん
 |
株式会社GRA代表取締役CEO 1977年、宮城県山元町生まれ。大学在学中に起業し、日本及び海外で複数の法人のトップを務める。2011年の東日本大震災後に、大きな被害を受けた故郷山元町の復興を目的にGRAを設立。著書は『99%の絶望の中に「1%のチャンス」は実る』(ダイヤモンド社)ほか。 |
■横山拓哉
 |
株式会社マイナビ 地域活性CSV事業部 事業部長 北海道出身。国内外大手300社以上への採用支援、地域創生事業部門などで企画・サービスの立ち上げを経験。2023年4月より同事業部長就任。「農家をもっと豊かに」をテーマに、全国の農家の声に耳を傾け、奔走中。 |
令和の米騒動について
岩佐:まずは「令和の米騒動」について、中森さんはどう見ていますか。
中森:まさにコメの値段が上がってしまった、というのが僕の感想です。供給能力が足りないと、価格は上がります。これまで需要が下がり続けたことから、供給量を落とすために、生産調整や価格政策が行われてきました。2030年頃を境に、消費よりも生産の縮小の方が大きくなると予測されていましたが、5年前倒しになっています。
岩佐:この状況をどう変えていくべきか、中森さんのアイデアを教えてください。
中森:これまでは生産調整と価格政策で米価を維持し、生産者の所得を間接的に補填(ほてん)する政策を行ってきました。しかし、消費量より生産量が落ちていくフェーズに入ったので、増産にかじを切らなければなりません。ただ、必要十分な量の増産ができるのかという問題があると思います。そのため生産調整ではなく、増産し過ぎたときの所得補償に切り替えないと、この国の食料安全保障としてリスクでしかないと思います。
岩佐:小泉進次郎農水相が、かなりの量の備蓄米の放出しました。それについてはどうですか。
中森:私は問題ないと思います。やらないと、一般関税枠での輸入米がとめどなく入ってきてしまいます。よく流通業者が在庫を抱えてもうけているといわれますが、彼らのビジネスにおいては、売り先に対して約束した量を出せないのが一番の懸念ですよね。高い・安い以前に、モノがあるか・無いかが重要。今すでに棚が心もとなくなっているということは、モノが無い状態です。なので正直、備蓄米の値段はいくらでもいい。とにかく今はモノを供給してあげることが重要ですから、賢明な判断だと思います。

集約を切り捨て、集積に特化した中森農産のビジネス
岩佐:創業から10年もたっていないのに、約330ヘクタールの農業経営者となった中森さん。どうやって成長してきたのでしょう。
中森:水田農業の最大のボトルネックは、農地の集積と集約です。これを徹底的にやることを念頭に置いていたので、まずはとにかく農地を集めました。特に僕の場合は、農地ゼロからのスタートでしたから、良い条件の農地を、高い集約度で集めることは不可能です。そこで最初の5年は集約を切り捨てて、集積に特化して集めてきました。
岩佐:1年目でどれぐらい集まりましたか。
中森:10ヘクタールです。研修中に地域を回って集めました。いつも「落ち着け」って言われていました(笑)。
岩佐:とにかくさっさとやるということですね。
中森:農地が無いと水田農業は成り立ちません。だからとにかく集めたいという、純粋な心でやっていました。でもそれができたのは、大規模で生産性の高い水田農業を日本に作らないと、本当に皆さんの食が失われかねないという問題意識があったから。さまざまな農家が居ると思いますが、大規模農家がある一定の規模に達すると、割に合わなくなってくることが多いんですよ。
岩佐:そうですよね。
中森:不確実性とかマネジメントコストが、規模の経済で飲み込めなくなる。つまり、規模の経済が働かなくなります。そこで、規模を縮小して最適化を始めるんです。それは良いことですが、それだと私の目標を達成できません。まずは農地を増やすことに取り組みました。とはいえ限界があるので、半径10キロ以内で集めました。その後、埼玉の圃場(ほじょう)を大きく2つに分けて、今は半径5キロ以内に集約しています。

現場サイドでの経営の工夫
岩佐:一方で、足元の経営も成り立させないといけません。現場サイドではどういった工夫をしていますか。
中森:拠点ごとに農地を最低限確保すれば、規模の経済がある程度働きます。そこに対して適切な設備投資をしています。ただ、事業を引き継ぐだけでなく、収益構造を再構築していかなければなりません。そこで今はオーガニックに取り組んでいます。うちは農地面積330ヘクタールのうち、70ヘクタールは有機的管理をしています。米価が高騰する中、オーガニックは倍の値段がつきます。その代わり、収量は少ないです。
岩佐:販売はどのように行っていますか。
中森:基本的にはBtoBです。いわゆる6次化もすごく価値があることだと思いますが、私たちが設定している課題は、生産分野の課題を解決すること。そのために、人もお金も投資しているので、販売は基本的にBtoBです。
岩佐:自分たちがやることを明確に決めているんですね。
中森:ただ、オーガニックをやっていることもあって、ノベルティ需要という形でBtoBtoCも始まっています。BtoBのコストで作って、BtoCの単価で売れるようにすれば、販売管理費が増大しません。オペレーションも簡易で済み、かつ収益性も上がります。これはぜひやろうということで進めています。
岩佐:オペレーションは他社に任せるということですか。
中森:基本的には、投資や設備の部分は全部任せています。

今後のビジョン
岩佐:今後のビジョンを教えてください。
中森:10万ヘクタールまで拡大しようと考えています。農業界の問題は、リーディングカンパニーがいないことだと思うんですよね。業界のイノベーションを起こしていくようなプレイヤーが必要です。まずはそこまでの事業規模にならないと、この国の食料安全保障を確立するのは難しいと思っています。
横山:なるほど。
中森:これから日本の水田はどんどん減っていきますから、そのうちの10%のシェアを持っていれば、事業規模でいうと最低1000億円規模の企業になることができます。そうなってこそ、本当の意味で水田農業改革ができる企業、未来を継承できる企業になれます。
岩佐:生産サイドでそこまでの規模の企業はないですからね。でも、中森さんだったらできそうなオーラがあります。
中森:私は本当にやらなきゃいけないと思っています。私ができるかどうかは分かりませんが、それをやらないと次の世代に顔向けできません。
まとめ
岩佐:中森農産のポイントをいくつかまとめてみたいと思います。
| 中森農産の農業戦略のポイント | ||
| ① | スピード感を持って事業を拡大する | 経営において重要なのは、勢いをどうつくるか。スピード感があれば、人もモノもお金もついてくる。 |
| ② | 戦略的に農地面積を拡大する | 集約ではなく集積に特化するなど、やらないことを決め、やることには徹底して取り組む。それによって自社のポジションが築かれる。 |
| ③ | 志とビジョンを持つ | 志やビジョンがビジネスの基礎をつくり、周囲との信頼関係を築く。 |
岩佐:地域への思いと、ビジョンを描き続ける経営者の姿を見せていただきました。ありがとうございました。
(編集協力:三坂輝プロダクション)