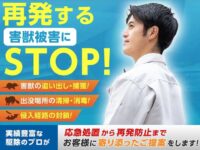イノシシの生態と特徴
日本国内に生息するイノシシは主に「ニホンイノシシ」と「リュウキュウイノシシ」に分けられます。それぞれの特徴は下記の通りです。

十二支の「亥(い)」として、また「猪突猛進」の語源として、日本人になじみの深いイノシシですが、その生態を把握している人は少ないでしょう。
野生のイノシシの寿命は、長くても10年程。子どもの頃はシマウリに似た縞模様の体毛が体に沿って縦に生えて「ウリボウ」と呼ばれるかわいい容姿ですが、成獣になると全身茶色あるいは黒色の硬い体毛に覆われます。

雑食性で湿地帯を好む
生息域は低山帯から平地の森林や雑木林で暮らしていますが、意外にも泳ぎが得意なため、河川が近い湿地帯を好みます。雑食性の動物で何でも食べますが、基本的には山林に生えている植物の根や地下茎、果実(ドングリなど)、タケノコ、キノコなど。季節の変化に応じて、昆虫類、ミミズ、ヘビなども食べるようです。
昼行性だが、夜に活動することも
通常メスとオスは別々に行動します。メスは母親と一緒に母系的な群れをつくりますが、オスは1~2歳で親元を離れて単独生活を行うか、小さな群れをつくります。
非常に神経質で警戒心が強く、見慣れないものを見かけると避ける習性がありますが、興奮状態の場合に不用意に近づいたりするとこちらへ向かってきます。基本的には昼行性ですが、人間を避けるため薄暗い時間帯や夜などに活動することもあります。
イノシシの危険性
特筆すべきは、その身体能力の高さ。普段はゆっくり歩いていますが、いざ敵と向き合うと時速40kmの速さで走り、1m以上にも及ぶジャンプ力を見せます。また硬い鼻先が強靭な武器となり、猛烈な加速をつけて突進してくるのでかなり危険です。イノシシは身の危険を感じたり興奮したりすると、突進したり、かみついてきたりすることもあるため、十分注意する必要があります。
イノシシ被害の現状
近年、日本各地でイノシシによる被害が急増しています。人里に出没する事例も見られており、特に過疎地や高齢化集落において農作物被害(食害、掘り起こしや踏みつけ)を及ぼすことが問題となっています。
イノシシによる農地や作物への被害
前述した通りイノシシは雑食のためさまざまなものを食べます。田畑ではイモ類、稲、カボチャ、豆類、トウモロコシなどを好んで食い荒らします。食害のほかにも、畑を踏みつぶしたり葉物野菜の畑を掘り起こすケースもあります。
農林水産省の調べによると、令和5年度のイノシシによる農作物への被害総額は約36億円。減少傾向にはあるものの、依然として高い水準にあるといえるでしょう。

イノシシによる家屋や庭への被害

本州の各地で住宅地や商業施設にまで出没し、人に噛み付くなどの人的被害や路上のゴミや家の庭を荒らす生活環境被害も多発しています。
体についた寄生虫を落とすために頻繁に泥浴びをする習性があり、水田の中に入ることもあります。泥浴びをしたあとは体を木にこすりつけて泥を落とすので、近隣の樹木にまで被害がおよび、田んぼのあぜを崩されることもあるようです。
感染症の危険も
さらに日本のイノシシは高い確率で日本脳炎ウイルスに感染しており、人との接触機会が増えると感染症伝搬のリスクも高まると言われています。
高い繁殖力も特徴
また、イノシシは年間平均4.5頭を出産し、その約半数が成獣に成長します。この高い繁殖率により、個体数が急速に増加し、被害が拡大する要因となっています。
農家にとってはまさに天敵、被害が拡大しないうちに撃退しなければなりません。
【ハンター直伝】イノシシ撃退テクニック

イノシシによる農作物被害が深刻化する中ですが、ここからは、初期投資を抑えつつ高い効果を発揮する対策をご紹介します。詳しいテクニックについて、猟師の遠藤夏日さんに話を聞きました。
イノシシから農作物を守るには、捕獲・整備・柵の設置が重要で、特に整備と柵については地域住民がこまめに対応する必要があります。改めて対応策を検討するヒントになれば幸いです。
■遠藤夏日さんプロフィール
 |
2020年より有害鳥獣駆除に従事。イノシシを中心に年間約100頭の有害鳥獣を捕獲している。近年は、捕獲個体の肉・骨・皮の資源活用にも取り組み、命を無駄にしない持続可能な活動を目指している。 |
イノシシ対策の基本的な考え方
イノシシは臆病ですが、興奮していると攻撃する可能性もあることを念頭に置きましょう。対策としては、捕獲・整備・柵の設置が基本です。特に整備に関しては、イノシシが隠れやすいような場所を作らないことが大切なので、耕作放棄地をなるべく減らしたり、こまめに草刈りをしたりするなど、基本的なことを押さえることがもっとも大切です。
また地域ぐるみでの対策が求められます。特に耕作放棄地や空き家などが多い地域では、自分の土地だけを徹底的に管理したところで、近くにイノシシが出没するものです。
地域の人たちと連携し、なるべく早期から環境整備や対策を始めて、柵などはこまめに管理するようにしましょう。
イノシシに遭遇したときの注意点
イノシシに遭遇した場合、基本的には刺激せずにゆっくり立ち去るようにします。追い払う場合は、近距離で棒などを使うと攻撃される可能性があるので、遠くから爆竹を投げるなどの方法で追い払うと良いでしょう。
「罠にかかっているイノシシは襲ってこないから大丈夫」と思われがちですが、何かの拍子に罠から足が外れて、興奮した状態で襲い掛かってくる可能性があります。猟師の中にも、興奮した状態のイノシシに襲われてケガをするケースが見られるので、興奮した状態のイノシシには要注意です。
興奮したイノシシに襲われそうになったときは、木に登って一時的に非難することも有効です。イノシシはクマとは違って木登りはできないので、近くに木があるときは活用しましょう。
ハンターが教える低コストで効果絶大な対策法5選
具体的にイノシシ被害を防ぐためには、どんな対策をしたら良いのでしょうか。プロハンター遠藤さんの視点で、特に有効な4つの対策方法をご紹介します。
1. 柵を活用した物理的な防御

イノシシへの基本的な対策のひとつである「柵の設置」。最もポピュラーな方法ですが、イノシシの特性に応じた設置と管理のポイントがいくつかあると言います。
電気柵やワイヤーメッシュを使った方法について、それぞれ詳しく解説してもらいました。
電気柵の設置と管理のポイント
イノシシは毛が分厚いため、電気柵に体がぶつかってもダメージは小さいのですが、毛のない鼻先が当たるとダメージを受けます。
設置のポイントは、次の通りです。
・一番下の電柵は、地上から15~20cmに張る(鼻が当たる位置)
・30cm間隔で上に1~2本追加する
・電圧チェックは毎週する
・草刈りは月に2回程度して漏電を防ぐ
「ここは侵入できる」と学習すると何度もやってくるので、畑に野菜がない時期も電気柵を設置しておくと安心できます。
ワイヤーメッシュの柵の設置と管理のポイント
ワイヤーメッシュを使った対策も効果があります。
設置のポイントは、次の通りです。
・左右のワイヤーメッシュ同士は結束する
・線の太さは6mm以上のものを使う(細いと溶接が弱いので破壊される)
・下部は地面に埋める
・上部は外側に曲げ、柵を飛び越えにくくする
・網やもう一枚のワイヤーメッシュを立てかけて補強する
イノシシは20cmの隙間があれば通り抜け、1mの高さは助走なしで飛び越えます。
ワイヤーメッシュをフェンスのように並べるだけでなく、下部は地面に埋め、上部は外側に曲げて角度をつけ、イノシシが入らないように工夫しましょう。
2.犬を飼う

原始的な方法ですが、犬を飼うとイノシシを追い払う効果があります。もし家にイノシシが近づいてきた場合は犬が吠えるので、追い払ってくれるのです。
もし追い払えなかった場合でも鳴き声を聞いた人間が家の中から確認しに行くと臆病なイノシシは逃げるので、田畑を守れます。
また犬やオオカミの尿を嫌うと言われており、オオカミの尿は商品として販売されているほどです。犬を飼うことで、犬の尿の臭いがして、それがイノシシを寄せ付けないことにつながるかもしれません。
3. 捕獲を依頼する
捕獲を行うには免許が必要です。基本的には役場に連絡をして、猟友会などに協力してもらいながら捕獲することになるでしょう。
猟友会だけでなく、民間の獣害駆除業者や狩猟をしている個人もいます。ただ、ハクビシンやアライグマを駆除する業者は多い一方で、イノシシなどの大きな動物を駆除する業者は多いとはいえません。
自治体によってよく出る動物や捕獲のルール、業者の有無が異なりますので、まずは役場に連絡することが一番です。
4. イノシシが近寄らず、住みつかない環境をつくる
イノシシが集落などにくる要因は、農作物だけではありません。放置された果実や野菜クズ、残飯や生ゴミなどを家や畑のそばに捨ててはいませんか?また放任果樹も集落に害獣がやってくる原因の一つです。
これらを食べて味を覚えたイノシシが、最終的には畑に侵入して農作物を食べるようになります。
イノシシの餌になりそうなものを適切に処理して、地域の環境を整備することもとても大事です。
放棄果樹は思い切って伐採するか、果実はすべて収穫するなど対策をしましょう。

また、害獣被害を防ぐためには、野生動物が隠れられる場所をなくす必要もあります。そういった場所をなくせば、害獣の出没自体を減らす効果も期待できます。
田畑のそばにある管理不足の竹藪や、耕作地周辺や休耕地の雑草などを刈ることも重要です。
5. 音や光を活用した忌避対策
ホームセンターを訪れると、音や光が出る装置が売られています。イノシシ被害を防ぐというより、なるべくイノシシを近づけないという意味合いのこの対策法。はじめは警戒して遠ざかりますが、慣れてしまうと効果がなくなる場合も。慣れを防ぐためにも、前述した対策方法と組み合わせて活用するのがおすすめです。
物理的対策に加え、地域内の連携も不可欠
イノシシによる農作物や住環境への被害は全国的に深刻化しています。身体能力が高く、警戒心も強いため、対応には工夫が必要です。電気柵や環境整備などの物理的対策に加え、地域全体での連携が不可欠です。まずは身近にできる対策から始め、必要に応じて専門家や自治体の力も借りていきましょう。
まとめ
今回は、日本にいるイノシシの種類から詳しい生態、イノシシの被害対策などご紹介しました。
イノシシは特に農家にとって多大な損失をもたらす害獣です。個体数増加の原因である、狩猟者の減少や高齢化に伴う農業後継者の不足、中山間地域の過疎化により生息適地である休耕地や耕作放棄地の拡大などは、今後も深刻化することが予想されます。
これらを放っておけば、イノシシの生息地や農作物被害の拡大につながってしまうのです。
イノシシの被害を減らすためにも、まず相手の生態や特徴を知っておくことが大切。習性などをよく知った上で、自分の集落や田畑に適した被害防止対策を行い、イノシシが生息しにくい環境づくりを心がけていきましょう。