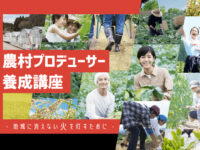さまざまな品種が誕生しているサツマイモ

サツマイモは、古くから食料不足の際の救世主としてなじみが深い野菜の1つです。用途によって品種を選ぶ楽しみがあるのもサツマイモの魅力です。最近は糖度が高いものが人気で、ホクホク系では紅あずまや金時などが、ねっとりした食味では安納芋などが特に人気を集めています。またムラサキイモも製菓用などとして菓子職人のみならず一般消費者からも注目されています。
サツマイモの原産地
サツマイモの原産地は中央アメリカで、紀元前3000年以前から栽培されていたとみられています。紀元前2000年頃に南アメリカに伝わり、15世紀末のコロンブスの新大陸発見によりヨーロッパにもたらされ、世界へ広まったと言われています。日本へは、17世紀初めに中国から琉球経由で薩摩に伝わり、九州南部で栽培されるようになりました。薩摩の特産だったことから「薩摩芋」と呼ばれ、江戸時代に救荒作物として全国に普及しました。
鮮度の良いおいしいサツマイモの見分け方
食味や糖度は品種によっても異なりますが、鮮度の良いおいしいサツマイモは、皮の色が鮮やかでツヤがあり、肌がなめらかで、色ムラがありません。形は細長いものよりも、ふっくらとしているもののほうが生育環境がよく、土の中で栄養をたっぷりと蓄えています。太く丸みを帯びてずっしりと重く、ひげ根の穴のくぼみが浅いものを選びましょう。深いものは繊維質が多くて食味があまりよくありません。
糖度が高いサツマイモの特徴
上下の切り口に蜜がにじみ出ていたら、糖度が高いサツマイモの証です。皮の表面にタールのような黒い粘液が付いているものも同様です。これは、サツマイモなどの一部のヒルガオ科の植物に特有のヤラピンと呼ばれる成分で、本来は白い液体が酸化して黒くなったもので、新鮮なものに見られます。
サツマイモの栄養

サツマイモには不溶性と水溶性の食物繊維が含まれています。不溶性食物繊維は腸の中で水分を吸い込んで膨らみ便通を促し、水溶性食物繊維は腸内環境を整えるのに役立ちます。また、切り口から出ている白い粘液は、ヤラピンと呼ばれる成分で、食物繊維と合わせて便秘解消に効果があると言われています。皮の近くに含まれているので、皮ごと食べると効果的に摂取できます。
また、でんぷんを非常に多く含むため、サツマイモに含まれるビタミンCが熱などで破壊されにくく、調理しても効率的に摂取することができます。抗酸化作用があるビタミンE、塩分を対外に排出するカリウムも含んでいます。エネルギー源となる炭水化物も多く、満腹感が得られる野菜です。
サツマイモの保存方法

サツマイモを家庭で保存するときには、温度と湿度に気をつけましょう。サツマイモは低温と水分に敏感なので、乾いた状態で新聞紙に包んで冷暗所に保存します。水に濡れているとそこから傷みやすく、冷蔵庫に入れると低温障害を起こして劣化が始まります。適切に保管していれば数カ月の長期保存が可能です。一度カットしたものは傷むのが早いので、残りはラップで包み冷蔵庫の野菜室に入れて早めに食べきるようにしましょう。
冷凍保存のポイント
加熱すれば、冷凍で保存することも可能です。洗ったサツマイモを丸ごと電子レンジか蒸し器で加熱して中心まで熱を通してラップで包んで冷凍庫へ。焼きいもにして冷凍し、食べるときに電子レンジで加熱すると焼きたてのような風味が楽しめます。
サツマイモの旬と時期
秋の味覚とも言われるサツマイモの収穫期は9月から11月です。収穫したての新物もおいしいけれども、サツマイモは2カ月ほど貯蔵すると水分が適度に蒸発して甘さが増してさらにおいしくなります。つまり、サツマイモの旬は新物の9月から11月のほか、貯蔵品が出回る10月から1月までの2回あると言うことができます。
産地や品種によっても旬が異なります。鹿児島県は加工用の栽培が多く温暖な気候で収穫期が早いため9月から11月に、茨城県では焼きいも・干し芋用の品種が多く栽培され12月から2月に貯蔵品が出回ります。生産量が多い都道府県は、1位の鹿児島県、2位の茨城県、3位の千葉県、4位の宮崎県で、この4県で全生産量の約90%を占めています(2020年)。
サツマイモの下ごしらえ
サツマイモはアクが強く、特に皮の下にアクの成分が多くあります。そのため空気に触れると酸化して色が黒くなりますが、皮の内側にある太いスジの部分まで、厚めに皮をむくことで色がきれいに出ます。皮は食物繊維が豊富なので、捨てずに油で揚げておやつにしたり、炒めてきんぴらなどに利用するとよいでしょう。
あく抜きのポイント
アク抜きは、サツマイモを切った後に水で洗ってから、さらに水にさらすようにしましょう。きんとんやスイートポテトなど、色を鮮やかに仕上げたいときには、時々水を交換しながら10分程度水にさらします。ただし、水にさらす時間が長いとビタミンCが溶け出してしまうので、仕上がりの色を気にしないときには、2、3分ほどさらせば十分です。
サツマイモをおいしくするワンポイント

甘くておいしいサツマイモですが、さらに甘くおいしくするコツがあります。ポイントは酵素の働きを活発化させること。その方法と合わせて、同じ品種の中で甘いものを見分けるヒントもあるので参考にしてみてください。
甘みを引き出したいときは?
サツマイモはゆっくりと熱を加えることで、でんぷんを麦芽糖に変える酵素が活発化します。酵素が活発になる温度は60〜75℃で、80℃を超えるとだんだんとその力は弱まっていくと言われています。甘みを引き出したいときはこの性質を利用して、じっくりゆっくりオーブンなどで加熱するのがいいでしょう。70℃まで一気に温度を上げ、その後は温度をキープして加熱するのがポイントです。
同じ品種なら小さいほうが甘みが強い
同じ品種のサツマイモで比較した場合、小さい方がより甘みが強いと言われています。また、細いサツマイモよりも太いほうが甘そうなイメージがありますが、実はその逆。細いサツマイモは地表に近い乾燥したところにできるため育成環境が厳しく、糖分を蓄えようとするからだと言われています。そのため、甘みの強い小ぶりのものは焼きいもなどに利用して、太くて大きいサツマイモは天ぷらなどの味をつけるような調理にするといいでしょう。
サツマイモを食べるとおならが出る?
余談ですが、サツマイモを食べるとおならが出ると一般的に言われているのは、食物繊維が多いためと考えられています。食物繊維が腸内細菌(善玉菌)によって分解される際に、腸内に二酸化炭素などのガスが発生しやすくなります。これを防ぐには、皮ごと食べるのが有効です。サツマイモの皮には、消化を助けるヤラピンという物質が含まれているため、ある程度ガスの発生を抑えることができます。
サツマイモの種類

サツマイモの主要品種は、作付けされているもので約60品種あると報告されています。食味で分けるとホクホク系としっとり系、色で分けると黄色、オレンジ、白、紫があります。ここでは、代表的な品種を見ていきましょう。
ベニアズマ
関東地方で多く生産されている品種です。皮は濃い赤紫色で中は鮮やかな黄色、果肉は粉質で食感はホクホクしています。繊維が少ないため口あたりがよく、糖度が高く甘みが強いため根強い人気を誇り、焼きいも、大学いも、天ぷらなどに適しています。貯蔵性があまりよくないため、12月から2月の旬を過ぎるとあまり出回らなくなります。
紅はるか
2010年に品種登録された比較的新しい品種です。外観が優れる「九州121号」と皮色や食味が優れる「春こがね」を交配させた見た目もよくおいしいサツマイモです。皮は紅色で、中身は白っぽく、加熱すると食感がなめらかになり、糖度が高いことから、焼きいも用として近年非常に人気を集めています。干し芋に加工されることもあります。
金時
地方によって名前が異なる高系14号の品種で、西日本で多く栽培されています。徳島県の「鳴門金時」、石川県の「五郎島金時」は全国的にも有名な品種です。宮崎県では「宮崎紅」として出荷されています。皮は真紅で中身は黄白色。粉質でホクホクしており、なめらかな食感、上品な甘さが特徴で、野菜料理にも向いています。
安納芋
鹿児島県種子島特産の品種です。形は太く短く、皮は赤く、中身は明るいオレンジ色で、水分が多く粘質性で焼くとねっとりとした食感になります。糖度が非常に高く甘いため、別名「蜜芋」と呼ばれ、焼き芋に人気の品種です。一般的な安納芋は「安納紅」と呼ばれ、その突然変異でできた皮が白いものが「安納こがね」と呼ばれています。
パープルスイートロード
色素成分であるアントシアニンを多く含むため、皮も中身も鮮やかな紫色をしているのが特徴です。一般的に紫色のサツマイモは甘みが弱いものですが、その中では甘みが強い品種です。焼いても、蒸しても、おいしく食べられ、特徴である色を生かして、ソフトクリームやスイートポテトなどお菓子の材料としてもよく利用されています。
【超絶品の人気料理】サツマイモのおすすめレシピ7選
おいしい食べ方は焼きいもだけではありません。サツマイモを主役に、おやつ、スイーツ、おかず、汁もの、ご飯ものなど、いろいろな料理が作れます。少ない材料で手軽に作れる、筆者おススメの人気レシピをご紹介します。
旨すぎる!「サツマイモとレンコンのデパ地下風」

甘辛でおかずになるサツマイモ料理はいかがでしょう。
皮つきサツマイモとレンコンの輪切りまたは半月切り(約1cm幅)に片栗粉をまぶして、それぞれフライパンに多めの油でこんがり揚げ焼き。砂糖醤油をよく絡めて、仕上げに黒ゴマを散らせばできあがり。サツマイモの甘くホクホクとした味わいと、レンコンのシャキシャキした食感を交互に楽しめて、箸が止まらなくなるおいしさです。色と形の見た目も楽しい一品です。鶏肉(市販の唐揚げでもよい)をプラスすると主菜にもなり、よりデパ地下の惣菜に近づきます。サツマイモはスライスしてすぐに水にさらすとアクが抜けて味と色がよくなります。
詳しいレシピはこちらからチェック
参照元:cookpad
たっぷりバターとみりんの上品な甘みが魅力!「スイートポテト」

材料の牛乳の代わりにみりんを使った、ほんのり和風でまろやかなスイートポテトです。バターはもちろん、みりんもサツマイモと相性がよく、仕上げのつや出しにも活躍します。
サツマイモは皮をむいて小さく切って耐熱容器に入れ、ここでみりんを加えてレンジで加熱。フォークなどでつぶしてなめらかになったら、グラニュー糖とバターを加えてゴムへらで混ぜ、さらに溶き卵の半量を加えてなじませます。生地を冷ましたら俵形に成形して天板に並べて溶き卵を塗り、黒ごまを中心にのせ、180℃のオーブンで焼き上げたら、加熱したみりんをスイートポテトの表面にはけで塗ってつやを出して仕上げます。
詳しいレシピはこちらからチェック
参照元:キッコーマンホームクッキング
わずか10分!おやつにもおすすめ「サツマイモのバター醤油煮」
材料は、サツマイモ、水、しょうゆ、砂糖、バターのみ。鍋ひとつでできるレシピです。食卓にもう一品ほしいときも、手早く調理できるお助け料理です
サツマイモはよく洗って、皮ごと一口サイズの乱切りにし、バター以外の材料と一緒に鍋に入れて強火にかけ沸騰したら中火にして煮ること10分。さつまいもが柔らかくなって水分がなくなったら弱火にしてバターを加えて混ぜるだけ。サツマイモは切ったあとに水にさらすと色がよく仕上がります。
副菜にも、おやつにも、シンプルにおいしい一品です。
詳しいレシピはこちらからチェック
参照元:Nadia
食卓にもう一品!生姜たっぷり「具沢山サツマイモの豚汁」

豚肉に加えて、にんじん、大根、サツマイモの3種の根菜類が入った満足感のあるお味噌汁。ごま油とショウガの風味が食欲をそそり、ぽかぽかと体も暖まります。
にんじん、大根は皮をむき、サツマイモは皮をむかずに、いずれもいちょう切りにして、耐熱容器に入れて電子レンジで5分加熱して火が通りやすく下ごしらえ。豚こま切れ肉と一緒に鍋でごま油で炒めて塩こしょうで味を整え、水と顆粒和風だしを入れてサツマイモが柔らかくなるまで煮て、味噌を溶かし入れ、すりおろしショウガを入れて混ぜ合わせて火を止めます。彩に小ねぎをトッピングしていただきます。
詳しいレシピはこちらからチェック
参照元:クラシル
超カンタンで早い!美味しい!「魔法の大学芋」

揚げ物は面倒だと思っている人に朗報。大さじ3の油で揚げずにできる、お手軽でヘルシーな大学芋のレシピです。
サツマイモ1本を皮ごと洗い、乱切りにして10分ほど水にさらします。先端は尖らせて切るとカリカリとおいしくなります。フライパンに油大さじ3を入れ、砂糖大さじ3、その上に水気を拭いたサツマイモを並べてふたをして中火で加熱。パチパチと音が激しくなったところで火を弱めて10分加熱します。サツマイモに竹串がスッと刺さるまで火を通したら、あめ状になった砂糖をまんべんなく絡ませ、表面がカリッとしたところで器に盛り、黒ごまを振りかけてできあがり。砂糖の代わりにハチミツを使ってもおいしくできます。
詳しいレシピはこちらからチェック
参照元:cookpad
電子レンジで時短!すぐ食べたい時は「さつまいもスティック」
外はカリカリ、中はほくほく、サツマイモのスティックが手早くつくれるレシピです。
サツマイモは皮つきのまま1cm角の棒状に切って、水にサッとさらし、水分を軽く拭き取って、耐熱容器に入れてレンジ(500W)で5分加熱。下ごしらえにレンジを使うことが時短のポイントです。フライパンに油大さじ1を引き、下ごしらえしたサツマイモを入れて、こんがりと焼き色をつけるだけ。仕上げに砂糖大さじ1と塩1つまみを振り入れて、フライパンを回しながら、全体にまぶしてできあがり。少量の油と砂糖でできるので罪悪感なく小腹を満たせます。砂糖の量は、サツマイモの品種や好みに応じて加減してみてください。
詳しいレシピはこちらからチェック
参照元:Rakutenレシピ
鶏肉など具材もたっぷり大満足!「サツマイモの炊き込みご飯」
秋が深まると食べたくなるサツマイモの炊き込みご飯。ホクホクと甘いサツマイモに鶏肉、にんじん、油揚げなどの具材も入っているのでこれだけで大満足。作り方はとても簡単です。
米は洗って30分以上水に浸して、水気を切っておきます。サツマイモは皮つきのまま1cm角、ニンジンは皮をむいて千切り、油揚げは短冊切り、鶏もも肉は一口大に切っておきます。調味料の分量は、米2合に対して、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ2、顆粒和風だし小さじ2が目安。炊飯釜で米2合と分量の水、調味料を混ぜ、具材を加えて炊飯。炊きあがったら軽く混ぜ合わせて完成です。
詳しいレシピはこちらからチェック
参照元:クラシル
品種の違いも楽しめる甘いヘルシーフード
日本の裏側で古代から食べられていたサツマイモ。日本には中国経由で伝来した名残りで甘藷(かんしょ)や唐芋(からいも)とも呼ばれています。昔は救荒作物として、現代は食物繊維が豊富でヘルシーな食材として重宝されています。ほっこりとした甘さや食感も人気の理由かもしれません。サツマイモは身近な野菜の1つですが、さまざまな品種が開発され、色や食味のバリエーションが豊富です。
また、昔に比べて随分甘くなっていることに驚いている方も多いのではないでしょうか。品種改良や栽培、貯蔵の技術進化の賜物ですが、その中でも甘いサツマイモの選び方、調理の際にさらに甘くする方法もあるので参考に。食事にもお菓子にも利用できるサツマイモ。ぜひ、さまざまな品種を食べ比べてみてください。
■参考
「野菜と果物の品目ガイド〜野菜ソムリエEDITION」(農経新聞社)