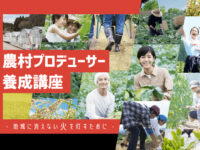覚えておきたい「梅の豆知識」

梅は古くから日本の食卓になじみのある食材のひとつ。梅干し、梅酒、ジュース、ジャムなど、家庭用の保存食にとても重宝されています。ここでは、梅の栄養、鮮度の良い梅の見分け方、旬や産地などの豆知識を紹介します。
梅の栄養

梅は果物の中でも高い栄養価があり、タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。ミネラル類では、カリウムはリンゴの4倍、鉄は6倍の量になります。カリウムは血圧調整やむくみの解消に、鉄は不足すると貧血を起こしやすくなります。ビタミン類ではビタミンEがリンゴの33倍含まれています。ビタミンEは脂溶性ビタミンで高い抗酸化力を持つことが知られています。
梅の酸味の元は有機酸です。主な有機酸はクエン酸で、疲労回復や食欲増進が期待されています。有機酸は旨味成分でもあり、梅にはリンゴ酸、シュウ酸、少量の酒石酸、乳酸、コハク酸も含まれています。抗酸化作用のあるポリフェノールも含まれています。
青梅には、青酸配糖体の「アミグダリン」という成分が含まれており、摂取した場合、青酸中毒を引き起こす危険があるので生食は控えましょう。また、未熟な種子は青酸系の強い毒を発生するおそれがあるため生食はできません。加工することで、毒性が抜けていきます。
鮮度の良いおいしい梅の見分け方
梅は、梅干しや梅酒、ジャムなどに加工して食べるのが一般的です。緑色で硬い青梅、黄色で柔らかくなった完熟梅など、熟度が異なる梅が売られているので用途に応じて選びましょう。梅酒にするときには青くて硬いものを選び、梅干しやジャムを作るときには、黄色みを帯びたものが良いといわれています。新鮮でおいしい梅は、果皮にハリがあり、形は丸くふっくらとした、表面に傷や斑点がないものを選びましょう。傷があるとそこからカビが発生しやすくなります。
梅の保存方法

生の梅は日持ちしないため、購入したらすぐに加工したほうがいいでしょう。やむを得ず保存する場合は、ダンボールや紙袋に入れて冷暗所で保存しましょう。冷蔵庫で保存すると果皮が黄色くなることを防ぐことはできますが、低温障害を起こして褐色に変色することがあるので注意が必要です。新鮮なうちに保存用袋に入れて冷凍保存するといいでしょう。
梅の旬と時期
梅の加工品は1年を通して売られていますが、生の梅が出回る時期は5月下旬から6月にかけて。出荷の最盛期は、6月上旬から中旬にかけてです。梅の産地として有名なのは、和歌山県で、全国の収穫量の65%を占めています。2位は群馬県、3位は三重県、4位は神奈川県、5位は福井県となっています(2021年)。
梅の主な品種
梅の種類は多種多様。大きさによって、10g以下の「小梅」、10〜25gの「中梅」、25g以上の「大梅」に分けられます。代表品種である南高や白加賀は大梅に分類されています。それぞれどのような加工に向いているのかも合わせて紹介していきます。

| 南高 | 大粒で、日に当たった果皮は赤く染まります。肉厚で梅干し向きで、和歌山県が主産地の高級梅です。 |
|---|---|
| 白加賀 | 中粒で、果肉が緻密で繊維が少なく、梅酒や梅干に最適な品種です。関東で主に栽培されています。 |
| 古城(ごじろ) | 鮮やかな緑色で、香りがいい品種。梅酒やジュースなどの飲み物向きです。 |
| 紅王 | 主に弁当用の梅干しに多く使われます。日が当たった部分が赤く色づきます。 |
| 白王 | 弁当用の梅干しに加工されることが多いです。和歌山県の小梅の主力品種です。 |
| 剣先 | 青みが強く、果肉は肉厚なのが特徴。梅酒やシロップ作りにおすすめです。 |
| 鶯宿(おうしゅく) | 果肉が硬めでカリカリとした歯ごたえになる梅です。梅酒に最適です。 |
| 改良内田(かいりょううちだ) | 梅には珍しく、自分の花粉で果実ができる性質があります。 |
梅干し作りの大まかな流れ
梅干し作りは、完熟した梅を使用すると追熟やあく抜きの手間がかからないため、梅が旬を迎える6~7月にかけて行います。梅干し作りの工程を大きく分けると「塩漬け」「赤しそ漬け」「土用干し」の3ステップがあります。流れを表にまとめました。
| 6月中旬 | 塩漬け | 梅を塩に漬け込む(1週間ほど) |
|---|---|---|
| 6月下旬 | 赤しそ漬け | 下処理した赤しそなどを加えて漬け込む(2週間ほど) |
| 7月中旬 | 土用干し | 天日干しをする(3~4日間) |
材料(梅5kg分)と用意するもの
梅干し作りを始める前に、材料と必要な道具を確認しておきましょう。
梅の塩漬けで使用する材料
・完熟梅 5kg
・粗塩 900g(梅の18%)
・焼酎(35度のもの)1/2カップ
赤しその下処理で使用する材料
・赤しそ 1kg(梅の20%)
・粗塩 200g(赤しその20%)
・白梅酢(塩漬けでできたもの)赤しそがひたひたになる量
その他準備が必要な道具
・ボウル(大)
・ふきん
・竹串 ※爪楊枝でもよい
・スプレー容器 ※なくてもよい
・漬物容器
・キッチン用アルコールまたはホワイトリカー
・重石 5kg
・落とし蓋
・盆ざる
・保存容器
梅干しの作り方と手順

梅干し作りは工程が多く各作業のタイミングが重要。初めて作る場合は、着手する前に手順を把握しておきましょう。梅を漬け始めてから食べ頃になるまでに約1カ月かかります。
①梅の準備と下処理
用意した梅が青梅の場合は、1〜2日常温で黄色くなるまで追熟させます。傷んだ実は取り除き、大きなボウルなどに梅を入れ、傷つけないようにやさしく水洗いして、清潔なふきんでやさしく梅の水分を拭き取ります。水分を拭き取った梅は、竹串で1個ずつヘタを取り、大きめのボウルに入れて、スプレー容器に入れた焼酎を吹きかけます。ボウルに焼酎を入れておき、梅を何回かに分けて入れ、まぶしていく方法もあります。
②梅干し漬けに使う容器の消毒
漬物容器の消毒の方法を3パターン紹介します。
・漬物容器は熱湯を入れて消毒し、中をよく乾かします。
・市販のキッチン用アルコールをスプレーで吹きかけて清潔なふきんで拭きます。
・ホワイトリカーを容器に入れて蓋をして振り、消毒した後は逆さにして乾かします。できれば日光に当てて乾かすといいでしょう。
③梅の塩漬け|梅と塩を交互に漬ける
まず、漬物容器の底に塩ひとつかみをふり、梅を敷き詰めるように並べます。さらに塩をふって梅を並べる作業を交互に繰り返します。梅全体が平らになるように並べ、最後に塩をふって、落とし蓋をして重石をして、容器に蓋をして冷暗所に置きます。容器の蓋がない場合は、埃が入らないようにラップや新聞紙で蓋をしましょう。
④白梅酢を取り出す
梅を塩漬けして1週間ほど経つと、透明な白梅酢が上がってくるので、梅がかぶるくらいの量を容器に残して取り出し、捨てずに取っておき、次の工程で使用します。
⑤赤しそ漬け|赤しその葉を塩もみして、アク抜きする
赤しその葉をたっぷりの水で2〜3回水を替えて洗い、よく水気を切る。大きめのボウルに入れて、分量の半分の塩を加え、よく押しもみして強く絞って汁を捨てます。同じ作業を繰り返してしっかりと汁を絞りきります。ボウルに赤しその葉を入れ、④で取っておいた白梅酢をひたひたに入れてもみほぐします。梅酢が赤く色づいたらOK。
⑦土用干しの方法|~3日間の天日干し~

梅雨が明けるのを待って、3日間ほど晴れが続く日を見計らって土用干しをします。大きく平たいざる(盆ざる)に梅を広げて並べます。梅と梅がくっつかないように間隔を少し空けて並べましょう。日当たりのよいところで干し、夜間は室内に取り込む作業を3日連続で行います。梅を天日干しすると余分な水分が蒸発して保存性が高まり、果肉もねっとりとした食感に変わります。
⑧梅干しの完成!すぐに食べてもOK
梅にしわが寄って、耳たぶぐらいの柔らかさになったら完成です。すぐにでも食べられますが、3カ月後頃から塩がなじんでよりおいしくなっていきます。密封できる保存容器に入れて、日の当たらない環境で常温に置くと数年にわたって長期保存することができます。
土用干しした梅干し|保存方法について
土用干しした梅干しを保存容器に入れて保存する際、2つの方法があります。「赤梅酢に戻して保存する方法」と「そのまま保存する方法」です。好みの仕上がりで保存しましょう。
赤梅酢に戻して保存すると、赤色が鮮やかに仕上がり、果肉がみずみずしくなり、酸味が強くなります。そのまま保存すると、色は茶色に近く、果肉はねっとりとして、酸味は穏やかで落ち着いた味になります。
梅干しを作る前に!知っておくと役立つポイント6選
梅干し作りは、旬を逃さず、丁寧に手間をかけて行う仕事です。初めてでも失敗しないためのワンポイントを紹介します。
「完熟梅」を選ぶと失敗しにくい!
市販の梅には青く硬い青梅と、熟して黄色く赤みがかった完熟梅があります。青梅は漬ける際にはあく抜きの工程が必要になるため、完熟梅を使うのが一般的です。また、完熟梅は仕上がりが柔らかくなり、梅干しが作りやすいため、初心者でも失敗しにくいことが利点です。
青梅を漬ける場合は、一晩水に漬けてあく抜きをし、白梅酢が出にくいため重石は完熟梅の2倍の重さにします。青梅の梅干しは程よく硬い食感が楽しめます。
赤しそを買うタイミング
赤しそは初夏が旬で、出回る時期は6月から7月までに限られています。梅を塩漬けにしてから1週間後に入手できるように、梅干し作りのスケジュールを立てましょう。店頭に並ぶ期間が短いので、見つけたタイミングで購入し、塩もみをした状態で、梅の塩漬けができあがるまで冷蔵庫で保管するのもいいでしょう。
粗塩や焼酎について
粗塩はミネラルが豊富で梅と絡みやすく、梅干しがまろやかな風味になります。粗塩の量は、漬ける梅の重さに対して約5分の1程度の18~20%が目安です。塩分18%以下で漬けるとカビが付きやすく、日持ちが短くなるため注意が必要です。塩分の少ない減塩梅干しにしたい場合は、18〜20%の塩分で作った後、水に浸して塩抜きをするといいでしょう。
焼酎はカビを予防するためにアルコール度数35度以上のものを使います。度数が低いものには水分が多く含まれているためです。家庭用の焼酎で構いませんが、アルコール度数15〜25度のものが多いので確認を。癖のない「甲類焼酎」がおすすめです。梅酒に使うホワイトリカーもOKです。
漬物容器・落とし蓋・重石などについて
容器の大きさの目安は、梅の重さに対して3倍程度の容量です。プラスチック製の漬物樽のほか、ガラス、陶器、ほうろう製で、広口のものを使います。プラスチック容器を使う場合は、衛生面や匂い移り、腐食の心配がないように、容器より少し大きめの漬物用ビニール袋に入れて漬けるといいでしょう。
落とし蓋は漬物容器に付属のものがなければ、大きめの皿などで代用できます。金属製のものは腐食し、木製のものはカビの原因となるので避けましょう。
重石は梅と同じ重量のものを使用します。市販のものを利用するか、なければ水を入れたペットボトルなどを利用しても構いません。漬け込みの途中で重さを減らす必要が出てくる場合があるので、調整用に軽めの重石も用意しておくといいでしょう。
カビの原因と対処法について
カビの原因としては、容器が清潔でない、塩分が低い、梅が傷んでいるなどが挙げられます。もしカビが生えてしまっても、状況に応じて対処すれば大丈夫です。
・塩漬け時の白い幕のようなカビは、カビのついた梅と白梅酢を取り出して煮沸して、梅は完全に乾かして容器に戻します。
・赤しそに生えたカビは、その部分だけ取り除きます。
・保存容器に移してから生えたカビは、カビが生えた実を取り除き、消毒しなおした瓶に入れなおして、早めに食べきります。
漬けた後に残った赤しそや梅酢は活用できる?
赤しそはふりかけなどに活用できます。軽く絞って刻んでしょう油などの調味料を加えて味を整えてご飯と混ぜます。炊いたひじきなど、他の具材と合わせて混ぜご飯にしてもいいでしょう。乾燥ふりかけは、赤しそを搾ってある程度広げて、1~2日ほど天日干しでカラカラ乾燥させ、フードプロセッサーまたはすり鉢とすりこぎで少し粗めに粉砕すればできあがりです。
梅酢は鮮やかな赤色を生かして、漬物や酢飯の色付けに使うことができます。保存瓶などに入れてとっておくといいでしょう。
梅干しレシピのバリエーションを紹介
赤しそ漬け以外にも梅干しのレシピがあります。梅干し作りのバリエーションとして、人気の高い関東干し(白梅干し)とはちみつ梅のレシピを紹介します。
しそなしでも漬けられる!関東干し(白梅干し)の作り方
梅干し作りの工程から赤しそ漬けの工程を省くと、関東干し(白梅干し)になります。ここでは、ジッパー付きポリ袋を使った作り方(梅1kg)を紹介します。

1. 下処理として、梅のヘタを取り外し、水洗いして一粒ずつ水気を拭き取り、大さじ2の焼酎をまぶします。
2. 下処理した梅をジッパー付きポリ袋に入れ、200gの塩を入れて全体に行き渡らせます。
3. 空気を抜き、袋の口を閉じてボウルに入れて、1kgの重石をして冷暗所に4日間ほど置きます。
4. 梅が隠れるくらいの白梅酢が上がってきたら、重しを外して冷蔵庫で梅雨明けまで保管します。
5. 梅雨明け後、晴天が続く時期に3日間天日で干します。全ての実に太陽が当たるように裏返しながら干し、夜は取り込みます。これで「白梅干し」の完成です。
はちみつ梅干しの作り方
はちみつ梅の作り方はいくつかありますが、ここでは関東干し(白梅干し)をベースとした減塩はちみつ梅干しの工程を紹介します。
はちみつ漬けで必要な材料や道具
はちみつ梅には、はちみつと氷砂糖を使います。作りやすい分量の材料と必要な道具を紹介します。
<材料>
・白梅干し 200kg
・砂糖 40g
・みりん 40cc
・はちみつ 40cc
・酢 40cc
・水 70cc
<道具>
・ボウル
・ざる
・保存容器(ガラス、陶器、ほうろう製で蓋付きのもの)
①梅の減塩
関東干し(白梅干し)200gと水1リットルをボウルに入れ、好みの塩分になるまで8~24時間水に浸けて減塩します。目安として約8時間で塩分約14%、約12時間浸けたあと水を交換して12時間置くと塩分約5~10%になります。水に浸けた梅はざるに上げ十分に水気を切っておきます。
②合わせ調味液を作る
砂糖、みりん、はちみつ、酢、水をよく混ぜ合わせて調味液を作ります。火にかける必要はありません。
③減塩梅干しを調味液に漬け込む
保存容器に①の減塩梅干しと調味液を入れて漬け込み、冷暗所で約1週間保存します。砂糖やはちみつが沈殿するので、1日1回は容器を揺らして中が均一になるようにならします。
④完成!
できあがったはちみつ梅は冷蔵庫で保存し、1週間をめどに食べきります。減塩しているので常温保存には向かないので注意しましょう。
まとめ
梅干しは黄色くなった完熟梅を使うことが、失敗しないための第1歩。「塩漬け」「赤しそ漬け」「土用干し」の大きな流れで、それぞれの工程を丁寧に行うことが成功の秘訣。材料や道具を揃えて作り始めましょう。手間ひまかけた赤しそ漬けのレシピをマスターすれば、関東干し(白梅干し)やはちみつ梅干しなどのバリエーションも作りやすく感じられることでしょう。慣れたら青梅から梅干し作りにチャレンジすると、また異なる味わいのレシピが増やせます。梅の実が熟す梅雨の時期に行う、日本の伝統食でもある梅干し作り。旬の手仕事として暮らしに取り入れてみてはいかがでしょう。