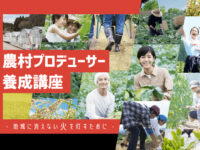多くのクラウドファンディングで送料と原価は込みと考えられる

多くのクラウドファンディングのリターンの値段には、送料が含まれています。そのため支援してくれた人に後から送料を請求することはできません。例外として、出張して何かをしてあげるサービスなどでは、リターンにすでに記載をしてあった場合のみ、後から出張費など支援した人の住んでいる場所などによって変動する料金を請求することはあります。
ここで考えなければいけないのは、リターンの値段に対して何%を原価と送料に充ててよいのかということです。
原価率をいくらに設定すればよいか
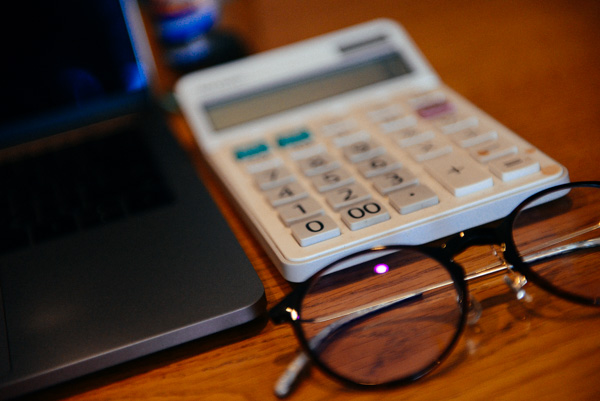
私がクラウドファンディングのリターンの原価率でおすすめしているのは30%です。30%と言うと少なすぎると感じる方も多いかもしれませんが、これにはクラウドファンディングの運営や、リターンの発送などに必要な手間賃が含まれていません。
原価率が30%を超えると、支援した人はお得な印象を得ることができますが、クラウドファンディングそのものが赤字になってしまってはファンディングそのものの意味がなくなってしまいます。一方で原価率が30%を切る場合、それでも支援してくれる方も確かにいるかもしれませんが、支援した人の気持ちは寄付をした時の感覚に近いものになり、集まったお金の使い道の詳細な報告や必要以上の待遇を期待されてしまうこともしばしばあります。
原価率30%程度で作ったリターンは、およそ市場の適正価格と同じになるはずです。クラウドファンディングでは、支援される数が一般的な店舗に卸す場合よりも少量になりがちなため、大量のロット数で作ることができません。このため、例えばジャムなどの加工品はスーパーマーケットで売っているものよりも割高になってしまうこともありますが、オリジナルのラベルを作ったり手紙を添えるなどして、その差を埋められるような付加価値をつけると良いでしょう。
送料が高い地域への発送について

送料については、沖縄や北海道、プラットフォームが許容している場合は海外など、規格外の送料がかかる場合は支援する前に相談が必要だとあらかじめ記載しておくのもひとつの方法です。同じく前述したように、あなたが実際に出向いて何かをしてあげるリターン──例えば料理教室やライブコンサートなど──は、支援してくれた人の住んでいる場所によって交通費が大きく変動するため、支援してくれた後に交通費を請求することをリターンの欄に記載しておきましょう。
クラウドファンディングはきちんと黒字に

クラウドファンディングは、アイデアに対して応援する気持ちでお金を支援してもらい、リターンを返した上で集まったお金でプロジェクトを実行するというシステムです。
目標金額以上のお金が集まっても、リターンの用意にかかる原価を差し引いた結果が赤字になってプロジェクトを実行できなければ元も子もありません。クラウドファンディングできちんと利益を出すことは、あなたのプロジェクトを責任を持って実行することへの第一歩なのです。
■次回はリターン履行の期限やトラブルについて
第13回ではリターンを履行するときの決まりやマナー、トラブルについて説明します。プロジェクトを始める前にこれらのリスクを理解してリターンを設定することで、あなたのプロジェクトはより信頼性の高いものになるでしょう。
【クラウドファンディングの仕組みを解説】シリーズ一覧はこちら!