コロナで消費者は5倍以上に増加、さらに発展させるには
高橋さんは東日本大震災後に産地を回り、消費者が生産者の実情をあまりにも知らないことを痛感、食材付きの情報誌「東北食べる通信」を2013年に創刊した。農業や漁業の現場を取材した情報と生産物をセットで届けることで、消費者にとって生産者をより身近なものにするのが目的だ。その活動をさらに発展させるため、インターネットで両者をつなぐポケマルを設立した。
ポケマルのサービスの特徴は、アプリを使って両者が交流できる点にある。例えば生産者は栽培方法などの情報を伝え、消費者は「新鮮でおいしかったです」といった感謝の言葉を返す。こうしたやりとりを積み重ねた結果、消費者が産地を訪ねるなど交流が一段と深まるケースも珍しくない。
サイトを立ち上げる際に交流機能を重視したわけについて、高橋さんは「食品ロスが年に600万トン以上出る飽食の時代にあって、食材だけでスーパーやコンビニと張り合うのは難しい」と説明する。そこでスーパーなどが提供しにくい付加価値になると考えたのが、「生産者と消費者の人間関係」。「ぼくらは産直のSNS(交流サイト)を目指している」と強調する。
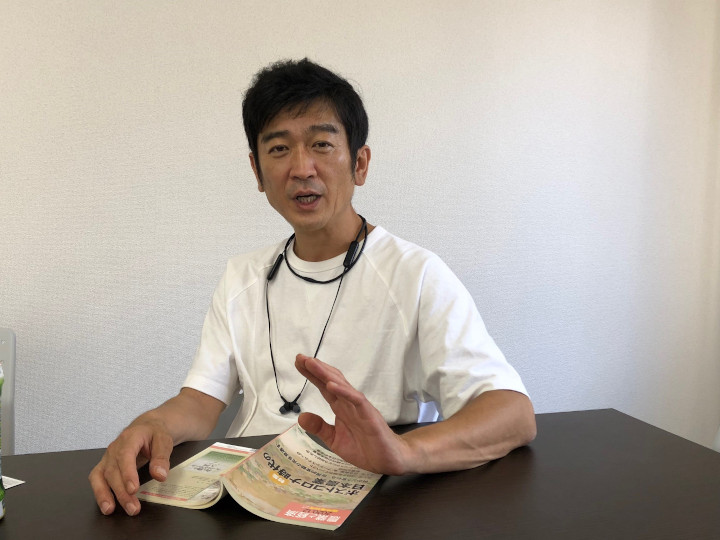
ポケマルを運営する高橋博之さん
こうした機能が評価され、サイトの利用は徐々に増えていたが、2020年の春過ぎから伸びがとくに急激になった。9月末の登録生産者数は3400人と前年同期比で2倍に増え、消費者の数は23万人と5倍以上になった。
背景にあるのが新型コロナの感染拡大だ。飲食店の休業などで売り先に困った生産者がネット販売に活路を求め、外食の機会が減った消費者が家に直接食材が届く便利さを歓迎した。生産者を応援するため、本来は消費者が払う送料を農林水産省が一部負担したこともこの流れに拍車をかけた。
「どこで何をどう食べるかといった食習慣を変えるのは難しいが、一度変わればなかなか元には戻らない」。高橋さんは先行きをこう展望する。たしかに、消費者が食品をネットで購入する習慣はある程度は定着するだろう。だがそれを確実なものにし、さらに発展させるにはサービスを提供する側と生産者ともにさらなる努力が必要になる。

人気商品の一つである野菜セット




























