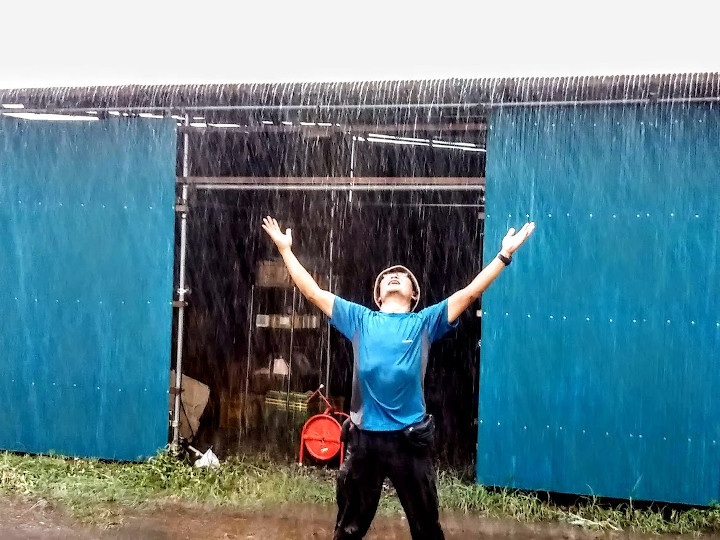農業用ハウスの実情から自分たちの技術を生かせると確信
タカミヤがハウスを運営しているのは、羽生市の郊外にある農業団地「羽生チャレンジファーム」。24ヘクタールの水田を市が畑に造成し直し、農業法人や企業を募って農業の新しいモデルをつくることを目指している。タカミヤのほかに、ハーブ農場やイチゴの観光農園などが入っている。
タカミヤが借りた敷地面積は3ヘクタールで、ハウスは2棟ある。いずれも地面に基礎を打ち、鉄骨で組み立てた大型のハウスだ。1棟目は面積が0.3ヘクタールで2021年8月に完成し、キュウリやイチゴ、ミニトマトを栽培している。2棟目は0.59ヘクタールで、近くキュウリの収穫を始める。
同社が農業関連の事業に参入したのは8年前。関東地方で大雪が降り、たくさんの栽培ハウスが倒壊したとき、自治体や農家から「力を貸してくれないか」と相談があったのがきっかけだ。足場材として金属製のパイプなどを扱っているので、ハウスの修復や建設ができないかと期待されたのだ。
このとき同社は農業用ハウスの実情を調べ、自分たちの技術を生かせるという手応えを得た。台風や大雪でハウスが壊れても往々にして補助金で直せるため、耐久性に十分に配慮していないケースがあることを知ったからだ。

1つ目のハウスの前に立つ吉田剛さん
同社が農業用のハウスで足りないと思ったのは、構造計算という考え方だ。鋼材をたくさん使えばハウスは丈夫になるが、その分、建設費もかさむ。そこで鋼材を補強する部品などをうまく活用し、できるだけ少ないコストで安全な施設をつくる。このノウハウを、農業に応用できると考えた。
こうして同社は農業用ハウスの製造と施工に参入した。大型の台風など自然災害が頻繁に起きたこともあり、注文は少しずつ増えていった。安くて耐久性に優れたハウスへのニーズは着実にあった。だが事業を本格的に大きくしようと思うと、一定の限界があることにも気づいた。
自治体や農協などとの打ち合わせで、「いかに頑丈か」を説明することはできる。だが「どれだけ収量を増やせるか」「糖度はどこまで上がるか」「収穫の時期はどこまで早められるか」といった質問にうまく答えることができなかったのだ。吉田さんは「そこにもどかしさを感じていた」と話す。
ハウスを購入する側が耐久性を軽視しているわけではないが、それ以上に関心があるのは作物の生育だ。そこで同社は施設の運営方法のノウハウを含めたパッケージで販売できるようにするため、自ら農場運営に乗り出した。吉田さんは「実際に自分たちで栽培してみたいとずっと思っていた」と語る。

ハウスで栽培したイチゴ
作物の生育を良くしたい農家の思いに応える独自の工夫とは
自治体や農協、生産者の第一の関心はいかに作物の生育を良くするかにある。その要望に応えるため、タカミヤは二酸化炭素の量などハウス内の環境をコントロールする設備を羽生チャレンジファームの施設に取り入れた。利用法に習熟するためだが、これは他の業者も追求しているノウハウだ。
これに対し、同社の持ち味を生かすために工夫したのが、ハウスの天井に設置するアーチ型のパイプだ。1棟目のハウスで採用したのは、同社がこれまで使ってきた建設現場の足場。本業で大量に使用しているので低コストで入手できるという利点もあるが、採用した理由はそれだけではない。
とくに注目したのがパイプの強度だ。直径は、農業用ハウスで一般的に使われているパイプの2倍。そしてふつうのハウスは0.5メートル間隔でパイプを設置するのに対し、同社は1.5メートルに広げた。耐久性に関する構造計算のノウハウを活用することで、間隔をぎりぎりまで大きくした。
直径はふつうのハウスの2倍だが、間隔は3倍なので、その分、ハウス内にできる影は小さくなる。つまり作物にたくさん日が当たる。光合成をしやすくすることで、生育にプラスの効果が出ることを期待したのだ。

パイプの間隔を広くとった1棟目の天井
2棟目のハウスは、天井のパイプの間隔を2.5メートルまで広げた。これは国内の建設現場で使っているものではなく、海外で製造されている特殊な形状のものを輸入した。2棟目のハウスは1棟目より軒高が2メートルほど高い。その分、受ける風圧などが強いため、より強度に優れた資材が必要になった。
結果はどうか。1棟目のハウスでキュウリがどれだけとれたのかを見てみよう。目標は、0.1ヘクタール当たりで1日に170~200キロ。これに対し、当初の実績は70キロ。最近は約2倍に増えたが、それでも目標には届いていない。ただし、採光を増やす効果がなかったと考えるのは早い。
収量が目標以下にとどまった理由は、栽培を始めたばかりでスタッフが慣れていなかった点にある。ツルが枯れる病気がキュウリで発生してしまったのだ。吉田さんが「初年度で目標に達するほど栽培は甘くはない」と言う通り、栽培技術を身につけるのも実証実験の課題だ。
やってみて大切さに気づいた点はほかにもある。パートをどう配置するかはその一つ。キュウリは盛期になると、猛烈な勢いで大きくなる。タイミングを逃すと、販売に適さない大きさまで育ちかねない。それを防ぐため、いかに適切な人数を配置するかはハウスの運営で必須のノウハウだ。
こうした課題を克服してはじめて、採光量を多くするために独自に設計したハウスの本当のポテンシャルが明らかになる。その結果を踏まえ、施設の運営方法を含めて自治体や生産者に提案することを目指している。

1棟目のハウスで育てたキュウリ
地域で一番の農家になりたい
かつて農業に参入した企業の多くは、既存の農家より自分がやったほうがうまくいくと漠然と思い込み、利益を出すことができずに失敗した。栽培と販売の両面で農業の難しさを理解せず、ねばり強くノウハウを高める努力も足りなかった。最近はこうしたタイプの参入はめっきり減った。
一方、タカミヤのケースは農場を運営する目的が明快だ。自ら各地に農場を設置するのが狙いではなく、ハウスを販売するためだ。だが、それには運営方法に習熟する必要があると考え、栽培まで手がけてみることにした。自分で使ってみることで、ハウスの設計の課題を見つけることもあるだろう。
ただし、実際に始めてみると、実験というレベルを超えて可能性を追求してみたくなるのも人情だ。羽生のハウスで育てた作物は現在、近隣のスーパーに販売しているが、吉田さんは「地域で一番のキュウリ農家になりたい」と話す。その思いがあってこそ、ノウハウの向上にも弾みがつくだろう。

地域の農家に負けないレベルを目指す