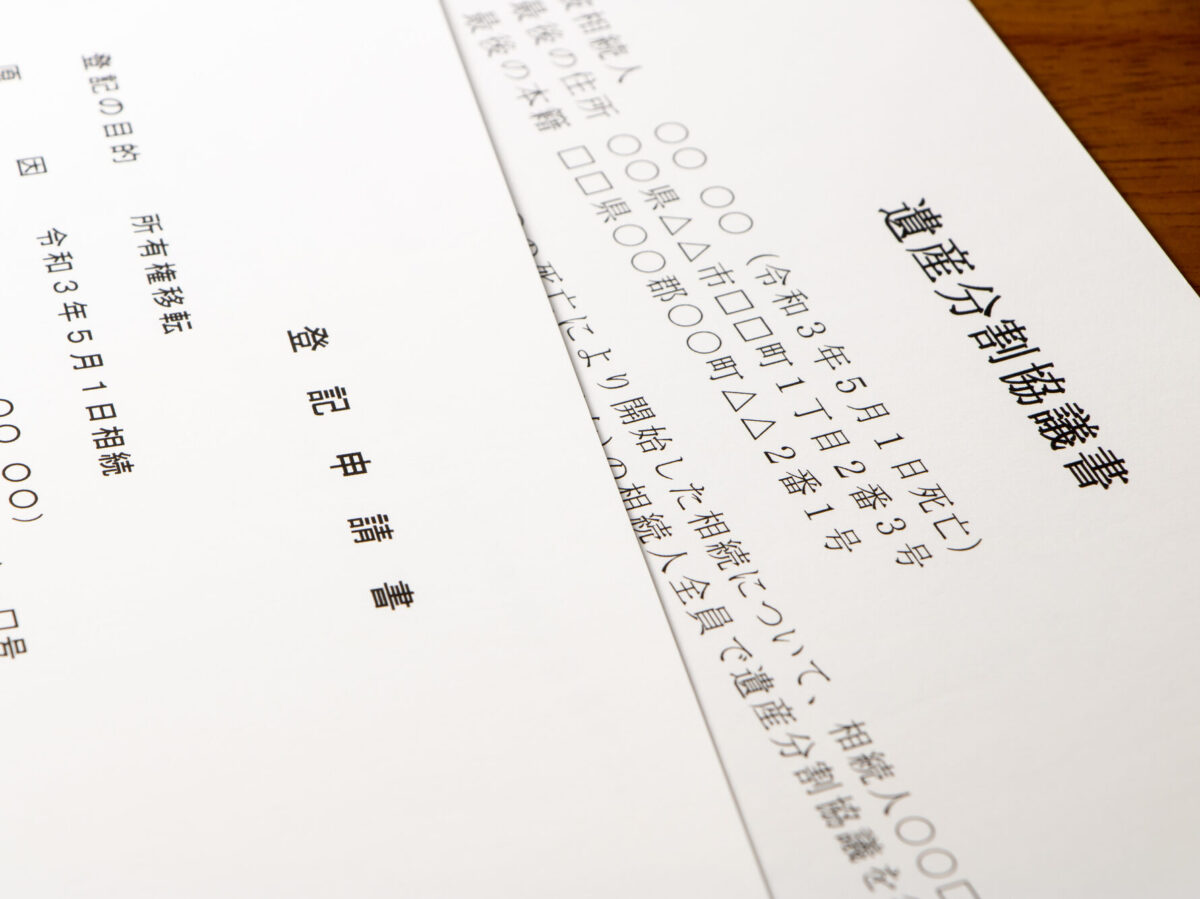正確には誤りだった「無農薬」の表記で、顧客からの信頼を損なう

直売所で店長をしております。
当店舗と最近、半年間の出荷契約を結んだ生産者が、農薬を使わずに栽培した野菜を「無農薬」の表記を記したパッケージで販売しています。当店では生産者の方へ、使っている肥料や農薬について記した栽培管理表の提出を求めており、それによると無農薬野菜との表記は問題ないものと契約段階では認識していました。
ほどなくして、これが誤りであることがお客さまからのクレームにより発覚しました。というのも、そのお客さまが生産者へ「苗はどこで購入しているのか」と尋ねた際、管内のJAで購入しているとの回答だったそう。そのJAへ問い合わせてみたところ、育苗期間に何度か消毒をしているとのことだったため、厳密には「無農薬野菜」という表記は誤りだったというのです。そのお客様はよくご家族で来店される方でしたが、このことがきっかけでひどくご立腹。そのため、お怒りの引き金となった生産者の方へは出荷契約の停止と損害賠償の請求を検討しています。このような事案の場合、そのような対応は妥当なものでしょうか。ご意見をいただけますと幸いです。
弁護士の見解
A 出荷契約の解除と生産者に対して損害賠償の請求が認められる可能性があり、ご諮問者様の対応は妥当であると考えます。
出荷契約の内容について
生産者に対して、出荷の停止や出荷契約の解除を求めることができるかについては、具体的にどのような内容の出荷契約を締結しているかによって結論が異なります。本事例における具体的な出荷契約の内容の詳細が不明であるため、最終的な結論は出荷契約の内容を精査したうえで判断する必要があるものといえます。もっとも、一般的には、出荷契約は民法上の委任契約に該当することが多いものと考えられるため、民法第651条第1項など民法の規定に基づいて出荷契約を解除することができることが多いものと考えられます。従って、本事例においても、ご質問者様は、委任契約に関する民法の規定に基づいて、生産者との出荷契約を解除できる可能性があるものと考えられます。
「無農薬野菜」との表記について
農林水産省が作成した「特別栽培農作物に係る表示ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)によると、野菜等の農作物について「無農薬」と表示することは禁止されています。この規定は、「無農薬」との表示について、消費差がその意味を正しく理解しておらず、「無農薬」という表示が優良誤認を招いているおそれがあるため、消費者の誤解を避けるために規定されたものであるといえます。消費者の「無農薬」という表示に関する誤解の具体例としては、「無農薬」と表示された場合、「土壌に残留した農薬や周辺ほ場から飛散した農薬を含め、一切の残留農薬を含まない農産物」であるとのイメージを受け取ってしまう場合や、原則として収穫前3年間以上農薬や化学合成肥料を使用せず、第三者認証・表示規制もあるなど国際基準に準拠した厳しい基準をクリアした「有機」の表示よりも「無農薬」の方が優良であると勘違いしてしまったりする場合があげられます。
以上から、本事例において「無農薬」との表記を行うことは、本ガイドラインに違反した行為であることとなります。もっとも、本ガイドラインは、法令に基づいて遵守義務を課すものではないため、本ガイドラインに違反したからと言って、直ちに法律上違法と判断されるわけではありません。
それでは、本事例のように「無農薬」と表示することは適法といえるのでしょうか。結論的には、「無農薬」と表示することは、違法であると判断される可能性が高いものと考えられます。
食品表示法第5条は、本事例の野菜のような食品を製造又は販売する者が、食品表示基準に従った表示がなされていない食品の販売を禁止しています。そして、食品表示基準第23条第1項第1号は、野菜などの農作物について、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語を表示してはならないと規定しています。前述した通り、「無農薬」との表示は、消費者が実際のものより著しく優良又は有利であると誤認する可能性の高いものであるといえるため、本事例においても「無農薬」との表示が食品表示法に違反しており違法であると判断される可能性が高いものといえます。
従って、本事例において、ご質問者様は、生産者に対して、生産者による食品表示法に違反する行為によって直売店の信用が棄損されたことを理由として、損害賠償を請求することができる可能性があるものと考えられます。ここで一つ注意すべき点としては、前述の食品表示に関する義務は、販売者にも課せられているため、本事例では「無農薬」と表示したことについて、生産者のみならず販売者である直売店も責任を負うこととなるという点です。このような事情があることから、ご質問者様が生産者に損害賠償を請求した場合、「直売店も違法行為を行っている」ということを理由として、認められる損害賠償の金額が減額される可能性があるものと考えられます。
本事案のポイントを整理
✅出荷停止や契約解除の具体的な条件は、出荷契約の内容によって定まることになる。
✅出荷契約は、民法上の委任契約に該当する可能性が高く、民法の規定に基づいて契約を解除することができる可能性がある。
✅「無農薬」との記載は、農林水産省のガイドラインで禁止されており、法律上も違法と判断される可能性が高いものといえる。
弁護士プロフィール
杉本隼与
2003年早稲田大学法学部卒業。2006年に旧司法試験合格(第61期)
2016年東京理科大学イノベーション研究科知的財産戦略専攻卒業 知的財産修士(MIP)
同年に銀座パートナーズ法律事務所を開設し、現在に至る。
銀座パートナーズ法律事務所