スギナとは?
ツクシとスギナの関係

スギナ(学名:Equisetum arvense)は、トクサ科に属する多年草で、春先に現れるツクシはスギナの胞子茎です。一見すると別の植物のようですが、地中で繋がっており、ツクシが繁殖機能(胞子)を担い、その後に出てくる緑の茎が栄養を蓄えるスギナとして成長します。ツクシは10~15cmほどの円柱形で、おひたしや佃煮にされることもあり、春の風物詩として親しまれてきました。
スギナの形態と生育環境
スギナは高さ30〜40cmほどの細長い緑の茎を持ち、節ごとに輪生した枝が生え、見た目が杉に似ていることからスギナ(杉菜)と呼ばれます。好むのは日当たりがよく、やや酸性の湿った土壌。河川敷や畑の周辺、道端などに多く見られ、地表の緑化を進める一方で、根が深く地下茎が横に張り巡らされるため、非常に駆除が難しい雑草とされています。
繁殖力と駆除の困難さ

スギナの最大の特徴はその繁殖力にあります。胞子での増殖に加えて、地下に張り巡らされた地下茎や塊茎からも新芽を次々と伸ばすため、少しでも根が残ると再生してしまいます。耕運機などで中途半端に掘り返すと逆効果で、切断された地下茎の節から新たに芽が出ることも。そのため、一般的な草刈りや手抜きでは完全な駆除ができず、地獄草と揶揄されることもあります。
スギナによる被害と注意点
スギナは地下茎によって広範囲に広がるため、畑や庭に一度侵入すると他の植物の生育を妨げてしまいます。栽培作物の根域に入り込んで養分を奪い取るほか、防除が難しいため農作業の負担も大きくなります。さらに放置すると、アレルギー体質の人にとっては皮膚炎や喘息などの症状を悪化させるリスクもあります。また、スギナの繁殖が隣家の敷地に及んだ場合、ご近所トラブルの原因になることも。単なる雑草と侮らず、早期の対策が必要です。
スギナに有効な除草剤って?

スギナはなぜ除草剤が効きにくい?
スギナは一般的な雑草と違い、表皮が硬く薬剤が浸透しにくい構造をしています。また、地中深くには地下茎や塊茎が生育しています。こうした特性から、スギナの駆除には地上部をしっかり枯らすことができる除草剤を繰り返し使用し、地下茎や塊茎への栄養補給を遮断することが最も重要です。
スギナに効く除草剤のタイプとは?
スギナ対策に有効なのは、葉や茎に薬剤をかけて有効成分を吸収させる茎葉処理型除草剤です。グリホサート系やグルホシネート系の除草剤が代表的なものです。さらに、再発を防ぎたい場合は、地面に散布して雑草の発芽を長期間抑える土壌処理型除草剤と併用することで、長期的な雑草管理が可能になります。
即効性と持続性のバランスが重要
除草剤には、早く枯らす即効性と、長く効き続ける持続性の両面があります。スギナのように地下茎から繰り返し再生する雑草には、複数回に分けての除草剤散布が有効です。見た目を早く改善したい場合は即効性重視、再発を防ぎたいなら持続性重視と、目的に応じて使い分けましょう。
グルホシネート系除草剤のザクサ液剤が効果的

グルホシネート系除草剤の代表格であるザクサ液剤は、スギナのように表皮が硬い雑草にも高い効果を発揮します。雑草を枯らすスピードが早く(即効性)、枯らした状態を保つ「抑草期間」も長いこと(持続性)が特長です。植物の細胞にアンモニアを異常蓄積させ、速やかに枯らす作用があり、地表に出たスギナに即効的に働きかけます。とくに雑草が密集していて刈り取りが難しい場所や、果樹園・家庭菜園の周辺でも安心して使用できるため、プロの農家からも高く評価されています。根まで完全に枯らすタイプではありませんので、水田畦畔等の傾斜した場所が崩れることもなく安心して使用できます。
スギナに有効な除草剤を選ぶときの注意点

周囲の作物への注意が必要
除草剤を使用する際は、対象となる雑草だけでなく、周囲の作物への影響にも注意が必要です。特に家庭菜園や果樹の根元など、栽培中の植物が近くにある場所では、薬剤が飛散しないように工夫することが重要です。
たとえばザクサ液剤のような非選択性のグルホシネート系除草剤は、葉や茎に付着した植物すべてに作用する特性がありますが、散布範囲をコントロールできれば非常に便利で効果的な除草剤です。 作物への付着を防ぐためには、風の弱い日を選び、ノズルの角度調整や飛散防止カバーを活用したスポット散布、周囲をビニールや養生シートでカバーするなどの工夫が有効です。
また、スギナのような頑固な雑草が限られた範囲に生えている場合には、部分的に非選択性除草剤を使い、ほかの場所では選択性の除草剤や手作業での除草と併用するのも良い方法です。用途や場所に応じて、適切に使い分けましょう。
安全性や環境への配慮も忘れずに
家庭で除草剤を使用する場合、人や動物への安全性、そして環境への影響にも配慮が求められます。特に小さな子どもやペットがいる家庭では、除草剤の選び方や使用方法に一層の注意が必要です。
また、水辺や側溝付近での散布には、水質汚染を防ぐために指定された使用条件や、拡散を防ぐ工夫が重要です。
結論!ザクサ液剤がスギナの除草におすすめ
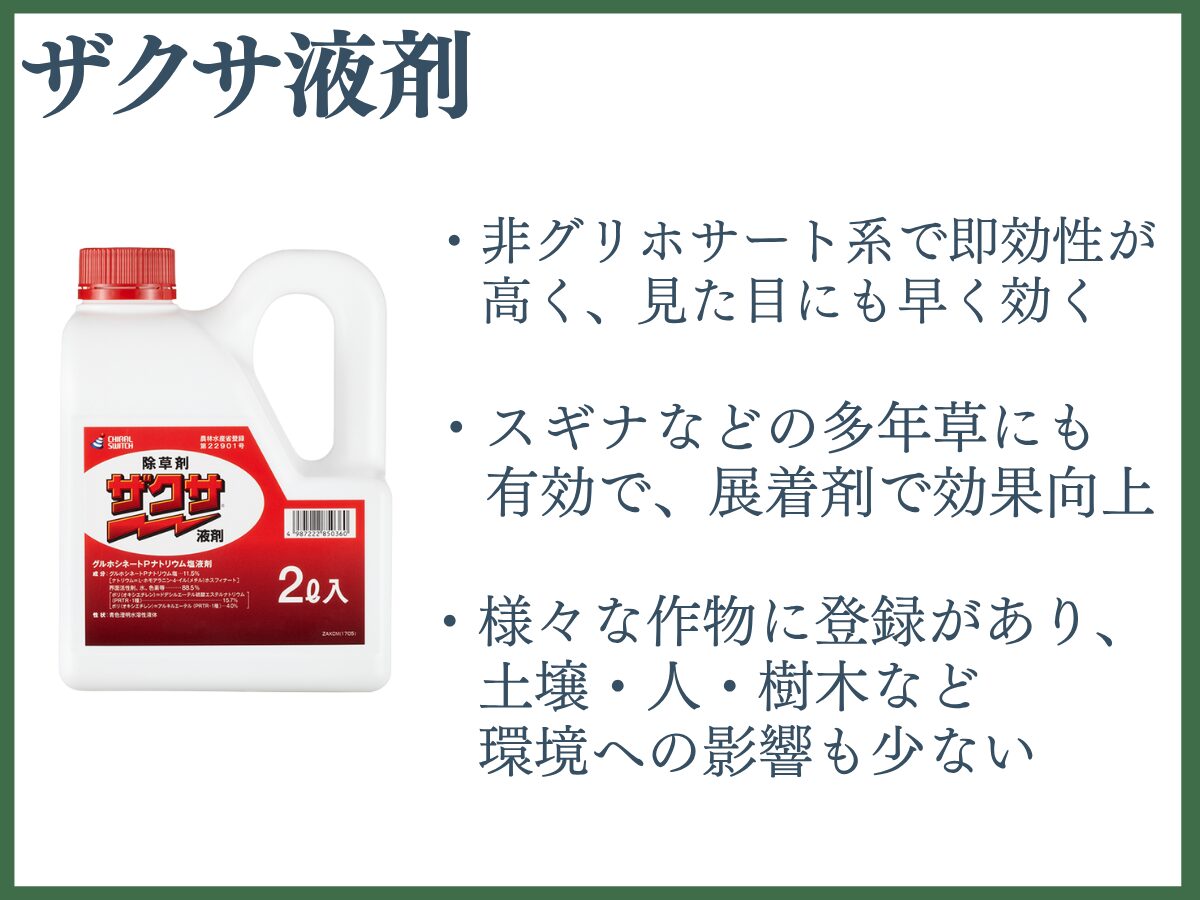
ザクサ液剤とは?基本情報と成分
ザクサ液剤は、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社と北興化学工業株式会社が販売する非選択性の茎葉処理型除草剤です。主成分はグルホシネートPナトリウム塩で、雑草の葉や茎にかかることで速やかに細胞にアンモニアが異常蓄積し、枯死させます。非グリホサート系で、土に落ちた成分がすぐに不活性化する特性があるため、作物の根に吸収されにくく、安全性が高いのも特長です。
スギナに対してなぜ効果的?
スギナのような表皮が硬く、根が深い多年草にも、ザクサ液剤は有効です。グルホシネートは植物内でグルタミン合成酵素の活性を阻害し、アンモニアが細胞内で異常蓄積し、光合成阻害などにより枯死します。スギナのような頑固な雑草でも、表面から深部までじわじわと枯らす力があります。また、ザクサ液剤にはすでに展着剤が配合されているため、薬液がしっかりと葉に付着しやすく、効果の安定性も高いのが特長です。
ザクサ液剤の魅力
ザクサ液剤は、しぶとい雑草にもスピーディに作用する即効型の除草剤です。散布から2~3日で枯れ始め、7~10日ほどで地表部が明らかに変化し、草刈りでは対応しきれない雑草対策の手間を大幅に減らせるのが特長です。 とくにスギナのような多年生かつ地上部が硬い雑草に対しても、高い効果が確認されており、目に見えて効きはじめるスピードに定評があります。
ザクサ液剤は根まで完全に枯らすタイプではありませんが、繰り返しの使用によって地上茎を確実に枯らすことで、地下茎の再生力を徐々に弱め、スギナの密度を抑えることが可能です。
また、散布後の土壌中では成分が速やかに分解されるため、環境や次作への影響が少ない点も安心材料のひとつ。長年にわたって選ばれてきた理由が、この「効きの早さ」と「扱いやすさ」に集約されています。
家庭でも使いやすい理由
ザクサ液剤は使用後の土壌残留が少なく、環境にも配慮された設計がなされており、家庭菜園や果樹園周りでも活用されています。 ただし非選択性のため、作物に直接薬液がかからないように細心の注意が必要です。 作物によっては、使用できるタイミングや収穫前の制限日数(収穫何日前まで)が設定されているため、必ずラベルで対象作物の「使用時期」や「使用回数」を確認しましょう。 なお、ザクサ液剤は原液タイプのみの展開で、使用時には希釈が必要です。ラベルに記載された薬量と希釈水量を守りましょう。
ザクサ液剤を使ったスギナ駆除の正しい手順
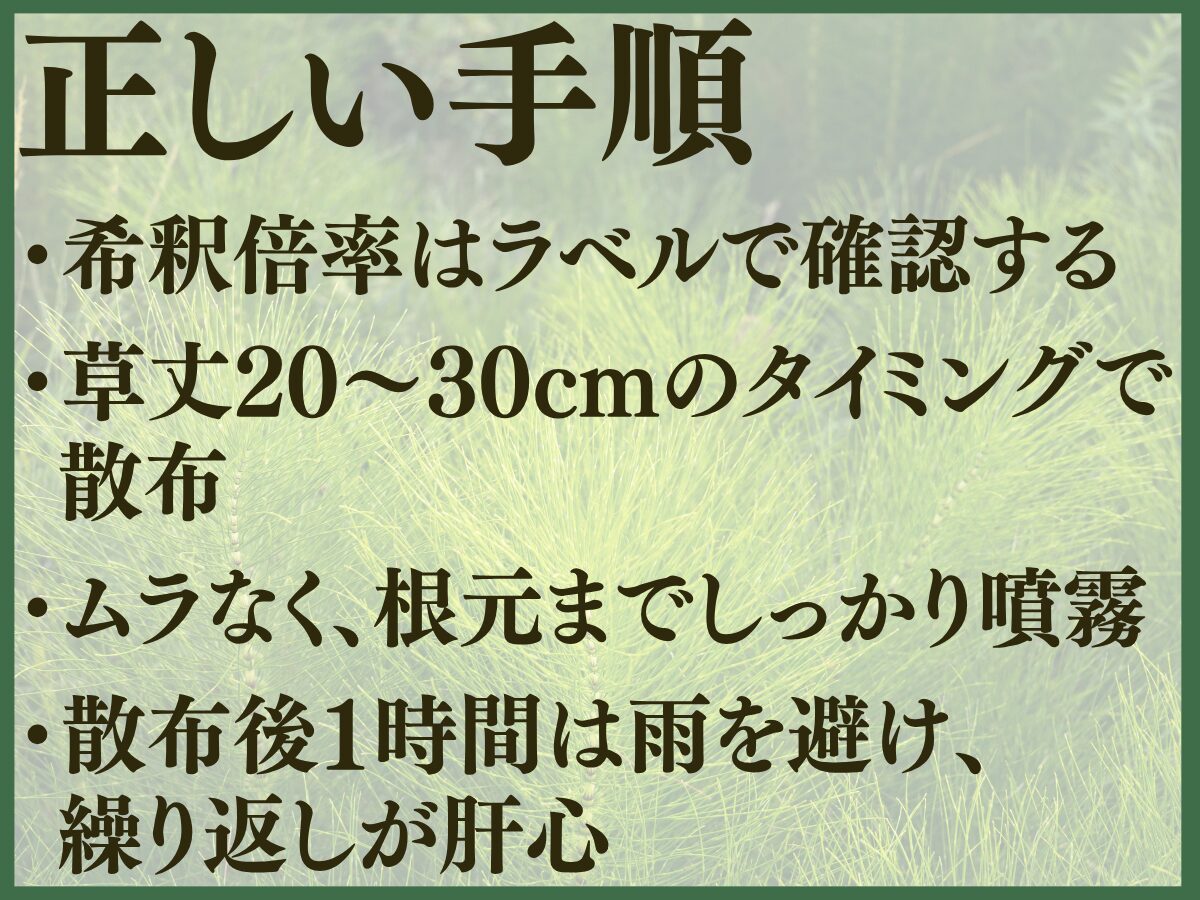
希釈倍率はラベルで確認する
ザクサ液剤を使用する際は、目的や作物、場所に応じて適切な希釈倍率で使うことが重要です。 たとえば一般的なスギナ駆除では100倍程度の希釈が目安になるケースもありますが、適用作物によっては100倍程度の希釈で使えないものもあります。誤った希釈倍率で使用すると効果が薄れ、作物に薬害が出るおそれがあるため、ラベルをよく読み、適用作物や雑草の種類に合った用法・用量を守ってください。
草丈20~30cmのタイミングで散布
スギナが地表に20〜30cmほど伸び、生育が活発になっている時期(5月〜9月)に散布するのが最も効果的です。とくに雨が降っていない穏やかな晴天の午前〜昼頃がベスト。風が強い日は避けましょう。
ムラなく、根元までしっかり噴霧
ザクサ液剤は葉や茎から吸収されるため、スギナ全体が濡れるようにまんべんなく噴霧することが大切です。表面だけでなく、葉の裏や茎の根元にも薬剤がかかるよう、ノズルの角度を調整しながら丁寧に散布しましょう。地面だけを濡らしても効果は薄いので注意が必要です。
散布後1時間は雨を避け、繰り返しが肝心
散布から1時間以上雨が降らなければ、効果に大きな影響はありません。ただし、ザクサ液剤は地中の根を枯らすわけではないため、スギナが再生する可能性があります。2~3週間おきに再散布することで、地上部を繰り返し枯らし、地下茎を徐々に弱らせていくのが効果的です。
・ペットや小さなお子さんが触れないよう、散布後しばらく立ち入らせないようにしましょう
・散布後は手袋を外し、手をしっかり洗うことも忘れずに
※農薬使用基準やラベルの記載を必ず確認してください。

まとめ
スギナは繁殖力が非常に強く、一般的な除草ではなかなか駆除できない厄介な雑草です。そんな中で注目されているのが、ザクサ液剤。即効性がありながら、多くの作物に登録があり、家庭でも農地でも活躍する優秀な除草剤です。適切な希釈・タイミング・手順を守れば、スギナ対策に強い効果を発揮します。しつこいスギナにお悩みの方は、ぜひザクサ液剤を検討してみてください。





























