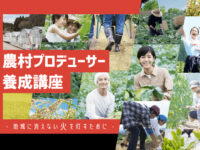フキとはどんな山菜?特徴や分布など

フキは春の訪れを告げる野菜のひとつです。独特の香りとほろ苦さ、茎の歯ざわりを楽しみます。冬に黄色い花を咲かせることから、冬黄(ふゆき)がつまって「ふき」と呼ばれるようになりました。
原産地は日本で、野生のフキは北海道から沖縄まで全国で見られます。古くから、せき止めや去痰に、葉は切り傷や虫刺されなどの薬用にも使われてきました。朝鮮半島や中国に分布していますが、日本で野菜として栽培が始められ、主に茎(葉柄)を加熱調理をして食用とします。中国では食用ではなく、薬用植物として用いられています。
フキノトウはその名の通り、葉が茂る前に根茎から生えるフキのつぼみ。山野の湿り気のある日陰、土手、沢沿いなどに群生し、早春の味覚として人気です。
フキの栄養と主な効能
フキの栄養価は、可食部100gあたり、脂質0g、炭水化物3g、エネルギー11kcalと極めて低く、ミネラル類ではカリウムが330mgと比較的多く含まれています。独特の苦味成分であるサポニンやタンニンは、消化を助け、食欲を増進させる効果があるといわれています。
9割以上が水分
フキは可食部100gあたり水分が95.8gと9割以上が水分です。同程度の水分量を含むレタスやキュウリのように、フキもみずみずしさが楽しめる野菜です。ゆでたフキは100gあたりの水分量が9.7gに増え、カロリーが11kcalから8kcalに下がるので、ダイエット中のカロリー制限にも役立てることができます。
食物繊維とミネラルが豊富
フキに含まれるミネラル成分の中で最も多いカリウムには、体内でナトリウムとともに体液の浸透圧を維持するとともに、利用作用があり、むくみの解消を助けます。また、可食部100gあたり1.3gが含まれる食物繊維は水溶性で、水に溶けるとゼリー状になって小腸をゆっくり動くので、空腹を感じにくくなる効果もあるようです。
高血圧や大腸がんの予防にも
カリウムには、体内でナトリウム(塩分)の排出を促して血圧を下げる作用があります。また、最新の研究成果として、フキノトウの苦味成分のひとつペタシンが抗がん効果を発揮することが学会発表されています。フキとフキノトウが、高血圧やがんなどの生活習慣病の予防に役立つかもしれません。
フキの花言葉は愛嬌・公平など
フキはキク科の多年草で、葉が出る前の3〜5月に黄白色の花が咲きます。その花のつぼみが、フキノトウ。フキの花言葉は、愛嬌、公平のほかに、「私を正しく認めてください」というものもあります。フキは昔から薬用植物として民間療法に使われてきましたが、その薬効を信じない人も多くいためこのような花言葉がつけられたと言われています。フキは漢字で「蕗」と書き、別名には「冬黄(ふゆき)」「款冬(カンドウ)」などがあります。
フキの旬は3月〜5月ころ!代表的なフキの種類は?

露地物や天然物のフキは3~5月が旬ですが、近年はハウス栽培のものが多く、夏を除いたほぼ一年中出回っています。全国の生産量の4割を1位の愛知県が占め、2位に群馬県、3位に大阪府が続いています。現在栽培されている品種のうち大半が愛知早生フキです。収穫量は少ないものの、水フキ、山ブキ(山蕗)、秋田フキなどの品種もあります。ここでは、それぞれの品種の特徴を詳しく見ていきましょう。フキノトウについても紹介します。
一般的に流通している「愛知早生」
茎は淡緑色で太く、根元は赤みがかっているものもあります。明治時代に現在の愛知県東海市で発見され、周辺地域に広まったもので、茎の伸びが早く、香りがよく、やわらかく、アクや苦みが少ないのが特徴です。知多半島はその一大産地で、10月から翌年1月に収穫される 「秋フキ」と、2月から5月に収穫される「春フキ」が生産されています。
山野に自生している「山ぶき/野ふき/水ふき」
山ブキ(山フキ)は、山野に自生しているもので、野ブキとも呼ばれています。茎は細めで、佃煮のきゃらぶきの材料として使われます。水フキは、茎は鮮やかな淡緑色、根元は赤色で、香りがよく、苦みは少なく、やわらかで、主に水煮や缶詰として加工されて販売されています。青ブキ、河内ブキ、京ブキなどの別名でも呼ばれています。
サイズが大きい「秋田ふき」
秋田フキは、フキの変種で秋田県に自生したことから、この名がつけられました。大型のフキで、茎は長さ2m、直径3~6cm、葉も1~1.5m幅になります。秋田県や北海道で栽培されていますが、肉質が堅いため野菜として出回ることはあまりなく、佃煮や砂糖漬けに利用されています。秋田県の仁井田では江戸時代から栽培され、現在は観光資源にもなっています。
日本一巨大な「ラワンぶき」
北海道足寄町(あしょろちょう)の螺湾(螺湾)地区の川沿いに自生している大型フキは、「ラワンぶき」と呼ばれています。秋田ブキと同じ品種と見られていますが、ラワンブキのほうが大きく育ち「日本一大きなフキ」として知られています。「ラワンぶき」は、足寄町農業協同組合が知的所有権(商標)を取得。種苗等の町外持ち出しが禁止されています。
フキの花つぼみ「フキノトウ」
フキの根茎から葉が出る前に地面に顔を出すつぼみが、フキノトウです。出荷のピークは2~3月。生育中のつぼみなので、フキよりも栄養が豊富に含まれています。つぼみが開く前のほうが食味がよく、開いたものは苦みが強くなります。アクが強いので、和え物やおひたしに使う場合は、ゆでた後に冷水にしばらくさらしてアク抜きをします。
おいしいフキの選び方とは?鮮度のいいフキを見分けるポイント
特有の風味と歯ごたえを楽しむフキ。鮮度がよく、おいしいフキは、新葉が伸びきり、みずみずしいのが特徴です。葉は黒い斑点がなく、鮮やかな緑色であることも要チェックです。見分け方のポイントを、さらに詳しく解説していきます。
1.新葉が伸び切ってみずみずしい
主に茎を食べるフキですが、選ぶときはまず葉を見ます。新葉が伸びきり、みずみずしく、色ツヤのいいものを選びましょう。葉の緑色の鮮やかさは鮮度のバロメーター。黄ばみや黒い斑点が見られたら、鮮度が落ちているサインです。
2.茎を持った時にしならない
新鮮なフキは、茎を持ったときにしならずにピンと張りを保っています。いくら茎がピンとしていても、太すぎると筋が硬い可能性があるので要注意。直径1.5~2cmぐらいの太さで、中に空洞のないものを選びましょう。
3.野生のものは太めの茎がやわらかい
野生のフキは細くて短かめです。 細い茎は食感が筋張っていることが多いので、その中でも太めで柔らかいものを選びましょう。茎がしなっと折れ曲がるものは、収穫してから時間が経っています。切り口が乾いていないかもチェックしましょう。
フキのおいしさを長持ちさせる保存方法!事前のアク抜きが重要
独特の香りや苦みが楽しめて、ときには春の訪れを感じさせてくれるフキですが、買ってすぐに調理しないと色や風味がどんどん落ちてしまいます。フキのおいしさを長持ちさせるために大切なのが、下処理です。少し手間がかかりますが、アク抜きや色落ちを防ぐ効果があるので惜しまず行いましょう。手順は、1.板ずり、2.下ゆで、3.皮むき、4.冷凍または冷蔵保存。それでは、それぞれのステップと作業のポイントを詳しく見ていきましょう。
1.程よいサイズに切り板ずり
フキはゆでる鍋に収まる範囲でできるだけ長めにカットします。長く切ったほうが後の皮むきが楽になります。切ったフキはまな板の上に並べて、塩(フキ6~8本あたり大さじ2程度が目安)をふり、両手で軽く押しながら転がして板ずりします。こうして板ずりをすることで、色鮮やかにゆで上がります。
2.下ゆで後に水で冷やす
鍋で沸騰させたゆで湯に、フキを塩がついたまま入れます。鍋はフキが折れ曲がらない大きさで。フライパンなどの面積が広く浅い鍋を使うといいでしょう。ゆで時間は太さに応じて、冷蔵保存する場合は3分~5分、冷凍保存する場合は1~3分。ゆで上がったフキは水に取り、しっかり冷まします。
3.皮をむいて水分を拭き取る
冷ましたフキは、根元の太いほうから皮をむきます。包丁を入れて薄皮を少しむいた後に、フキを回しながら引っ張るようにしてむくと作業がスムーズです。皮が残っていると食べたときに筋っぽく感じるので、きれいにむいておきましょう。
4.冷蔵もしくは冷凍保存
皮をむいたフキは、調理しやすい大きさにカット。冷蔵保存する場合は、保存容器に入れて水を張って冷蔵庫へ。水は毎日取り替えると色持ちがよくなります。冷凍保存する場合は、キッチンペーパーなどで水気を取り、小分けしてラップで包み、保存袋に入れて冷凍庫へ。冷蔵で1週間、冷凍で1カ月ほど保存できます。
保存したフキをおいしく食べる!おすすめの調理方法

下処理して保存したフキは、食べたいときに必要なだけ料理に使えて便利。ここで、覚えておきたいのが、保存方法によっておいしく食べるための調理方法も異なることです。冷凍・冷蔵のそれぞれに適した調理方法を見ていきましょう。
冷蔵保存のフキはレシピが豊富!炒めものや天ぷらなど
冷蔵保存したフキは、食感やみずみずしさを残すことができるため、和え物やおひたしはもちろん、炒め物や天ぷらなど、幅広い料理に使うことができます。調理する際は、保存容器の水から取り出したフキを、軽く洗い流してから使いましょう。
冷凍保存のフキは繊維が強い!煮物や佃煮にピッタリ
冷凍保存したフキは、水分が抜けて繊維質が強くなるため、煮物や汁ものにすると煮汁やだし汁の旨味を吸っておいしくなります。佃煮(きゃらぶき)などの常備菜にも適しています。フキは凍ったまま使用することができます。
フキをおいしくするワンポイント
アクが強くて風味豊かなフキ。扱うのが難しそうですが、おいしくするためには、できるだけ鮮度を保ち、下ごしらえを丁寧にして、適した調理をすることが大切です。ここでは、そのコツをワンポイントで紹介していきます。
1.その日に食べるなら下ごしらえを丁寧に
採った・買ったフキをその日に食べる場合は、下ごしらえが大切です。葉と根元の硬い部分を少し切り落とし、まな板に並べて塩をふって転がしながら板ずりをし、下ゆでして流水にさらして、アクを抜いてから使用します。葉は食べるには苦味が強すぎるかもしれませんが、捨てずに、下ゆでをするときに一緒に入れると香りが良くなります。
2.茎・葉それぞれに適した調理方法を
フキの葉も食べられますが、アクが強く苦味があるので必ず下処理をしましょう。沸騰した湯に一つまみの塩を入れて葉を1分ほどゆで、冷水にさらして途中で水を替えながら数時間~一晩かけて十分にアクを抜くのがポイント。佃煮やフキみそなどに利用できます。茎は和え物やサラダに。下ゆでしたものを冷蔵庫で冷やし、食べる直前に調味料を和えたりドレッシングをかけると、歯ざわりが一段とよくなります。
3.切り口が劣化したら根元を切って水に浸そう
フキの切り口は、空気にふれると酸化してすぐに茶色くなってしまいます。切り口が劣化してしまったときは、根元を切り、水に浸しておくことで、鮮度を保つことが可能です。すぐに調理の下ごしらえや保存のための下処理ができない場合は、葉と茎を切り離し、それぞれラップに包んで冷蔵庫の野菜室で一時保管するといいでしょう。
春の山菜といえば「ウド」も定番!

春を告げる山菜といえば、ウドも忘れてはなりません。日本が原産で、全国各地の山野に自生しています。食用としているのは日本だけで、古くは野生種が薬用とされていましたが、17世紀ごろに土栽培が始まり、本格的に食されるようになりました。江戸時代から栽培が盛んな東京では「江戸東京野菜」の一つに指定されています。
ウドの種類は栽培方法によって2つに大別されます。一つは、トンネルなどで遮光して軟白(なんぱく)栽培する「軟白ウド」。もう一つは、株根に盛り土をして下部をやや軟白化させ、芽を日光に当てて緑色にする緑化ウドで、市場では「山ウド」と呼ばれています。軟白ウドは周年出回っていますが3月が出荷のピーク。山ウドは冬から春にかけての2月から4月が旬です。
ウドの栄養と主な効能
ウドはほとんどが水分で構成されています。栄養素としては細胞の浸透圧の維持に関わるカリウムが多いのが特徴です。カリウムは、体内に余分に蓄積されたナトリウムを排出して高血圧の予防にも効果があるといわれています。また、抗酸化作用が期待できるとして、近年注目を集めているポリフェノールもわずかですが含んでいます。
鮮度が良いおいしいウドの選び方

ウドは独特の香りとシャキシャキとした食感を楽しむ野菜です。新鮮なものを選んで、春の味覚を存分に楽しみましょう。太さが均一なものが良質で、うぶ毛が密生していれば新鮮です。選び方のポイントを見ていきましょう。
1.切り口から穂先まで同じ太さ
良質なウドは、株の切り口から芽まで太さが均一です。軟白ウドは太く、芽先までピンと張っているものを。山ウドは、茎が太く短めで葉がしおれていないものを選びましょう。
2.茎が白くハカマがピンク色
軟白ウドは、茎が白く、まっすぐで、芽先と根元のハカマがきれいなピンク色をしているものを選びましょう。山ウドは、赤い線がクリアなものが鮮度が高く良質です。
3.うぶ毛が密生している
ウドのうぶ毛は、鮮度を見極めるポイントです。軟白ウド、山ウドともに、やわらかなうぶ毛が密に生えていることが、新鮮な証です。
ウドの保存方法
ウドは光に当たると劣化が進んで硬くなってしまうので、新聞紙などに包んで、冷暗所で保存します。常温で2日から3日、冷蔵庫の野菜室では最大で1週間ほど保存することができますが、新鮮なうちにできるだけ早く食べきりましょう。
ウドをおいしくするワンポイント

色白なウドですが、アクが強いため、切った端から空気にふれて茶色に変色してしまいます。アクを抜いて食味をよくし、白くきれいに仕上げるための下ごしらえのポイントを紹介します。
1.アク抜きは酢水にさらして
ウドは4センチほどの長さに切り、皮をむきます。皮の近くにアクの原因となる成分を多く含むので、切り口の内側の円の部分まで厚めにむいて、酢水にさらしましょう。酢には酸化酵素の作用を抑える働きがあり、アクが抜けて色も美しい白に仕上がります。
2.炒めものはスピード勝負
ウドの苦みは油と好相性。ウドを炒めるときには、手早く炒めるのが最大のポイントです。火を通しすぎると歯ごたえが悪くなるので、スピーディーに仕上げましょう。厚めにむいたウドの皮も、千切りにして水にさらして、さっとゆでてからきんぴらにするとおいしく食べられます。
3.穂先は天ぷらやお吸い物に
ウドの穂先の柔らかい部分は、生のまま天ぷらにしたり、お吸い物に入れて、おいしく食べられます。皮と一緒にきんぴらにするのも食欲をそそります。ウドは1本丸ごと、無駄なく味わい尽くせる旬の味覚です。
ひと手間かけて春を味わう
フキは少し苦みがあり、アクが強く、それが好きな人はもちろんいますが、調理するのも食べるのも、苦手な食材と思われがちです。しかし、その苦味成分に新陳代謝を促す働きがあると聞くと、ちょっと見る目が変わるのではないでしょうか。フキやウドなど、春の野菜・山菜に苦みがあるのは、冬の間に体に溜め込んだ老廃物をデトックスするための自然の摂理とも言われています。フキは下処理や下ごしらえをすれば、おいしく食べられ、料理の失敗もありません。家庭料理のレパートリーが増え、常備菜も充実します。時間のあるときに冷蔵・冷凍保存しておけば、手早く使える食材になります。今度の春は、新鮮なフキを選び、ひと手間かけて、ほろ苦い旬の味覚を楽しんでみませんか。
参考書籍 草土 花図鑑市リース4 花図鑑 野菜+果物(草土出版)