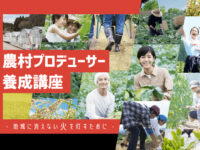センサーを導入し、水やりを自動化した
久松さんを取材していていつも驚かされるのは、その論理性の高さだ。何となく作業したり、やり方を変えたりすることはまずない。新しく導入した栽培支援のシステムについて質問していたときも、そのことを強く感じた。
システムは大きく2つの体系に分かれている。1つは、井戸から水をくみ上げ、灌水(かんすい)チューブを通して農場に水をやるシステムだ。以前は手でコックを開け閉めし、作物に水をやっていたが、今はスイッチを入れたり切ったりすることで、電動で水を流すことができるようになった。取材の最中、久松さんは試しにスイッチを入れてみて一言。「ほら、シャーって音がしたでしょ」

圃場の環境を計測するシステムの「みどりクラウド」(セラク)。久松農園は日射量のデータを活用し、水やりをコントロールしている
もう1つが農場に設置したセンサーで、日射量や温湿度、土の中の水分量などを計測する。このうち日射量のデータと水やりのシステムを組み合わせることで、積算の日射量が一定の水準に達したら自動で水を流す仕組みを作った。植物が光合成のために使う水が足りなくなるのを防ぐためだ。
対象にする作物は、ハウスで育てているトマトと、近くの露地で栽培しているナスやキュウリ、オクラ、ピーマン。センサーはハウスに設置した。ナスはトマトなどより水を必要とするため、水やりの回数を増やすなど、作物に合わせて水分量を調節している。オランダの巨大なガラスハウスなどで行われている環境制御型の栽培技術のエッセンスを取り入れた。

いろんな野菜に水を供給するチューブ
久松さんが脱サラし、就農したのが1999年。自動灌水のシステムを前に「20年前と比べると、技術的にはずっとやりやすくなってます」と話す。
ここまで読んできて、「これって有機農業に特有の技術ではなくて、農薬や化学肥料を使う慣行農業と同じ技術ではないのか」と思う人もいるかもしれない。新しい土づくりの方法など、有機農業ならではの技術を期待した人もいるだろう。その点に関する久松さんの説明は、有機農業の本質を鋭く言い当てていた。
「有機農業ってよく考えたら、作物を健康に育てて農薬が要らないような状態にすることだと思うんです」
虫がつくのを防ぐ防虫ネットや、雑草の種を高熱で処理する太陽熱マルチといった資材はある。だが、久松さんがここで強調したいのはそれ以前のもっと根本的なことだ。ナスを見ながらこうも話した。「こいつら光合成してる生き物なので、その原料をちゃんと与えないとダメ。このナス元気でしょ。水を十分にやると病気にならないし、虫も食べに来ないんです」
では昔ながらのやり方でそれはできないのか。「手動では現実的に無理です。だって十何個もあるようなコックを、10時に何分間、12時に何分間それぞれ開け閉めしようと思ったら、人が張り付いていなければならなくなります」。少量多灌水を持続的に人がやるのは無理があるのだ。