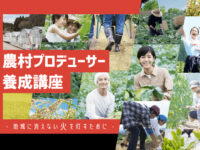「ヨーカ堂は一生懸命やってるよ」
イトーヨーカ堂が農業に参入したのは、店舗で売れ残った野菜などの食品残さを有効利用するのが目的だ。専門の業者に委託して堆肥(たいひ)に加工し、農場で活用する。農場は各地の生産者などと共同で開設しており、すでに全国12カ所にある。セブンファーム富里はその第1号だ。
設立は2008年。イトーヨーカ堂と富里市農業協同組合、地元のベテラン農家の津田博明(つだ・ひろあき)さんが共同で出資して立ち上げた。現在の栽培面積は5ヘクタール強。ニンジンやダイコン、キャベツ、トウモロコシなどさまざまな野菜を栽培し、イトーヨーカ堂に出荷している。栽培を担当しているのは、セブンファーム富里の社長を務める津田さんだ。
津田さんに最初に取材したのは、設立の翌年の2009年だ。イトーヨーカ堂でセブンファームを担当している久留原昌彦(くるはら・まさひこ)さんが同席している取材で、津田さんが次のように語ったのが強く印象に残っている。
「農家にとって取引が見えるのは市場まで。企業はもっと遠くのほうにいて、見えない。まるで化け物みたいに感じることもある」

セブンファーム富里の看板
それまで直接接することのなかった大手企業と組むことへの戸惑いを表現した言葉だ。文字だけ読むとキツイ言葉のように感じるかもしれないが、津田さんはつねに笑みを絶やさない人で、その場の雰囲気がとげとげしくなったわけでは決してない。その後で、津田さんは「でもヨーカ堂は意外とよかったな。みんな一生懸命だ」と続け、久留原さんらをほっとさせた。そのとき筆者が感じたのは、一国一城のあるじである農家の芯の強さだ。誰が相手でも遠慮せず、ストレートに率直に話す。別の取材では、久留原さんを横目に、「ちょっとしゃべりづらいから、どこかへ行ってもらおうか」と話した。もちろん冗談。思ったことを率直に話すという意思表示だ。
この取材からちょうど10年。営農に何か変化は起きているだろうか。そう思って久々に農場を訪ねると、津田さんはイトーヨーカ堂に勧められて認証を取得した農業生産工程管理(GAP)のことを語り始めた。
「最初のうちはなんでこんな面倒くさいことやらなければならないのかと思ったよ。でも2~3年たつと、自分のためになるんだとわかってきた」。歯にきぬ着せずにものを言う「津田節」は健在だった。

JGAPの認証を取得した
GAP認証がもたらした意外な効果
GAPは農薬を適切に使用し、農産物に異物が混入するのを防ぎ、従業員のケガを防止することなどを目的にした農作業の管理規定で、それぞれの目的を達成するために細かいチェック項目が定められている。セブンファーム富里は、日本GAP協会がつくったJGAPの認証を2009年に取得した。
当時の取材でJGAPが話題にならなかったのは、やっている津田さん自身、なぜ作業を細かく点検しなければならないのか、ふに落ちていなかったからだ。例えば、農協に提出する栽培履歴は農薬の商品名を記載すればすむ。これに対しGAPに対応するには農薬の成分を確認し、記録する必要がある。そのころ津田さんはテレビ番組の取材でGAPの認証を取った効果について「農場がきれいになった」と答えている。ほかにあまり手応えがなかったからだろう。