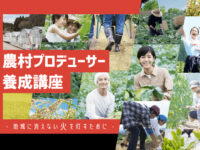八百屋の歴史

広辞苑には、八百屋について「野菜類を売る商家。また、その人。青物屋」と記載されています。「青物(あおもの)」とは野菜の総称のことで、「青物屋」とは「野菜や果物を売る店」のことを言います。
日本での八百屋の始まりは平安時代の10世紀ごろで、当時は自分で作った野菜類を町で売り歩いていたようです。江戸時代の17世紀に、店での野菜類の販売がはじまり、そのころは野菜類以外の物も売られていたと言います。
そして18世紀に入ると、商品は野菜類に限られて、葉菜類、根菜類、果菜類だけが店頭で売られるようになりました。この頃には流通の流れもできていて、都市の青物市場に野菜類が集荷されて、八百屋はそれを仕入れて小売りしていたそうです。
19世紀後半になると、八百屋では果物も販売されるようになります。さらに第二次世界大戦後はスーパーマーケットや産地直売が普及しはじめ、八百屋でも缶詰や瓶詰類も置かれるようになりました。そして現在、八百屋はその形や販売経路を変えながら、私たちの生活の身近な存在であり続けています。
八百屋の語源は諸説あり!

それでは、なぜ「八百屋」と呼ばれているのでしょうか。
記事の冒頭にもあったように、江戸時代、八百屋は「青物屋」とも呼ばれていました。これが「青屋」と略されて、さらに「やおや」と呼ばれるようになったというのが一説です。
一方、日本大百科全書では、語源について「そこではいっさいの精進の調菜(副食物)、乾物、海藻、木の実、草根などを扱っていたので八百屋といった」と説明されています。店で野菜販売が始まった17世紀当時は、野菜類以外のさまざまな食材も一緒に売られていたことから、物事の数が多いことを表す「八百」という言葉が当てられて「八百屋」と呼ばれるようになったという説もあるようです。
八百屋になるには?

八百屋になるために、資格は特に必要ありません。ただ、市場での取引をするためには「売買参加者」としての資格が必要になります。
「売買参加者」とは、卸売市場において卸売業者から卸売りを受けることについて、市場や取扱品目の部類ごとに、開設者の承認を受けた人のことです。市場ごとに承認基準は異なりますが、例えば沖縄県中央卸売市場では、「取扱品目の取引業務に現に従事し、かつ、満3年以上の経験を有する者であること」や「当市場における年間買付金額が、青果部においては1,000万円以上、花き部においては100万円以上見込まれる者であること」という項目があり、とても厳しい条件であることがわかります。
また、「売買参加者」になるために八百屋が組織する組合への加入登録が義務付けられている場合もあり、そのための加盟費用や出資金も必要です。八百屋の組合に入ることで、他の組合員からいろいろなことを教えてもらえたり、仲間ができて協力しあったりできるというメリットもありそうです。さらに、店で加工食品をあつかう場合には、保健所に食品衛生法上の営業許可の手続きを行う必要があります。
八百屋は、朝早くから市場に出向き、安くて新鮮な野菜や果物を仕入れます。そして、店に戻り、仕入れた野菜や果物を並べて売る準備をします。お客さんに買ってもらうためにどんな風に並べるか、そこも八百屋の腕の見せどころです。
他にも、商品を売るためにSNSで発信したりチラシを作ったり、お客さんに直接珍しい野菜の調理方法について説明したりと、さまざまな仕事をこなさなければなりません。近頃では、野菜や果物を売る小売業だけでなく、農業や飲食業などと兼業する八百屋も多く、その仕事内容は多様化していると言えそうです。
八百屋はなぜ安いのか?

スーパーで売られている野菜と比較して、八百屋の野菜は安いと感じたことがある人は多いでしょう。
八百屋が安い理由は、在庫数が限られているからです。八百屋は、基本的に在庫をたくさん持つことができないため、野菜を仕入れたらすぐ売らなければいけません。必要最低限の在庫だけ持つようにすると、スーパーと比べて廃棄となる野菜の数も少なくなります。
そのため、販売価格を決定する際に廃棄分を想定して上乗せする金額が最小限に抑えられます。
また、スーパーより臨機応変に対応できるという理由も考えられます。八百屋の場合、スーパーや同じ地域で野菜を販売する同業者の価格を調査した上で、商品を仕入れて販売価格を決めることが可能です。八百屋は仕入れから販売まで全てを自分達で対応していることもあり、その日の状況に応じて臨機応変に行動できます。
一方、スーパーの場合はそれぞれの担当が細かく決められており、仕入れ担当と販売担当の人員は異なります。そのため、スーパーの場合は、八百屋ほどスピーディーに対応することはできないのです。
青果店と八百屋の違いは?

青果店と八百屋には、大きな違いはありません。
現代では青果店も八百屋も、「野菜や果物を販売するお店」です。ただ、それぞれの言葉が持つイメージは異なり、八百屋は古いイメージ、青果店はより現代的なイメージが持たれています。これは八百屋の語源が江戸時代にあることにも繋がっていると言えるでしょう。
先程お伝えした通り、野菜以外にもさまざまなものを取り扱っていたとされる江戸時代の八百屋とは違い、現代では主に野菜と果物を販売するお店となっています。お店で売られるものが限定されるようになり、野菜と果物という意味がある「青果」を用いた言い方が一般的になったのかもしれません。
おしゃれな八百屋5選

昔ながらの八百屋も良いですが、最近では現代に合わせたおしゃれな八百屋も増えてきています。ここからは、おしゃれな八百屋5選を紹介します。
1. 旬八青果店
旬八青果店は、東京都内に9店舗を展開する八百屋です。旬にこだわり、安心・安全な野菜を提供しています。
都内にしか店舗はありませんが、オンラインショップで商品を購入することも可能です。定番の野菜から珍しい野菜まで、旬の野菜をまとめた詰め合わせセットがおすすめです。野菜の保存方法や調理方法が記載された説明シートが入っているので、珍しい野菜が入っていても安心です。
また、旬八青果店の新鮮な青果で作ったメニューが提供されている旬八キッチンというお店もあります。毎日届く新鮮な青果で作ったスムージやお弁当が並べられています。
2. 三茶ファーム
三茶ファームは、東京・三軒茶屋のエコー仲見世商店街にあります。店舗に並ぶ野菜は、どれも信頼できる提携農家で作られた有機野菜や自然栽培で作られた野菜ばかりです。
市場を経由せず、農家から産地直送の新鮮な野菜が届きます。三茶ファームの特徴は、栄養士の資格を持ったスタッフがいることです。旬のおいしい野菜やその野菜に合った調理方法など、他の八百屋ではなかなか聞けない質問もできます。
店舗まで行くのが難しい場合は、提携農家が作った旬の野菜やなかなか手に入らない珍しい野菜などがセットで届く「宅配やさいBOX」というサービスを利用するのもおすすめです。
ボックスの中には野菜の産地や農薬・化学肥料の使用状況などの情報が書かれた紙が同封されているので、お店に行ったことがない人でも安心して購入できます。
3. 八百屋 瑞花
八百屋 瑞花は、東京・神楽坂にある八百屋です。
「旬の食べ物で、季節に合った体作りを伝えたい」という想いから作られたお店です。八百屋に足を運んだとしても、自分でおいしい野菜を見極めるのは大変です。八百屋 瑞花では、野菜に詳しいスタッフがおいしく食べるための情報を教えてくれるので安心です。
旬のおいしい野菜や果物はもちろんのこと、調味料などの加工品も並べられています。
4. 808inluck
808inluckは、愛知・名古屋にある八百屋さんです。まるで海外のお店に来たかのようなおしゃれな佇まいが注目を集めています。808inluckでは、名物のトマトタワーが人気です。
お店に入ると、色鮮やかなトマトが並べられたタワーが見えます。お店で売られている野菜は、実際に栽培されている産地まで足を運んで確かめたものばかりで、本当においしいと感じた野菜のみ仕入れられています。
5. 神楽坂野菜計画
神楽坂野菜計画は、東京・神楽坂駅の近くにある八百屋です。
店舗には、農家から直接仕入れた新鮮な野菜が並びます。前日の夜までに収穫したものに加えて、その日の朝に収穫された採れたてのものもあり、いつでもフレッシュな野菜を楽しめます。
野菜はバラ売りでも購入できるため、普段食べない野菜にチャレンジしてみるのもおすすめです。店舗内では、お店で販売されている野菜と果物を使ったスムージーが販売されています。
スムージーの味が気に入ったら、その日に使われている野菜と果物を買ってみるのも良いかもしれません。
野菜の流通を支える八百屋のこれから

農産物は、主に生産者から農協などの出荷団体へ出荷され、卸売市場から小売業者を経て、消費者の元に届けられています。農林水産省の推計では、2016年時点で国産の野菜と果物の79.5%が卸売市場を経由して流通していて、卸売市場は生鮮食料品などの流通のインフラとして、大きな役割を担っていると言えます。
一方で、卸売市場を通さずに、生産者や出荷団体が直接スーパーマーケットなどに出荷するという販路も開拓されていて、農産物の流通には変化の兆しも見られます。生産者が直売所やマルシェなどに出荷したり、宅配便を使って消費者に農産物を発送したりと、生産者が消費者に農産物を直接届ける販路も一部で確立されつつあります。
経産省の経済センサスによると「野菜・果実小売店」の数は、1991年には46700店だったのに比べて、2016年には18397店まで減少していて、八百屋の数は減り続けています。スーパーマーケットやコンビニ、ショッピングモールが台頭してきたことや、商店街自体の衰退も影響しているのかもしれません。
そんな今こそ、直接市場に農産物を買い付けに行き、専門知識を持った八百屋には、生産者と消費者の間をつなぐ役割が期待されています。そして、実際にその期待に応える八百屋も多くあり、注目を集めています。例えば、インターネットでも販売を行ったり、直接契約農家から仕入れを行ったりと、その工夫はさまざまです。
【マイナビ農業でご紹介した八百屋さんの記事】
鮮度抜群! 適正な価格で野菜が都心で買える話題の八百屋「旬八青果店」
「野菜のセレクトショップ」yaotomiに学ぶ、本当に届けたい野菜とは
”旅する八百屋”に聞いた「ぼくらが八百屋になった理由(わけ)」
鮮度と価格で主婦を魅了する店【八百屋ファイル:おなかすいた】
さまざまな取り組みで、私たちの食を支えてくれている八百屋さん。今回はその歴史や仕事内容について、ご紹介してきました。その数は減少しているものの、仕入れや販売の方法に工夫を凝らし、商売を続けている八百屋さんがたくさんいます。これから八百屋がどのようなスタイルを確立していくのか、その行く末にこれからも注目していきたいと思います。
参考文献:
「日本大百科全書(ニッポニカ)」
出版:小学館
「大人の最強雑学1500」
著者:雑学総研
出版:KADOKAWA